- 株式会社OKI人事総務部 健康推進担当
- 三浦 亜衣子
vol.136 OKIグループにおける健康経営の取り組み
配信日:2024.04.15
他サービスでも配信中
出演者
-

-

- 株式会社AW Stage代表取締役社長
- 田村 亜弥
他サービスでも配信中
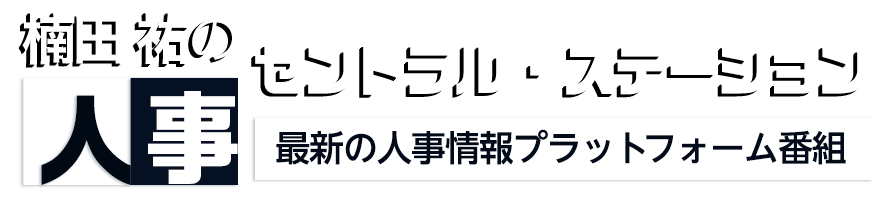

配信日:2024.04.15
他サービスでも配信中


他サービスでも配信中
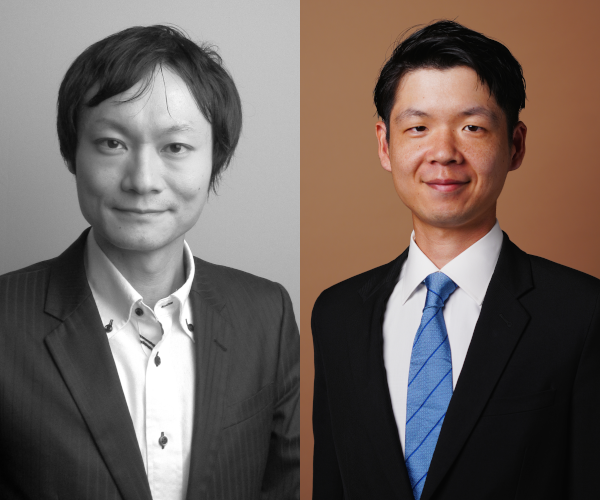 vol.135 資生堂における採用ミスマッチを防止するリファレンスチェック活用の取り組み
vol.135 資生堂における採用ミスマッチを防止するリファレンスチェック活用の取り組み
株式会社資生堂HR Manager Talent Acquisition
大石 大志
株式会社ROXX取締役 上級執行役員 SVP of Corporate
山田 浩輝
 vol.134 博士号取得人材の企業での活躍に向けて
vol.134 博士号取得人材の企業での活躍に向けて
経済産業省産業技術環境局大学連携推進室 室長補佐(企画調整)
米山 侑志
株式会社アカリク社長室 プロジェクト開発グループ マネージャー
鬼頭 祐介
 vol.133 「多様な目線」で「多様な人材」を見出す~三菱UFJ信託銀行における採用品質向上の取り組み~
vol.133 「多様な目線」で「多様な人材」を見出す~三菱UFJ信託銀行における採用品質向上の取り組み~
三菱UFJ信託銀行株式会社人事部 採用・キャリアグループ 課長
金子 怜子
三菱UFJ信託銀行株式会社人事部 採用・キャリアグループ 調査役
徳永 まなか
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
亀山 太一
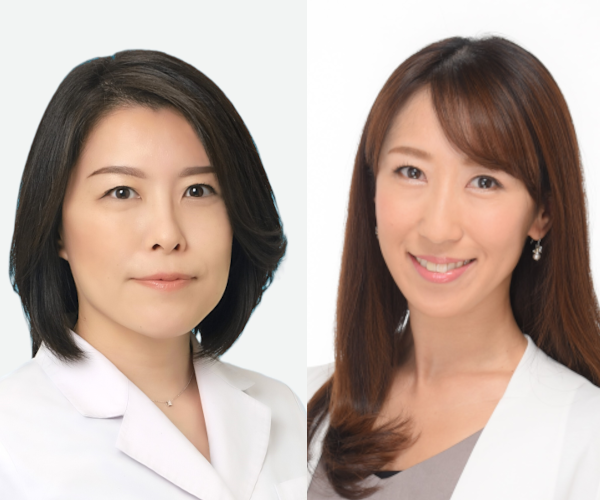 vol.132 産婦人科専門医と考える女性のヘルスケア
vol.132 産婦人科専門医と考える女性のヘルスケア
さやかウィメンズヘルスクリニック広尾院長 産婦人科専門医 がん治療認定医 医学博士
池田 さやか
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.131 ノンデスクワーカー採用の市場と動向 〜agent bankが解決する日本の社会問題〜
vol.131 ノンデスクワーカー採用の市場と動向 〜agent bankが解決する日本の社会問題〜
株式会社ROXX代表取締役
中嶋 汰朗
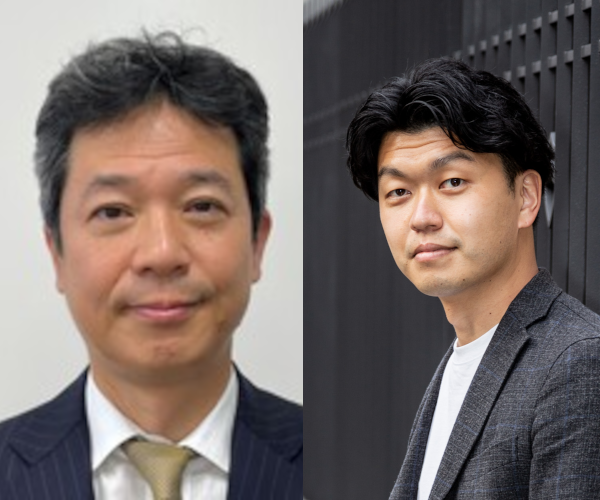 vol.130 多様な個の終身成長と共創力で未来を切り拓く〜旭化成の人財戦略〜
vol.130 多様な個の終身成長と共創力で未来を切り拓く〜旭化成の人財戦略〜
旭化成株式会社上席執行役員 人事担当 健康経営担当補佐
西川 知
株式会社 アカリク代表取締役社長
山田 諒
 vol.129 【新春特番】2024年の抱負
vol.129 【新春特番】2024年の抱負
株式会社アカリク代表取締役
山田 諒
株式会社ROXX代表取締役
中嶋 汰朗
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
株式会社AW stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.128 採用の未来の扉をひらく〜HireVueのヒューマン・ポテンシャル・インテリジェンス〜
vol.128 採用の未来の扉をひらく〜HireVueのヒューマン・ポテンシャル・インテリジェンス〜
HireVue Inc.カスタマーサクセス SVP
ジェフ・キャンプリン
タレンタ株式会社カスタマサクセス マネージャー
茂木 麻早
タレンタ株式会社カスタマサクセス マネージャー
忠村 佳代子
 vol.127 バンダイナムコオンラインに於ける健康推進の取り組み
vol.127 バンダイナムコオンラインに於ける健康推進の取り組み
株式会社バンダイナムコオンライン経営企画部 ゼネラルマネージャー
能間 崇
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.126 NECにおけるリファレンス・コンプライアンスチェック活用の取り組み
vol.126 NECにおけるリファレンス・コンプライアンスチェック活用の取り組み
日本電気株式会社人材組織開発統括部 タレント・アクイジショングループ ディレクター
大橋 康子
株式会社ROXX取締役 上級執行役員 senior vice president of Corporate
山田 浩輝
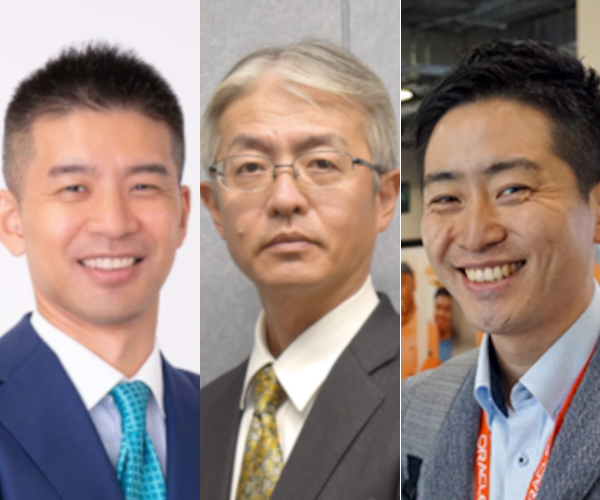 vol.125 HR Tech Conference & Expo 2023の最新情報 ラスベガスから現地レポート
vol.125 HR Tech Conference & Expo 2023の最新情報 ラスベガスから現地レポート
株式会社Tokyo Consulting&Intelligence代表取締役
河野 英太郎
タレンタ株式会社専務取締役兼CFO
中村 究
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
亀山 太一
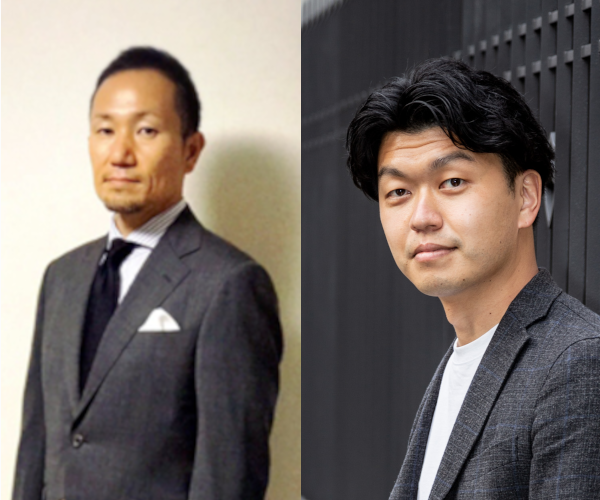 vol.124 文系大学院生のインターンシップと就職動向
vol.124 文系大学院生のインターンシップと就職動向
立教大学キャリアセンター
林 良知
株式会社 アカリク代表取締役社長
山田 諒
 vol.123 ライオンに於ける健康経営〜新社屋での取り組み〜
vol.123 ライオンに於ける健康経営〜新社屋での取り組み〜
ライオン株式会社人材開発センター 健康サポート室 副主任部員
川本 和江
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.122 大転職時代!リファレンスチェックが必要な理由とは
vol.122 大転職時代!リファレンスチェックが必要な理由とは
株式会社プロレド・パートナーズ執行役員 CHRO 人事総務本部長
中西 一統
株式会社ROXX取締役 上級執行役員 senior vice president of Corporate
山田 浩輝
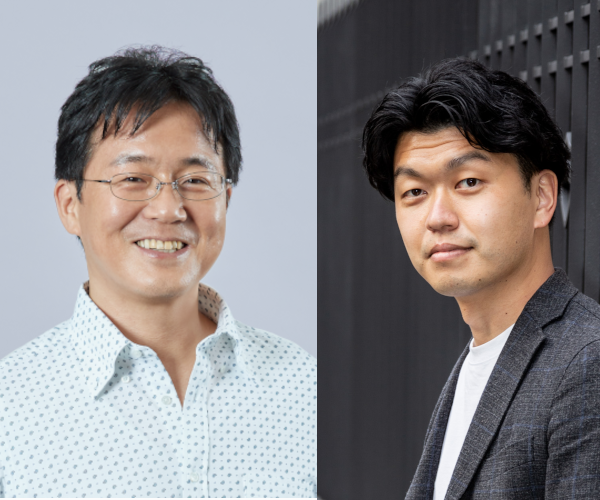 vol.121 パナソニックコネクトにおける理系人材の活躍の場
vol.121 パナソニックコネクトにおける理系人材の活躍の場
パナソニック コネクト株式会社執行役員 ヴァイス・プレジデント チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー
新家 伸浩
株式会社アカリク代表取締役社長
山田 諒
 vol.120 グローバルにおける360度フィードバックの活用トレンド〜カナダ発のサーベイ自動化プラットフォーム Blue CEO初来日!~
vol.120 グローバルにおける360度フィードバックの活用トレンド〜カナダ発のサーベイ自動化プラットフォーム Blue CEO初来日!~
カナダ・Explorance社CEO
Samer Saab
カナダ・Explorance社バイスプレジデント ソリューションアーキテクチャ
Mohammed Sheraidah
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
茂木 麻早
 vol.119 【リニューアル記念番組】
vol.119 【リニューアル記念番組】
株式会社アカリク代表取締役社長
山田 諒
株式会社ROXX代表取締役
中嶋 汰朗
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.118 異業種交流プログラムのトレンド
vol.118 異業種交流プログラムのトレンド
CrossUS株式会社代表取締役
瀬戸口 航
 vol.117 バンダイナムコアミューズメントの施設運営事業における「全員戦力化」の取り組み
vol.117 バンダイナムコアミューズメントの施設運営事業における「全員戦力化」の取り組み
株式会社バンダイナムコアミューズメントオペレーションサポート部
もっとファン課 マネージャー
甲斐 啓介
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
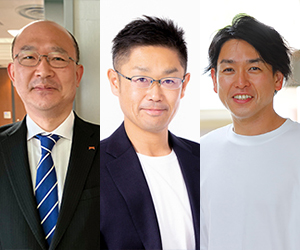 vol.116 食品業界におけるこれからの新卒採用
vol.116 食品業界におけるこれからの新卒採用
テーブルマーク 株式会社人事総務部 人事戦略チーム
佐原 正高
株式会社i-plug代表取締役社長
中野 智哉
株式会社マキシマイズ代表取締役
三浦 力
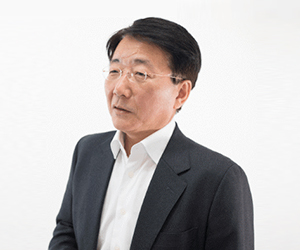 vol.115 書籍「エンゲージメントを高める会社」発売記念番組!歴史的使命を終えたMBOや評価制度を抜本的に変革する
vol.115 書籍「エンゲージメントを高める会社」発売記念番組!歴史的使命を終えたMBOや評価制度を抜本的に変革する
株式会社アジャイルHR代表取締役社長
松丘 啓司
 vol.114 三井住友海上における越境学習の取組みと展望
vol.114 三井住友海上における越境学習の取組みと展望
三井住友海上火災保険株式会社人事部 能力開発チーム 課長
山本 悠太
株式会社セルム執行役員
瀬戸口 航
 vol.113「記憶の人事」から「記録の人事」へ 大和ハウスにおける人事DXの取り組み
vol.113「記憶の人事」から「記録の人事」へ 大和ハウスにおける人事DXの取り組み
大和ハウス工業株式会社本社人事部 人事DX推進グループ/
西日本採用グループ
和田 光弘
タレンタ株式会社カスタマ―サクセスマネージャー
亀山 太一
 vol.112 i-plugとVISITS Technologies が見据える、学生のキャリア選択の在り方
vol.112 i-plugとVISITS Technologies が見据える、学生のキャリア選択の在り方
VISITS Technologies株式会社代表取締役 CEO
松本 勝
株式会社i-plug代表取締役社長
中野 智哉
 vol.111 アンチエイジング
vol.111 アンチエイジング
株式会社AW Stage代表取締役会長
楠田 祐
 vol.110 野村證券における越境学習の取組みと展望
vol.110 野村證券における越境学習の取組みと展望
野村證券株式会社人材開発部 L&D 人材開発三課
網谷 秀夫
株式会社セルム執行役員
瀬戸口 航
 vol.109 ネイサン・モンドラゴン博士来日!「産業組織心理学の人事への活用の実際」
vol.109 ネイサン・モンドラゴン博士来日!「産業組織心理学の人事への活用の実際」
HireVue, Inc.取締役・チーフサイコロジスト
ネイサン・モンドラゴン
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
茂木 麻早
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
東畑 千波
 vol.108 採用力を高める適性検査の活用法とそのポテンシャル
vol.108 採用力を高める適性検査の活用法とそのポテンシャル
株式会社ワークス・ジャパン人材ソリューション事業本部
ITソリューション事業部
プロダクトマネージメント部 部長
阪 真以子
株式会社イー・ファルコン代表取締役
田中 伸明
 vol.107【新春特別番組】2023年 4社座談会
vol.107【新春特別番組】2023年 4社座談会
株式会社i-plug代表取締役社長
中野 智哉
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
株式会社セルム執行役員
瀬戸口 航
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.106 三菱自動車工業が取り組む女性の健康づくり
vol.106 三菱自動車工業が取り組む女性の健康づくり
三菱自働車工業株式会社人事本部ビジネスパートナー人事部 担当部長
有吉 晋作
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.105 ダイドードリンコにおける次世代リーダー育成の取組みと展望
vol.105 ダイドードリンコにおける次世代リーダー育成の取組みと展望
ダイドードリンコ株式会社人事総務部 人財開発グループ
シニアマネージャー
石原 健一朗
株式会社セルム執行役員
瀬戸口 航
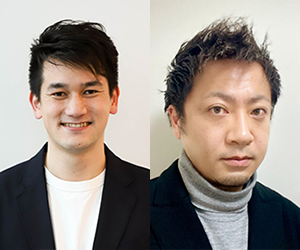 vol.104 株式会社ダイセルにおける、理系学生に自社の技術力を最大限に訴求するためのオンライン型コンテンツの進化
vol.104 株式会社ダイセルにおける、理系学生に自社の技術力を最大限に訴求するためのオンライン型コンテンツの進化
株式会社ダイセル事業支援本部 人事グループ 課長代理
岡嶋 顕史
株式会社i-plugエンタープライズソリューション部 ゼネラルマネージャー
筏井 岳
 vol.103 健康eラーニングの取り組み
vol.103 健康eラーニングの取り組み
株式会社レビックグローバル代表取締役社長
柏木 理
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
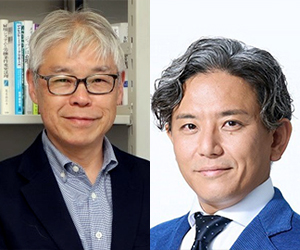 vol.102「越境学習」を加速させる「組織力開発」とは
vol.102「越境学習」を加速させる「組織力開発」とは
学習院大学 経済学部教授一橋大学名誉教授
守島 基博
株式会社セルム執行役員
瀬戸口 航
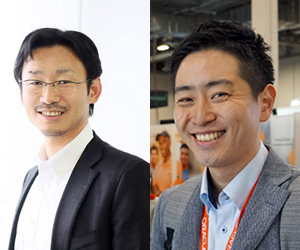 vol.101 HR Tech Conference & Expo 2022の最新情報 ラスベガスから現地レポート
vol.101 HR Tech Conference & Expo 2022の最新情報 ラスベガスから現地レポート
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
タレンタ株式会社カスタマ―サクセスマネージャー
亀山 太一
 vol.100 HR Technology Conference & Exposition 2022のプレビュー
vol.100 HR Technology Conference & Exposition 2022のプレビュー
タレンタ株式会社カスタマ―サクセスマネージャー
亀山 太一
 vol.99 日本マイクロソフトにおける、長期インターンシップの取り組みと進化
vol.99 日本マイクロソフトにおける、長期インターンシップの取り組みと進化
日本マイクロソフト株式会社APJ University Recruiting Recruiter
岩渕 美菜子
株式会社i-plugエンタープライズソリューション部
ゼネラルマネージャー
筏井 岳
 vol.98 日清食品ホールディングスにおける新入社員研修での健康づくりの取組み
vol.98 日清食品ホールディングスにおける新入社員研修での健康づくりの取組み
日清食品ホールディングス株式会社人事部 主任
山梨 夏希
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.97 世界遺産・高野山から学ぶ、リベラルアーツ(文化財×人材育成)
vol.97 世界遺産・高野山から学ぶ、リベラルアーツ(文化財×人材育成)
凸版印刷株式会社人事労政本部 人財開発センター 課長
山崎 智子
凸版印刷株式会社文化事業推進本部 事業企画部
事業企画3T 課長
内山 悠一
株式会社セルム執行役員
瀬戸口 航
 vol.96 荏原製作所におけるデータドリブン人事の現在地と今後の展開
vol.96 荏原製作所におけるデータドリブン人事の現在地と今後の展開
株式会社荏原製作所データストラテジーチーム
データストラテジー &
アナリシスディレクター
三隅 光
株式会社荏原製作所人事統括部人材開発部
ダイバーシティ・リクルーティング課
西尾 舞
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
 vol.95 BIPROGYにおける”イントラパーソナル・ダイバーシティ”実現に向けた新卒採用の取り組み
vol.95 BIPROGYにおける”イントラパーソナル・ダイバーシティ”実現に向けた新卒採用の取り組み
BIPROGY株式会社人事部 採用マネジメント室
新卒採用チーム リーダー
田村 日和
株式会社i-plugエンタープライズソリューション部
ゼネラルマネージャー
筏井 岳
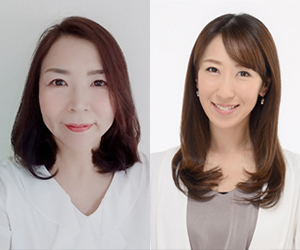 vol.94 そごう・西武の新入社員が身につける立ち居振る舞いと健康意識
vol.94 そごう・西武の新入社員が身につける立ち居振る舞いと健康意識
株式会社そごう・西武人事部 教育推進担当
小畑 光代
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.93 企業と大学の両面から見る2022年度新入社員の傾向
vol.93 企業と大学の両面から見る2022年度新入社員の傾向
明治大学就職キャリア支援部
就職キャリア支援事務室
原口 善信
住友生命保険相互会社人事部リクルート推進室室長
西浦 知世
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
 vol.92 グローバルにおける採用DX動向と最新のAI活用事例
vol.92 グローバルにおける採用DX動向と最新のAI活用事例
HireVue, Inc.APAC Head of Assessment
Tom Cornell, MSc
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
東畑 千波
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
茂木 麻早
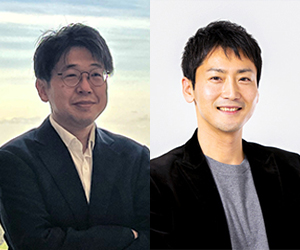 vol.91 帝人における個別最適化採用への進化
vol.91 帝人における個別最適化採用への進化
帝人株式会社人財開発部 採用グループ
採用グループ長
遠山 卓
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.90 水ingにおける女性の健康づくりの取組み
vol.90 水ingにおける女性の健康づくりの取組み
水ing株式会社ガバナンス推進本部
総務・人事統括部 人事部
由比 伸一
水ing株式会社ガバナンス推進本部
総務・人事統括部 人事部
廣瀬 陽子
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.89 メルカリのオンボーディングとそれを支えるカルチャー
vol.89 メルカリのオンボーディングとそれを支えるカルチャー
株式会社メルカリPeople & Culture・Learning &Development Team
マネージャー
橋本 佳苗
株式会社メルカリPeople & Culture・Learning &Development Team
オンボーディングリード
細谷 杏
株式会社ファーストキャリア営業本部 西日本支社
シニアマネージャー
河野 裕介
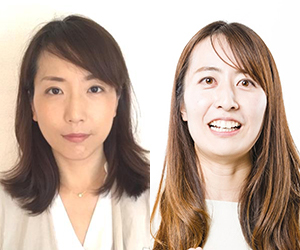 vol.88 東急株式会社による新たな採用DXの取り組み~印象だけではない選考 「ヒトとAIの協働」の狙い~
vol.88 東急株式会社による新たな採用DXの取り組み~印象だけではない選考 「ヒトとAIの協働」の狙い~
東急株式会社人材戦略室 人事開発グループ
採用センター 課長
初田 直美
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
忠村 佳代子
 vol.87 22卒採用のオンライン化から見えた課題と23卒採用の変化
vol.87 22卒採用のオンライン化から見えた課題と23卒採用の変化
三井住友カード株式会社人事部(東京)グループ長
古市 幸子
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.86 コニカミノルタに於けるオンラインウォーキングイベントの取り組み
vol.86 コニカミノルタに於けるオンラインウォーキングイベントの取り組み
コニカミノルタ健康保険組合事務長 兼 コニカミノルタ株式会社
人事部 健康管理グループ
渕上 武彦
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.85 DMMが取組む人材育成と人事の役割
vol.85 DMMが取組む人材育成と人事の役割
合同会社DMM.com組織管理本部 人事部
人事戦略グループ 育成チーム
杉山 弘明
株式会社ファーストキャリア営業本部 営業本部長
池田 和史
株式会社ファーストキャリア営業本部 営業マネージャー
石原 陽平
 vol.84 ITの進展とHRテクノロジーの未来
vol.84 ITの進展とHRテクノロジーの未来
タレンタ株式会社代表取締役会長兼CEO
石橋 愼一郎
 vol.83 【新春特別番組】2022年 4社座談会
vol.83 【新春特別番組】2022年 4社座談会
株式会社i-plug代表取締役社長
中野 智哉
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.82 ソニーグループの新卒採用におけるミスマッチ解消の取組み
vol.82 ソニーグループの新卒採用におけるミスマッチ解消の取組み
ソニーグループ株式会社Professional Services
SPPS管理室 採用Gp
清水 舞子
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.81 美しい姿勢と健康的なウォーキングのすすめ
vol.81 美しい姿勢と健康的なウォーキングのすすめ
株式会社AW Stageウォーキングスタイリスト
田沼 由希
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.80 “ドコモパーソナルトレーニング”による、個に合わせた育成の体現
vol.80 “ドコモパーソナルトレーニング”による、個に合わせた育成の体現
株式会社NTTドコモ人事部 人事企画担当 主査
緒方 隆仁
株式会社セルム 執行役員 兼 株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
株式会社ファーストキャリア営業本部 マネージャー
石原 陽平
 vol.79 印象だけではない選考 「ヒトとAIの協働」が創り出す、新たな採用DXの取り組み ~阪急阪神百貨店、ユニ・チャームの成功事例~
vol.79 印象だけではない選考 「ヒトとAIの協働」が創り出す、新たな採用DXの取り組み ~阪急阪神百貨店、ユニ・チャームの成功事例~
株式会社阪急阪神百貨店人事室 人材開発部 採用チーム
松尾 泰文
ユニ・チャーム株式会社Global人事総務本部 人事部 Career形成支援Group
佐々木 一真
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
東畑 千波
 vol.78 すららネットにおけるミスマッチを起こさず即戦力化する新卒採用の取組み
vol.78 すららネットにおけるミスマッチを起こさず即戦力化する新卒採用の取組み
株式会社すららネット 企画開発グループ 兼 人財戦略室
マネージャー
坪田 未歩
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.77 アサヒ飲料におけるコンディションを整えるセルフケアの講座
vol.77 アサヒ飲料におけるコンディションを整えるセルフケアの講座
アサヒ飲料株式会社人事総務部 人材開発グループ
グループリーダー
鈴木 隆士
アサヒ飲料株式会社人事総務部 人材開発グループ
林 佳央
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.76 パナソニックにおけるピープルアナリティクスの取り組み
vol.76 パナソニックにおけるピープルアナリティクスの取り組み
パナソニック株式会社リクルート&キャリアクリエイトセンター 企画部 戦略企画課 課長
坂本 崇
株式会社セルム 執行役員 兼 株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
株式会社ファーストキャリア営業本部 西日本支社 シニアマネージャー
河野 裕介
 vol.75 深層ダイバーシティの見える化を起点としたワークエンゲージメント向上アプローチ
vol.75 深層ダイバーシティの見える化を起点としたワークエンゲージメント向上アプローチ
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
 vol.74 株式会社ダイセルが実践するイメージギャップの壁を超える新卒採用
vol.74 株式会社ダイセルが実践するイメージギャップの壁を超える新卒採用
株式会社ダイセル事業支援本部 人事グループ 課長代理
岡嶋 顕史
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.73 髙島屋に於けるe-ラーニングによる健康づくり講座の取り組み
vol.73 髙島屋に於けるe-ラーニングによる健康づくり講座の取り組み
株式会社髙島屋人事部 ダイバーシティー推進室 室長
三田 理恵
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.72 技術起点のソリューション開発×リーダー育成の可能性
vol.72 技術起点のソリューション開発×リーダー育成の可能性
株式会社セルム / 株式会社ファーストキャリアパートナーコンサルタント
(株式会社Co-learning 代表取締役)
竹枝 正樹
株式会社セルム 執行役員 兼 株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
 vol.71 リスナー累計45万人突破記念番組「カナダ発のサーベイ自動化プラットフォーム Blue CEOインタビュー」
vol.71 リスナー累計45万人突破記念番組「カナダ発のサーベイ自動化プラットフォーム Blue CEOインタビュー」
ExploranceCEO
Samer Saab
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
タレンタ株式会社カスタマ―サクセスマネージャー
茂木 麻早
 vol.70 ミクシィにおける「個」を重視した新卒採用の取り組み
vol.70 ミクシィにおける「個」を重視した新卒採用の取り組み
株式会社ミクシィ人事本部 人材採用部
新卒採用グループ タレントディスカバリーチーム
大谷 耕一郎
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.69 ロフトが実施する新入社員研修における健康増進の取組み
vol.69 ロフトが実施する新入社員研修における健康増進の取組み
株式会社ロフト人事部 労務厚生担当課長
吉田 文彦
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.68 【(株)セルム 東証ジャスダック上場記念 】セルムグループが考えるこれからのリーダーシップ・パイプライン
vol.68 【(株)セルム 東証ジャスダック上場記念 】セルムグループが考えるこれからのリーダーシップ・パイプライン
株式会社セルム代表取締役CEO
加島 禎二
株式会社セルム 執行役員 兼株式会社ファーストキャリア 代表取締役社長
瀬戸口 航
 vol.67 守島基博教授 × ミレニアルズ女性対談「個を尊重する人材マネジメント」
vol.67 守島基博教授 × ミレニアルズ女性対談「個を尊重する人材マネジメント」
一橋大学名誉教授/学習院大学教授
守島 基博
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
東畑 千波
タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャー
忠村 佳代子
 vol.66【東証マザーズ上場記念番組】 複雑化、多様化する新卒採用時代における勝つための採用変革とは
vol.66【東証マザーズ上場記念番組】 複雑化、多様化する新卒採用時代における勝つための採用変革とは
株式会社i-plug代表取締役 CEO
中野 智哉
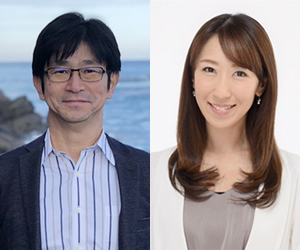 vol.65 生協連における健康経営の取組み
vol.65 生協連における健康経営の取組み
日本生活協同組合連合会全国生協・人づくり支援センター
村田 二三男
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.64 三越伊勢丹における若年層の育成とキャリア
vol.64 三越伊勢丹における若年層の育成とキャリア
株式会社三越伊勢丹総務人事グループ人材開発部 部長
東 紀久子
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
 vol.63 日立製作所の採用業務におけるデジタルトランスフォーメーションの取り組み
vol.63 日立製作所の採用業務におけるデジタルトランスフォーメーションの取り組み
株式会社日立製作所人事勤労本部
タレントアクイジション部 主任
古田 祐一
タレンタ株式会社カスタマ―サクセスマネージャー
亀山 太一
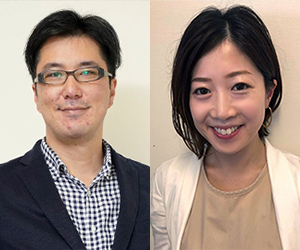 vol.62 採用チームのマンパワーとコストを最小化する課題に取組むベンチャー企業事例
vol.62 採用チームのマンパワーとコストを最小化する課題に取組むベンチャー企業事例
ソウルドアウト株式会社執行役員 グループ人財本部長
宮武 宣之
株式会社i-plug RP部 関東RPグループ
グループマネージャー
伊藤 麻貴
 vol.61 コニカミノルタにおける健康経営の取組み
vol.61 コニカミノルタにおける健康経営の取組み
コニカミノルタ健康保険組合 事務長 兼 コニカミノルタ株式会社人事部健康管理グループ
渕上 武彦
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.60 東京海上日動火災保険における若手育成の取り組み
vol.60 東京海上日動火災保険における若手育成の取り組み
東京海上日動火災保険株式会社人事企画部 人材開発室 課長代理
菊地 謙太郎
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
 vol.59 【新春特別番組】2021年 4社座談会
vol.59 【新春特別番組】2021年 4社座談会
株式会社i-plug代表取締役社長
中野 智哉
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
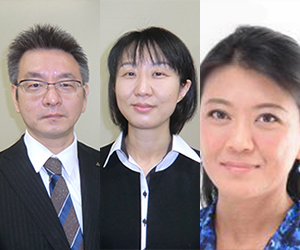 vol.58 チャレンジする自治体~都城市における採用DXの取り組み
vol.58 チャレンジする自治体~都城市における採用DXの取り組み
都城市総務部職員課人事給与担当 副課長
野﨑 康治
都城市総務部職員課人事給与担当 副主幹
小森 直美
タレンタ株式会社カスタマ―サクセスマネージャー
茂木 麻早
 vol.57 新卒ダイレクトリクルーティングの醍醐味
vol.57 新卒ダイレクトリクルーティングの醍醐味
大和ライフネクスト株式会社人材開発部 人材開発課
菱谷 竜太
株式会社SHIFT人事本部 コーポレート人事部
コーポレート採用グループ
遠藤 剛
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.56 小田急電鉄に於ける健康増進の取り組み
vol.56 小田急電鉄に於ける健康増進の取り組み
小田急電鉄株式会社執行役員 人事部長
深海 尚
小田急電鉄株式会社人事部 小田急研修センター 副所長
草薙 まり
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
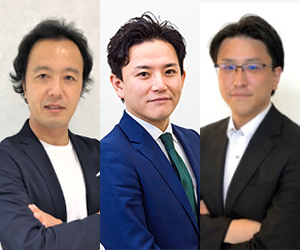 vol.55 アサヒ飲料における若手選抜育成の取り組み
vol.55 アサヒ飲料における若手選抜育成の取り組み
アサヒ飲料株式会社人事総務部 部長
相田 幸明
株式会社ファーストキャリアアサヒ飲料株式会社
瀬戸口 航
株式会社ファーストキャリア営業本部
石原 陽平
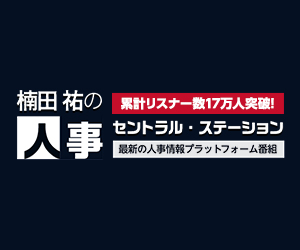 vol.54 米国ラストベルト~シリコンバレー~シリコンスロープスの理解と採用DXの進化
vol.54 米国ラストベルト~シリコンバレー~シリコンスロープスの理解と採用DXの進化
タレンタ株式会社専務取締役 兼 CFO
中村 究
 vol.53 三井住友カードにおける22卒採用の変化
vol.53 三井住友カードにおける22卒採用の変化
三井住友カード株式会社人事部 兼 人材開発室
グループマネージャー
赤井 洋介
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.52 エイブリックに於ける健康増進の取り組み
vol.52 エイブリックに於ける健康増進の取り組み
エイブリック株式会社執行役員 兼 CAO
長野 典史
エイブリック株式会社タレント・モチベーション・グループ
採用・共育センター リーダー
飯田 沙織
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.51 KDDIにおける人財開発の取り組み
vol.51 KDDIにおける人財開発の取り組み
KDDI株式会社人事本部 人財開発部長
千葉 華久子
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
 vol.50 DX時代における日本発のイノベーティブリーダー育成
vol.50 DX時代における日本発のイノベーティブリーダー育成
株式会社サンブリッジ 取締役 創業者タレンタ株式会社 社外取締役
アレン・マイナー
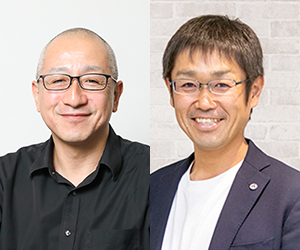 vol.49 22卒インターンシップと21卒の内定者サポート
vol.49 22卒インターンシップと21卒の内定者サポート
ProFuture株式会社代表取締役社長 兼 HR総研 所長
寺澤 康介
株式会社i-plug代表取締役 CEO
中野 智哉
 vol.48 1on1オンラインエクササイズ -zoomによる週1回から始まる運動習慣-
vol.48 1on1オンラインエクササイズ -zoomによる週1回から始まる運動習慣-
株式会社商船三井専務執行役員(アジア・中東・大洋州担当) <兼> MOL(Asia Oceania )Pte. Ltd. Managing Director
八嶋 浩一
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
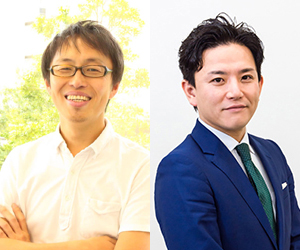 vol.47 ヤフーにおけるフルオンライン新入社員育成の取り組み
vol.47 ヤフーにおけるフルオンライン新入社員育成の取り組み
ヤフー株式会社コーポレートグループ
ピープル・デベロップメント統括本部
カンパニーPD本部PD企画部企画2
リーダー
小金 蔵人
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
 vol.46 コカ・コーラ ボトラーズジャパンにおける採用デジタル・トランスフォーメーションの取り組み
vol.46 コカ・コーラ ボトラーズジャパンにおける採用デジタル・トランスフォーメーションの取り組み
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社人事・総務本部 人事統括部
人財開発部 人財開発部長
東 由紀
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社人事・総務本部 人事統括部
人財開発部 採用課長
巻山 修二
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
タレンタ株式会社セールス&マーケティング マネージャー
鈴木 善幸
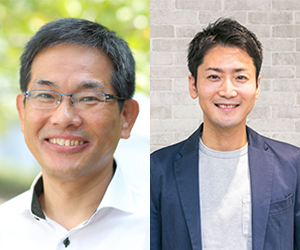 vol.45 NECソリューションイノベータに於ける新卒採用と育成の取組み
vol.45 NECソリューションイノベータに於ける新卒採用と育成の取組み
NECソリューションイノベータ株式会社執行役員兼人財企画部長
瓜生 光裕
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.44 テレワークの課題と軽い運動のすすめ
vol.44 テレワークの課題と軽い運動のすすめ
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.43 日本IBMにおける Next Generetion の活躍推進〜若手人材オンボーディング取り組み事例〜
vol.43 日本IBMにおける Next Generetion の活躍推進〜若手人材オンボーディング取り組み事例〜
日本アイ・ビー・エム株式会社人事 エンゲージメント 部長
花田 尚美
株式会社ファーストキャリア代表取締役社長
瀬戸口 航
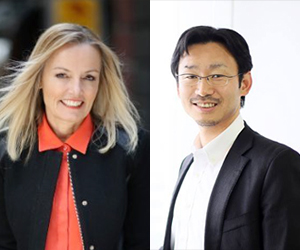 vol.42 自律と成長を促進する Fuel50 CEO インタビュー
vol.42 自律と成長を促進する Fuel50 CEO インタビュー
Fuel50 Inc.共同創業者兼CEO
Anne Fulton
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
 vol.41 学習院大学に於けるベトナムインターンシップ
vol.41 学習院大学に於けるベトナムインターンシップ
学習院大学キャリアセンター 担当次長
淡野 健
株式会社i-plug代表取締役 CEO
中野 智哉
 vol.40 伊勢丹浦和店における立ち振る舞いトレーニング〜美と健康のための身体づくり〜
vol.40 伊勢丹浦和店における立ち振る舞いトレーニング〜美と健康のための身体づくり〜
株式会社三越伊勢丹伊勢丹浦和店 総務部長
東 紀久子
株式会社三越伊勢丹ホールディングスチーフオフィサー室 事業企画推進ディビジョン プランニングスタッフ
塚谷 一貴
株式会社三越伊勢丹総務人事部人事ディビジョン
藤原 千鶴
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
 vol.39 川崎重工業が大切にする採用と育成のブランディング
vol.39 川崎重工業が大切にする採用と育成のブランディング
川崎重工業株式会社コーポレートコミュニケーション部 部長
鳥居 敬
株式会社ファーストキャリア営業本部 本部長
池田 和史
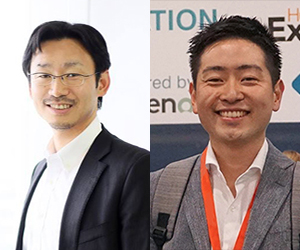 vol.38 自律的な成長とキャリア開発を促進するプラットフォーム
vol.38 自律的な成長とキャリア開発を促進するプラットフォーム
タレンタ株式会社代表取締役社長兼COO
田中 義紀
タレンタ株式会社カスタマ―サクセスマネージャー
亀山 太一
 vol.37 アイスタイルの事業多角化と採用における変化
vol.37 アイスタイルの事業多角化と採用における変化
株式会社アイスタイルリクルーティング部 部長/採用責任者
田中 秀平
株式会社i-plug取締役 COO
直木 英訓
 vol.36 ローソンにおける健康推進の取り組み
vol.36 ローソンにおける健康推進の取り組み
株式会社ローソンローソングループ健康推進センター センター長代行
四方田 美穂
株式会社AW Stage代表取締役社長
田村 亜弥
NECなど東証一部エレクトロニクス関連企業3社の社員を経験した後にベンチャー企業社長を10年経験。会長を経験後に中央大学大学院ビジネススクール客員教授(MBA)を7年間経験。2015年は日テレのNEWS ZEROのコメンテーターを担当。2016年より人事向けラジオ番組「楠田祐の人事放送局」と「楠田祐の人事アウトサイド・イン」のパーソナリティを毎週担当。2017年よりHRエグゼクティブコンソーシアム代表に就任。2018年より株式会社AW Stage 代表取締役会長に就任。2023年よりHRテクノロジーインスティチュート代表に就任。

2001年秋田放送アナウンス部に配属。
入社後すぐ最も人気のあった情報バラエティー番組MCに抜擢。
ラジオの冠番組では全国で2位のアクセス数を打ち出す。
秋田の3年半を経て、2006年文化放送にアナウンサーとして入社。
「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛(パッション)」
「近藤真彦 くるくるマッチ箱」など番組担当多数。現在は企業の人事として活躍。


