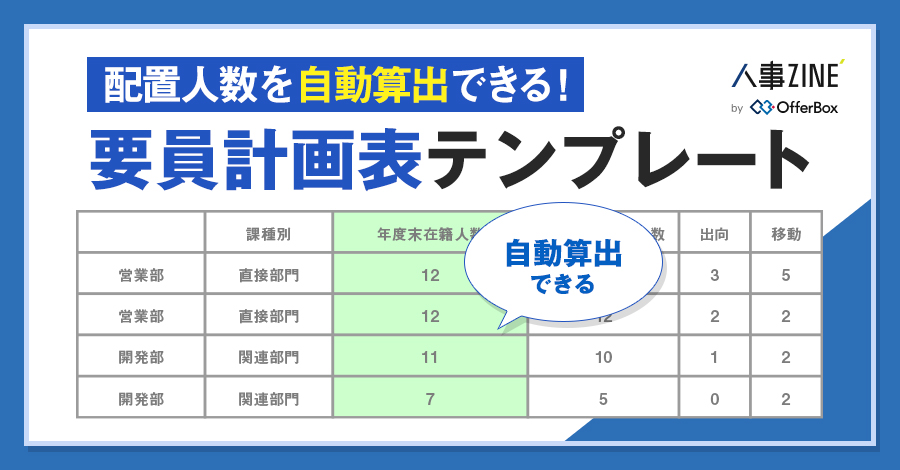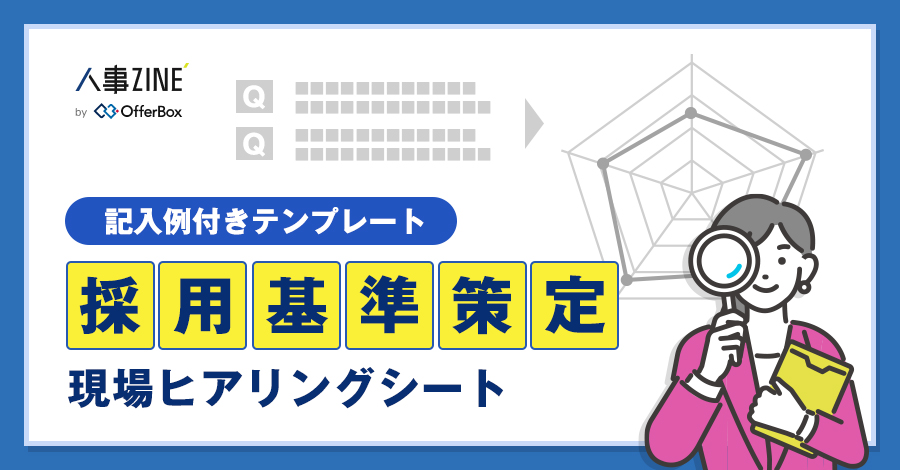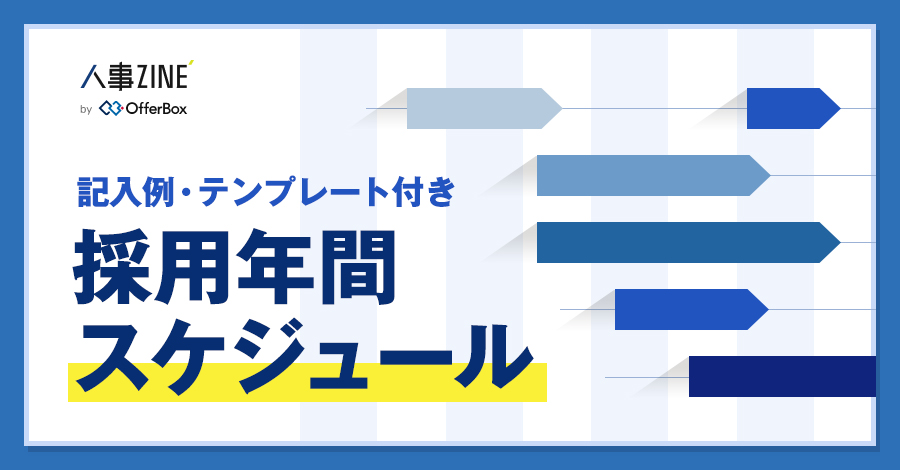新卒一括採用は見直されるべき?企業動向を踏まえて採用戦略を解説

経団連は、2022年入社以降の学生に対する就活ルールを廃止し、採用活動の時期を定めないこととしました。それに伴って「だとすれば新卒一括採用も変わるのでは?」という議論が生じています。
現状では、ほとんどの企業が新卒一括採用を実施している中、「就活ルールが廃止されたら新卒一括採用も消失するのか?」「他の企業は今後どんな手を打つのか?」と気になっている人事担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、新卒一括採用は本当に見直されるべきなのか、そもそもなぜ見直しの必要性が出てきたのか、今まで新卒一括採用を当然とみなしてきた企業はどうするべきか、について考察いたします。
人事ZINEでは、これからの採用市場がどうなっていくのかがわかる「2025年卒の市場を分析!これからの新卒採用戦術」をご用意しています。Z世代の学生の特徴や採用成功に向けて立てるべき戦略などを解説しています。学生のニーズや他社の採用状況が気になる人事・採用担当者の方は、ダウンロードしてご活用ください。

目次
新卒一括採用とは?|制度の概要と日本独自の背景

日本の採用慣行の中心にある「新卒一括採用」は、長年にわたり企業と学生の双方にとって前提となってきた制度です。しかしこの制度は、実は海外にはほとんど見られない日本独自の文化的・経済的背景から生まれた仕組みです。
本章では、新卒一括採用の基本的な定義から、制度が根付いた経緯、そして海外との比較から見える特異性までを網羅的に解説します。制度を「続けるべきか」「変えるべきか」を議論する前に、その前提となる全体像を正確に理解しておくことが重要です。
新卒一括採用とは何か?基本的な定義
新卒一括採用とは、企業が毎年決まった時期に、主に大学や大学院を卒業予定の学生を対象に一括で採用活動を行う仕組みです。説明会、エントリー、選考、内定といったプロセスが同時進行するのが特徴で、採用スケジュールが一律になっている点が最大の特徴です。
日本では「4月入社・一括内定・同期文化」が前提となっており、企業側も学生側もこのサイクルを当然視してきました。通年採用やインターン活用が広まりつつある現在でも、なお主流であり続けています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 学生を一律のスケジュールでまとめて採用する方式 |
| 対象 | 主に新卒(大学・大学院卒) |
| 特徴 | 年度単位・同期文化・4月入社を前提とした運用 |
日本で新卒一括採用が定着した背景と歴史
新卒一括採用は、高度経済成長期の労働力確保と終身雇用制度の定着を背景に発展しました。戦後の労働市場では、企業が若手人材を一括で獲得し、長期的に育成・雇用することで組織の安定を図るという発想が支配的でした。
大学卒業と同時に「正社員」として入社することが社会的にも一般化し、企業と学校が協力してこのモデルを支えてきた歴史があります。年功序列やメンバーシップ型雇用と密接に結びついており、制度的にも慣習的にも根深く日本企業に根付いてきました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定着の背景 | 終身雇用・年功序列・高度経済成長 |
| 主な特徴 | 一括入社→長期雇用を前提とした人材育成 |
| 制度的根拠 | 法律ではなく企業慣習と教育現場の連携による |
海外との比較から見える日本特有の採用文化
日本の新卒一括採用は、海外と比べて非常にユニークな仕組みです。欧米では職務内容やポジションに応じて個別に採用する「ジョブ型」が一般的であり、卒業後に数年の空白があってもキャリア構築に支障が出ることは少ないのが特徴です。
一方、日本では卒業後すぐに正社員として就職することが常識とされ、タイミングを逃すと「新卒扱い」されなくなることもあります。こうした文化は学生に強い時間的プレッシャーを与えるとともに、企業にとっても画一的な採用設計を強いてきました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 海外の主流 | ジョブ型・職務別採用が一般的 |
| 日本との違い | 卒業時期と採用タイミングが連動している |
| 影響 | 学生も企業も採用活動に時間的制約を受けやすい |
新卒一括採用の課題と制度的変化の背景

- 企業が学生一人ひとりの就活時期を考慮した採用スケジュールを組むことができない
- 新卒一括採用ルール自体が形骸化している
- 新卒一括採用と関連性の深い「終身雇用」「年功序列」が崩れ始めている
- 学生の就活行動の変化(早期化・分散化)
①企業が学生一人ひとりの就活時期を考慮した採用スケジュールを組むことができない
新卒一括採用では、毎年採用スケジュールが決められており、応募期間も限定的であるため、そのスケジュールに合わせられない学生は、応募の機会を逃してしまうことになります。
例えば、下記のような学生です。
- 海外留学中で就職活動に参加できない
- 海外の大学に通っていて、卒業時期(9月)が4月入社の条件に合わない
- 病気などのやむを得ない事情で、新卒一括採用の時期に就職活動を行えない
そもそも海外では、自分のタイミングで就職活動をするのが一般的であるため、海外留学自体が、在学中に就職活動をすることを前提としている新卒一括採用と相性があまりよくありません。
どれだけ優秀であっても、年に1度のタイミングに合わせられなかったというだけで、その学生は応募の機会を得ることができず、企業からすると、その優秀な学生を逃がしてしまうことになるのです。
②就活ルール自体が形骸化している
政府や経団連はこれまで、在学時の就職活動による学業への悪影響を軽減させるために、「選考活動開始時期を遅らせる」「説明会や面接を解禁する時期をそろえる」といった就活ルールを定めてきました。
しかし、経団連非加盟の外資系企業やベンチャー企業はルールに縛られない独自の採用手法をとっていること、経団連加盟企業がルールを破っても特に罰則などはないこと、といったことから「ルールこそあるものの形骸化している」のが実態です。
また正式な選考・面接とはしていなくても、面談という形式で早期に学生に接触するリクルーター制度、実質的な採用活動そのものとなっているインターンシップ、といった採用活動を早期化している企業は増加傾向にあります。
このように就活ルールは形骸化されており、それに伴って、新卒一括採用のあり方も見直すべきではないか、と議論を呼んでいます。
③新卒一括採用と関連性の深い「終身雇用」「年功序列」が崩れ始めている
新卒一括採用は、「終身雇用」「年功序列」といった日本の雇用システムと深い関連性があるとされています。
即戦力を目的とする中途採用でなく、新卒採用を毎年実施する目的には、「組織の活性化」「企業理念の浸透や文化・風土づくり」といったものがありますが、これらを達成するには「長期的な教育」が必要となります。
さらにその長期的な教育を支え続けるために「終身雇用」が条件として置かれ、毎年一定数の新卒グループが入ってくる前提のもと、新卒教育システムを成立しやすくするために「年功序列」が必要とされるのです。
3〜5年ごとに実施されるジョブローテーションなども終身雇用(もしくは長期的な雇用)を前提とした教育システムの一環です。
このように新卒一括採用の目的は、「終身雇用」「年功序列」などに見られるような長期雇用ありきで考えられていました。
しかし、現代は、労働力人口の減少やテクノロジーの発展による経験・スキルの陳腐化によって「年功序列」が成立しづらくなり、キャリアアップのために数年単位で転職することも珍しくなくなりました。
また「終身雇用」を約束しないとする大手企業も出てきています。
これまで新卒一括採用と深い関連性があり、日本の雇用システムの柱とも考えられていた「終身雇用」「年功序列」が崩れ始めたことで、「新卒一括採用も機能しなくなるのでは?」という懸念が広がっているのです。
④学生の就活行動の変化(早期化・分散化)
学生の就活行動は「早期化」と「分散化」が進んでいます。インターンを通じて大学3年の夏から企業選定を始めるケースが増え、従来の「説明会→選考→内定」という一律フローは崩れつつあります。
さらに、ナビサイトだけでなくSNSやスカウト型サービスの活用が浸透し、情報収集チャネルも多様化しました。企業としては、画一的な一括採用モデルだけでは接点を持ちきれず、接点の早期化+複線化が鍵となります。人事施策にも「早めに仕掛け、継続的に関係構築する」という視点が不可欠です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 就活の変化 | 学生の動きが早期化・分散化 |
| 主な要因 | インターン重視・SNS/スカウト利用 |
| 必要な対応 | 複数チャネルでの早期アプローチ設計 |
新卒一括採用を実施する企業が活かすべき4つの機能的特徴

一方で、経団連加盟・非加盟に関わらず、新卒一括採用がうまく機能しているという企業もあります。
そういった企業は、次に挙げられる新卒一括採用の特徴を効果的に機能させ、上記で問題視されている部分もうまく解消できていると考えられます。
- 多くの学生に対して一斉にアプローチを行える
- 採用活動に必要なリソースを最小限に抑えられる
- 新入社員の教育コストを削減できる
- 新卒採用のノウハウが蓄積しやすい
詳しく見ていきましょう。
①多くの学生に対して一斉にアプローチを行える
情報収集、エントリー先の検討など、学生は就活解禁日から一斉に動き始めます。
学生の就活に対する意識が高まっているタイミングに合わせて、企業は採用競合と並んで一斉に多くの学生にアプローチを行うことができます。
景気や時期、職種によってばらつきがある中途採用と違って、新卒採用は、採用力さえあれば、企業が安定して人員を確保するのには適した市場です。
たとえ中小企業であっても、入念な戦略とそれに伴う採用力があれば、採用目標を達成することは可能です。
加えて、教育体制も整っているのであれば、決まった時期にまとまった人数を確保できる新卒一括採用は、その企業にとって適した採用手法の1つと言えるでしょう。
②採用活動に必要なリソースを最小限に抑えられる
新卒一括採用では、毎年採用時期が決まっており、説明会、試験の実施、面接、内定通知などの時期は年に1度しか訪れません。
よって、それらにかかる人事部や採用担当への負担を最小限に抑えることができています。
逆に言うと、年間を通して採用活動を行えるだけのリソースのない中小企業は、新卒一括採用によって、時期や採用コストを絞った採用活動ができているということになります。
③新入社員の教育コストを削減できる
就労経験のない新卒学生を雇用するということは、中長期的な教育を行って、将来的に活躍する人材を育てていくということです。
研修計画や場所の確保、教育上長の決定、研修前後の評価など、新卒一人当たりにかかる教育コストは決して安いものではありません。
しかし新卒一括採用によって、新入社員が全員同じ時期に入社することで、新入社員研修やその後の教育カリキュラムも入社年度ごとに一括で行うことができ、教育コストをおさえることができます。
④新卒採用のノウハウが蓄積しやすい
毎年同じ時期に一定の新卒採用を行うということは、どの時期に、誰が、どんな動きをして、結果として何が得られたかの推移が明確に表れやすく、人事の採用戦略に活かしやすいということです。
採用活動を定量的に分析・評価し、各フェーズの課題を抽出・改善策の実行を繰り返すことで、新卒採用におけるノウハウを蓄積しやすく、効率的な採用活動のレベルアップが可能となります。

今後予想される企業の動き【中小企業はどうする?】

では、今後、就活ルールが廃止・新ルールに変更されると、企業はどのような採用活動にシフトするのでしょうか。
ここまでお話してきたように、新卒一括採用には多くのメリットがあるので、就活ルールを廃止した結果、採用トレンドが全体的に通年採用に移行するわけではありません。
現状では、下記2パターンの企業の動きに分けられます。
- もともと新卒一括採用以外も取り入れた採用活動を実施している企業
- 新卒一括採用に限定して採用活動を実施している企業
それぞれの企業について、今後予想される動きを以下考察します。
①もともと新卒一括採用以外も取り入れた採用活動を実施している企業の動き
経団連に加盟していないIT企業や外資系企業は、もともとルールに縛られない採用活動を行っているところもあります。
ただし、これまでは経団連が定める選考解禁時期や大手の採用競合のスケジュールという目安があったため、それを基準にして本格始動の時期や選考のタイミングをズラすことができたとも言えます。
また一部の大手企業は、通年採用(年間採用)を一部の職種で実施しているところもあり、経過を見て総合職へも広げていく見込みです。
②新卒一括採用に限定して採用活動を実施している企業の動き
一方、現状で新卒一括採用に限定して採用活動を行っている企業は、就活ルールが廃止され、通年採用が普及して行った場合に、幅広い採用時期への対応を検討する必要性が生じます。
採用活動期間を拡張させる方向へ→通年採用の検討
現在の新卒採用市場には、採用活動の早期化と長期化のトレンドがあります。
採用競合よりも早い段階で学生にアプローチをかけようとインターンシップの導入が普及し、冬のインターン導入企業の増加に伴って、それよりも早い夏に実施する企業も増えてきました。
しかし、「ただ早くすれば欲しい学生を採用できる」ではなく、企業は「就活ルールが廃止になったら、新卒一括採用のみに限定するのではなく、それに加えて採用時期を拡張するような通年採用も検討するべきか?何か他に競合と差を付けられる手法はないか?」と模索しているのです。
これまで通りの新卒一括採用を続ける:最善の選択肢となるか唯一の選択肢となるかの2パターン
また、今後も新卒一括採用を続ける意向を示している企業もあります。
それは下記2パターンに分かれます。
- 現状で就活ルールに基づいた新卒一括採用がうまく機能し、毎年一定数の新卒を確保できている企業
- 採用活動に割けるリソースを考えると、通年採用を実施する選択肢がない企業
うまく機能しているものに、わざわざ変化を加えたくないという前者に対し、後者は、本当は通年採用にも取り組みたいけど、リソースの関係上、当面は新卒一括採用のみを続けるしかないという企業です。
中小企業は、総務・経理・人事を兼務している場合も少なくなく、「時期を絞っても採用期間中は負担が大きいのに、1年中採用活動を行うなんてとんでもない。」などリソースの都合が付きにくい苦労が考えられます。
同じ新卒一括採用で中小企業がブランド力のある大手企業と対峙するための2つの対策

前述したように、就活ルールに基づいた新卒一括採用が効果的に機能している企業は、その特徴をしっかりと理解し、適切に活かすことができています。
ネームバリューこそ大手に劣るものの、中小企業であっても入念に戦略を立てれば、新卒一括採用で採用目標を達成することが可能です。
具体的な対策としては下記2つが挙げられます。
- 採用選考時期を競合大手企業とズラす
- 企業から会いに行く採用活動をする
新卒一括採用の事前戦略:まずはターゲットを明確にする
選考時期を大手とズラすにも、会いに行くにも、ターゲットを明確にしないことには採用戦略を立てることができません。
- ターゲットは企業に何を求めているのか、またどんなことを懸念しているか
- ターゲットに会うために何をすればいいのか
- ターゲットはどこでどういう活動しているのか
- ターゲットにどんなメッセージを送ればいいのか
以上のように、全ての採用計画において、ターゲットを軸に戦略やスケジュールを立てていきます。
中小企業の新卒一括採用① 採用選考時期を競合大手企業とズラす
採用活動にかけるリソースの関係上、時期を決めて動くしかない中小企業が大手企業に対峙するには、「採用選考時期をズラす」という方法があります。つまり直接的な対峙を避けるという方法です。
これは、「大手企業の選考で不採用になった自社にとって採用したい学生」を狙うという戦略の下、大手企業の選考期間よりも少しだけ後ろ倒しにするのが一般的です。
もし大手企業より前倒しのスケジュールを組んで早く内定を出しても、その後に大手企業の選考が終わるまではキャンセルが出るかもしれませんし、内定者フォローもその分長引いてしまいます。
採用のマンパワーが十分でない企業は、大手企業よりも選考時期を後ろにズラす方が、採用担当の負荷は少なくて済みます。
中小企業の新卒一括採用対策② 企業から会いに行く採用活動をする
こちらは企業自らが積極的に学生に声をかけて、学生を口説き落とすという、大手企業との対峙回避とは異なる攻めのアプローチです。
企業から学生を検索して見つけ出すには、例えば以下のような方法が考えられます。
- 合同説明会などでターゲットに近い学生に直接声をかける
- 就活ツイッターなどのSNSで企業から学生を検索する
- 研究室訪問や大学OBの派遣(理系学生対象)
- 人材紹介サービスの利用
- ダイレクトリクルーティングサービスの利用
大手企業の場合は、上記の他にインターンシップで学生と早期に接触していたり、企業PR用のSNSアカウントなどで情報発信を頻繁に行っていたり、多様な取り組みもしている可能性が高いです。
採用活動全体にかけられるリソースが少ない中小企業は、ターゲットを絞り込むなどして、一人ひとりと濃密なコミュニケーションを取って、自社に振り向かせるといった工夫も必要になってくるでしょう。
自社に合った採用手法を選ぶための判断フレーム

採用の手法は「どれが流行っているか」ではなく、「自社にとって成果につながるか」で選ぶべきです。特に新卒一括採用が過渡期にある今、企業には自らの採用目的や体制を再定義し、最適な手法を主体的に選ぶ力が求められます。
本章では、自社の採用目標と言語化、組織特性と手法の適合性、手法選定のための判断軸などを、実務に直結する視点から整理します。迷いがちな採用方針を、論理的かつ納得感のある形で決定するヒントになるでしょう。
自社の採用目標と人材要件を言語化する
適切な採用手法を選ぶには、まず「何のために採用するのか」「どのような人材を求めているのか」を明確にする必要があります。
たとえば「将来の幹部候補を育成したい」のか「即戦力が必要なのか」で選ぶ手法は異なります。採用目標と人材要件が曖昧なままだと、手法の検討も表面的になりがちです。採用計画の出発点は、「成果を出す人材はどういう人物か?」という問いに対し、スキル・価値観・成長性の3軸で明確な言語化を行うことです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出発点 | 採用の目的・期待役割を明確にする |
| 言語化すべき要素 | スキル・価値観・ポテンシャル |
| 効果 | 採用手法やチャネル選定の軸がぶれなくなる |
新卒一括採用がフィットする組織としない組織の特徴
新卒一括採用が機能するのは、教育リソースが豊富で、長期育成を前提とした人事戦略を持つ組織です。明確な研修制度や配属計画、キャリアパスが用意されている場合には、ポテンシャル重視の新卒採用が有効に機能します。
一方で、即戦力が求められるポジションや小規模で人事制度が未整備な組織では、通年採用や中途採用、スカウト型採用の方が合理的です。組織規模や育成力、業種特性によって「合う・合わない」がはっきり分かれるのが新卒一括採用です。
| 項目 | 合う組織 | 合わない組織 |
|---|---|---|
| 組織規模 | 中堅〜大手企業 |
小規模・ベンチャー企業 |
| 人材戦略 | 長期育成・研修重視 |
即戦力重視・実務優先 |
| 採用力 | 体制が整っている |
現場依存・属人的になりがち |
自社に最適な採用手法を選ぶための判断基準
自社にとって最適な採用手法を選ぶには、「採用目的」「必要人材のタイプ」「社内の受け入れ体制」「採用リードタイム」の4点から評価すると整理しやすくなります。
例えば短期間で即戦力が欲しいなら中途採用やリファラルが適し、文化適応重視なら新卒採用+長期インターンが効果的です。大切なのは「他社がやっているから」ではなく、「自社にとって成果に直結するかどうか」という軸で冷静に手法を選択することです。
| 判断軸 | 選定ポイント |
|---|---|
| 採用目的 | 育成前提か、即戦力か |
| 必要な人材タイプ | 技術職、営業職、文化適応重視など |
| 社内体制 | 教育制度の有無、受け入れ余力 |
| 緊急性 | すぐに欲しいか、余裕を持って採用できるか |
新卒一括採用の是非は自社の新卒採用目標に立ち返って考えよう
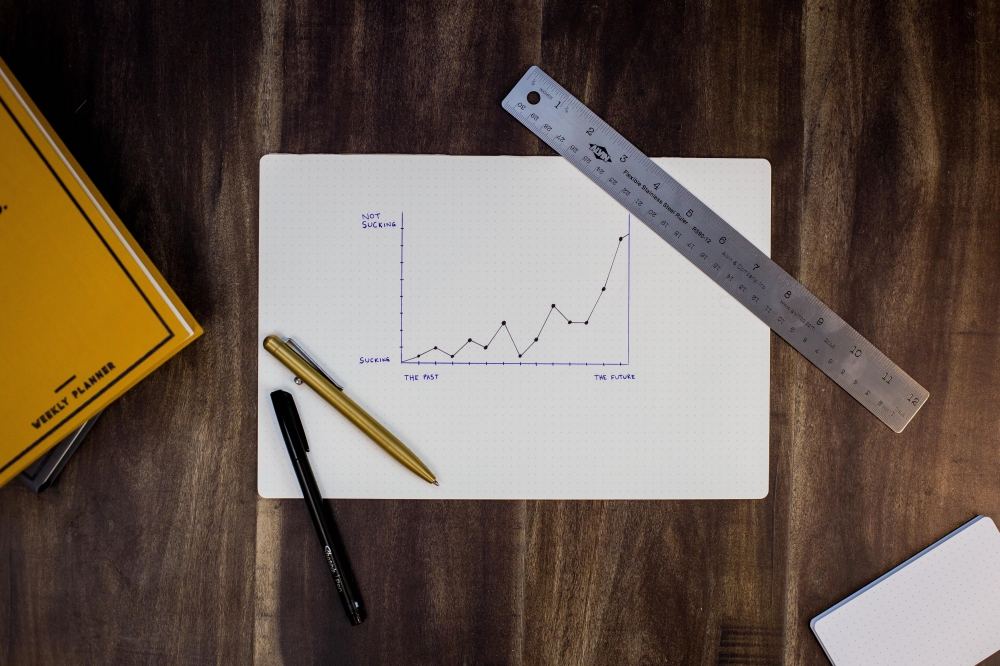
今回のポイントをまとめます。
- 現状ではほとんどの企業が新卒一括採用を実施している
- 新卒一括採用が廃止される背景の1つに、就活ルールが形骸化されているところがある
- 新卒一括採用は「終身雇用」「年功序列」といった日本の雇用システムと相関性がある
- 新卒一括採用の特徴を理解し、うまく機能させて、毎年一定数の新卒を確保できている企業もある
- 中小企業は、通年採用を取り入れたくても、リソースの関係上、現実的には新卒一括採用に限定して続けるしかないという実情がある
- 同じ新卒一括採用でも戦略次第では、中小企業がブランド力のある大手に対峙することも可能
近年、採用活動期間が長期化し、採用手法が多様化してきているとは言え、ほとんどの企業が新卒一括採用の考え方をベースとした採用戦略を取っています。
新卒一括採用が是か非かという議論は長年にわたって続けられてきましたが、新卒一括採用が善か悪かと単純に考えるのではなく、何が問題視されていて課題はどこにあるのかという点を、まず整理することが重要です。
そもそも「自社が新卒採用に求めているものは何なのか?」というところに立ち返って、それが新卒一括採用で達成されるのか?というところに焦点をあてて、今後の新卒一括採用の採否を考えてみてはいかがでしょうか。
最新の採用市場動向が知りたい人事・採用担当者の方には、こちらの資料もおすすめです。ダウンロードしてご活用ください。