
就職活動のスタートとして、インターンシップに参加する学生は年々増えています。近年では、インターンシップの認知度や重要性が増し、1,2年生から参加する学生も少なくありません。
このようにインターンシップが「当たり前」になりつつある一方で、「インターンシップにはどんな種類があるのか」「なぜ参加したほうがよいのか」「どうやって探せばいいのか」疑問に思う学生も多いです。
この記事では、インターンシップに関する情報をまとめました。開催時期や開催期間、2028卒のインターンシップの開催スケジュールなども紹介しています。
さらに、2022年4月に決められた、2025卒から始まったインターンシップの変更点についても解説しているので、インターンシップの情報を整理したい方は参考にしてみてください。
OfferBoxは、就活生の約24万人(※1)に利用されている新卒逆求人サービスです。 プロフィールを見て、あなたに興味を持った企業から直接オファーが届くので、効率よくインターンシップを探すことができます。 また、累計登録企業数は約20,423社(※2)で、大手から中小・ベンチャー企業まで幅広い企業に登録されています。 ぜひ、ご活用ください。
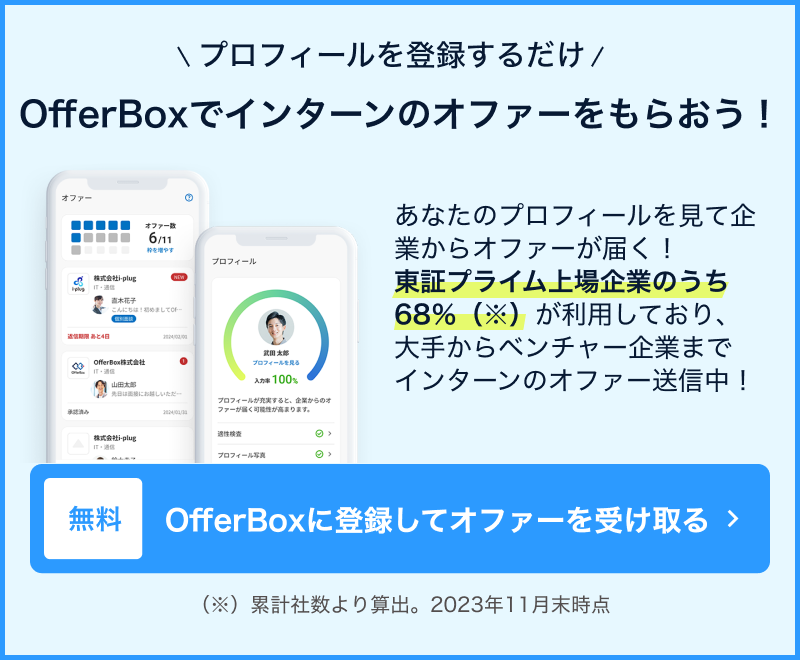
(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより
(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)
目次
就活のインターンシップとは?
インターンシップとは、「就業体験の場」です。
学生はインターンシップを経験することにより、その職業のスキルの一部を会得したり、知識を深めたりすることができます。
近年は、インターンシップも多様化しており、職業体験だけでなく、企業を知るための説明会や面接対策などのコンテンツで実施する企業も増えています。
いずれのインターンシップも、一般的には「就業体験の場」として位置づけられています。
インターンシップとアルバイトの違い
特に長期のインターンシップは、有給のケースが多いです。その場合、「アルバイトと何が違うの?」と思われる方もいるでしょう。
1番の大きな違いは、「企業側の目的」です。
企業側のインターンシップの目的
- 優秀な学生と早期接触・選考したい学生と早期に接触すること
- 業界・企業の魅力を伝えたい学生に企業理解、職種理解を深めてもらうこと
- 学生との相互理解を深めたい企業が学生を理解し、自社にマッチするか見極めること
- 学生のスキルアップを促し即戦力化したい
企業側のアルバイトの目的
- 必要な業務をしてもらうこと
2025卒から採用直結インターンが解禁に
2025年卒からは、採用直結インターンシップ(インターンシップ時の学生情報の本選考利用)が認められるようになりました。
以前からも、一部インターンシップは採用選考に組み込まれていたのが実態ですが、公認されたことで、より企業の採用につなげる場としての意味合いが強くなっている傾向があります。3年生のサマーインターンシップが就活のスタート地点と考え、それに向けて準備を進めていきましょう。
また、5日間以上のインターンシップについては、募集時に産学協議会で定められた基準を満たしていることを表す「産学協議会基準準拠マーク」を記載できるようになったため、今後は大手企業を中心に5日間以上のインターンシップが増えると見込まれています。
以前よりインターンシップにかかる時間も増えるため、学業と就活を両立できるようスケジュールを調整しておきましょう。
インターンシップへの参加は就活で有利になる?
先述した通り、インターンシップの重要性はますます高まっており、多くの企業が採用活動の一環として位置付けています。特に早期選考を実施する企業では、インターンシップ参加者が本選考で優遇されるケースもあるため、積極的に参加しておくべきといえるでしょう。
インターンシップを通じて企業の業務を体験するとともに、文面の募集要項では分からない企業の雰囲気をつかむことができるため、企業への理解度が増します。
また、志望度の高さをアピールすることにもつながるため、就活を有利に進める手段として参加することがおすすめです。
「OfferBox(オファーボックス)」ならインターンシップのオファーも届く
インターンシップの探し方に悩んでいる人には、逆求人型の就活サービス「OfferBox(オファーボックス)」の活用がおすすめです。登録したプロフィールをもとに企業側からオファーが届く仕組みになっており、就活生の約24万人(※)が利用しています。
「OfferBox」はインターンシップのオファーも流通しています。自らナビサイト等でインターンシップ先を探しつつ、同時にOfferBoxなどの逆求人型サービスに登録して企業からのオファーを受け取ると、効率的にインターンシップ先を見つけることができるでしょう。
「OfferBox」は完全無料で使えるので、ぜひ活用してみてください。
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
(※)OfferBox 2024年卒利用実績データより
インターンシップで給料は発生する?
インターンシップには「無給」と「有給」の2種類があり、プログラムの内容や期間によって給料の有無が異なります。1dayや短期インターンなど業界説明や職場見学を目的としたものは基本的に無給です。
一方、3ヶ月以上の長期インターンや実務に深く関わる内容のインターンでは、アルバイト契約を結び、時給制で給料が支払われるケースもあります。応募時には募集要項をよく確認しましょう。
インターンシップに参加するメリット
インターンシップは就活を有利に進めるだけでなく、自分に合った企業や仕事を見極める機会ともいえます。実際の業務を体験することで企業理解を深めたり、ビジネススキルを身につけたりと多くのメリットがあります。
業界・企業理解
インターンシップに参加することで、業界全体の動向や各企業のビジネスモデル、事業戦略について深く学ぶことができます。企業のWebサイトや説明会では知ることができない、実際の職場の雰囲気や社員の働き方を直接体感できる点も大きなメリットです。
さらに、複数の企業のインターンに参加することで、それぞれの企業の違いや特徴を比較し、より自分に合った企業を選ぶ材料になります。
ビジネススキルを学べる
インターンシップでは、社会人としての基本的なマナーやコミュニケーション能力、プレゼンテーションスキルなど、実際の業務を通じてさまざまなビジネススキルを身につけることができます。
特に、グループワークやプロジェクト型のインターンでは、課題解決能力やチームワークの重要性を学ぶ機会が多く、就活だけでなく入社後の仕事にも役立つスキルを実践的に習得できるのがメリットです。
入社後のミスマッチを防止できる
就活では、基本的にナビサイトや企業のホームページ、や説明会を通じて情報を収集しますが、実際に働いてみると「思っていた環境と違った」と感じることも少なくありません。
インターンシップに参加することで、職場の雰囲気や働き方を直接体験できるため、入社後のギャップを抑えることができます。
また、自分がその企業で働くイメージを明確にできるため、より納得感を持って就職先を選択できますよ。
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
就活のインターンシップの種類

次にインターンシップには、どんな種類があるのかお伝えします。
期間で分けると、インターンシップは大きく3種類あります。
- 1dayインターンシップ
- 短期インターンシップ
- 長期インターンシップ
1dayインターンシップ
1〜3時間程度のインターンシップです。1dayインターンシップは、説明会やセミナーといった、企業側の話を聞くタイプのコンテンツのものが多いです。面接対策講座など、就職活動に役立つ知識を身につけられるものもあります。
応募試験は不要なものが多く、気軽に参加できるのが特徴です。まずはさまざまな業界・企業のインターンシップに参加してみたい人におすすめです。
短期インターンシップ
短期・長期の具体的な定義はありませんが、1週間から長くて1ヶ月程度のものが多いです。学校の長期休みの期間に開催されることが多く、1日の拘束時間も比較的長めです。
グループワークなどを通して、その企業の業務に関した、何かしらの課題を解決するようなコンテンツが多いです。
参加人数枠にもよりますが、応募試験はあることが多いです。本選考との関係性も強いケースが多いため、志望業界が決まっている人におすすめです。
長期インターンシップ
1ヶ月以上のものが多いです。大半の企業では、アルバイトのように、参加日程を企業と個別に調整できます。
実際の仕事の現場に入り、社員と肩を並べて、業務の一部を任されるコンテンツが多いです。1day、短期インターンシップとの大きな違いとして、大抵の場合、給与が支払われます。
参加人数枠は少ないため、応募試験は大抵あります。また、本選考との関係性もとても強いです。
志望度が高い人だけでなく、スキルを身につけたいという人にもおすすめです。ただし、拘束時間が長いため、ほかのインターンシップと並行して参加するのが難しいこともあります。
1day/短期インターンシップは主に3年生から
1day/短期インターンシップは企業の採用活動の色合いが強く、就活が本格化する大学3年生から開催され始める傾向にあります。学業と就活の両立で忙しい3・4年生が対象だと、長期よりも1day/短期のほうが参加率が上がるためです。
ただ、中には1・2年生でも参加できる1day/短期インターンシップもあります。インターンシップの種類によって参加のメリットは異なるので、自分の目的に合ったインターンシップに参加してみてください。
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
就活のインターンシップの開催時期・参加時期
インターンシップは大学の長期休暇に合わせて開催する企業がほとんどですが、なかには独自の日程で開催している企業もあります。
「いざ参加しようと思ったら既に終了していた」という失敗を避けるためにも、興味がある企業のインターンシップの開催時期と募集時期はしっかりと把握しておきましょう。
サマーインターンシップ(8、9月)
まずは、サマーインターンシップの参加メリットやスケジュールについてお伝えします。
初めてインターンシップに参加する学生が多いのが、夏季休暇に開催されるインターンシップです。サマーインターンシップで「就活を始める」という学生も少なくありません。
選考要素の少ないインターンシップが数多く開催されるのが特徴です。
サマーインターンシップに参加するメリット
- さまざまな企業、業界を効率的に知ることができ、志望業界を定められる
- 就職活動のコンテンツや、ほかの就活生を知ることで、頭が「就活モード」に切り替わる
- 企業との早期接触ができる
2028年新卒のサマーインターンシップのスケジュール
インターンシップの開催時期、応募時期は企業により異なります。以下は、大枠のスケジュールとなります。
2026年4~5月:サマーインターンシップの情報が公開。早い企業では募集開始・エントリーシート(ES)提出
2026年6月:本格的にインターンシップの募集開始・ES提出
2026年7月:参加選考
2026年8〜9月:インターンシップ開催
内閣府による調査結果を見ても、大学3年生や大学院1年生の夏休みにあたる7〜9月に参加する学生が最も多く、就活の第一歩として多くの人がサマーインターンからスタートしていることがわかります。
(引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」 インターンシップの参加時期)
秋・冬インターンシップ(10~2月)
次に、秋・冬に開催されるインターンシップについて説明します。
こちらは主に、夏季休暇後から年明けにかけて開催されるインターンシップを指します。
秋・冬インターンシップを開催する企業は、学生が既に何かしらのサマーインターンシップに参加したことがあり、ある程度志望業界を絞っていることを想定しています。
そのため、より実務的なコンテンツや本選考との関係性が強いものが多いです。
秋・冬インターンシップに参加するメリット
- 夏に接点が持てなかった業界・企業と、本選考前に接点が持てる
- サマーインターンシップに比べて選考の意味合いが強く、本選考に有利なことがある
- 実務に近い経験ができるものが多く、業務イメージを把握しやすい
2028年新卒の秋・冬インターンシップのスケジュール
こちらもサマーインターンシップと同様に、開催時期、応募時期は企業により異なります。
2026年9〜10月:募集開始・ES提出、参加選考
2026年10月〜12月:インターンシップ開催
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
インターンシップの目的
学生と同様に、企業にももちろん、インターンシップの目的があります。主には以下の4種類です。
- 優秀な学生と早期接触・選考したい
- 業界・企業の魅力を伝えたい
- 学生との相互理解を深めたい
- 学生のスキルアップを促し即戦力化したい
それでは、それぞれの目的について解説していきます。
優秀な学生と早期接触・選考したい
少しでも早く優秀な学生と接触し、選考につなげる目的があります。実際に学生の人柄や能力を評価するのは本選考が始まってからですが、採用試験だけでは学生が持つ魅力をほとんど見極められません。
そのため、インターンシップ中の働きぶりや、周囲との関係性の築き方から将来有望な人材を見極めようとしているのです。2025卒から採用直結インターンが解禁されることで、今後はより早期接触・選考する目的が強くなっていくでしょう。
業界・企業の魅力を伝えたい
ホームページや就活ナビサイトだけでは伝えきれない、自社の魅力を伝えることが目的です。学生にとってイメージがしづらいBtoBのビジネスモデルの企業は、この目的のためにインターンシップを開催することが多いです。
具体的な事業内容や、実際の会社の雰囲気など、文字だと伝わりづらいことをインターンシップを通じて知ってもらいたいと考えています。
学生との相互理解を深めたい
自社のことを知ってもらうだけでなく、参加してくれた学生のことを知ることも目的です。「学生は自社のどんな部分に興味を持ってくれているのか?」といった、学生目線を知るだけでなく、参加学生との個々の相性や適性も見ています。
説明会よりも、互いに意見交換のできるワークショップ形式のインターンシップには、特にこうした目的があります。
学生のスキルアップを促し即戦力化したい
この目的を据えている企業の場合、インターンシップと本選考が密接に関係しているケースが多いです。インターンシップの種類としては、数ヶ月以上の長期インターンシップの一部などが該当します。
ぜひ入社して欲しい学生に、実際の業務に近い経験を積んでもらうことで、自社に対する理解を深めてもらうと同時に、入社後スムーズに仕事に馴染めるようになってもらうことが目的です。
これらの目的は、全て当てはまる企業もあれば、1点しか当てはまらない企業もあります。
企業ごとにインターンシップを開催する目的は異なります。
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
インターンシップの探し方
いざインターンシップに参加しようと思っても、どうやって探せばいいのか分からない人もいるかもしれません。そんな人には、就活サイトを使って情報を集める方法がおすすめです。
就活ナビサイト
開催時期はいつなのか、どんなインターンシップがあるのかなど、ひと通り情報を集めたい人には就活ナビサイトがおすすめです。就活ナビサイトとは、大企業から中小企業まで幅広い企業のインターンシップ情報を掲載しているサイトのことを指します。
広く情報が載っているため、あらゆるインターンシップの中から自分に合うものを探すことができます。また、インターンシップの選び方や応募方法など、就活に役立つ情報が載せられている点も就活ナビサイトの特徴です。
新卒オファー型就活サイト
まだ志望業界・企業が明確に決まってない人には、オファー型就活サイトがおすすめです。オファー型就活サイトの特徴は、プロフィールを載せることで自分に興味を持つ企業からオファーをもらえる点です。
就活ナビサイトのように自分から応募しなくても、企業のほうから声をかけてもらえる可能性があります。オファーをもらった企業の特徴から、自分に合う業界や職種を見つけられるのがオファー型就活サイトを利用するメリットです。
OfferBox(オファーボックス)に登録して、インターンシップのオファーを受け取ろう
新卒オファー型就活サイトの中でも、企業が丁寧にオファーを送ってくれるのが「OfferBox(オファーボックス)」です。
企業側は一斉送信ができない仕組みになっているため、1通ずつしかオファーを送ることができません。そのため企業は、1人ずつ丁寧にプロフィールを見て、自社のインターンシップに参加して欲しいか判断し、オファーを送ります。
OfferBoxは、大学3年生・大学院1年生の4月から、企業からのオファーを受け取ることが可能です。特に、6月から7月にかけてはサマーインターンシップのオファーが多く飛び交う傾向があります。
そのため、「まずはどんなインターンシップに参加したらいいかわからない」という人や、「インターンシップの探し方がわからない」という人には特におすすめです。
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
インターンシップの選び方
多くの企業がインターンシップを実施しているため、どのように就業先の企業を探せばいいのか迷ってしまう方も多いでしょう。
選び方のポイントとして「業界・企業」「実施期間」「プログラム内容」の3つの視点を意識することで、自分にとって有意義なインターンシップを見つけやすくなります。
興味のある業界・企業で選ぶ
まず、インターンシップを選ぶ際は、自分が興味のある業界や企業に注目しましょう。
インターンシップは実際にその業界や企業の業務を体験できる貴重な機会です。複数の企業のインターンシップに参加することで、それぞれの社風や働き方の違いを知り、自分に合った企業を見極めることができます。
また先述した通り、インターンシップ参加者向けの特別な選考ルートが用意されていることもあるため、志望企業のインターンシップには積極的に参加するとよいでしょう。
実施期間で選ぶ
インターンシップには、1日や数日間で完結する「短期インターンシップ」と、数週間から数カ月にわたって行われる「長期インターンシップ」があります。
短期インターンシップはさまざまな企業を比較しやすく、業界研究の一環として参加するのに適しています。
一方、長期インターンシップはより実践的な業務を経験できるため、仕事のリアルな部分を深く知れるのがメリット。自分のスケジュールや目的に合わせて、適した期間のインターンを選びましょう。
プログラム内容で選ぶ
インターンシップのプログラム内容は、企業ごとに大きく異なります。座学やワークショップ中心のもの、実際の業務に携われるもの、グループワークを通じて課題解決を行うものなど、さまざまです。
自身の目的に合わせ、成長につながるプログラムを選ぶことが重要です。例えば、ビジネススキルを磨きたいなら実践的な業務があるインターンシップを、業界全体の理解を深めたいなら座学やセミナーのものを選ぶといいでしょう。
>> 【無料】OfferBoxでインターンのオファーを受け取る
インターンシップの申し込み方法・選考方法
インターンシップに参加するには、まず基本の申し込み方法を理解し、企業ごとの選考フローに備えることが重要です。申し込み方法や選考内容は企業によって異なるため、募集要項をしっかり確認し、早めの行動を心がけましょう。ここでは、一般的な申し込み方法と選考方法について詳しくご紹介します。
インターンシップの申し込み方法
インターンシップの申し込みは、企業の採用ページや就活サイト、大学のキャリアセンターなどを通じて行います。エントリーには基本的に履歴書やエントリーシートの提出が必要で、申し込み受付は早い企業で4〜5月から始まることもあります。先着順で締め切られる場合もあるため、気になる企業はこまめにチェックし、早めに準備を始めましょう。
インターンシップの選考方法
インターンの選考は、書類審査のみの企業もあれば、適性検査や面接を実施する企業もあります。志望度が高い企業のインターンでは、エントリーシートや面接で熱意をしっかり伝えることが重要です。
企業によっては早期選考ルートに直結するケースもあるため、事前に過去の選考情報や体験談を確認しておくと安心です。応募準備には時間をかけましょう。
インターンシップ参加時に気をつけること
インターンシップでは、プログラムの成果やチームワークだけでなく、社会人としての基本的なマナーも見られています。どんなに短期間でも言動や態度には細心の注意が必要です。ここでは、参加時に特に気をつけたい3つのマナーについて紹介します。
時間厳守(遅刻しない)
インターンに限らず、時間を守ることは社会人の基本です。集合時間の10分前には到着するよう意識し、万が一遅れる場合はすぐに連絡を入れましょう。遅刻は信頼を大きく損なう原因になり、今後の選考にも影響することがあります。事前にアクセス方法を確認し、余裕をもって行動するよう心がけましょう。
服装・身だしなみを整える
インターン中の服装は、企業の指定がある場合はそれに従い、ない場合はスーツまたはオフィスカジュアルが基本です。清潔感のある髪型や爪の長さ、靴の状態まで気を配りましょう。
第一印象は見た目で決まることが多く、TPOに合った身だしなみは社会人としての基本マナーです。不安な場合は、企業の雰囲気を事前に調べておくと安心です。
参加後はお礼メールを送る
インターン終了後には、担当者や受け入れ企業にお礼のメールを送るのがマナーです。学んだことや感謝の気持ちを簡潔にまとめて伝えることで丁寧な印象を残せます。
お礼メールはできれば当日か翌日中に送り、ビジネスメールの形式に沿って作成しましょう。
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
インターンシップを就活で活かすコツ
インターンシップは企業の業務内容や社風を知るだけでなく、自分の強みを見つけたり、志望動機を明確にしたりする材料にもなります。せっかく参加するなら、その経験を最大限に活かしましょう。
ここでは、就活に役立てるためのポイントを解説します。
自分の強みや適性を再確認
インターンシップでは、実際の業務を通じて自分の得意なことや課題を発見することができます。例えば、チームワークが得意だと感じたなら「協調性」、課題解決が好きなら「問題解決力」など、自分の強みを具体的に整理してみましょう。
逆に苦手な部分が見えた場合は、今後の成長につなげるチャンスです。
インターンシップ中に得た気づきを振り返り、自己分析を深めることで、より自分に合った企業や職種を見極めることができますよ。
己分析を行うなら、自己分析・適性診断ツール「AnalyzeU+」の活用もおすすめです。設問に回答することで、自分の強みや価値観、考え方の傾向を診断できます。約100万人のデータに基づいた精度の高い診断結果が出るため、客観的な自分の強みや弱みなどを知りたい人におすすめのツールです。
自己PRや志望動機へ活用
インターンシップでの経験は、エントリーシートや面接での自己PRや志望動機の根拠として活用できます。「〇〇のインターンで△△の業務を経験し、自分には□□のスキルがあると実感した」など、具体的なエピソードを交えることで説得力が増します。
また、インターンシップを通じてその企業や業界への理解が深まったことを伝えれば、志望度の高さが伝わるでしょう。事前に振り返りを行い、自分の成長や学びを明確にしておくことが大切です。
>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る
就活のインターンシップに関するよくある質問
インターンシップの重要性が増している中で、多くの学生が「参加しないと不利になるのか」「何社参加すればよいのか」など、さまざまな疑問を抱えています。
ここでは、就活生が特に気になるインターンシップに関する質問について詳しく解説します。
インターンに参加していないと就活で不利になる?
インターンシップに参加していなくても、就活では十分に戦えます。
しかし、近年ではインターンシップを開催する企業が増えていたり、参加することで特別選考に進めたりとインターンシップに対する重要性が高まっていることは頭に入れておき、なるべく計画的に参加するようにしましょう。
インターンに参加していない場合でも、学業やアルバイト、サークル活動などの経験を通じて得たスキルを自己PRに活かせます。大切なのは、インターンの有無ではなく、「自身の経験をいかに就活に結びつけられるか」です。企業が求める人材像を意識しながら、自分の強みを明確に伝えられるよう準備しましょう。
インターンシップに行かないのもアリ?
他に取り組んでいること、熱中していることがあれば行かないのもOKです。ただし、「面倒くさい」「参加しても意味なさそう」といった理由で参加しないのはやめましょう。
インターンシップは企業や業務への理解を深めるいい機会なので、基本的には少しでも興味が持てるものは参加することをおすすめします。
インターンシップに行ってないけどどうしたらいい?
1dayインターンシップのような参加のハードルが低いものでもいいので、参加してみましょう。就活の遅い段階でなかなか時間を確保できない場合でも、1日で終わるインターンシップなら気軽に参加できるはずです。
まだ志望業界・企業が決まっておらず、自分に合ったインターンシップを探すのが難しい場合は、オファーをもらった企業に行ってみるのもおすすめです。それまで興味を持っていなかった企業でも、インターンシップをきっかけに興味が生まれることもあります。
インターンシップは髪色自由?
髪色は特に指定がない場合がほとんどですが、ビジネスの場に適した身なりで参加することをおすすめします。就業体験の場といっても、採用活動の一環として実施されるイベントであることには変わりありません。
特にインターンシップが本選考に影響する度合いは年々高まっているため、既に選考は始まっていると考え、身なりにもしっかりと気を配りましょう。金や赤のような派手な髪色は避けるのが無難です。
インターンシップは何社受けたらいい?
特に行くべき社数は決まっていません。自分のスケジュールと相談しながら、参加するインターンシップを選びましょう。
1社だけでは比較検討ができないため、目安として10社ほど参加してみるとかなり企業ごとの違いが見えてきます。参加できそうであれば、数多く応募してみましょう。
長期インターンシップは3社、1day/短期インターンシップは7社といったように設定するなど、無理のない範囲で興味のある企業のインターンシップに参加してみてください。
まとめ
以上、インターンシップの目的やスケジュールについて解説しました。
インターンシップの開催が活発化するのは大学3年生の夏頃からですが、なかには1・2年生の頃から参加できるものもあります。
参加が早ければ早いほど将来のことを考える時間を確保できるので、時間に余裕のある1・2年生の頃から積極的に参加することをおすすめします。
まだ志望業界・企業が決まってない場合は、オファー型就活サイトを利用してインターンシップを探す方法もあります。
「志望業界・企業が決まっていない自分にはまだ早い」などと考えず、本格的な就活解禁に向けて早めの準備に取りかかりましょう。


