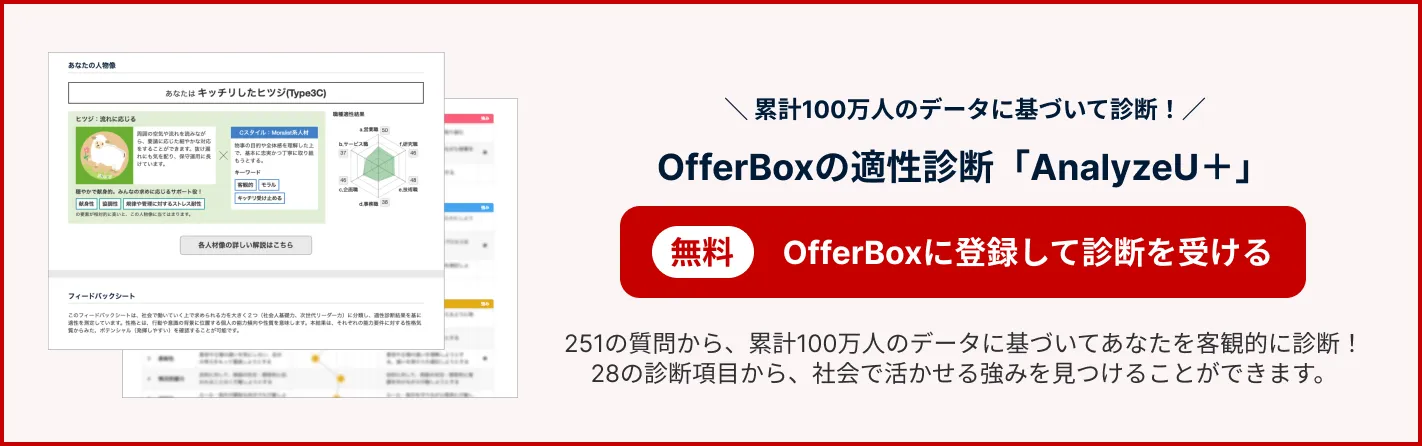「就活では何社エントリーすればいいの?」と不安を感じる学生は多いでしょう。特に文系・理系を問わず、周りの学生がどれくらい応募しているのか気になるものです。
この記事では、まず周りの就活生がどれくらい選考に応募しているかの指標となる「平均エントリー数」を紹介します。
さらに文系・理系で平均エントリー数に差がある理由、ベストな選考数など就活を成功に導く上で知っておくべき内容を解説していきます。
OfferBoxは、就活生の約24万人(※1)に利用されている新卒逆求人サービスです。
OfferBoxに登録するプロフィールや自己PRがES(エントリーシート)の代わりになるため、効率的に就活を進めることができます。
また、累計登録企業数は約20,423社(※2)で、大手から中小・ベンチャー企業まで幅広い企業に登録されていることも特徴です。
効率的に就活を進めたい方は、ぜひ活用してみてください。
(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより
(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)
目次
就活では何社受ける?平均エントリー数
大学生の就活で何社受けるべきかは、学部や専攻、希望業界によっても変わります。周りの就活生が平均何社にエントリーしているかを知ることで、自分自身の就活に対する向き合い方を理解できます。
平均エントリー数に比べて極端に少なければ、もう少し就活に時間を費やさなければいけませんし、多くの企業と接点を持てるように努力する必要があるでしょう。
内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」(2024年発表)によると、2023年度の大学4年生のエントリーシート提出数は「10~19社」が最も多く、全体の約3割を占めています。
同様に平均エントリー数が10社以下の割合も多いですが、30社以上受けている就活生も2割程度いることも分かります。
以上のことから、ライバルとなる多くの就活生がいる中、希望の企業から内定を獲得する可能性を上げるには、エントリー数20社以上を視野に入れる必要があるでしょう。文系と理系で平均エントリー数に差はある?
文系と理系の平均エントリー数を比較すると、文系の方が多い傾向があります。理由としては、理系が専門スキル・知識を活かせる企業を中心にエントリーするのに対し、文系は幅広い業種・職種にエントリーする就活生が多いためです。
また、一般的に文系の募集人数は理系より多いのですが、人気企業は競争が激しいため、内定の可能性を広げる目的で文系の方が多くの企業にエントリーする傾向があります。
理系の学生は推薦を受けて通常とは異なるルートで選考を受けるケースが多いことも、平均エントリー数が文系より少ない一つの原因です。
就活で効率的にエントリーする方法は?
エントリー数が少なくても早い段階で希望の企業から内定をもらう就活生もいるので、平均エントリー数を全く参考にしない学生も多いです。
しかし、多くの就活生にとってミスマッチのない就活を実現させるには、限られた時間の中で選考対策の質を上げ、ある程度の応募数は確保する必要があります。ここでは、就活において可能な限り効率的に企業の選考にエントリーする方法を紹介していくので、今後の参考にしてみてください。
逆求人サービスを活用する
逆求人サービスとは、学生がプロフィールを登録し、それを見て興味を持った企業がオファーを送る就活支援サービスです。
企業はプロフィールを見て自社にマッチした人材を厳選してオファーを送るので、自分で応募先を選定する時間を短縮でき、多くの企業にエントリーするチャンスが広がります。また、企業によっては登録したプロフィールをエントリーシートの代わりと位置づけるため、効率的に自分の強みをアピールできる利点もあります。
ただし、プロフィールに空欄が目立つ場合や内容に不備がある場合は、自分にマッチしたオファーをもらうのが難しくなる可能性は高いです。
一つ一つの内容をチェックされていると思い、企業にエントリーシートを提出する時と同じ熱量で作成しましょう。
効率的に就活を進め、できるだけ早く内定がほしい方に逆求人サービスはおすすめです。
逆求人サービス「OfferBox(オファーボックス)」
OfferBoxは、24万人(※3)の学生が利用する逆求人サービスです。
利用企業数も業界トップクラスを誇り、中小から東証プライム上場企業まで全国各地の幅広い業種・職種の企業が利用しています。
OfferBoxは学歴によるオファー受信の偏りが少ないのが強みで、プロフィールを80%以上入力した場合の平均オファー受診数は41件(※4)と採用に積極的な企業が多いことが特徴です。また、OfferBoxでは自分を象徴する写真を登録でき、文章だけでは伝えられない普段の表情を伝えられるなど、プロフィールシートの内容も充実しているといえるでしょう。
OfferBoxならではの強みを上手く活用すれば、就活が効率化して多くの企業とコンタクトを取れるようになります。
>【無料】「OfferBox」に登録して効率的に就活を進める
(※3)OfferBox 2024年卒利用実績データより
(※4)OfferBox2023年卒利用実績データより
就活の軸を決めておく
就活の軸とは、自分自身の価値観と照らし合わせて、どのような仕事や職場環境で働きたいのか「就活で欠かせないポイント」を明確にしたものです。
就活の軸を事前に決めておくメリットは、応募する企業を選定する判断スピードが上がる点です。就活の軸と方向性が一致しない企業は、応募先の候補から迷わず除外できるようになるので、自分にマッチした企業を中心に効率よく応募できます。逆に就活の軸を定めないと、応募するかしないか判断に迷う機会が増えるので、応募するまでに時間がかかってしまいます。また、時間が無くなると精神的な焦りから感覚だけで応募先を選んでしまう恐れもあるでしょう。
いくら条件が良い企業でも自分の価値観との差が大きいほど長続きしない可能性が高くなります。また、ミスマッチが生じると長期的なキャリア形成にも影響を及ぼします。どんどん応募したい気持ちは一旦抑え、急がば回れの精神で就活の軸を明確にしていきましょう。
就活でエントリー数が多い場合のメリット・デメリット
就活を進めるにあたって、過去の平均エントリー数と比べて多く応募したからといって内定につながるとは限りません。
エントリー数が多いと得られるメリットも多いですが、同時にデメリットもあります。両者を理解した上でバランスよく就活を進めましょう。
就活でエントリー数が多い場合のメリット
まずは、就活において多くの企業にエントリーするメリットを見ていきましょう。
多くの企業同士を比較できる
エントリー数を増やすメリットの一つは、多くの企業と接点を持てるため企業同士を比較検討できる点です。同じ業界でも企業によって事業の方向性や評価基準は異なります。
できるだけ多くの企業を知ることは、自分の強みを活かせる最適な職場を見つける上で大切といえるでしょう。
新卒という周りからのサポートを受けながら成長できる貴重な機会を、企業選びの失敗で棒に振ってしまうのは勿体ないことです。
就活に影響が出ない範囲でエントリー数を増やし、多くの企業の中から本当に自分がやりがいを持ち長く働ける職場を見つけることは就活の成功には欠かせません。
面接慣れができる
エントリー数が増える分だけ、面接慣れできるメリットがあります。
面接では緊張から本来の力を発揮できず、アピールしたい内容の半分も伝えられないケースも少なくありません。
面接で緊張するのは、単に面接対策が不足しているだけではなく、就活を始めたばかりで面接の雰囲気に慣れていない「経験不足」が原因の場合もあります。
本番特有の面接の雰囲気を何度か経験する中で、緊張に打ち勝ち徐々に自分の想いを適切に表現できるようになっていきます。
就活でエントリー数が多い場合のデメリット
冒頭にも説明した通り、エントリー数が増えることによるデメリットもあります。
ここでは、就活でエントリー数が多い場合の代表的なデメリットを紹介していきます。
1社あたりに割ける時間が減る
就活に費やせる時間は限られているので、エントリー数を増やすほど1社あたりの選考対策に割ける時間が減ってしまうのがデメリットです。平均エントリー数など他の学生の状況を見て、全く応募できていない現状に焦り、がむしゃらに応募数を増やし対応できなくなる就活生もいます。
そのため、エントリー数を増やす場合でも選考対策の質が落ちない範囲にとどめ、自分の強みが活かせる企業を厳選してコツコツと応募していく姿勢が大切です。
エントリー数を意識し過ぎて、本来の就活の目的を見失わないようにしましょう。
管理の手間がかかる
エントリー数を増やせば、各企業の説明会や選考などで予定がいっぱいになり、スケジュール管理が大変になります。他の企業と選考の日程がかぶる可能性もあるので、選考対策も計画性をもって進めなければいけません。
一定のエントリー数を確保することも必要ですが、自分のキャパシティを超えない無理のないスケジュールで、選考を受けていくことも大切です。
OfferBoxでは、サービス上の「日程調整」の画面で予定されている面談・セミナーの一覧を確認できるため、スケジュール管理を正確に行えます。
自分で都度スケジュールを追加する必要もないので、選考対策に集中できるのが強みです。
>【無料】「OfferBox」に登録してプロフィールを入力する
就活でエントリー数が少ない場合のメリット・デメリット
エントリー数が極端に少ないと選択肢が減る分、就活の視野が狭まったり、自分に合った企業を見つけづらくなる場合があったり何かとデメリットはあります。
ただ、エントリー数が少ない場合のメリットもあるので、平均エントリー数と比較して多少応募した企業が少くなくても前向きに就活を進めていく姿勢が大切です。
就活でエントリー数が少ない場合のメリット
まずは、エントリー数が少ない場合のメリットを見ていきます。
過去の平均エントリー数を意識し過ぎて、がむしゃらに応募しても結果につながると限らないことを理解できるので、ぜひ参考にしてみてください。
1社ごとにしっかり選考対策ができる
エントリー数が少なければ1社の選考対策に時間を割ける分、面接本番でもしっかり力を発揮できます。応募先の企業は同業他社ではなく自社を選んだ理由を重視するので、ある程度時間をかけて企業研究をしないと入社の熱意が伝わらない可能性もあるでしょう。
そのため、特に就活に慣れていない間は、エントリー数を抑えて1社あたりの選考対策の質を優先する必要があります。
選考対策では、他社にはない応募先企業の強みを探すことを重点的に取り組み、可能であればエージェントなどプロの立場から一社一社フィードバックをもらうとよいでしょう。
まずは量より質を重視して、就活に慣れてきた段階でスピードも意識してみてください。
気持ちに余裕を持つことができる
多くの就活生は選考と学生生活を両立しなければならず、人によっては周りの就活スケジュールに合わせるのが難しい場合もあるでしょう。
その点、エントリー数が少ないほど時間に追われる機会が減るので、就活において精神的なゆとりが出るメリットがあります。
自分の現状に照らし合わせて無理のないエントリー数であれば、学業に力を注ぎながらも選考対策を充実させられるので自信を持って応募できるでしょう。
また自分の感情は言動になってあらわれるので、気持ちに余裕を持つことで企業にスマートで落ち着いた印象を与えられるメリットもあります。
就活でエントリー数が少ない場合のデメリット
前節で説明した通り、就活に慣れていない理由で最初だけエントリー数を少なくするなら、後から挽回もできるので問題はありません。
しかし、就活全体を通して極端に応募した数が少ない場合、様々なデメリットが生じる可能性があるので注意が必要です。
就活の視野が狭まる
エントリー数が少ないと応募が特定の業界や職種に偏よりやすくなります。その結果、就活の視野が狭まり、自分に合った仕事や本当にやりたい仕事を見つけるチャンスを逃してしまう恐れがあるでしょう。
今まで特定の仕事に絞って就活してきた場合でも、関連性のある他の業界や職種にも目を向けてみることで、新たな仕事の魅力に気付けるかもしれません。
就活の視野を少し広げてみることで、エントリーしたい企業も増え、就活にもやりがいを持ち取り組めるようになるでしょう。
リスクが大きい
エントリー数が少ないと、たとえ内定を獲得できても就職先の選択肢は少なくなります。
そもそも企業を比較してから入社を決めるのが難しくなるので、就活生にとっては少しリスクが大きくなるでしょう。
もちろん、選考中だけで企業を完全に理解するのは難しいですが、エントリー数が多ければ選考を受ける中で徐々に企業を見る目も養われてきます。
逆に限られた求人にしか応募しないと他の会社の状況が分からないので、本当にこの会社が自分に相応しいのか確信を持てず、不安な気持ちのまま入社することになるでしょう。
何より少ないエントリー数の中で確実に内定を獲得できるとは限らないので、卒業までに就職先を決められないリスクと向き合わなくてはなりません。
就活で何社受けるか迷ったら?
平均エントリー数という一つの目安もありますが、実際に何社の選考に応募すればよいか迷う場合もあると思います。
そこで、ここでは就活で何社エントリーするか迷った場合に「どのようなことを考えて決めればよいか」「何か行った方がよいことはあるか」を紹介していきます。
まずは10社エントリーしてみる
何社応募するか迷ったら、まずは気になった企業を中心に10社を目安にエントリーしてみましょう。10社程度の併願であればスケジュール的に無理が生じませんし、学生生活との両立にも支障が出づらいからです。
エントリー数が極端に少ないと内定を獲得するチャンスを逃してしまう場合もあります。一方、多すぎるとスケジュール管理が大変になり忙しくなります。
また、もし選考を辞退する場合、辞退メールを作成したり企業にお詫びの連絡を入れたりするのも結構時間がかかる作業です。
エントリー数が多すぎて選考対策が手薄になっては元も子もないので、就活に慣れるまでは無理なく対応できる範囲で応募していきましょう。
志望企業リストを作成しておく
経歴を問われづらい新卒採用でも、ES選考の段階で落ちてしまう場合もあります。
面接にたどりつく前など早い段階で落ちてしまうことも踏まえ、いつでも次の企業に応募できるように、志望企業のリストを作成しておくのがおすすめです。求人サイトではお気に入り企業を登録できる仕組みがあり、応募の締め切りが近づくと通知してくれるので、応募管理が容易にできます。
またOfferBoxでも、自分のプロフィールを見てお気に入り登録をした企業を把握できる他、自分にマッチした企業を表示する仕組みなど、志望企業リストを作成する手助けになる機能があります。
OfferBoxも有効活用して、自分に合った志望企業をリストアップする際に役立ててみてください。
まとめ
エントリー数を増やし過ぎて、選考対策が雑にならないようにしましょう。
過去の平均エントリー数は考慮しつつ、自分に無理のない範囲で応募することが大切です。まずは10社を目安にエントリーしてみて、就活に慣れてきたら徐々に応募を増やしてみてください。OfferBoxに登録している企業は、学生のプロフィールを見て採用基準に近い場合にオファーを送るので、エントリーする企業に迷ったら応募を検討してみてください。
また、OfferBoxの『Analyzeu+』は、累計100万人以上のデータを活用した自己分析ツールです。自分の強みを客観的に把握し、適切なエントリー戦略を考える際に活用できます。
エントリー数の割に結果につながらない場合は、軌道修正をはかるために活用してみてください。