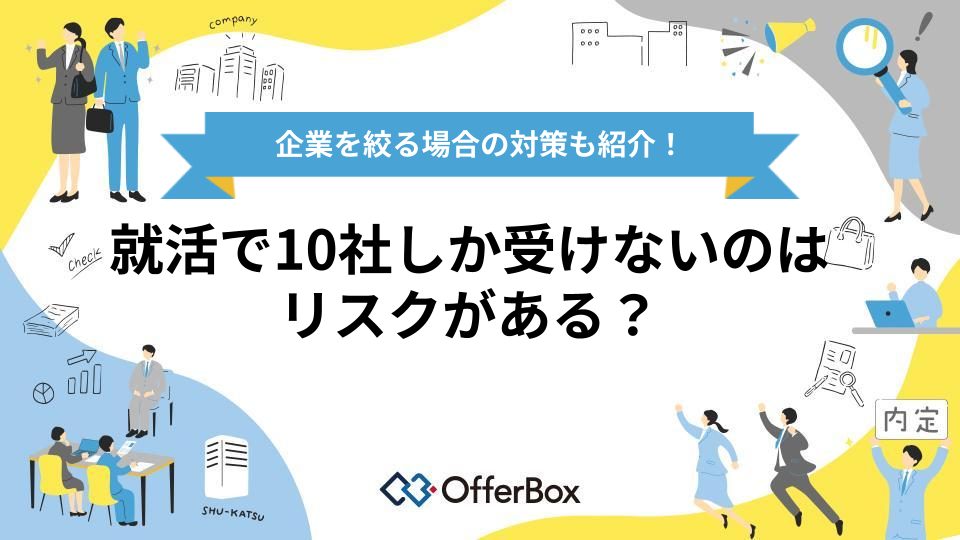
30社以上エントリーする学生も少なくないので、就活で10社しか受けないのはリスクがあると気になる就活生は多いでしょう。
この記事では就活で10社しか受けないメリット・デメリット、受ける企業を絞った場合の対策を紹介していきます。
予想以上に早く内定をもらい就活を続けるか迷っている方も、ぜひ参考にしてみてください。
OfferBoxは、プロフィールに登録しておくと企業から選考やインターンシップのオファーが届く新卒逆求人サービスで、就活生の約23万人(※1)に利用されています。
また、累計登録企業数は約21,280社(※2)で、大手から中小・ベンチャーまで幅広い企業に登録されています。
完全無料で利用できるため、ぜひ活用ください。
(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより
(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)
就活で10社しか受けないのはリスクがある?
10社を少ないと感じるかは、自己分析によって就活の軸を明確にできているかどうかや就活生の価値感の違いにもよります。
自分で決めた就活の軸や今後のキャリアを踏まえて選んだ企業であれば、10社でもよいと考える人もいますし、それでも少ないと捉える人もいるでしょう。
大切なのは、何社にエントリーするかではなく、自分自身が納得するまで就活を全力でやり抜くことです。
極端な話、100社エントリーしても就活に手を抜いていれば、たとえ内定を獲得できても、本当にこのままで良いか最後まで不安が残るでしょう。
また、企業研究が雑になることで、合わない企業に入社して短期離職につながるリスクも出てきます。
人によっても違いはありますが、就活を終えた後に10社が少ないと感じるか十分と感じるかは、就活への取り組み方が関係するといえるでしょう。
つまり、エントリー数が少ないことによるリスクを引き起こす原因は、実は自分自身にあるといえます。
就活生が受ける企業数の平均は?
内閣府による調査である「エントリーシートの提出数」によると、10~19社にエントリーシートを提出した就活生が約3割と最も高い割合でした。実際に「今年度調査(令和6年)」学生全体の平均を出すと、約17社という結果になります。
10社以下の学生も2割弱いますが、同様に30社以上にエントリーした学生も約2割いることからも、就活生によってエントリー数に対する捉え方に差があるといえるでしょう。
ただ、応募しないにしても、できるだけ多くの企業と接点を持つ機会があった方が、合わない企業に入社するリスクを減らせます。
エントリー数に正解はありませんが、なるべく他の学生の平均に近い20社以上は受けることをおすすめします。
就活で10社しか受けないメリット・デメリットは?
ここでは、就活でエントリー数が10社以下であると、多くの就活生にとって少ないという前章の内容を前提に、10しか受けないメリット・デメリットを解説していきます。
何社にエントリーするかは就活生の自由ですが、無理のない範囲で選考に応募するのが理想だということを頭に入れて読み進めてみてください。
就活で10社しか受けないメリット
まずは、就活でエントリー数が少ない場合のメリットを紹介していきます。
就活に支障の出ない範囲でエントリー数を減らすことで、良い結果に結びつくこともあるので参考にしてみてください。
1社ごとの対策にしっかり時間をかけられる
10社以下のエントリー数でも希望の企業から内定を獲得できる人もいます。
一方で、20社・30社受けても採用に結びつかない人も少なくありません。
その大きな違いは、1社ごとの選考対策にしっかり時間をかけられるかどうかです。
選考結果は基本的に相対評価で決まるため、他の応募者より選考対策の質が高ければ良い結果につながりやすくなります。
また面接での受け答えがスムーズだと選考に向けて努力してきたと伝わるため、人物面でも良い印象を持たれやすくなり、一般的には選考で有利に働きます。
時間をかければ結果につながるとは限りませんが、自信を持って選考に臨めるのは確かなので、少なからず本番で力を発揮しやすくなるといえるでしょう。
タスク・スケジュール管理がしやすい
10社以上にエントリーすることを考えると、一度に複数の募集に応募する必要が出てくるしょう。そうなると企業同士で選考日程が重複したり、講義やバイトとバッティングしたりして、タスク・スケージュール管理が複雑になる場合があります。
逆に応募数が現状より減りタスク・スケジュール管理がしやすくなれば、目標達成のためにやるべき事や段取りが明確になり、就活全体の効率化につながります。
特にタスク管理は、一つ一つのタスクをしっかりリスト化できるため、途中で就活の段取りを変更してもやるべき事を忘れる心配がなく、就活の効率化を実現する上で欠かせません。
無理なく企業説明会や面接の日程調整をできる範囲で、エントリーすることも意識していきましょう。
企業に本気度が伝わりやすい
新卒は基本的にポテンシャル採用です。
企業は選考において能力やスキルも重視しますが、同じくらい入社意欲も考慮して採否を決めます。面接中のやり取りの中で、時間をかけて自己分析や企業について調べてきたことが伝われば、多少言葉がつたなくても熱意は伝わるでしょう。
逆に、いくら応募数を増やしても、1社1社の選考対策が雑になると熱意が伝わらず内定からは遠のいてしまいます。それどころか、何社応募しても受からない焦りから就活のモチベーションの低下につながる恐れもあるでしょう。
応募先企業の他社にはない魅力にくわえ、企業の課題も自分なりに分析して本気で入社したい気持ちを示すようにしましょう。
就活で10社しか受けないデメリットは?
続いて、エントリー数が10社以下など少ない場合のデメリットを解説していきます。
細かい選考対策をしづらい
限られた企業の選考しか受けていないと、面接や筆記試験の傾向を把握するのが難しく、他の企業の選考に応用しづらくなる場合も少なくありません。
企業によって採用基準は違うとはいえ、選考で聞かれる内容は共通している部分も多くあります。そのため様々な企業の選考を経験するほど、面接時の大体の質問内容や質問意図を予測できるようになり、より具体的な選考対策が可能になります。
多くの企業がどんな就活生を求めているかを理解し、それを選考対策に反映させるためにも、ある程度は色々な企業の選考を経験したいところです。
気持ちに余裕が持てない
エントリー数が少な過ぎても、不安な想いが先行して逆に気持ちに余裕が持てなくなるものです。
確かに、周りが懸命に就活に励んでいる中で自分のスケジュールに余裕があると、気になってしまうのは仕方がない部分はあります。
ただ、周りがどうであろうと自分のやるべき事を計画通り行っていれば本来は問題ありません。気になってしまうのは、少し就活に対して自信を失っている証拠かもしれません。
スケジュールに余力があるなら、もう一度自分の強みを整理して、選考でのアピールの方向性を考え直してみてもよいでしょう。
それでも不安な気持ちが強ければ、敢えてエントリー数を増やしてみて、嫌でも就活に集中できる状況を作ってみるのも一つの方法です。
面接になかなか慣れない
面接は場数を踏むことで慣れてきます。
いくら想定質問に対して完璧な回答を用意しても、実際に本番の緊張感のある中で伝える経験を積まないと面接力は中々向上しません。
就活で10社しか受けないと、次の面接まで間が空いてしまい本番特有の雰囲気を忘れてしまう場合もあるでしょう。
勉強やスポーツもブランクがあると中々技術が定着しないように、就活も次の面接まで間が空くと自分の強みを上手く伝える能力が身に付きづらくなります。面接に慣れるには、ある程度の期間は継続して面接を受ける必要があるでしょう。
受けたい企業が見つからない場合は?
エントリー数を少しずつ増やそうと考えても、肝心の受けたい企業が見つからない場合も少なくありません。
ここでは、自分の希望や適性に合った応募先を見つけるための有効な方法を紹介していきます。
逆求人サービスを活用してみる
逆求人サービスとは、登録したプロフィールに興味を持った企業からオファーが届くスカウト型就活サービスです。
応募前にオファーを受けた企業について調べる必要はありますが、ナビサイトには掲載されていない優良企業に出会える可能性があるので、利用を検討してみてください。
また、企業から届くオファーの内容から自分の新たな強みに気付けるメリットもあります。
受けたい企業が見つからないのは、自分自身への理解が浅く、就活に自信が持てないのも一つの原因です。
一つでも多く自分の強みに気づければ「こんな企業でも活躍できるかもしれない」と色々な求人に積極的に応募したい気持ちが芽生えるでしょう。
逆求人サービス「OfferBox(オファーボックス)」
OfferBoxは累計企業登録数19,607社以上を誇る逆求人サービスの老舗で、全国の幅広い大学・学部に所属する24万人の学生が利用しています。
学歴によるオファー受信の偏りも少なく、東証プライム上場企業のうち半数以上がOfferBoxを利用しているので、大手優良企業に出会えるチャンスがあるのが強みです。
また、OfferBoxを実際に利用した学生の中には、自分が志望していない業界の企業からもオファーが届いたことで、やりたい仕事の幅を広げている方もいます。
プロフィールを80%以上入社した場合、OfferBoxの平均オファー受信数は42社です。
インターンシップやセミナーの案内も含め、登録すれば何かしらオファーを受けられる可能性が高いので、受けたい企業が見つからない場合は一度利用してみてください。
自己分析から適職を見つける
受けたい企業を見つけるには、まずは徹底した自己分析によって自己理解を深めなければなりません。
そもそも自己分析のやり方がよく分からない場合は、自己分析ツールの活用がおすすめです。
自己分析ツールを活用することで、自分の強み・弱み、性格や価値観を詳細なデータを元に客観的に分析できるので、適職を見つけるには最適といえます。
OfferBoxの「AnalyzeU+」は、累計100万人ものデータに基づき、適職や自分の強み・弱み、社会で活かせる能力などを診断できる無料の自己分析ツールです。
客観的な視点から自分を見つめ直すことは適職を見つける上で大切なので、ぜひ利用を検討してみてください。
インターンシップに積極的に参加する
限られた業界・職種ではなく、色々な企業のインターンシップに参加してみましょう。
実際に企業から話を聞いたり、仕事を経験したりできるので、インターン先が所属する業界で働くことを具体的にイメージできるようになります。
「この業界・職種は文系の人が活躍しそう」など、漠然としか理解していなかった仕事のイメージが変わり、新たに実現したいキャリアプランが見つかることもあるでしょう。
インターンシップを通して社会に一歩踏み出してみることで、働くことに対して現状より広い視野を持てるようになります。そのことで求人の見方も変わってくるので、受ける企業の幅を広げたい方は積極的にインターンシップに参加してみてください。
就活で10社しか受けない場合の対策は?
部活や研究などが忙しくて、就活にあまり時間をかけられない学生もいるでしょう。
また、中には就活は量より質と捉え、その考えを譲れない学生もいるかもしれません。
ここでは、就活で10社しか受けないなど多くの企業にエントリーしない場合でも、希望の企業から内定を獲得するための対策を紹介していきます。
アピール内容をブラッシュアップし続ける
少ないエントリー数で結果につなげるには、1社1社の選考対策の質を上げることが欠かせません。具体的には、自己PRやガクチカをはじめ選考におけるアピール内容をブラッシュアップし続ける姿勢が大切です。
タイミングとしては、1社の選考を受けた直後でもいいですし、会社説明会の後でもよいでしょう。何かしら就活に関する有益な情報を得た時や自分に対して新たな気付きがあった時などには、アピール内容を見直すようにしてみてください。
ただし、一度作成した自己PRやガクチカを変更することで、不要な内容まで盛り込まれ、ブラッシュアップしたつもりが逆効果になるケースも少なくありません。
ブラッシュアップした自己PRやガクチカはエージェントなど就活のプロに共有し、フィードバックをもらうのがおすすめです。
業界・企業分析を徹底する
10社しか受けない分だけ1社あたりの選考対策に時間をかけられるので、企業や業界について徹底的に調べていきましょう。
業界・企業研究はホームページだけではなく、就活四季報や業界地図など企業の詳細な情報を掲載した書籍も参考にしてみてください。
就活四季報では、事業戦略や企業の基本データ、求める人材など就活に役立つ情報が企業ごとに同様のフォーマットでまとめられているため、同業他社との比較が容易にできます。
また、会社説明会やインターンシップにも可能な限り参加して、ネットや書籍にはない生の情報を仕入れることも業界・企業分析には大切です。他には投稿者の本音が読み取れる「Xや口コミサイト」を参考にすることも、企業を理解するうえで有効といえます。
企業が重視する「なぜ敢えて当社を志望したのか」「同業他社にはない魅力は何か」といった質問にも、自信を持って答えられるようにしましょう。
応募候補の企業を別途準備しておく
「就活生が受ける企業数の平均は?」でも説明しましたが、就活生は平均して約20社はエントリーしています。
10社しかエントリーしないのは一般的に少ないので、全て落ちてしまった場合を想定して次に受ける企業をリスト化しておいた方がよいでしょう。
10社不採用になってから次に受ける企業を探し始めると、そもそも募集期限に間に合わない恐れがあり、せっかく興味を持っても選考に参加できないことになりかねません。
多くの就活サイトでは応募検討中の企業をお気に入り登録でき、募集期限が近くなると通知してくれる機能があるのでリスト作成に役立ててみてください。
次に受ける企業があると思えば、不採用になっても気持ちをすぐに切り替えられるので、落ちた場合の応募先の候補は常に探しておくとよいでしょう。
まとめ
10社しか受けないのは一般的に少ないといえますが、エントリー数を増やすことばかりにこだわって選考対策が雑にならないようにしましょう。
あくまでも、スケジュール・タスク管理が無理なく行える範囲で受けていくのがおすすめです。就活に慣れないうちはエントリー数にこだわらず、選考を経験する中で徐々に増やしてみてもよいでしょう。
応募する企業を絞っても就活が上手くいくかは、最適なマッチングが行えるどうかもポイントです。自分の強みを活かせる企業と早い段階で出会えれば、たとえ10社しか受けなくても希望の企業から内定を獲得できる可能性は十分にあります。
OfferBoxではオファー送信数が限られているため、企業はプロフィールを熟読して本当に選考を受けてほしい就活生にオファーを送ります。自分で応募先を探すより内定に結びつきやすいといえるので、利用を検討してみてください。


