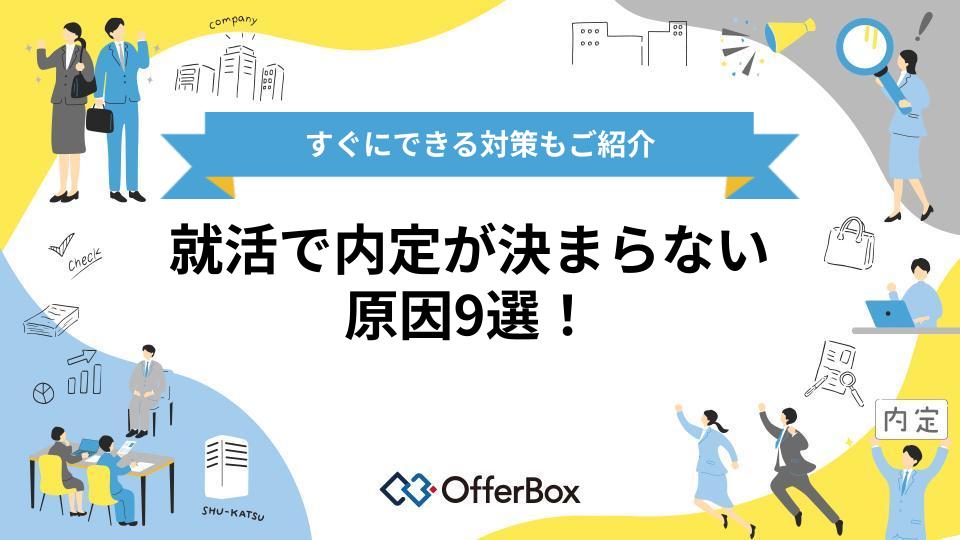
内定を獲得できるかはタイミング次第のところもありますが、就活で内定が決まらない学生には少なからず共通点があります。
この記事では、就活で内定が決まらない主な原因と対策を9つ厳選して紹介していきます。
努力は人一倍しているのに、就活で中々内定が決まらずに悩む就活生は多いです。
本記事の内容を参考にして、前向きに就活に取り組んでいきましょう。
OfferBoxは、プロフィールに登録しておくと企業から選考やインターンシップのオファーが届く新卒逆求人サービスで、就活生の約23万人(※1)に利用されています。
また、累計登録企業数は約21,280社(※2)で、大手から中小・ベンチャーまで幅広い企業に登録されています。
完全無料で利用できるため、ぜひ活用ください。

(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより
(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)
就活で内定が決まらない…。
就活で内定が決まらなくても、極端に落ち込んだり、すぐに諦めたりしないようにしましょう。
企業によっては秋採用や通年採用を実施するなど、人材を積極的に募集している場合もあるため、内定のチャンスは十分にあります。
これまで以上に隅から隅まで求人情報を探す意識を持ち、教授や就職課からの紹介も含めて色々な方法で応募先を見つけていきましょう。
また、採用されないのは面接の出来に問題があるのではなく、自分に合った企業を見つけられていないだけの可能性もあります。仕事探しの方向性を変えてみると採用につながる場合もあるので、一度これまでの就活のやり方を見直す時間を作ってみてもよいでしょう。
OfferBox(オファーボックス)の活用も検討してみて
就活で内定が決まらない場合は、OfferBoxの利用を検討してみてください。OfferBoxは新卒専用の逆求人サービスで、登録したプロフィールに興味を持った採用に積極的な企業からオファーが届くサービスです。
(プロフィールを80%以上記入した場合)OfferBoxのオファー平均受信数は41件と、企業からほぼ確実にオファーが届くので効率的に就活を進められます。
多くのオファーが届くことで企業から必要とされている実感を持つこともでき、内定を中々獲得できずに失っていた自信の回復にもつなげられるでしょう。
OfferBoxは逆求人サービスの老舗らしく登録企業数も多く、2025年1月の時点で累計企業登録数は19,807社以上を誇ります。全国各地の幅広い業種の企業が利用し、東証プライム上場企業のうち68%も利用するなど信頼性の高さも魅力です。
他にも累計100万人のデータをもとにした適職診断ツール「AnalyzeU+」を利用できるなど、自分に合った仕事を効率的に見つけられるので、ぜひ利用を検討してみてください。
就活で内定が決まらない原因と対策9選
就活では限られた採用枠に応募が集中するので、内定が決まらないのは他の応募者の状況も関係してくるでしょう。
しかし、もし就活や選考対策のやり方自体に問題があれば、応募者数に関係なく採用対象からは除外されてしまうので注意が必要です。
ここからは、内定が決まらない人に共通している原因と対策を9つ厳選して紹介していきます。
自己分析に課題がある
自己分析が浅はかだと、自分の強みや弱み、価値観などが定まっていない状態で就活に臨む
形になります。その結果、自己PRで自分の魅力や入社後の目標を適切にアピールできず、企業側に採用メリットを伝えるのが難しくなるでしょう。
また自己分析に課題があると自分に合った応募先の特徴を理解できないので、仮に選考を突破しても早期離職につながるリスクがあります。
自己分析はESや面接をはじめ就活の土台になるので、周りの力も借りながらでも丁寧に進めていきましょう。
自己分析に課題がある場合の対策方法
「自分にどんな強み・弱みがあるか」「どんな企業で働きたいか」を自信を持って説明できなければ、まだ自己分析が浅いと考えてよいでしょう。また、ES選考や一次面接など早い段階で頻繫に不採用になる場合も、自己分析に課題がある可能性があります。
自己分析が不十分だと思ったら、やるべき事はシンプルで現状より自己分析の質を上げることです。自己分析にはジョハリの窓や自分史など色々な手法があるので、利用した経験がない場合には取り入れてみてください。
就活のプロに自己分析を手伝ってもらうのもおすすめです。
特に就活エージェントは採用事情を熟知しているので、企業の視点から有益なアドバイスをしてくれます。何より就活は他者から評価されるので、認識できていない自分の一面を発見できる点でもエージェントの利用は有効です。
選考企業が偏っている
「大手がいい」「この業界が絶対にいい」など選考を受ける企業に偏りがある学生ほど、内定が決まらない傾向があります。
例えば、人気のある大手だけに応募先を限定すると、他の応募者との競争もあって選考のハードルが高くなり、内定が中々決まらない事態を招いてしまうでしょう。
就活のゴールは人それぞれですが、企業規模や業界を限定せずとも目標を達成できる可能性はあるので、もっと広い視点で仕事を探すことも大切です。
選考企業が偏っている場合の対策方法
選考企業が偏っている場合は、特定の業界や職種、企業以外についても調べてみるとよいでしょう。これまでイメージでしか捉えていなかった仕事や企業の魅力に気付ければ、応募先の選択肢を広げられるようになります。
例えば、合同企業説明会に参加する際は、敢えて通常は立ち寄らないブースの説明を聞いてみるのもよいでしょう。
「絶対に大手!地元!」など就活で譲れないポイントがあれば別ですが、いつも応募先の候補から除外していた求人にも目を向けてみると新たな発見があるかもしれません。
業界・企業研究が不足している
企業は同業他社ではなく自社を志望した理由を重視します。
業界・企業研究が不足すると、応募先の事業内容や仕事について理解が乏しくなるので、志望動機を聞かれた際にありきたりな回答しかできなくなってしまうでしょう。
新卒は基本的にポテンシャル採用なので、企業側は意欲の高い学生を優先して採用します。就活は多くの企業と並行してエントリーしますが、どの応募先も第一志望のつもりで受ける意識が大切です。
業界・企業研究が不足している場合の対策方法
業界や職種について理解を深めるには、企業説明会やセミナーに参加して現役で働く社員から直接話を聞く機会を設けるのが有効です。
ホームページや四季報などには記載されていない非公開の情報を得られる場合もあり、社員の口から直接聞いた内容のため情報の正確性も高いといえます。
企業説明会やセミナーへの参加は選考には直接影響しませんが、他の就活生にはない「あなただけの」志望動機を作成するためにも積極的に参加しましょう。
志望動機と自分の強みを上手くリンクさせられるように、企業説明会に参加する前には質問内容を考えることを忘れないようにしてください。
就活の軸が定まっていない
就活の軸とは会社や仕事選びの自分なりの判断基準を指し「就活の道しるべ」や「キャリアの方向性を示す指針」と言い換えられます。
就活の軸が定まっていないと、応募する企業を決める際に迷いが生じ、選考に対するモチベーションが曖昧なままエントリーすることになりかねません。
また面接で志望理由や将来のキャリアプランを聞かれても、一貫性を持って答えるのが難しくなり、何処かあやふやな回答内容になってしまうでしょう。
自己分析と同様、就活の軸が具体的に定まっていない状態だと、就活全体が上手く回っていかない恐れがあります。
就活の軸が定まっていない場合の対策方法
就活の軸は「自分が得意なこと」や「ストレスなく働ける職場環境」を基準に考えると、上手く設定しやすくなります。
職種や業界に対する個人的なイメージのみで就活の軸を決めるよりも、自分自身の特性や内面に焦点を当てた方が長く活躍できる企業を見つけられるからです。
得意なことや強みが思い浮かばない場合は、少しハードルを下げて、自分が行って苦痛にならないことを基準に考えても問題ありません。
自分自身が「本心から」どんな仕事や職場なら長く働けそうか、できるだけ具体的にしていきましょう。
ES(エントリーシート)対策が不足している
ES対策が不十分だと自分の魅力を適切に伝えられず、次の選考ステップに進むのが難しくなってしまうでしょう。
仮に選考が進んだ場合も、ESから伝わるイメージと実際の人柄や能力にギャップがあると捉えられ、自分の強みをスムーズにアピールするのが難しくなります。
面接では履歴書だけではなくESを元に質問されるので、内容を充実させるとともに、どんな質問をされても答えられるようにしましょう。
ESは企業に対して自分自身の強みや人間性を適切に伝えるための大切な書類だと捉え、丁寧に作成してください。
ES(エントリーシート)対策が不足している場合の対策方法
まずは、過去に提出したエントリーシートの下書きを改めて確認してみて、内容が理解しづらい場合や読みづらい場合は修正するようにしてください。
エントリーシートを書いた本人が読みづらいと感じる場合は、企業側はもっと理解できない可能性があります。
文章の構成は結論ファーストを意識して、途中で趣旨がぶれないように意識してみてください。
誤字・脱字も含めてパッと見て文章自体が分かりづらいと、中身まで読まれない可能性があるので注意が必要です。
また、ESの質問に対する回答がどこの会社でも通用するような内容になっていないかもチェックしましょう。
企業側は使い回しのエントリーシートは簡単に見抜きます。具体的なエピソードも交えながら「応募先でなければならない理由」を明確に示しましょう。
面接対策が不足している
面接を突破するには場慣れも必要ですが、面接対策がどれだけ充実しているかが大切です。
面接対策が不足していると自分の魅力を伝えきれず、あと一歩のところで他の応募者との競争に負けてしまうケースも少なくありません。
そもそも面接対策に手を抜いてきたことが明らかに分かる学生には、企業側も本気で向き合おうとする気持ちが起きないでしょう。
企業にとっては入社意欲が見えなければ、いくらスキル面が優れていても採用をためらってしまいます。
面接対策が不足している場合の対策方法
企業は面接中に様々な質問をしますが、一つ一つの質問の意図をたどると結局は「あなたを採用するメリット」を知りたいことが分かります。
面接が中々上手くいかない場合は、まずは自己分析や企業研究をもとに、自分の強みが応募先企業でどう活かせるかをもう一度考えてみてください。
自分を採用するメリット=誰にも負けない自分の強みを明確にしたら、その内容をベースに面接で想定される様々な質問に対して「自分の言葉」で回答する練習をしてみましょう。
面接でされる全ての質問に対して自分の強みをベースに応えられるようになれば、回答内容に一貫性を持たせられます。
選考の振り返りができていない
一社一社の選考に対する振り返りができていないと、今後も目的意識なく選考に挑んでしまうことになります。
面接で上手く行かなかった時や不採用通知を通知をもらった時に、何が課題なのかを明確にしていないので就活力が向上していない状態といえるでしょう。
もし自分に決定的なNGポイントがあって内定をもらえていない場合は、今後も同じ理由で不採用を繰り返してしまう可能性は高いです。
選考に落ち続けると「どうせ今回も落ちる」と諦めムードになり、徐々に就活に対するモチベーションが下がってしまうでしょう。
選考の振り返りができていない場合の対策方法
ESや一次面接など選考ステップごとに振り返りを行い、いつでも見返せるように自分なりにノートやPCにまとめていきましょう。
選考後の心境を反映する気持ちで、上手く行った点や改善点を思いつくまま書いていくと、現状の課題に加えて、自分の新たな強みも見えてくる場合もあります。
また時間があれば、自分でまとめた選考後の振り返りをもとに、エージェントや大学の就活課などに応募書類の添削や模擬面接をお願いしてもよいでしょう。
まとめるだけではなく実際にアウトプットした方が内容は定着しやすいので、より今後の選考に活かせるようになります。
就活と私生活を両立できていない
就活と私生活を両立できず、結果的にどちらも上手くいかずにストレスを抱える学生も多いです。
例えばアルバイトや部活が忙しくて選考対策まで手が回らないと、モチベーションが上がらない状態で選考に臨むことになります。
その結果、実際の選考で集中力を欠いてしまったり、就活が上手く行かない焦りから仕事でもミスをしてしまったりするなど、悪循環に陥ってしまう場合もあります。
企業側は思っている以上に就活生の態度を観察しているので、気持ちが乗っていない時こそ注意が必要です。
就活と私生活を両立できていない場合の対策方法
多くの企業はエントリー期限を定めているので、就活は時間勝負の側面もあります。
どうしても私生活との両立が難しければ、一定の期間だけでも就活優先で動けるように周りに協力してもらいしましょう。
就活は今後の人生を左右しかねない大切なイベントの一つです。
今はどうしても就活に全力で向き合わなければいけない旨を誠意を持って伝えれば、周りはきっと理解してくれるでしょう。
就活に対するモチベーションが低い
就活は長丁場になりがちなので、そもそも就活に対するモチベーションが低ければ最後までやる気を持続させるのは難しいでしょう。
企業は応募者がどれだけ本気で選考に臨んでいるかは簡単に見抜きます。
もちろん選考対策に手を抜いている場合も分かるので、いくら優秀でもやる気が伝わらない時点で企業は内定を出すのをためらうでしょう。
人はどうしても楽な方に流れがちになるので、そこをどうモチベーションに変えていけるかが重要です。
就活に対するモチベーションが低い場合の対策方法
就活に対するモチベーションが上がらない場合は、人生の目標を考えてみてください。
「何のために働くのか」「何が好き/得意で仕事として携わりたいのか」など、実現したいキャリアプランや人生の目標を視点に考えてみましょう。
強制されるのではなく、自分から能動的に就活に取り組めるようになればモチベーションも自ずと上がってきます。
逆に、就活に取り組まなかった場合の最悪の未来を想像するなど、無理やりモチベーションを上げるやり方はおすすめしません。
むしろ自分を追い込み過ぎて、逆効果になってしまう場合もあるので注意しましょう。
就活で内定が決まらなくても諦めずに原因を探ろう!
就活はトライアンドエラーの繰り返しです。
不採用通知をもらったら、なぜ採用に至らなかったか原因を探ることに徹しましょう。
一社一社の選考から学びがあれば、徐々に自分の想いを上手く表現できるようになり内定につなげられるようになるので、諦めずに就活を続けていきましょう。
OfferBoxは一般的なナビサイトとは異なり、オファー送信数に制限があります。
そのため、オファーを送る学生を企業側で厳選した上でスカウトするので、内定の可能性を少しでも上げたい場合に有効です。
また、オファー文面から企業から評価されているポイントを把握できるため、選考でアピールが足りなかった部分を理解するのに役立つ場合もあります。
企業からあなたに向けた本気オファーがたくさん届くOfferBoxであるからこそ、色々な活用の仕方ができるので積極的に利用してみてください。



