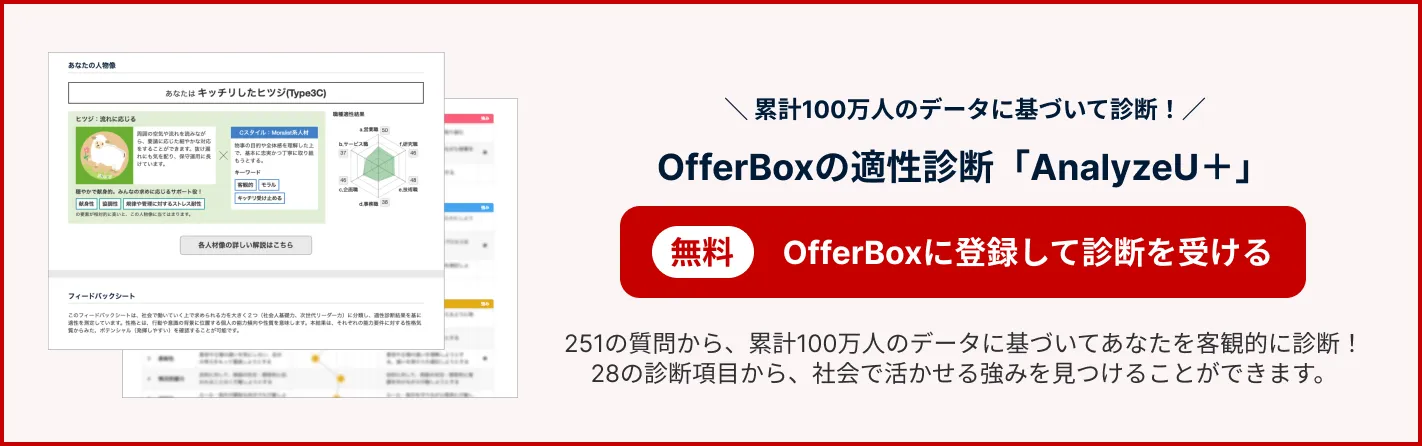>>【無料】AnalyzeU+で自分の強みを見つけてキャリアを考える
「将来の自分像がイメージできない」
「面接で将来の自分について聞かれてうまく答えられなかった」
就活を進めるなかで、このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。
「将来の自分」は面接での頻出質問の一つですが、まだ働き始めてもいないのに5年後、10年後の自分をイメージするのはなかなか難しいですよね。なんとかイメージしても、取り繕ったような答えになってしまい、この答えで大丈夫なのかと不安に感じている人も多いでしょう。
今回は将来の自分像がイメージできない人向けに、企業が「将来の自分」を質問する意図や、「将来の自分」の見つけ方をご紹介します。面接で聞かれたときの答え方と例文も紹介するので、参考にしてみてください。
新卒逆求人サービス OfferBoxの適性診断「AnalyzeU+」では、約100万人のデータに基づいて客観的に診断されます。
28の項目から、あなたの強みや弱み、職種適性などを知ることができ、将来のキャリアや就活の軸を考える基準にもしていただけるでしょう。
OfferBoxに登録していれば無料で診断できるので、ぜひご活用ください。
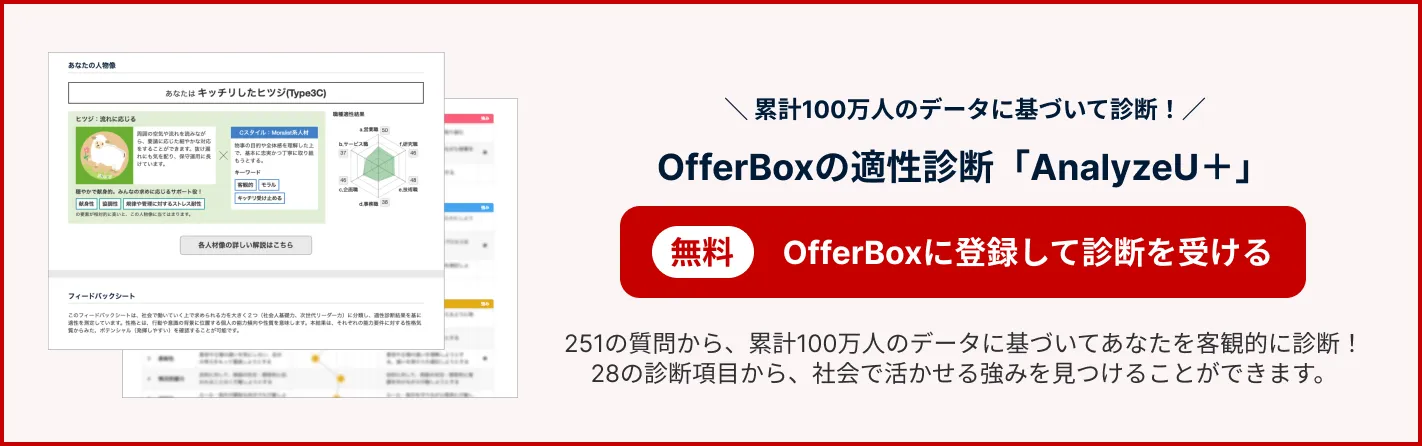
目次
将来の自分の質問で聞かれていること
なかには「将来の自分像が曖昧でうまく言葉にできない」と悩む人もいると思いますが、まだ働き始めてもいない段階で、数年後のビジョンを具体的に立てられないのは当然のことです。
面接官としても、まだ将来の自分が明確になっていない学生が多いとわかったうえで質問しているので、「将来の自分像」の答えは完璧なビジョンでなくても問題ありません。
就活の段階では「10年後はこんな社会人になっていたい」「5年後は社内でこんな役割をこなしたい」など、なんとなくのイメージでも大丈夫です。
10~15年後になりたい社会人像の場合が多い
「将来の自分像を教えてください」といったように、具体的な数字が含まれていない質問は、10~15年後になりたい社会人像を聞いている場合がほとんどです。そのため、基本的には10〜15年後くらいになりたい社会人像を答えるとよいでしょう。
なりたい社会人像の例
- きちんとした目標を持っている人
- オンオフの切り替えがうまい人
- 考え方が柔軟な人
- 周囲から信頼される人
- 細かい気配りができる人
前提がわからない場合は確認してOK
質問の前提がよくわからない場合は、きちんと面接官に確認してから答えるのがベストです。
「将来の自分」は少し抽象的な質問なため、面接官の聞き方によっては10年後のことなのか、5年後のことなのか、それとも将来達成したい目標のことなのか読み取れないケースがあります。
前提がわからないまま答えてしまえば、質問の意図に合わない回答になる恐れがあるため、わからない点は素直に質問して問題ありません。
反対に、質問の意図がきちんと理解できていないのに、勝手な解釈をして答えるのはよくありません。見当違いな答えは理解力を疑われるばかりか、コミュニケーション能力が欠如していると捉えられる可能性もあります。
質問の意図を確認するのは失礼な行動ではないので、わからないことはわからないままにせず素直に聞き返すのが無難です。
将来の夢・目標は「達成したいこと」
「将来の自分」とよく似た質問として、「将来の夢・目標」を聞かれる場合もありますが、こちらはより明確なプランを答えることが求められています。2つの違いをみていきましょう。
将来の夢・目標
「入社後に実現したい目標」のように、将来的に何を達成したいのかという明確なゴールを指します。例えば「話題になるようなヒット商品を開発したい」がゴールなら、そのゴールを目指す理由や、どう実現していきたいのかを伝えなければなりません。
将来の夢・目標の例
- 自分がリーダーとなり、新規事業を立ち上げたい
- 採用に関わる仕事がしたい
- 話題になるようなヒット商品を開発したい
- 顧客からも同僚からも信頼される営業になりたい
- 人材育成に携わりたい
将来の自分
一方「将来の自分」は、夢や目標ほど明確なゴールがなくても問題ありません。先に挙げた例のように明確なゴールがなくても、「こんな人になりたい」といったイメージができていれば問題ありません。
>>【無料】AnalyzeU+で自分の強みを見つけてキャリアを考える
将来の自分について質問する企業の意図

企業が質問する意図は主に以下の3つの理由があります。
- 学生の目指しているものが何か知りたい
- 学生が成長できる人材かどうかを知りたい
- 不確かな将来でも論理的に説明できるか知りたい
学生の目指しているものが何か知りたい
1つ目の意図は、学生が目指しているものを知り、その姿に近づく環境が自社で用意できるかを確かめるためです。あらかじめ目指しているものを聞いておき、少しでも入社後のミスマッチのリスクを減らそうとしています。
たとえ明確な社会人像をイメージできていたとしても、近づける環境が企業になければ、当然その社会人像は実現できません。
なりたい社会人像を実現できない環境では、仕事にストレスを感じて早期退職されたり、能力を十分に活かせなかったりする可能性が高くなります。そのため企業は面接で「将来の自分」を聞き、学生と自社の相性を確かめているのです。
学生が成長できる人材かどうかを知りたい
2つ目の意図は、学生が入社後に成長していける人材なのかを確かめるためです。
5年後、10年後といった将来を見据えて就活を進めている学生は、入社後も明確な目標を持って真摯に仕事と向き合い、どんどんと成長していく姿をイメージできます。
なりたい社会人像に近づくため努力を続け、結果的に企業に長く貢献してくれるでしょう。
企業は採用活動で「自社に長く貢献してくれる人材か」を1つのポイントにしているため、「将来の自分」の質問から、理想の自分像を持ってそこに向かって努力できる人材かどうかを見極めています。
不確かな将来でも論理的に説明できるか知りたい
3つ目の意図は、自分の考えを人にわかりやすく伝える力が備わっているか確かめるためです。
まだ働き始めてもいない就活の段階では、将来の自分が明確でまったくぶれない学生はほとんどいません。そうした不確かなことでも、現時点での考えをもとに論理的に話を組み立てて説明できるかを見極めています。
人にわかりやすく伝える力を企業が見極めるのは、こうした能力が働くうえで欠かせないからです。社内会議やプレゼンテーション、上司とのやり取り、チーム作業など、人にわかりやすく伝える力はあらゆる場面で必要になります。
このような理由から、企業は「将来の自分」について学生自身に説明させ、考えや意見を人にわかりやすく伝える力が備わっているか確かめています。
>>【無料】AnalyzeU+で自分の強みを見つけてキャリアを考える
将来の自分の考え方
将来の自分について考えるためには、まずは自分自身のことを客観的に理解する必要があります。自分にはどんな強み・弱みがあり、仕事で何を実現したいかを把握することが大切です。
以下のポイントに沿って、将来の自分について考えてみましょう。
10、20年後など遠い将来から逆算して考える
まずは10年後、20年後などの遠い将来から逆算して考える方法がおすすめです。
近い将来から考えると「今現在の自分にできること」にとらわれがちなのに対し、遠い将来から逆算すれば、固定観念なしでさまざまな可能性をイメージできます。
まずは「なんとなくこうなりたい」という漠然としたイメージでもいいので、そこから具体的な自分像へとつなげていきましょう。
逆算して考える例
- 「人材育成に携わりたい」→「周囲から信頼される人」
- 「話題になるようなヒット商品を開発したい」→「目標を持って働ける人」
- 「いつか英語を使う仕事をしてみたい」→「常に学ぶ姿勢を持ち続ける人」
1年後など近い将来から積み上げて考える
もし遠い将来だとイメージしにくい場合は、近い将来から段階的にどうなっていきたいかを考えてみましょう。
1年後、3年後、5年後といった段階を踏んで考えていくと目標が明確になり、将来の自分像もイメージしやすいでしょう。
ただし、近い将来から積み上げて考える場合は、「今現在の自分にできること」ばかりにとらわれないよう注意が必要です。今できることにとらわれてしまうと、なかなか理想が見えなくなってしまうものです。
そのため、積み上げで考えた場合は、最終的に行き着いた10年後20年後の目標にワクワクするか、最後に考えるようにしてください。
段階的に考える例
- 1年後「仕事を早く覚える」
- 3年後「新しい知識やスキルを身につける」
- 5年後「周囲の人をサポートできる余裕をもつ」
- 10年後「周囲から信頼される人になる」
OB・OG訪問でロールモデルを作る
いずれの方法でも将来の自分像をイメージするのが難しければ、OB・OG訪問で自分の理想像を探すのも1つの手です。
仕事のやりがいや大変さ、その仕事を選んだきっかけ、職場の雰囲気など、実際に働いた人にしかわからない生の声を聞き、「自分もこうなりたい」という将来像を固めていきます。
他人に対する憧れや尊敬の念は、自分がなりたい社会人像と重なるところがあります。OB・OG訪問で、「この人の仕事に対するポリシーはかっこいいな」「この人みたいな社会人になりたい」と感じたら、なぜそう感じるのかを考えてみましょう。
そうすれば、おのずと自分がなりたい社会人像が見えてくるはずです。
>>【無料】AnalyzeU+で自分の強みを見つけてキャリアを考える
将来の自分像が想像できないときの対処方法
「考えてはみたけど、やっぱり将来像をイメージできない」と悩む人も多いと思います。まだ将来のイメージが明確になっていない人にとって、面接にふさわしい回答を考えるのは難しいですよね。
そこで、上記の3つの方法を試してもイメージできない人向けに、おすすめの対処方法を紹介します。実践的な自己分析の方法も紹介するので、ぜひ試してみてください。
自分の過去の経験から考える
学生時代にやりがいを感じたことや、幸せに感じたことからでも将来像をイメージできます。過去の経験の中で自分がどんな行動を取り、どんな考えをもったのか振り返り、大切にしている価値観から将来像をイメージしていきましょう。
過去の経験から考える際は、自分史を作成して分析する方法がおすすめです。
自分史とは、自分の過去の出来事を時系列で書き出したもの。その出来事を経験したときの自分の考えや感情、取った行動、学んだことなどを振り返っていけば、将来像をイメージするヒントになります。
ただし、過去の経験から考える方法は、現在の延長になりやすい点に注意が必要です。現在まで大切にしてきた価値観が将来にも当てはまるとは限らないため、本当にそれでいいのかを改めて考えることが重要になります。
自分史についてはこちらの記事で進め方やテンプレートを紹介していますので、ぜひご活用ください。
自己分析シート無料ダウンロード|手順や便利なツールを紹介「経験を元に納得感を高める自分史」
反面教師から考える
質問の答えにはなりませんが、「なりたい姿」を考えるうえで「なりたくない姿」を考えてみるのは有効な手段です。これまでに出会った反面教師を起点に考えると、自分のなりたい姿が見つかる場合があります。
学校の教師やクラスメイト、アルバイト先の上司など、「自分はこうなりたくないな」と感じた苦手な人から考えてみましょう。
反面教師から考える例
- 「言い訳が多い人にはなりたくない」→「自分のミスを素直に認められる人になりたい」
- 「頑固な人にはなりたくない」→「柔軟な考えをもった人になりたい」
- 「感情の起伏が激しい人にはなりたくない」→「嫌なことがあっても冷静に対応できる人になりたい」
将来の自分像がないことを正直に伝える
どうしてもイメージできない場合は、現時点では将来像がないことを正直に伝えましょう。評価を下げまいと取り繕った回答をするより、自分の現状を正直に伝えるほうが好印象です。
面接官もまだ将来像が明確でない学生が多いとわかったうえで質問しているので、自分の考えをしっかりと持っていれば、将来像がないからといって極端に評価が下がることはありません。
将来像がないと伝える例
私はまだ具体的な将来像はイメージできていません。
将来像をイメージするために、現在、OB・OG訪問をするなどして、理想の将来像を描こうとしています。
また、今後やりたいことが見つかったときにそれができるよう、目の前のことに愚直に取り組んで、色々な経験と知識を身につけていくつもりです。
>>【無料】AnalyzeU+で自分の強みを見つけてキャリアを考える
面接で将来の自分について聞かれたときの答え方

結論から述べる
将来の自分についての質問に限らず、面接でのあらゆる質問には必ず「結論→根拠」の順で答えるよう心がけましょう。
結論から話し始めることで、これからどんな話をするのかの宣言になり、面接官に話の内容を理解してもらいやすくなります。
また、結論はわかりやすく簡潔に述べることが大切です。冒頭で「私は将来は〇〇になりたいです」と一言で結論を伝えてから、その後のエピソードを話し始めましょう。
結論に至った背景は具体的かつ明確に
自身の人間性を面接官に理解してもらうためには、結論に至った背景をあわせて伝える必要があります。
特に、「将来の自分」は数年先の不明瞭なイメージでしかなく、結論も具体性に欠けがちです。だからこそ、その将来像を持つに至った背景をなるべく具体的に伝えることを意識しましょう。
内容は、過去の自分の経験でも、OB・OG訪問であった人でも問題ありません。そのときのエピソード、考えたこと・感じたことを具体的に話し、面接官があなたの心境が理解できるようにしましょう。
企業で成し遂げたいことと絡める
最後に、自分の将来像を実現するために、その企業を選んだ理由・企業で成し遂げたいことと絡めて伝えましょう。単に自分の将来像を伝えるだけでは、自社と学生の相性を見極めたい企業側の意図を満たせません。
そのため自分の将来についての質問に答える際は、自分の将来像と合わせてその企業を選んだ理由も伝えましょう。具体的な理由を答えられれば、面接官は学生が入社後に成長していける人材なのか確かめやすくなりますし、同時に企業への理解度の高さもアピールできます。
企業を選んだ理由を伝えるときは、具体的な業務内容や取り組みを交えて答えるのが効果的です。例えば、その企業にしかない独自の取り組みを引き合いに出して自分の将来像を伝えれば、なぜその企業を選んだのかがよくわかります。
>>【無料】AnalyzeU+で自分の強みを見つけてキャリアを考える
10年後の将来の自分の例文
ここでは「過去の経験から考えた場合」と「理想のOB・OGから考えた場合」の2つのケース別に例文をご紹介します。
これまでに紹介してきた将来の自分の考え方と面接での答え方を踏まえ、自分なりの回答を考えてみてください。
過去の経験から考えた場合の例文
私は将来、先輩にも後輩にも慕われる人になりたいです。
このような将来像をイメージするようになったのは、学生時代に経験した居酒屋のアルバイトで、誰からも慕われている先輩に出会ったことがきっかけです。
初めてのアルバイトでミスばかりだった私にも丁寧に仕事を教えてくれ、自分がミスをしたときには言い訳をせずきちんと謝罪できる先輩の姿が強く印象に残りました。そんな先輩と一緒に働くうちに、自分も誰からも慕われるような人間になりたいと感じるようになりました。
御社は良い意味で上下関係を気にせず、全員が積極的に意見を出し合える社風だと伺っています。若手が意見を出せるのは上司が信頼されている証拠なので、そのように信頼される上司の振る舞いを参考にしながら、私も慕われる人間になっていきたいです。
ポイント
誰からも慕われている先輩と一緒に働いた経験をエピソードとして伝えることで、将来の自分像をどういったプロセスで築いたのかが明確になっています。企業の社風と絡めながら、入社後の抱負を伝えている点も好印象です。
理想のOB・OGから考えた場合の例文
OB・OG訪問でお話を伺った御社の〇〇さんのように、切り替えがうまい人になりたいです。
仕事を長く続けられる秘訣を〇〇さんに聞いたところ、「気持ちの切り替え」と「オンオフの切り替え」が重要だと教えられました。
切り替えがうまくできれば常に前向きな気持ちで仕事に臨め、モチベーションも維持しやすくなるという考え方に共感し、それ以来「切り替えがうまい人」をなりたい社会人像にしています。
私は休みの日でも色々と考え込んでしまう節があるので、仕事の日は仕事モード、休みの日はオフモードと割り切り、ストレスをうまくコントロールしながら日々の仕事に臨みたいとい思います。
朝食サービスの導入やマッサージルームの設置など、オンオフの切り替えをしやすいような環境づくりに励んでいる点も、御社を志望した理由の一つです。
ポイント
OB・OG訪問で出会った人を参考にし、自分のなりたい社会人像を具体化するのも一つの方法です。ただの憧れだけに終わらないよう、どんなところに共感したのか伝えることを忘れないようにしましょう。
将来の自分像ができたらOfferBoxに登録しよう
記事の内容をもとに将来の自分像ができあがったら、「OfferBox」のプロフィール内の「私の将来像」に登録して企業からのオファーを待ちましょう。
OfferBoxは、プロフィールを入力すれば、待っているだけで自分に興味のある企業からオファーがもらえるため、今までは知らなかった、自分に合っていそうな企業と出会える可能性があります。
また、自分のプロフィールにどれだけ企業がアクセスし、興味を持ったのかを詳細なデータで確認できる機能があるのもOfferBoxの魅力の一つです。より自分の魅力が伝わる回答にブラッシュアップするために、データを元にどういったエピソードが興味を持たれいやすいか分析してみてください。
>>【無料】「OfferBox」に登録して就活をスタートする
まとめ
以上、企業が将来の自分について質問する意図や、将来像がイメージできないときの対処方法についてご紹介しました。
将来像のイメージが明確だと、自分が今後進んでいくべき道がわかりやすくなるのは確かですが、就活の段階ではまだイメージできていなくても問題ありません。社会人として経験を積んでいくうえで、実現したいことやなりたい社会人像を見つけていきましょう。
また、面接で将来の自分について聞かれたときに注意したいのは、まだ将来像がイメージできていないのに取り繕った回答をしてしまうことです。将来像が明確でない学生が多いことは面接官も重々承知しているので、その際は「まだ具体的な将来像はありません」と正直に答えましょう。
とはいえ、理想はあなたなりの将来像が描けた状態です。理想の将来像に向けたキャリアを歩める、あなたに最適な企業と出会えることを願っています。