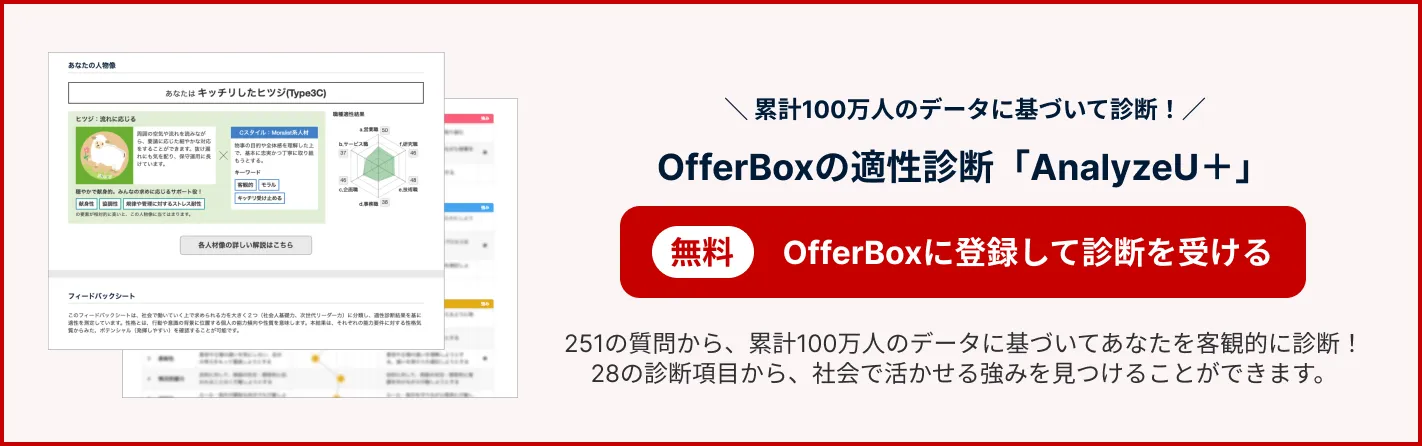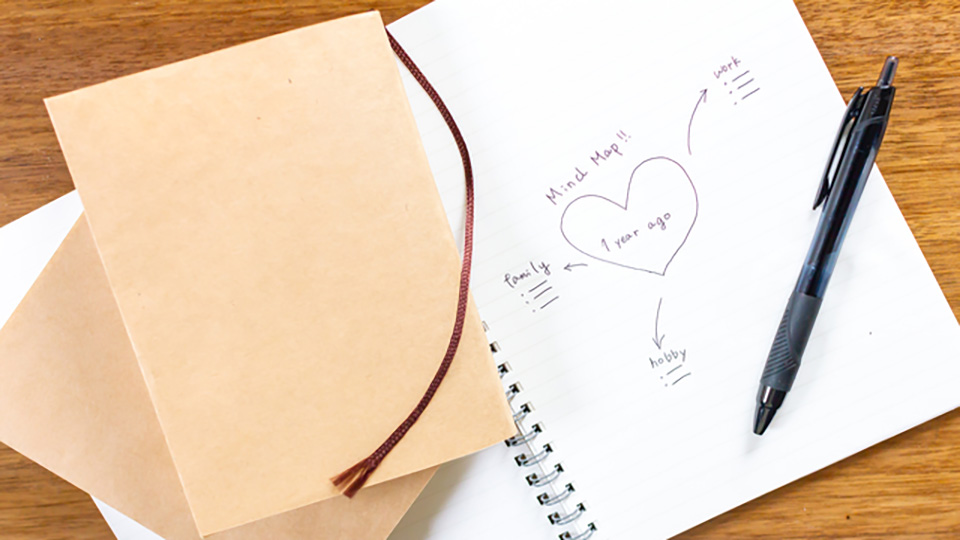
就職活動で自分に合った企業を選び、自分を正しくアピールするためには、自己分析が重要です。
自己分析の情報を見やすくまとめたものが「自己分析ノート」です。
しかし、自己分析ノートには「自分史」「モチベーショングラフ」「マインドマップ」といったように様々な種類があり、どのように作成したらよいかいいか分からない方も多いでしょう。
これから自己分析ノートを作成したいと考えている方向けに、自己分析ノートの主な作成方法や種類、書き方のポイントについてまとめました。
自己分析ノートはエントリーシートの作成や面接対策の際にも活躍してくれます。
本記事を参考にしながら、ぜひオリジナルの自己分析ノートを作成してみてください。
新卒逆求人サービス OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」では、約100万人のデータに基づいて、客観的な自分の強みや弱み、社会で活かせる力を診断できます。
OfferBoxに登録していれば無料で診断できるので、ぜひご活用ください。
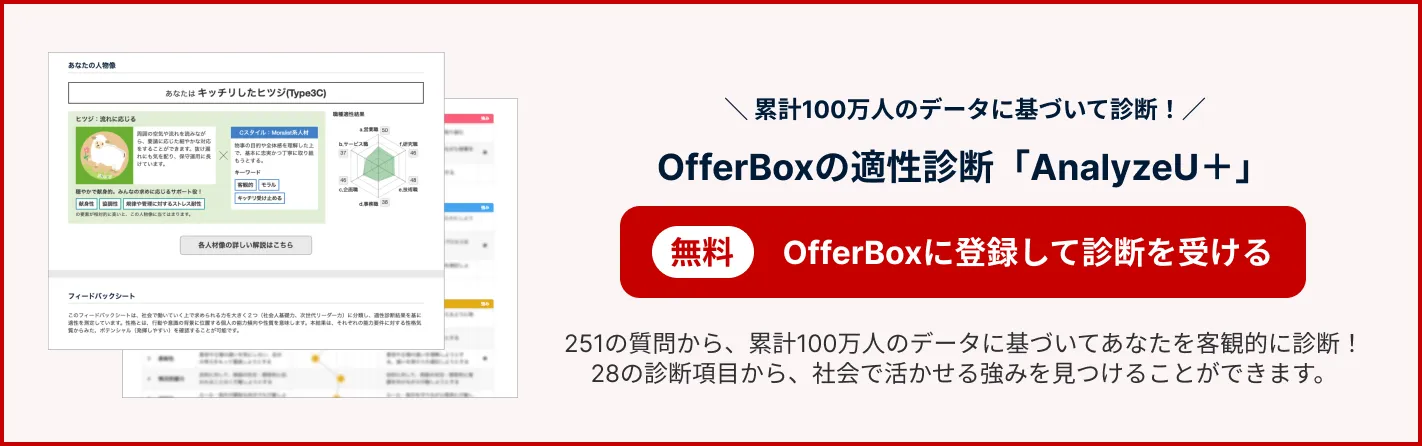
目次
自己分析ノートとは
「自己分析ノート」とは、就職活動に欠かせない「自己分析」の結果や過程を分かりやすく取りまとめたノートのことです。主に、エントリーシート(ES)内や面接で問われる自己PRの内容を整理する目的で使います。
自己分析ノートを作成することで自分の長所や経験、考え方などを言語化・一覧化することができるため、自己分析を効率的に進めることができます。
自己分析ノートといってもその種類はさまざまで、「自分史」「モチベーショングラフ」「マインドマップ」などの方式があります。
各種類の詳しい書き方については後述するので、参考にしてみてください。
よく間違えられやすい「就活ノート」は、各企業の選考情報から業界・研究で調べた企業情報、会社説明会の日程、OB・OG訪問で聞いた内容などをまとめたノートのことを指します。
自己分析ノートも広い意味で就活ノートと同義だと捉えられる場合もあり、就活ノートの中に「自己分析編」としてメモする人もいます。
1冊にまとめた方が見返しやすいメリットもあるので、必ずしも自己分析ノートと就活ノートを分ける必要はないことを覚えておきましょう。
就活の「自己分析」とはそもそも何?

自己分析の主な目的は以下の通りです。
・将来の夢や目標を明確化にして、入社後の活躍イメージを企業に持ってもらうため
・企業選びの軸を明確化にして、入社後のミスマッチを防ぐため
・面接官に「スキル」「人間性」「志向性」を正確に伝えられるようになるため
・キャリア形成の道標を作り、「5年後・10年後携わっていたい仕事」「身に付けていたいスキル」を明確にするため
選考を突破するため、企業から内定を獲得するためだけでなく、入社後に長く活躍するためにも重要なのが自己分析です。
自己分析全般について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
就活の自己分析はいつすべき?
選考に臨む過程でも自己分析は深められるので、そもそも始まりや終わりといった概念はないと考えるのが打倒でしょう。ただ、就活スケジュールの早期化も進んでいることもあるため、なるべく早い段階から準備しておくほうが安心でしょう。
自己分析のスケジュールとしておすすめなのは、3年生の春あたりには実施しておくことです。6月頃には各企業で夏のインターンシップの募集が始まります。その募集に合わせて自己分析を実施し、プログラムに参加しながら、3月に企業が採用情報を解禁する前の1〜2月までに内容をブラッシュアップさせる形がいいでしょう。
自己分析ノートを作成するメリット
頭ではしっかりイメージできているつもりの強みも、面接の場になると言葉に詰まったりして伝え方に困る場合がほとんどでしょう。
自己分析ノートを作成すれば、面接前に書いてまとめるというアウトプットができるので、適切に自分の想いを表現しやすくなります。
ここでは、自己分析ノートを作成するメリットを詳しくみていきましょう。
自分の経験や考えを整理しやすくなる
「自分のことはよくわかっているはず」と思っていても、いざ言語化しようとすると、なかなか明確に理解していないことに気づく人は少なくないはずです。
理解があいまいで上手く言葉にできない内容も、話したり書いたりしてアウトプットする機会を持つことで、他人に自信を持って伝えられるようになります。
自己分析ノートに自分の言葉で書くという作業の中で、自分の経験や考えをしっかり整理することができ、伝えたい内容を体系化できるようになるでしょう。
さらに、書いた内容を図にまとめて可視化すればいっそう理解が深まり、選考直前にも短時間で見直せるため便利です。
20年以上生きて自分の考えや価値感はある程度固まっていると思うかもしれませんが、周囲からの影響を受けてこれからも徐々に変化するものです。
そのため、就職活動の選考前には自己分析ノートにまとめて現状を整理し、常に自分像を言語化できるようにしておきましょう。
自分の強み・弱みを深掘りしやすくなる
自己分析ノートを使って自分像を言語化・可視化することで、自己分析を深堀りしやすくなるメリットもあります。
自己分析ノートに目に見える形で記録することで、全体を見返した時に新たな気づきが生まる場合もあるためです。
「なぜこの時このような行動を取ったのだろう?」
「自分は人と会っている時が楽しいと感じる傾向にありそうだ」
「でも、実はこんな特技や強みはないか?」
このように、書いた内容を見ながら色々と思考を巡らす中で、さらに発展した分析を行うことが可能です。頭の中だけの不確かな記憶を頼りにするよりも、質の高い分析ができます。
自己分析ノートは単純に書いて終わりではなく、情報をまとめたら全体を俯瞰してみて、もう少し深掘りできるポイントはないかという意識を持ちましょう。
自己分析の結果を後から見返すことができる
自己分析ノートが手元にあれば、自己分析の結果を面接前など必要な時に見返すことができます。面接直前で緊張感が高まっている中に、自分のアピールがしっかりまとまったノートが一冊あれば大きな安心材料になるでしょう。
自分の言葉で書いた内容の方が頭に残りやすいので、直前の選考対策において重宝します。
自分の考えや価値感は周囲からの影響で変化していくことは、先述した通りです。
就活を進める中で自分の新しい強みに気がついたり、価値観が変化したりする可能性は可能性はあるので、些細な気づきでもどんどん書き足して中身を充実させましょう。
自己分析ノートを見返せば自分の変化に気付ける場合もあるので、企業に対して自分という人間をより正確に伝えられるようになります。
自己分析ツールを活用するのもおすすめ
自己分析の方向性に迷った場合や自分の新たな一面を発見したい場合は、自己分析ツールを利用してみるのもおすすめです。自己分析ツールを活用することで、客観的な分析結果を確認することができます。
スカウト型就活サービス「OfferBox」に登録すると無料で利用できる「AnalyzeU+」は、累計100万人のデータから客観的な分析結果を確認できます。251の質問に答えることで計28項目の診断結果で表示され、「社会人基礎力」や「次世代リーダー力」など働くうえで必要な能力から、動物タイプ(役割志向タイプ)などユニークなものまでさまざまな項目から自分を見つめ直すことができます。
また、分析結果はOfferBoxのプロフィールに反映されます。企業は診断結果も参考にオファーを送るため、あなたに合う企業とマッチしやすくなります。
自己分析ノートの書き方とテンプレート
自己分析ノートを種類ごとに解説していきます。
・自分史の書き方・テンプレート例
・モチベーショングラフの書き方・テンプレート
・ジョハリの窓の書き方・テンプレート
・マインドマップの書き方・テンプレート例とおすすめアプリ
各項目の最後にテンプレート付きの解説記事を記載しているので、ぜひ参考にして自分に合ったものを使用してみてください。
書き方①:自分史
自分史は自分が経験してきたことを時系列でまとめたものです。
幼少期も含めて今までの人生で起きた出来事や経験で、現在まで印象に残っている内容を書き出します。
また、エピソードと一緒に自分のキャラクターや心境の変化、その時々の行動などを書き出し、自分の価値感や考え方の特徴を明らかにしていくのも自分史の意義です。
「自分はこういったことには時間を忘れて取り組める」「こんな環境に置かれたら力を発揮できる」といったように自己理解が深まり、自己分析の土台を固められるでしょう。
自分史を作成する過程で忘れかけていた過去の自分を思い出し、自分らしさとは何なのかを自信を持って語れるようになります。
書き方の手順とテンプレート
自分史は以下の手順で作成します。
- 年代ごとの出来事をまとめるフォーマットを作成もしくはダウンロード
- 各年代の自分のキャラクター、実際のエピソードを時系列でなるべく多く挙げる
- エピソードを厳選し、選んだ理由も記載
- 当時のモチベーションをグラフ化する
- 当時考えていたことをなるべく多く書く
- エピソードや経験に対する、振り返りと学びを書いていく
- 全体を俯瞰して自分の人間性を表す共通点を探ぐる
自分史は自分でExcelなどで作成してもよいですし、規定のフォーマットを利用して作成してもよいです。
▼自分史のテンプレートはこちらからダウンロード
▼自分史の書き方の詳細はこちらの記事で解説しています
書き方②:モチベーショングラフ
モチベーショングラフとは、自分の過去を振り返り、幼少期から現在に至るまでのモチベーションの変化を時系列で表した曲線のグラフです。
モチベーショングラフを活用すれば、人生のどの時期にやる気が高まり、逆に下がったのかを可視化できます。
過去の経験・出来事がモチベーションにどのような影響を与えてきたかを理解できるので、自分の性格的な特徴や適職の傾向を知るのに役立てられるのが強みです。
モチベーションの源泉をグラフで可視化することで、自分を客観視できるとともに自己改善のヒントも得られます。
自己分析はもちろん就職活動の面接対策、今後のキャリア選択においても活用できます。
選考対策では、自分史を作成した後にモチベーショングラフを作成するのも良いでしょう。
書き方の手順とテンプレート
モチベーショングラフは、以下の手順で作成します。
- 縦軸にモチベーションの高さ、横軸に時間の2軸を置き直線を引く
- ※幼少期~現在までのモチベーションが大きく変動した出来事を年齢別に書く
- 当時のモチベーションの高さを点で書く
- 点をつないでモチベーションの推移を確認できるようにする
- モチベーションが山と谷になっている部分の理由を書く
- モチベーションの源泉や困難な場面をいかに乗り越えてきたかをまとめる
※幼少期・小学生・中学生・高校生・大学生の5つの時期に分ける
▼モチベーショングラフのテンプレートはこちらからダウンロード
【モチベーショングラフExcelテンプレート】ダウンロードする
【モチベーショングラフPowerPointテンプレート】ダウンロードする
【モチベーショングラフWordテンプレート】ダウンロードする
▼モチベーショングラフの書き方の詳細はこちら
書き方③:ジョハリの窓
ジョハリの窓とは、自分が気付いていない自分の本質の理解など、他人と自分の認識のズレを明確にするための自己分析・他己分析の手法です。
自分の性格は一番自分がよく分かっていると思っていても、実際には見えていない部分もたくさんあります。
自分の性格を正確に理解していないがゆえに、自己分析をしようとしても、自分を大きく見せようとしたり、反対に謙遜してしまったりして、どうすればいいのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。
他人と自分との関係から自己分析を行い、自分への気づきを深めたい方、他者との円滑なコミュニケーション方法の模索をしたい方はジョハリの窓を利用してみてください。
書き方の手順とテンプレート
ジョハリの窓は他人の考えも必要になるので、できるだけ付き合いが長く忖度なく意見を出し合える人と行います。複数名のグループワークで行えば詳細に分析できますが、難しければ1対1でも構いません。とにかく本音ベースで自分の性格やコミュニケーションの傾向について意見を出してもらい、自己理解を深められるようにしましょう。
▼ジョハリの窓のテンプレートはこちらからダウンロード
上記テンプレートの使い方としては、まずは自分で「記入シート_A(本人)」に強みだと思うことを記入します。その上で「記入シート_B~D」に他者から見た自分の強みや性格、コミュニケーションの特徴などを記入してもらうことで、以下4つの窓に分類できます。
- 「開放の窓(自分も他人も分かっている自分)」
- 「未知の窓(誰からも知られていない自分)」
- 「秘密の窓(自分は気付いているが他人は気付いていない自己)」
- 「盲目の窓(自分は気付いていないが他人は気付いている自己)」
- シートに記入した内容を元にディスカッションをする
開放の窓の内容を元に自分の強みに客観性を持たせたり、未知の窓の内容を元に自分では気づかなかった自分の強みに気付いたりすることができます。
▼他己分析やジョハリの窓の詳細についてはこちら
書き方④:マインドマップ
人は一つのことを考えていても、話の流れなどがきっかけで連想ゲームのように関連性がある他の内容を自然に考えはじめるものです。
マインドマップは人が自然に行っている思考をマップ構造で可視化して、発想を広げるのに役立ちます。
就活においては、自己分析を項目ごとに深堀りしたい場合、面接の質問に対して論理的に答えられるように回答パターンを整理するためなどに使われるのが一般的です。
考えや記憶、情報をマップ化し可視化するマインドマップは、自己分析への活用はもちろん、自己PR文や志望動機の作成にも役立てられるので、この機会に覚えておくことをおすすめします。
書き方の手順とおすすめアプリ
マインドマップを作成する際は、1つの内容を深掘りする前に、まずは発想を横へ横へと広げていくことが大切です。最初から内容を深掘りしようとすると、マインドマップが特定の領域に偏ってしまう場合もあります。今やるべきことや思い出したことなど、現段階で思い浮かぶことを「自由」に書き出していくようにしましょう。
常識や固定概念は自分の思考を整理する際の邪魔になる恐れがあるので、マインドマップを作成する際は一旦取り払ってください。
上記の内容を踏まえ、マインドマップは以下の手順で作成しましょう。
- 用紙(罫線や柄がないものが理想)の中心にメインテーマを書く
- メインテーマから連想することを周りに書き並べる
- 同じワードから派生したグループごとに色分けする
- 色ごとにグルーピングされた内容を深掘りする
- 掘り下げている過程で思いついたことがあれば項目の追加はOK
紙にペンを使って作成する方法もありますが、オンラインでダウンロードできるスマホ用やPC用のアプリもあるので、ぜひ使ってみてください。
【スマホで利用できるマインドマップアプリ】
・SimpleMind
・miMind
・Mindly
【PCで利用できるマインドマップアプリ】
・FreeMind
・Xmind
・MindMeister
マインドマップの書き方の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
マインドマップとは?就活活用例やアプリも紹介
自己分析ノートで整理したいポイント
自己分析ノートで整理したいポイントをご紹介します。
- 興味・関心(就活の軸)
- 長所・短所(アピールポイント)
- 将来の目標(キャリアプラン)
- Will・Can・Must(やりたいこと・できること・必須なこと)
それぞれ詳しく解説していきます。
興味・関心(就活の軸)
就職活動を進めるにあたって、まずは就活の軸を決めることが必要です。
自分の興味や関心事は就活の軸を考える際のベースとなりやすいため、自己分析の際に必ずまとめておきましょう。
何に取り組んでいる時にやりがいを感じるのかや、どのような環境でモチベーションが上がりやすいのかなど、自分の興味・関心に着目して客観的に言語化してみてください。
就活の軸を決めかねている場合や、興味関心と仕事の結びつけ方がわからない場合は、以下の記事もご活用ください。
長所・短所(アピールポイント)
長所・短所は、エントリーシートや面接での自己PRのベースとなります。
長所と短所を整理して、各内容の質問にも答えられるように深堀りしておきましょう。
長所は自分の強みとして、どのように仕事に活かせるのかに繋げて考えることが大切です。
また、短所はネガティブに捉えてしまいがちですが、他の言葉に言い換えてみたり、長所と一貫性をもたせたりすることで説得力を高められる可能性があります。
長所と短所の詳細については、こちらの記事も参考にしてみてください。
将来の目標(キャリアプラン)
目先のことにとらわれず、将来の目標やキャリアプランについても考えてみましょう。
就活の軸や目指す業界・企業を決めたら、その環境で自分のどんな強みを活かしてキャリアを築いていくのか総合的にプランを立てていきます。
先にご紹介した「興味・関心(就活の軸)」と「長所・短所(アピールポイント)」の項目を結びつけることにも繋がるので、ぜひ一度整理してみてください。
将来の目標が上手く見つからない場合や面接での答え方などについての詳細は、こちらの記事を参考にしてみてください。
Will・Can・Must(やりたいこと・できること・必須なこと)
上記の3つについて整理を終えたら、「Will・Can・Must(やりたいこと・できること・必須なこと)」もまとめてみましょう。
Willは「自分が今やりたいこと」、Canは「自分が今できること」、Mustは「自分が今しなければならないこと」で、一般的に、これらが重なり合う仕事に就くと最もパフォーマンスが発揮しやすくなるといわれています。
Will・Can・Mustの進め方はシンプルで、それぞれの項目について列挙してみましょう。
そして挙げられた項目をみて、どのような業界・企業・仕事であれば同時に満たせるのかを考えてみてください。
自己分析ノートのおすすめの活用方法
自己分析ノートのおすすめの活用方法についてご紹介します。
- 毎日・週一など定期的に更新する
- 業界研究ノートや企業研究ノートと照らし合わせる
それぞれ詳しく解説していきます。
毎日・週一など定期的に更新する
自己分析ノートを一通り作成したら、「毎日更新」「週一更新」など、期間を定めてこまめに更新していきましょう。
定期的に振り返りの習慣をつけることで、自分の考えや選考対策を深められるだけでなく、就職活動を進める途中での変化にも敏感に気づくことができます。
また、就職活動の進み具合も意識しながら対策を進められるので、ぜひ振り返りの癖をつけておきましょう。
業界研究ノートや企業研究ノートと照らし合わせる
自己分析だけでなく、選考を受ける業界や企業の研究も大切です。業界研究や企業研究をノートにまとめることで選考対策に繋がるのはもちろん、志望していた業界や企業と自己分析の結果に大きな乖離がある場合は、もっと他に自分にあった業界や企業がある可能性も見えてきます。
志望動機をさらに深掘りするためにも、自己分析ノートが完成したら、ぜひ業界研究ノートや企業研究ノートも作成してみてください。
業界研究ノートの作成方法はこちらをご覧ください。
企業研究ノートの作成方法はこちらをご覧ください。
自己分析ノートに関するよくある質問
自己分析ノートに関するよくある質問を簡単に紹介します。
・自己分析ノートの内容をESや面接対策に活かす方法は?
・自己分析ノートを手書きで作成する方法は?
それぞれについて解説していきます。
自己分析ノートの内容をESや面接対策に活かす方法は?
自己分析の結果から、自分の強みや弱みが見えてくるかと思います。まずは強みや弱みに基づくエピソードをESに記載したり、面接で話せるようにまとめてみましょう。
まとめ方としては、PREP法を意識してみてください。
・R=Reason(理由)
・E=Example(具体例)
・P=Point(結論を繰り返す)
また、できるだけ定量的な情報(数字)を入れることもポイントです。具体的な数字が入っていることで、企業側に伝わりやすくなるほか、印象に残る自己PRになるでしょう
自己分析ノートを手書きで作成する方法は?
自己分析ノートを手書きで作成する場合、まずはテンプレートを参考に記入欄を作成しましょう。
自己分析ノートの種類に関わらず、全体像を把握してから書き始めることが重要です。
全体のうち、どの部分を作成しているのか見失ってしまわないように、先にご紹介したテンプレートを活用して、各項目の記入目的を意識しながら作成してみてください。
自己分析ノートのやり方に迷ったらOfferBox(オファーボックス)
今回は自己分析ノートの主な作成方法や種類、各書き方のポイントについてご紹介しました。
一口に自己分析ノートといっても「自分史」「モチベーショングラフ」「ジョハリの窓」「マインドマップ」などさまざまな種類があるので、自分の目的にあったものを選ぶようにしましょう。
自己分析ノートはエントリーシートの作成や面接対策にはもちろん、就職活動の軸を決める際にも活躍してくれます。
早めに取り掛かるほど就職活動に活かすことができるので、本記事を参考にしながら、ぜひ自分オリジナルの自己分析ノートを作成してみてください。
また先述した通り、OfferBoxに登録して使用できる自己分析ツール「AnalyzeU+」もご活用ください!