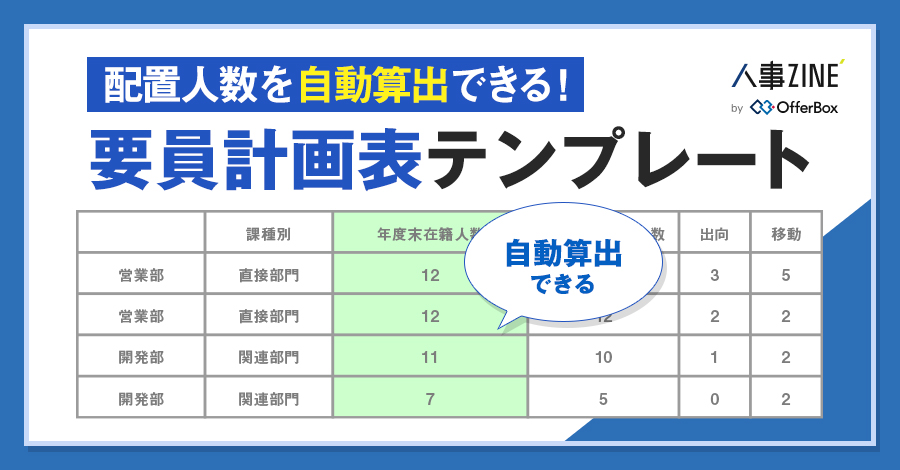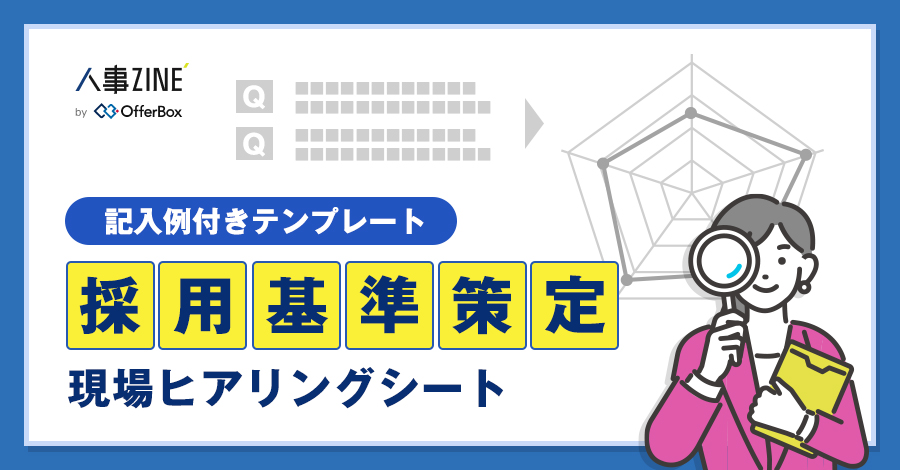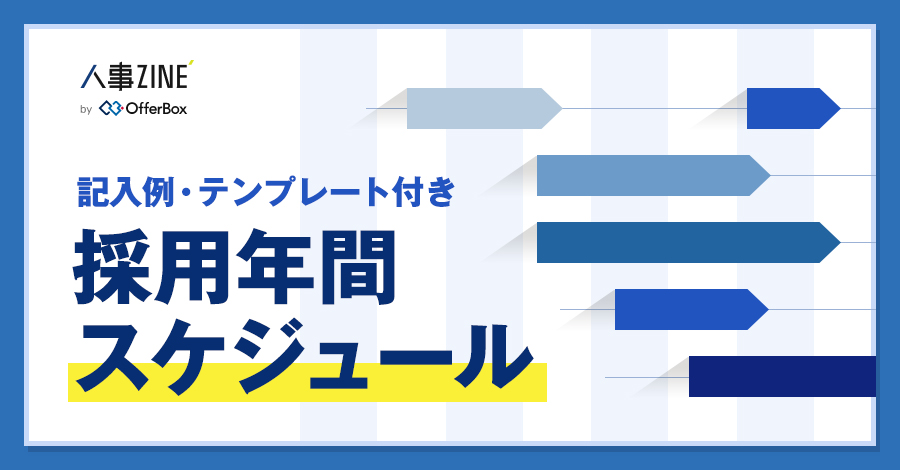コンプライアンス研修で優先すべき6分野と違反を防ぐポイント

会社の利益、イメージ、社員の心身の健康を守るとともに、人材の流出を防ぐためにも、コンプライアンスに関する意識づけは重要です。
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、契約違反、個人情報の流出などが起こらないようにするためには、どのような対策をすればよいのでしょうか。
この記事では法令や社会規範に反した場合に起こるリスクや、コンプライアンス研修のポイントなどについて解説します。

目次
コンプライアンス研修の重要性
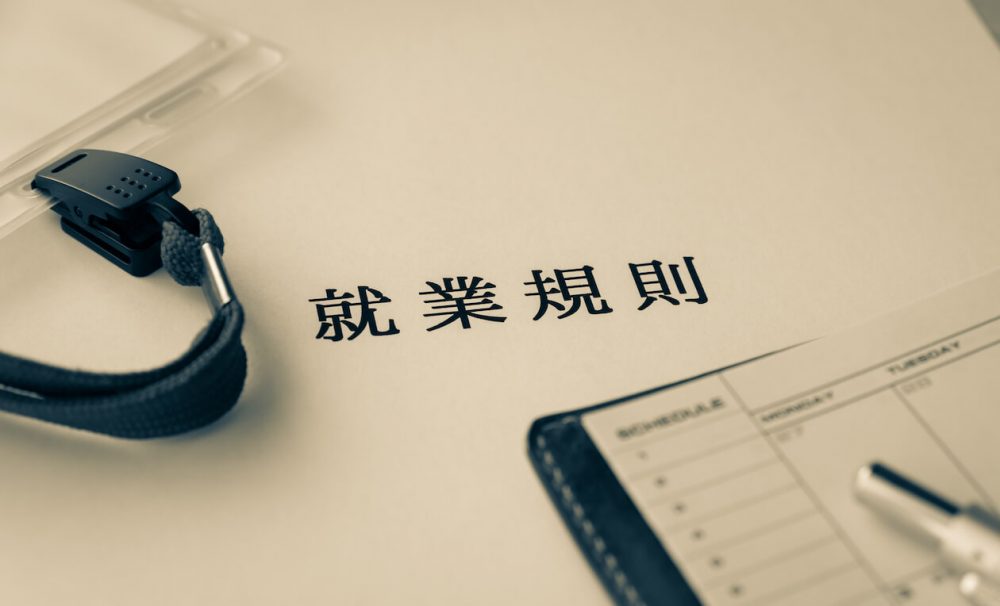
コンプライアンスとは法令順守のことを指しますが、法令以外にも社会的規範などが守られるべきこととして含まれています。会社にとってコンプライアンスは非常に重要な意味を持ち、従業員の意識を高めるために研修を行うことも多くあります。
なぜ、コンプライアンスへの意識を持つことが必要なのでしょうか。また、コンプライアンスが徹底されていないとどのようなことが起こるのでしょうか。コンプライアンスの基本について見ていきましょう。
社会的なコンプライアンス意識の高まり
社会的にも広くコンプライアンス意識の高まりがある一方、コンプライアンス違反を犯したと判断されれば、組織の根幹を揺るがす事態にもなりかねません。そこで、法令や社会規範などについて全社で学んで意識を高め、会社の利益を守りたいところです。
また、コンプライアンスを順守することは、従業員にとって働きやすい環境を作ることにもつながります。会社に関する法令や社会規範には、個人の権利を守るものが多く含まれているからです。
他にも、コンプライアンス順守により取引先や顧客から信頼できる会社と判断され、長いお付き合いが生まれるきっかけになる可能性があります。
会社の利益を守るとともに、顧客や社員にとっても理想的な状況を生み出すのがコンプライアンス順守の大きな目的です。
組織風土・モラルの定着
コンプライアンス研修を実施し、「不正や逸脱行為は起こさない」という意識が定着すると以下のようなリスクを減らすことが可能になります。
- 取引などに関する不正
- 業務上の事故・過失
- 社内規則違反
- 法令違反
- 社会からの信頼の失墜
会社内で起こる不正や法令違反、社会の期待に反する行為にはさまざまなものがありますが、なかでも会社を悩ませるのが不適切な行為を動画としてSNSなどに流出させるいわゆる「バイトテロ」や、上司から部下に対して行われるパワハラなどです。
また、業務ごとに配慮することが必要な法令を失念していたばかりに、法律上の罰則を受けることもあります。例えば「薬機法を守らずにWeb上に広告を出してしまった」「販売をする際に必要と定められている顧客への説明を怠った」などが挙げられます。
リスクマネジメントをしっかりとしてモラルを守り、そのような事態が起こらないような組織風土にすることが現代の会社に求められています。
人材確保
コンプライアンスの意識の低さは、人材を失うことにもつながります。
例えば、パワハラやセクハラなどの問題が頻繁に起こると、せっかく入社した社員もすぐに辞めてしまうことになります。また、ネットなどで「ブラック企業」のようなイメージが拡散すれば、良い人材が集まらなくなります。問題が大きくなれば企業イメージに大きな傷がつき、さらに人が流出するようになるでしょう。
一方、コンプライアンス研修で組織風土を良好に保てば働きやすいと感じることが増え、人材の定着率向上につなげられます。また、法令を順守しモラルを守る会社であるというイメージが広まれば、人材も集まりやすくなります。
コンプライアンス研修の主なテーマ6種類

コンプライアンスの意識を高めるためには、定期的な研修が必要です。
しかし、コンプライアンスは内容が多岐にわたるため、研修ごとにテーマを決めることが大切です。どのようなテーマ、内容に重点を置くのがよいのでしょうか。
関連法令
会社には、会社の運営そのものや、業務別に知っておかなくてはならない法令がさまざま存在します。
人事担当者や各部署の管理職としては、「労働基準法」「労働契約法」などの労働関連法や、下請事業者の利益を保護する法律「下請法」について熟知しておくべきです。
また、経営層としては会社の運営や管理などについて定めた「会社法」、万一経済的な破綻状態に陥ったときに必要な「破産法」「民事再生法」などへの知識が必要です。
事業部のスタッフとして知らなくてはいけないものとしては、取引について定めた「特定商取引法」「独占禁止法」、プロモーションなどの際に注意が必要な「景品表示法」「薬機法」などがあります。
以上のような法令をテーマにした研修を設けることで、取引や契約、雇用、会社運営などのトラブルを避けることができます。
商慣習
ビジネスシーンには長く行われてきた商慣習があり、プロであれば知っていて当然とされています。法令ではないにしろ、商慣習を知って守ることは相手への配慮であり、ビジネスを成功させるためのポイントでもあります。業種や製品・サービス、地域によっても商慣習は異なることがあるため、常に学んだり確認し直したりしておくことが大切です。
さらに、注意を必要とするのが海外と取引がある場合です。国・地域ごとに異なる法令、独特のルール、慣習が存在します。日本では問題がなくても、海外ではタブーとされる慣習も存在し、反してしまったために商取引が進まなかったり、場合にっては訴えられてしまうこともあります。
ハラスメント
研修をする際に最も優先したいテーマがハラスメント(嫌がらせ)に関することです。なかでも事例が多く重要な課題になるのがパワーハラスメント(パワハラ)です。パワハラは立場上の強者にあるものが弱者に対して行うもので、社会からの目も厳しくなっています。
また、セクシャルハラスメント(セクハラ)、マタニティーハラスメント(マタハラ)を防ぐためにも、しっかりとした意識づけが必要です。
そのようなハラスメントは決して起こしてよいものではありません。ただし、難しいのは環境差、世代差、個人差などによりさまざまなギャップがあり、何がハラスメントなのか本人も周囲も線引きしにくいことにあります。
そこで、定期的な研修によりどのような言動がハラスメントになるか、指導する必要があるのですす。
セキュリティ
ハラスメントと並んで会社の問題となりやすいのがセキュリティに関することです。社員がうかつに会社のデータを持ち出したために起きた機密漏洩や、個人のパソコンへの侵入、パスワードの流出などの事態も想定されます。
特に最近はオンラインを経由して仕事をする機会が多いうえ、リモート・在宅勤務の普及も加速しており注意が必要です。機密性の高い情報も簡単に共有できる環境であるため、情報の取り扱いルールを再確認しておくようにしましょう。
また、実は怖いのが取引先社員になりすましたメールが送られる「標的型攻撃」です。取引先の社員のメールを盗み取られたために、ウィルス付きメールが送られれば、多大な迷惑をかけてしまうことになります。
情報リテラシー
SNSでの軽率な投稿により炎上して企業ブランドまで毀損するケースもあります。「店内で不謹慎な行動をとった写真を流出させた」「お客様の悪口をSNSに書き込んだ」「会社の名前を使って問題のある意見を書き込んだ」などが批判され、会社が炎上したというニュースをたびたび目にすることがあるかと思います。
業務でもメール・チャットやSNS、Web会議など、情報ツールを使いこなすことは大切ですが、正しい運用がされていなければトラブルに発展します。情報流出や他人を不快にさせる事態を防ぐためにも、しっかりと研修を通してルールを周知することが大切です。
「会社の情報を流出させない」「IDやパスワードを流出させない」「SNSなどに不用意な書き込みをしない」などのほか、ネットの怪しい情報に惑わされないように意識づけをしたいところです。
ビジネスマナー
新入社員向けに対してはビジネスマナー研修の一環としてコンプライアンスに関する事柄も教えることが大切です。
ビジネスの世界には学生時代にはないマナーやルールがあり、反していれば相手を不快にさせたり傷つけたりすることもあります。そこで、座学やOJTなどで最初にしっかと学べる機会を設けましょう。
例えば、営業などで社外の人と接する際には、会社の機密情報や、ほかの社員の個人情報を流さないように注意が必要です。また、宗教、思想、差別、ジェンダーに関する事柄についても、避けるべきことについて指導するようにします。
ビジネスマナーおよびコンプライアンスについて最初にしっかりと学ぶことは、従業員の将来にとっても良い影響をもたらすと考えられます。
コンプライアンス違反を防ぐためのポイントとは?

コンプライアンス違反によるダメージを会社が挽回するのには相当な努力が必要になります。そこで、違反を防ぐためには、どうすればよいのでしょうか。より効果的に結果が望める研修のポイントについて解説します。
定期的な実施と振り返り
研修は一度だけ実施すればよいというわけでなく、定期的に行うことが大切です。繰り返して学び考えることで身になっていきます。
もし、従業員に対して一斉に研修を行うのが難しければオンライン学習(Eラーニング)を取り入れるのも有効です。ただし、動画は流して見てしまうこともあるので、後からレポートを提出させるなどの方法も取り入れるようにします。
また、事件が起きて社会的に注目されているようなタイミングで研修を行うのも大切です。そのほうが、誰もがコンプライアンスの順守について重く考えるため、印象に大きく残るからです。
コンプライアンス違反は頭では分かっていても、うっかりやってしまうことがあります。研修の数を重ねることで、常に意識を持てるようにしておくことが大切です。
管理者による意識の徹底
従業員だけに学ばせるのではなく、管理職が率先してコンプライアンスを守る姿勢を持つことも重要です。管理職が正しい姿勢を見せることで、部下の空気も変わっていきます。
そもそも、管理職は現場の従業員と業務を統括しているため、最もコンプライアンスを守らなくてはならない立場にあるといえます。管理職が業務の指示を出す時点で法令を知らなければ、従業員は間違った指示のまま違反を犯してしまうことがあるからです。
また、ハラスメントなどを撲滅し従業員の適切な業務環境を守ることで、人材の定着につなげることも管理職の大切な役割です。管理職自身も研修などで学ぶ機会を設け、率先して順守する姿勢を見せることでよりよい職場環境を実現できます。
コンプライアンス違反を早期発見する仕組み作り
社内でコンプライアンス順守に取り組むなかで、違反を早期発見する仕組みも作りたいところです。重大なトラブルを生んでからでは修正は容易ではありませんが、早期段階であれば簡単な注意で済む場合もあります。
コンプライアンス相談窓口の設置、匿名投稿の受付、調査体制の整備などしておくと、万が一コンプライアンス違反に該当する疑いがある事例が発生した場合も、早く発見・対処できます。
直接、管理者が面談などで話を聞いてもよいのですが、従業員が打ち明けにくい場合もあります。その際の対策を考えておくことが大切です。
まとめ
今回はコンプライアンス研修について見てきました。
ハラスメントや情報管理、労務管理、ビジネスマナー、取引などに関する会社や管理職、従業員が守らなくてはいけない法令や社会規範は広範囲にあります。守られていない場合、法的・世間的なペナルティが課され、会社に多大な損害を与えることも多々あります。そうならないためにも定期的な研修を全ての階層で行い、常に意識づけておくことが必要です。