内々定・内定の定義とは?法的な観点でリスクや役割を専門家が解説
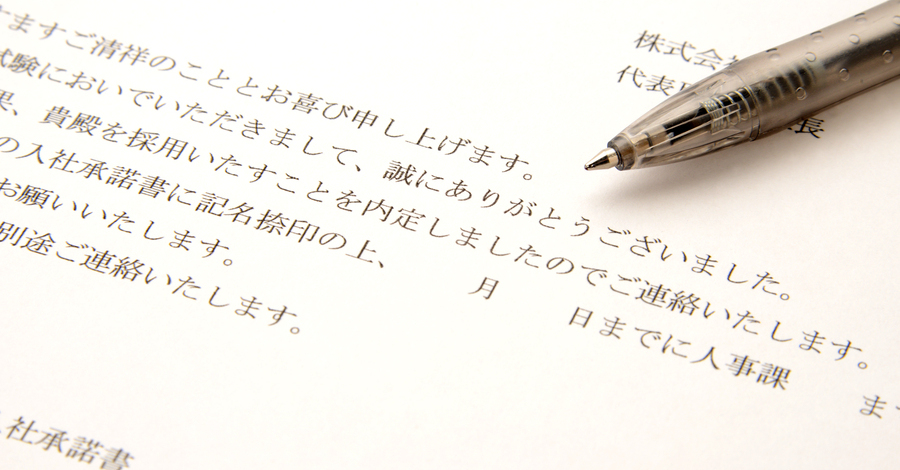
夏が終わり秋には多くの学生が企業から内定や内々定をうけます。この記事では、内定や内々定において採用担当者が知っておくべき基礎知識だけでなく、法的観点からの定義やリスクについてKKM法律事務所 代表弁護士 倉重公太朗氏にお話しいただきました。
また、こちらの資料では、内定者フォローや内定辞退の原因を解説しています。内定者が実際に入社するまでの間に「どんなフォローが必要になるのか」や「内定辞退の原因別の具体的なソリューション」を紹介しております。ぜひダウンロードしてご活用ください。

内定とは?採用担当者が知っておくべき基礎知識
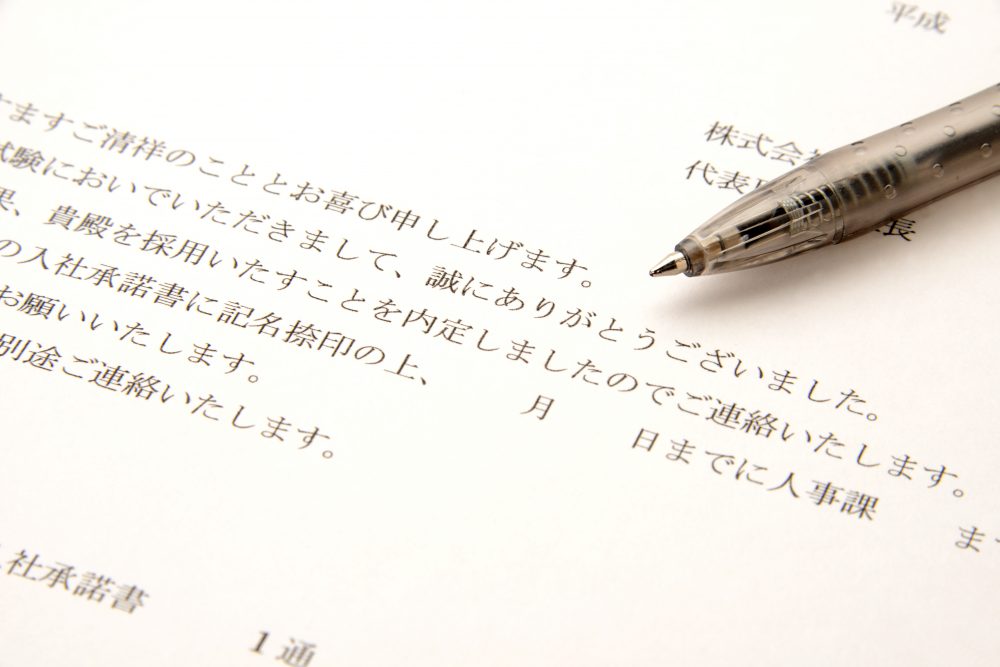
まずは、内定の定義を押さえておきましょう。採用担当者が知っておくべき基礎知識とあわせてご紹介します。
内定の定義
採用活動(就職活動)における内定とは、労働が始まる前の段階でありながら、採用が内々に決まることです。つまり内定は、企業にとっては「卒業後はあなたを当社が雇用する」、学生にとっては「卒業後は貴社で働く」と契約することです。

編集部

倉重
弁護士
いつから内定の契約が成立したかは、企業の採用プロセスによって変わります。内定を出すタイミング方法や、選考プロセスがどのように終了するかは、企業により異なっているからです。よって「内定式をしていないから内定ではない」「内定承諾書にサインがないから内定ではない」という一定の定義はありません。状況が成熟した段階にあり、実質的な契約が成立しているかを判断します。考慮する点としては、採用のプロセスが一定終わっているか、企業は学生さんの採用を決めているか、といった状況を見ます。

編集部

倉重
弁護士
いわば、内定とは企業と学生の両者を守るための契約であり、労働契約がされている状態とみなされます。つまり、『内定を取り消す=解雇』と同じ扱いです。契約が成立されているということは、お互いを法律で拘束している状況なので、原則として内定を取り消すことはできないです。
内定と内々定の違い

編集部

倉重
弁護士
内々定・内定の取り消しのリスクやルール
前述の通り、正当な理由なく内定を取り消すことはできません。ここでは、企業側が内定を取り消すリスクや取り消しを認められるケースについて解説します。
企業からの正当な理由があって内定の取り消しを行った場合でも、企業は以下のようなリスクを負うことになります。
- 訴訟リスク
- 企業イメージやブランド力の低下
企業からの一方的な内定取り消しは損害賠償請求などにつながるリスクがあります。やむを得ず内定を取り消す場合にも、「事前に十分な説明をして理解を得る」「他の就職先を紹介する」など、訴訟リスクを回避する措置を取ることが重要です。
また、近年ではSNSやインターネットを日常的に利用する内定者も多いため、内定取り消しによって自社についての悪い口コミ投稿が拡散されるリスクもあります。このような事態になれば、企業イメージやブランド力の低下につながりかねません。
たとえ正当な理由による内定取り消しでも、内定者に対して丁寧かつ誠意ある対応を心がけることが重要です。

編集部

倉重
弁護士
例えば、2020年の新型コロナウイルスの拡大がその一例です。当時、内定の取り消しが認められるケースがいくつかありました。ただし、そのケースでも新型コロナウイルスの影響を直接的に受ける業種に限ります。「なんとなく景気が悪化した」という場合は認められません。自社に直接どういった影響があるかをみられます。

編集部

倉重
弁護士
基本的には内々定も内定と同じように、安易に取り消して良いものではありません。また、企業も学生も多くのプロセスを経て内々定に至っています。企業の一方的な都合で取り消すことで、法的な観点だけではなく信頼の大きな低下につながるリスクも考えるべきです。
まとめ
内定は労働が始まる前段階でありながら、法的な拘束力を持つ労働契約の一種です。そのため、採用担当者は正しい知識を知り、適切な方法で内定者への対応をする必要があります。また法的な観点だけでなく、さまざまなリスクを知り、学生と向き合う必要があるでしょう。
さいごに:倉重氏からのコメント

倉重
弁護士
内定や内々定について、採用担当者が知っておくべき基礎知識や法的観点でのリスクについてご紹介しました。
とはいえ、実際に内定者とどう向き合っていくのか迷っている人事の方も多いのではないでしょうか。こちらの資料では、内定者フォローの具体的な手法や辞退防止のためのポイントなど、全般的なフォロー方法を紹介しております。ダウンロードして活用いただき、内定者フォロー施策の企画にご活用ください。








