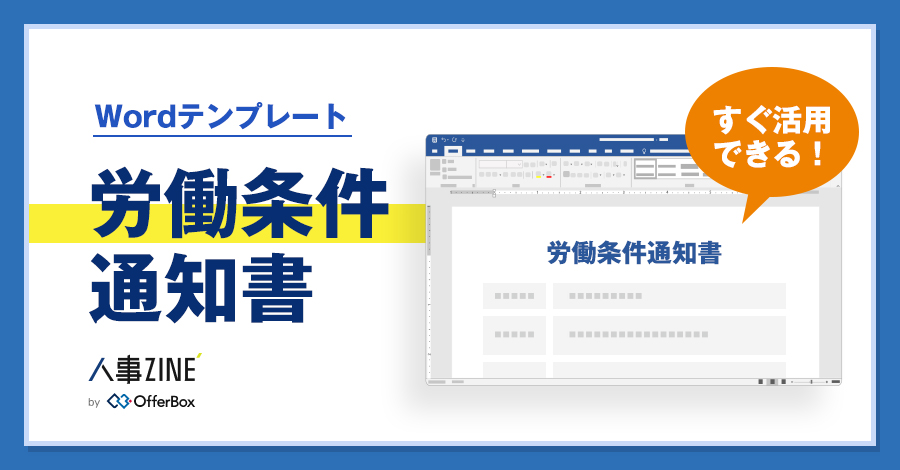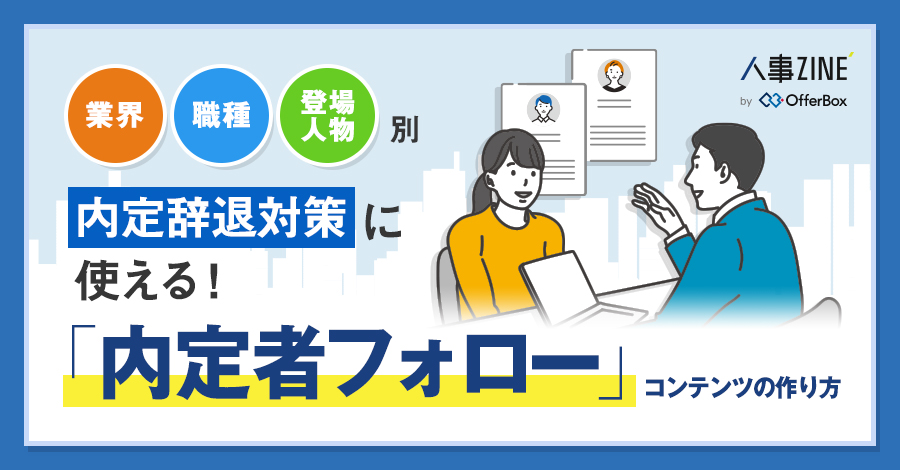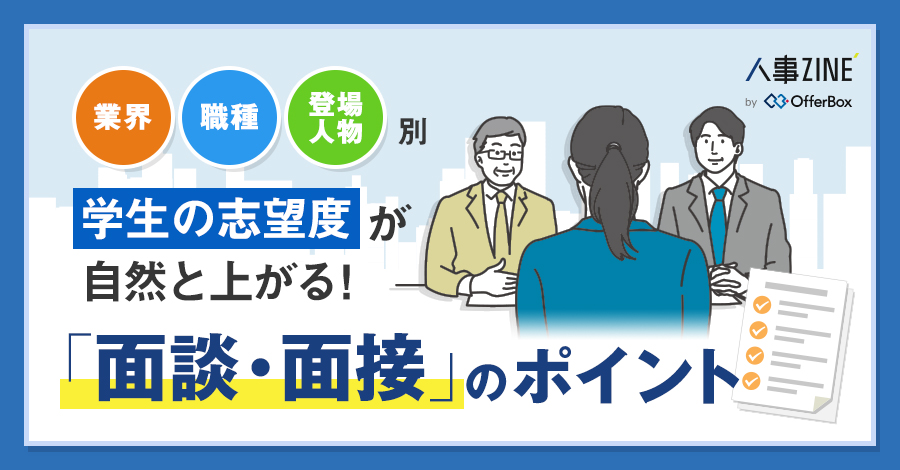残業手当(時間外手当)とは?割増率・計算方法や企業側の注意点

残業手当の運用は法令遵守、企業としての信頼性や社員の働きやすさにつながるテーマであり、人事担当者や管理担当者は正確な理解・対応が求められます。一方、残業に関するルールは複雑で、また「働き方改革関連法」が順次適用されてきたなか、正しく理解するのは簡単ではありません。
本記事では、まず残業手当の基本を解説し、次に法定外残業手当や休日手当といった関連する手当も整理します。また、計算方法や企業が注意すべき点、みなし残業制や特例業種の扱い方など、働き方改革関連法の適用が完了済みの2024年末時点の情報をもとに、実務に役立つテーマも取り上げます。
人事ZINEでは、「【サンプル】労働条件通知書」をご用意しております。残業をはじめとする労働条件を通知書に取りまとめるのは工数がかかるものですが、本資料を用いればテンプレートに沿ってスムーズに作成できます。ぜひダウンロードのうえご活用ください。
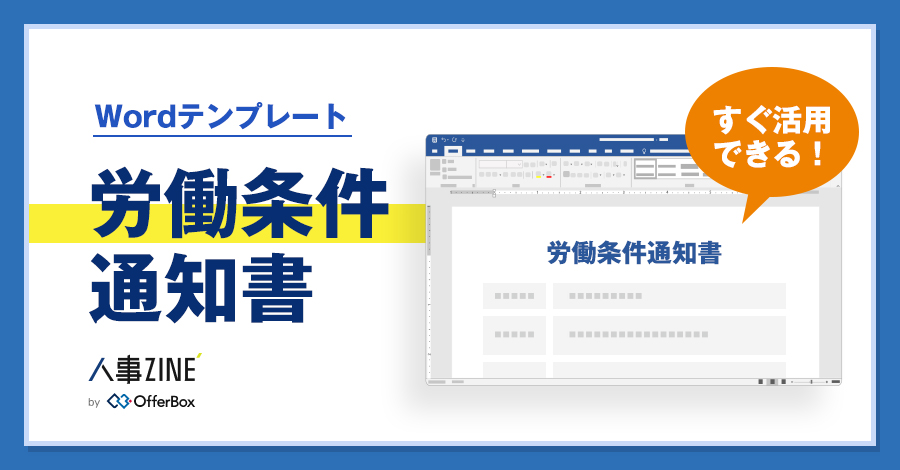
目次
残業手当とは

残業手当とは、残業に対して支払う賃金を広く指します。
なかでも「法定時間外労働」と呼ぶ場合は、労働基準法にもとづき、法定労働時間を超えて働いた時間に対して支払う割増済み賃金です。これは法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超える労働が対象となります。例えば、所定の1時間あたり賃金が2,000円の場合、残業時の割増率が25%であれば、1時間あたりの残業手当は2,500円です。
ただし、残業にも「法定時間外労働」「法定時間内労働」といった種類があり、種類によって割増の有無や割増率が異なります。さらに、休日労働や深夜労働では異なる割増率が適用されるケースもあります。残業手当を正確に理解するためには、まず残業そのものの概念を正確に把握することが重要です。
なお、残業手当は正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートタイム社員といった雇用形態を問わず適用されます。
残業について整理しておくべきポイント
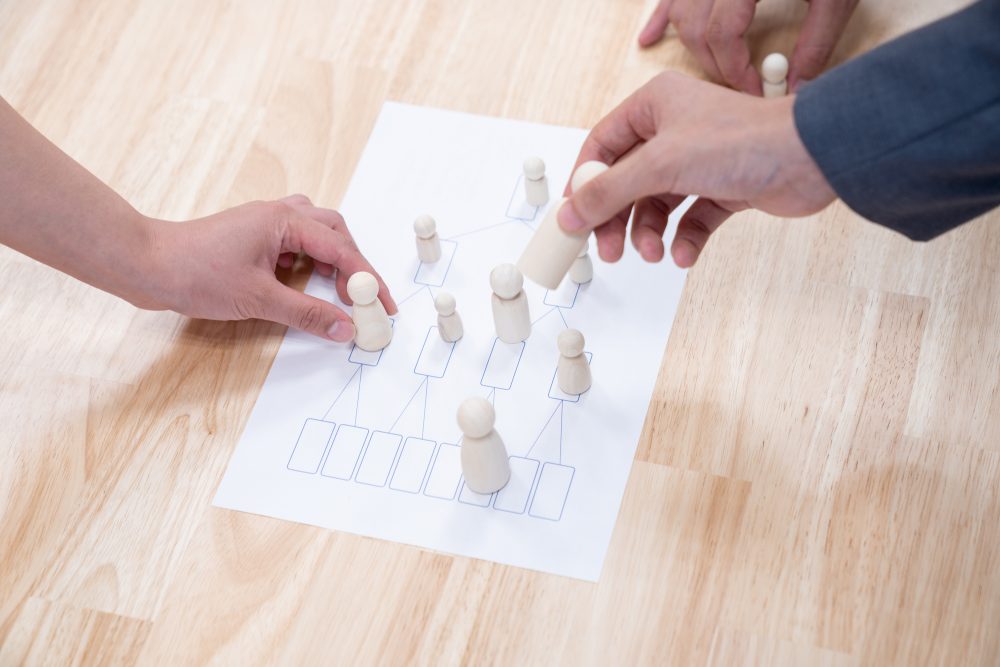
残業手当について考える際は、残業の定義やその種類を整理しておくことが欠かせません。ここでは、まず残業の定義やその種類について整理します。
残業とは
「残業」とは、企業が定めた所定労働時間を超える労働を広く指します。所定労働時間とは、就業規則や労働契約により、企業ごとあるいは労働契約ごとに定めている1日の労働時間のことです。例えば、1日の所定労働時間が午前9時~午後5時(休憩1時間含む)で7時間の場合、7時間を超える部分が残業に該当します。
なお1日の労働時間は、実際に出勤した時間から起算します。企業によっては始業時刻よりも早く業務を開始することを「早出残業」と呼ぶケースもありますが、労働基準法においては上記の例のように「出勤した時間からカウントして所定労働時間を超えた部分」が残業に該当します。
時間外労働とは
「時間外労働」とは、「法定労働時間」を超える労働を指します。労働基準法では、法定労働時間は「1日8時間・週40時間」と規定されています。この時間を超える部分は、時間外労働として割増賃金の支給対象になります。
企業が時間外労働を命じるには、労使協定である「36協定」(通称「サブロク協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。36協定により時間外労働の上限時間や特別条項を定めてはじめて、企業側は時間外労働をさせることができます。
法定内残業と法定外残業の違い
残業には、「法定内残業」(法内残業)と「法定外残業」(法外残業)の2種類があります。
法定内残業は、「企業が定める所定労働時間を超えるが、法定労働時間内に収まる」残業を指します。例えば、所定労働時間が1日7時間の企業で、7時間を超えて8時間まで働く場合が該当します。この場合、法定労働時間を超えないため割増賃金の支払い義務はありません。
残業には、25%以上の割増賃金を支給することが法律で義務付けられています。さらに月60時間を超える法定外残業に対しては50%の割増率が適用されます。
残業手当と関連する手当の種類

「残業」そのものについて整理したところで、残業手当も解説します。「法定外残業手当」「法定内残業手当」、そして関連する「休日手当」の3種類について見ていきます。
法定外残業手当(時間外手当)
法定外残業手当は、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えた労働に対して支払う割増賃金です。割増率は最低25%で、以下のように割増率が段階的に上昇します。
| 種類 | 支払う条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外 (時間外手当・残業手当) |
||
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
|
時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間など)を超えたとき | 25%以上 |
|
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき | 50%以上 |
法定外残業の基本的な条件として、法定労働時間を超える労働が対象となり、25%以上の割増賃金が発生します。
「限度時間」とは、1ヶ月45時間・1年360時間を指します。この時間を超えた労働に対しては、割増率が25%超になるよう努めることとされています。
時間外労働が月60時間を超えると、50%以上の割増率が適用されます。このルールは大企業に先行して適用され、中小企業向けの経過措置がありましたが、2024年末時点では全ての企業が対象となっています。
法定内残業手当
法定内残業手当は、企業の所定労働時間を超える労働に対して支払う賃金です。「法定労働時間の範囲での残業に割増賃金を適用すること」は、法律上の義務ではなく、企業の裁量に委ねられています。
例えば、所定労働時間が1日7時間の企業で、1時間の残業が発生した場合、法定労働時間(8時間)を超えていないため、法律上は割増賃金を支払う必要はありません。しかし、企業独自の規定により、このようなケースでも割増の残業手当を支給する企業も存在します。
休日手当
休日手当は、「法定休日」に労働が発生した場合に支払う賃金です。労働基準法では、週に最低1日の休日を法定休日として定めています。この法定休日に労働が発生した場合、割増率35%以上の休日手当を支払う必要があるのです。
週休2日制を採用している企業の場合、1日は法定休日、もう1日は法定外休日となります。法定外休日に労働が発生した場合、法律では割増賃金の支払い義務はありませんが、法定内残業手当と同じく、企業によっては独自に手当を設けている場合もあります。
深夜手当
深夜手当は、深夜時間帯に労働が発生した場合に支払う賃金を指します。労働基準法では、22時から翌朝5時までの間を「深夜時間」と定めており、この時間帯に勤務させた場合、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
さらに、深夜手当は時間外手当と同時に発生する場合があります。例えば、1日8時間以上継続して働かせ、かつ22時以降の勤務が発生したケースでは、以下のような計算になります。
- 法定外残業手当:22時以前の労働時間が法定労働時間を超えた場合、25%以上の割増率が適用
- 深夜手当:22時以降の労働時間については、さらに25%以上の割増率が適用
後者のケースのように、重複して適用される場合、割増率は合計で50%以上となります。
時間外手当(残業手当)の計算方法

続いて、時間外手当(残業手当)の計算方法を例を出して解説します。
時間外手当(残業手当)基本の計算式
時間外手当(残業手当)の基本的な計算式は以下の通りです。
時間外手当(残業手当)=1時間あたりの賃金×時間外労働の時間数(時間)×1.25
時間外手当(残業手当)の計算例
所定労働時間が午前9時から午後5時までの勤務(休憩時間が1時間)で、1時間あたりの賃金が1,000円の社員が、午後8時まで「残業」を行った場合
午後5時から午後6時までの法内残業
1,000円(1時間あたりの賃金)×1時間(午後5時から午後6時)=1,000円
午後6時から午後8時までの法外残業
1,000円(1時間あたりの賃金)×2時間(午後6時から午後8時)×1.25=2,500円
よって、支給すべき残業手当(時間外手当)は
法内残業分の手当1,000円+法外残業分の手当2,500円=3,500円
となります。
休日・深夜手当を考慮した計算例
法定休日に労働が発生した場合の休日手当の計算方法は以下の通りです。
1,000円(1時間あたりの賃金)×5時間×1.35=6,750円
また法外残業と深夜勤務が同時に発生する場合の賃金も計算してみます。例えば、時給1,000円の社員が時間外労働でかつ22時以降も勤務した場合、25%以上の割増率が同時に適用され、その時間帯の賃金は以下のように計算できます。
1時間あたり賃金=1,000円(1時間あたりの賃金)+法外残業分の割増賃金250円+深夜の割増賃金250円=1,500円
休日・深夜の割増賃金にも注意
休日や深夜に労働した場合も割増賃金が支給されます。休日労働とは「法定の休日に勤務させる」ことで、労働基準法によって通常賃金から35%割増しして支給することが定められています。
また、午後10時から午前5時の深夜に労働した場合にも、通常賃金の25%割増しした賃金を支払わなければなりません。
時間外手当と深夜の割増賃金は合わせて計算されます。そのため、午後10時以降の法外残業については、時間外労働分の割増率25%と深夜労働分の割増率25%を合わせた50%が適用されます。
時間外労働が発生する際に企業側が守るべき注意点

残業のなかでも時間外労働が発生する場合、企業側はいくつかのルールに注意する必要があります。ここでは主な3つを紹介します。
36協定を締結する
労働基準法第36条では、「会社は法定労働時間を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労働組合などと書面による協定を結んで労働基準監督署に届け出ること」が義務付けられています。
この協定を一般的に「36協定」と呼びます。この36協定を結ばずに時間外労働や休日労働をさせた場合には違法の対象です。
労働条件を通知する
企業側は、36協定で合意した内容をはじめ、労働条件を社員に開示する必要があります。残業ルールや割増率といった条件に変更が発生した場合は労働条件を通知しましょう。
人事ZINEでは、「【サンプル】労働条件通知書」をご用意しました。テンプレートに沿って作成でき、またWordファイルでダウンロードしてすぐにご活用いただけます。労働条件通知書を作成する際はぜひご活用ください。
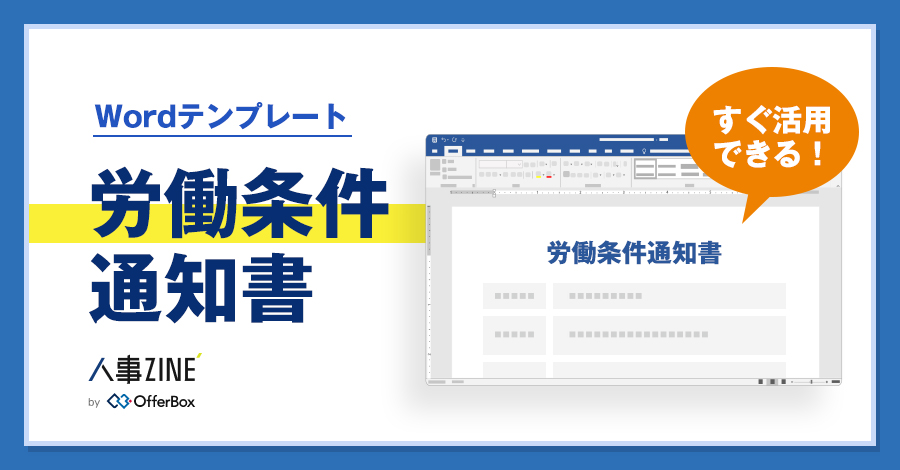
時間外労働の上限規則を守る
時間外労働は原則として月45時間、年360時間の上限が決められています。特別の事情がなければ、この上限を超えることはできません。
特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は以下の範囲で収める必要があります。
- 年720時間以内
- 時間外労働+休日労働は月100時間未満
- 2~6ヶ月平均80時間以内
そして、原則である月45時間を超えられる範囲は、年6ヶ月までです。これに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
特殊なケースでの残業の取り扱い方法
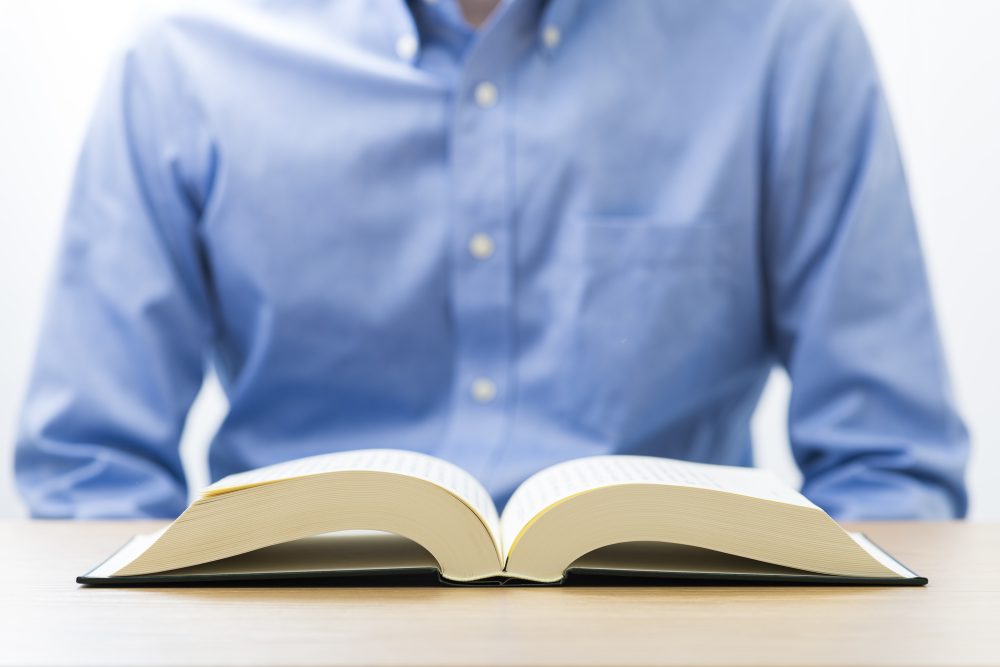
残業の取り扱いには基本的なルールがある一方で、特定の条件や業種においては特例もあります。ここでは、「みなし残業制」(固定残業代制)と「時間外労働の上限規制の特例業種」について詳しく解説します。
みなし残業制(固定残業代制)
みなし残業制とは、一定の時間分の残業をあらかじめ基本給とともに支払う仕組みです。
しかし、この制度を導入している場合でも、法定労働時間を超える労働に対しては時間外労働の割増率が適用されます。また、みなし残業代の範囲を超える労働が発生した場合は、当然ながら追加の賃金を支払わなければなりません。
さらに、みなし残業制を適切に運用するためには、設定する想定残業時間が重要です。具体的には、時間外労働の限度時間である「月45時間」や年間上限の「360時間」を超えないように設定するのが無難とされています。仮にみなし残業時間が月30時間を超える場合、年間上限の360時間を上回ることから、監督機関や求職者から「過剰な残業をさせているのではないか」と疑問を持たれる可能性があります。こういった理由で、みなし残業時間を月30時間以内に収めるケースもあります。
時間外労働の上限規制の特例業種
働き方改革関連法により、2024年4月までに時間外労働の上限規制(月45時間以内・年360時間以内)が全ての業種に適用されました。ただし、「医師」「バス・タクシードライバー」「建設職」といった特定の業種では特例が認められています。
例えば、「バス・タクシードライバー」の場合、「1日の拘束時間は13時間以内」(最大15時間まで延長可能)とされており、法定労働時間の8時間よりも長く設定されています。一方、「1日の休息期間は11時間以上を基本とし、9時間を下回らない」というインターバル休息ルールも定められており、企業側はこういった制度も正確に理解したうえで運用することが欠かせません。
参考:厚生労働省特設サイト はたらきかたススメ「バス・タクシー」
まとめ

本記事では、残業手当に関する基本的な考え方から、関連する深夜手当、休日手当の計算方法、そして注意すべき労務管理のポイントまで幅広く解説しました。残業手当の運用は法令遵守や社員の働きやすさを実現するうえで重要な課題であり、制度を正確に理解して適切に対応することが欠かせません。
人事ZINEでは「【サンプル】労働条件通知書」をご提供しています。残業などの労働条件をまとめる通知書を作成する際、本資料を活用すればフォーマットに沿いながらスムーズに進められます。ぜひダウンロードのうえご活用ください。