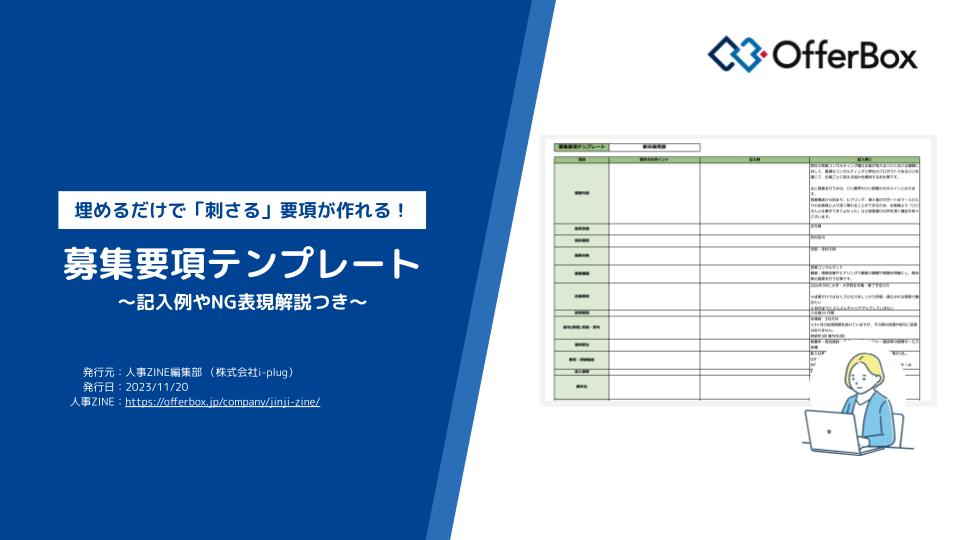新卒採用の手法一覧・トレンドと採用課題・お悩み別のおすすめ手法

新卒採用の計画を立てるとき、「どの求人媒体(ナビ)を使おうか?」「人材紹介のほうがいい?」「逆求人が流行っているらしい」「うちでもリファラル採用ってできるの?」…など、採用の“手法”に迷うことも多いのではないでしょうか?
近年、学生に認知してもらうには大手ナビ媒体への掲載は必須かと思われました。しかし今年度の就活生アンケートによる「活用する就職関連サイト」では、「リクナビ」「マイナビ」との回答率は昨年より約20ポイントも下落しており、人事担当者が感じていた「学生のナビ離れ」が数字にも表れた形となりました(HR総研:「2020年卒学生 就職活動動向調査(3月調査)」結果報告 による)。
ナビ媒体は就活生の大半が登録するため、広範囲・大人数にアプローチできそうな印象がありますが、
- 学生の認知がない/業界イメージがよくないと、社名や業種で検索してもらえない
- 高額なプランを申し込まないと上位表示されない
- 掲載料を先払いするため、採用できなかったときの損失が大きい
といったデメリット(リスク)もあります。
ナビ媒体に限らず、「自社に合った採用手法」を選択することが、新卒採用成功のカギとなります。
それでは、下記の採用手法一覧について、お悩みの課題別におすすめをご紹介します。

目次
【採用課題別】最新版 新卒採用の手法一覧
まずは、一般的な手法を挙げてみます(これらの手法のうちいくつかを組み合わせて実施している企業が多いです)。
<一般的な手法>
- 大手ナビ媒体(求人広告サイト)
- 就職イベント(合同説明会、マッチングイベント)
- 大学内イベント(業界・企業研究セミナー、大学内合説)
- インターンシップ
- ダイレクトリクルーティング(企業が求職者の資質を見てスカウトする採用)
- リファラルリクルーティング(従業員が知人を自社に紹介する採用)
- ソーシャルリクルーティング(SNSなどを広報やスカウトに活用する採用)
- 会社説明会(合同説明会ではなく自社単独のもの)
- 自社の採用ホームページ
- 専門ナビ媒体(地方・職種・理系・体育会など特化型)
- 人材紹介
- ハローワーク
<補助的ツール>
- 適性検査
- 能力検査
- 採用管理ツール
- 採用代行
……などといった手法があります。
それでは、企業のお悩み課題別におすすめの手法とおおよそのコスト目安をご紹介し、それぞれ解説していきます。
【課題1】エントリーが集まらない・・・
<お悩み内容>
- BtoBや地方企業で、自社を知ってくれている学生の数が少ない
- 業界のマイナスイメージが強く説明会に来てもらえない
- ナビ媒体には載せているが、エントリーが年々減っている
- 学生を選考で選りすぐれるほどの母集団が形成できない
これらの課題に対しておすすめの新卒採用手法を、以下にご紹介します。
ダイレクトリクルーティング:成功報酬 約30万円/人〜
大手ナビ媒体に掲載しているのに応募が集まらないとお悩みの企業には、人数だけでなくマッチング度までコストパフォーマンスが優れた「ダイレクトリクルーティング」、いわゆる「逆求人型」「スカウト型」と言われる手法がおすすめです
| メリット |
・ナビ媒体からの不特定多数の応募を待つなど、応募の「数」を必要とする手法とは異なり、応募の「質」=マッチング度を高めることで、選考通過率の高い人材のみを必要最低限だけ、効率的に集めることができる。 |
|---|---|
| デメリット | ・100人など大量採用を全てダイレクト・リクルーティングで行うと、費用がかさむ。 |
大手ナビ媒体(求人広告サイト):掲載料 約80万円〜
まだ大手ナビ媒体に載せていないが採用意欲が高い、ベンチャーなどの成長企業であれば、思い切ってナビ媒体に載せることも手段です。ナビ媒体にはベンチャー企業よりも老舗企業や大手企業、インフラ系、自治体などの掲載が多いため、「ベンチャー」「スタートアップ」などのキーワードで検索するベンチャー志向学生に見てもらえる可能性があります。
| メリット |
・大手ナビ媒体(リクナビやマイナビ)は就活生の大半が登録するため、知名度がある企業は掲載するだけでそれなりにエントリー数が増えることが見込める。 |
|---|---|
| デメリット |
・掲載スペースを大きくしたり、検索結果で上位に表示されるには、高額なプランやオプションを申し込む必要がある。 |
人材紹介:成功報酬 約80万円/人〜
採用人数の目標は必達ではなく「良い人材がいれば若干名採用する」といった程度で、新卒採用サービスに投資するほどでもないとお考えであれば、人材紹介も一つの手です。メリットは何より、成功報酬型で投資のリスクがないことです。
人材の質も紹介会社(エージェント)に指示でき、ある程度スクリーニングしてもらってから、絞られた人材にのみ会うことが可能です。ただしエージェント個人のスキルやモチベーションに左右される部分がある点には注意が必要です。
| メリット | ・求める人材のみを紹介してくれるサービス。
・初期費用も少なく、入社前に内定辞退があれば返金されるなど、成功報酬型のサービスが多い。 |
|---|---|
| デメリット |
・成功報酬型が一人80〜100万円程度と高額になる(中途人材紹介では初年度年収の3割程度が相場。理系は特に高額で100万円超のケースも)。 |
【課題2】理系が採れない・・・
<お悩み内容>
- 理系学生は人数が少なく、とにかく売り手市場!
- 機電系や建築系のエンジニアがほしいのに……!
- 大手メーカーとの「理系の取り合い」に勝てない……
- 事業内容のイメージが先行して、欲しい理系学部からの応募が少ない……
(例:食品メーカーで化学・農学系は集まるが、工場の機械を管理できる機電系が来ない)
これらの課題に対しておすすめの新卒採用手法を、以下にご紹介します。
ダイレクトリクルーティング:成功報酬 約30万円/人〜
理系学生は母数自体が少なく、また就職活動も文系のようにナビ媒体メインというよりは、研究室や大学経由で知った企業へ入社することが多くなります。研究室教授や大学とのコネクションを新規に築くことは難しいものですが、ダイレクトリクルーティングに登録している、就職意欲の高い理系学生は一定数います。
| メリット |
・学部や専攻内容で対象を絞り込み、直接アプローチできる。 |
|---|---|
| デメリット | ・大学や研究室、教授などとの直接のコネクションから採用することと比較すると採用コストがかかる。 |
大学内イベント・研究室訪問:イベント出展料 無料〜
地元の大学や、ニッチな研究内容など、具体的に狭いターゲットが決まっているのであれば、直接その大学や学部の学生だけにアプローチできるこの手法で十分だと考えられます。
| メリット | ・研究内容が予め分かっているため、自社に必要な研究をしている人材のみに効率的に接触できる。 |
|---|---|
| デメリット |
・合説イベント同様、学内イベントへの学生の参加率も下がっている。 |
【課題3】優秀層の学生に会えない・・・
<お悩み内容>
- MARCH以上を採りたいと思っても、エントリーが少ない……
- 業界大手とバッティングしてしまう。差別化する機会を持てない。
- 内定者フォロー期間が長くなりすぎるので、あまり早くは内定を出せない……
- 成長意欲やガッツのある学生はどこにいるの?
- 早ければ早いほど良いの?3月や6月からは出会えないの?
これらの課題に対しておすすめの新卒採用手法を、以下にご紹介します。
インターンシップ:インターンシップナビ媒体掲載料 無料〜
早期に学生と接触することができ、また能力や資質を実際の業務をさせて見極めることができる機会として、インターンシップは年々注目が高まってきました。優秀層は就職活動の開始時期も早く3年生の夏にはインターンシップに参加します。優秀層が受けたいと思うような充実したプログラム内容、「実際の仕事を体験できる」「責任を与えられる」「フィードバックがある」といったインターンシップを用意できると良いでしょう。
| メリット |
・ボリュームの大きいプログラムや、早期のスケジュールで実施することで意欲の高い学生に出会える。 |
|---|---|
| デメリット | ・開催時期やプログラムを策定し現場に受け入れを依頼するなど、受け入れの準備には工数がかかる。 |
ダイレクトリクルーティング:成功報酬 約30万円/人〜
具体的にターゲットとしている大学・学歴がある場合や、これまでのナビ媒体での募集では集まりにくかった層から、いくらかの人数を採用したいという場合には、ダイレクトリクルーティングによる詳細なターゲティングがおすすめです。
| メリット |
・事前にプロフィールや自己PRを確認できるため、学歴のほか、志向、経験、自信のあることなど様々な条件で対象を絞り込み、自社のターゲットである層にのみ直接アプローチできる。 |
|---|---|
| デメリット | ・自社にとっての「優秀」とは何かを要件定義する必要がある。 |
【課題4】入社までに内定辞退が出てしまう・・・
<お悩み内容>
- 大手の内定出しに合わせて一気に内定辞退が出た
- 夏インターンから入社まで2年近くフォローし続けるなんて、無理……
- 「御社が第一志望です!」って言ってたのに……もう誰も信じられない……
これらの課題に対しておすすめの新卒採用手法を、以下にご紹介します。
ダイレクトリクルーティング:成功報酬 約30万円/人〜
最初から使うことで学生のエンゲージメント(企業への思い入れ)を高めることはもちろんですが、内定辞退が出た際の補充など追加施策としてもおすすめです。学生の大半が複数内定を保有し内定辞退する今、内定辞退は「必ず発生するもの」という前提で、予めしっかりと追加施策を用意しておくのが賢明でしょう。
| メリット | ・一人一人に個別のオファー文を送ることで、自己肯定感や承認欲求を重視する今の学生世代のエンゲージメントを得やすい。 |
|---|---|
| デメリット | ・内定承諾後のフォローは自社でしっかりと丁寧に行う必要あり。 |
人材紹介:成功報酬 約80万円/人〜
人材紹介も、どちらかというと内定辞退が出た際の追加施策として持っておくと良いかと思います。
| メリット |
・学生が自分から動かなくても就職先を斡旋されるサービスのため、部活・公務員・教免などで動き出しが遅れた学生などの「就活のやり方がわからないけれど優秀な層」に夏以降でも接触できる。 |
|---|---|
| デメリット |
・成功報酬型が一人80〜100万円程度と高額(中途人材紹介では初年度年収の3割程度が相場。理系は特に高額で100万円超のケースも)。 |
インターンシップ:インターンシップナビ媒体掲載料 無料〜
インターンシップは、選考が始まる前からの早期接触において、学生との相互理解に有効です。相互理解(企業が学生を知るだけではなく、学生にも企業を深く知ってもらうこと)は、内定辞退対策や早期離職防止に非常に重要だと言われています。
| メリット |
・就業体験を通して、会社の風土や仕事内容に深い理解を得られるため、ギャップを感じて途中で辞退される確率が下がる。 |
|---|---|
| デメリット |
・開催時期やプログラムを策定し現場に受け入れを依頼するなど、受け入れの準備には工数がかかる。 |
【課題5】一人当たりの採用単価を抑えたい!
<お悩み内容>
- 上層部から「経費を抑えろ!」とプレッシャーをかけられている……
- 高いコストをかけても良い人材が取れるとは限らないと思う
- 採用人数が多いので、一人当たりの採用単価は安く済ませたい!
これらの課題に対しておすすめの新卒採用手法を、以下にご紹介します。
リファラルリクルーティング:社員への紹介マージン等 数万円/人〜
社員が知人を紹介する「リファラル採用」は、社員に紹介マージン等を支給するのであれば数万円程度、支給しないのであれば無料で活用できる採用手法です。すでに社内にいる人材が「一緒に働きたい」と思う人材を紹介するため、マッチングの精度が高く、近年注目が高まっています。
| メリット | ・自社の社員が「一緒に働きたい」「自社に合っている」と思う人材を紹介するため、マッチングが期待できる。 |
|---|---|
| デメリット |
・新卒採用の場合、今いる社員の「後輩」に当たる人材を紹介する必要があり、1〜3年目くらいまでの社員のみが紹介者となるため、紹介できる母数は少ない。 |
ダイレクトリクルーティング:成功報酬 約30万円/人〜
「待ち」の姿勢で採用するナビ媒体と反対に、「攻め」の採用と呼ばれるダイレクトリクルーティングでは、ターゲットとする学生にだけアプローチすることができます。ナビ媒体のように閲覧する学生をコントロールしづらい「広告」とは異なり、企業が見つけたその学生「一人」にメッセージを送るサービスなので、労力はかかりますが安価です。
| メリット |
・必要な母集団にだけ自社をアピールすることができ、無駄がない。 |
|---|---|
| デメリット |
・企業が学生にアプローチするという労力がかかる。 |
大手ナビ媒体(求人広告サイト):掲載料 約80万円〜
採用人数が2桁〜3桁など大量採用の場合は、一人あたり採用につき成功報酬が発生するようなサービスよりも、大手ナビ媒体から募集するほうがコストを抑えられる可能性が高くなります。
ただし、ナビ媒体はあくまでも「広告」です。多くの学生に閲覧させることができれば、そこからいくらかの割合でエントリーがあり、説明会参加があり、選考参加があり……という「確率」の世界になります。どれだけ多くの学生に閲覧させられるか、つまり学生が検索する業種・職種やキーワード、掲載順位などで「勝ち目」がなさそうなときには、別の手法を考えたほうがよいでしょう。
| メリット | ・掲載料は採用人数に関わらず掲載スペース等によって決まっているので、多い人数を一気に集めて採用できれば、採用単価が抑えられる。 |
|---|---|
| デメリット |
・学生が検索するような社名・グループ・業界・働きやすい条件等がないと、母集団形成が難しく、予定人数を採用できないリスクがある。 |
ナビサイトとダイレクトリクルーティングサービスを併用することで、求める人材の採用に成功している企業もあります。詳しくはこちらの資料で解説していますので、ダウンロードして自社の採用手法の検討にご活用いただければ幸いです。

その他の採用手法のメリット・デメリット
これまで紹介した採用手法以外にも、SNSやオウンドメディアを活用した手法が注目を集めています。それぞれのメリット・デメリットを解説します。
ソーシャルリクルーティング(SNS採用)
TwitterやInstagram、LINEなどのSNSを用いた採用活動は、近年で人気の手法です。日頃からSNSを利用している幅広い層にアプローチでき、従来の採用活動では接点を持てなかった潜在層までリーチを広げることが可能になります。またアカウントは無料で作成できるため、採用コストを抑えたい企業にもおすすめです。
ただし、採用に特化した媒体ではないため直接採用に結びつくとは限らず、母集団形成には不向きといえます。ブランディングやイメージアップを目的として、長期的に取り組む姿勢が必要です。
オウンドメディア
自社ホームページやブログなどのオウンドメディアでは、フォーマットに縛られず自由に情報を掲載できます。社風や雰囲気といった定性的な情報を伝え、自社の魅力を引き出すことが可能です。
注意点として、ホームページのみでの集客は困難なため、学生の流入経路を別に確保しておく必要があります。SNSや求人媒体と組み合わせて使うなど、認知度を高める施策もあわせて考えておきましょう。
またページ内の情報が古くならないよう、更新体制を確立しておくことも大切です。求職者は応募や選考の前に高い確率でホームページを閲覧しますので、更新が滞らないよう運用責任者を定めておきましょう。
新卒採用におけるトレンド手法
新卒採用のトレンドは、以下の3つの観点にまとめられます。
- 個別採用+マス型採用による質の高い母集団形成
- SNSを活用する企業の急増
- 選考のリモート化
まず、「個別採用+マス型採用」の併用によって、母集団の量だけでなく質を高める手法がトレンドとなっています。新卒採用の売り手市場化がますます進み、求人を掲載して応募を待つという受け身型の採用手法では採用計画を達成できない企業が増えているなか、攻めの手法であるダイレクトリクルーティングが注目され、導入数も増えつつあります。その一方で、マス型採用により母集団の量を確保する動きも健在。大規模説明会だけでなく、ターゲットを絞りやすい学内セミナーなども人気の傾向にあります。
また学生がSNSで情報収集するのが当たり前になった点にも注目です。学生とより幅広く接点を持てる可能性が高まったことから、SNSでの情報発信に注力する企業も増えています。
さらに新型コロナウイルス感染症のまん延により、面接や会社説明会をオンラインで開催する企業も急増しました。当初は戸惑いの声が多かったリモート採用でしたが、コスト削減や遠方の学生にもアプローチできるといった点から、積極的に導入する企業が増えています。学生にとっても、遠征費用の削減や複数企業に参加しやすいといったメリットがあり、歓迎する声が多い模様です。
採用課題に合う手法をきちんと選べば、新卒採用はできる!
以上、お悩み課題別のおすすめ手法を解説してきました。
「採用できない…!」とお困りの企業様であっても、新卒採用をされている以上、それなりの金額を投資していらっしゃるのではないでしょうか
- どの手法が自社に適しているか(これまで使ってきた手法は本当に費用に見合う効果をあげているか、あるいは過去あげていてもここ数年不調になってきたのか)
- 採用できない理由は何なのか(応募数が少なすぎるのか、応募数はこのままでも応募者の質が上がれば良いのか、内定承諾がもらえないのか)
- 入社後の社員を観察すると、どの手法で採用した人材が優秀なのか
……など、「どこに課題があるのか」を一度考え直してみて、その解決のための手法を選ぶという観点から、採用活動を見直してみると良いかもしれません。

おわりに
以上、新卒採用手法の定番から最先端のトレンドまで、お悩み課題別におすすめの手法をご紹介しました。
売り手市場や、若者世代の価値観の変化によって、「最近なんだか採用活動がうまくいかないなあ……」と思いつつも、「まあ、どの会社もこんなもんだろう」と、課題をそのままにしていませんか?
採用はその年だけで終わるものではなく、新入社員が入社してから退職するまでの数十年、会社の業績を大きく左右する、重要な「人員計画」そして巨額の「投資」です。
毎年前年のやり方を踏襲しているという企業も多い「採用」という分野ですが、これからの組織づくりを意識して、今年は何か一つでも変えてみませんか?