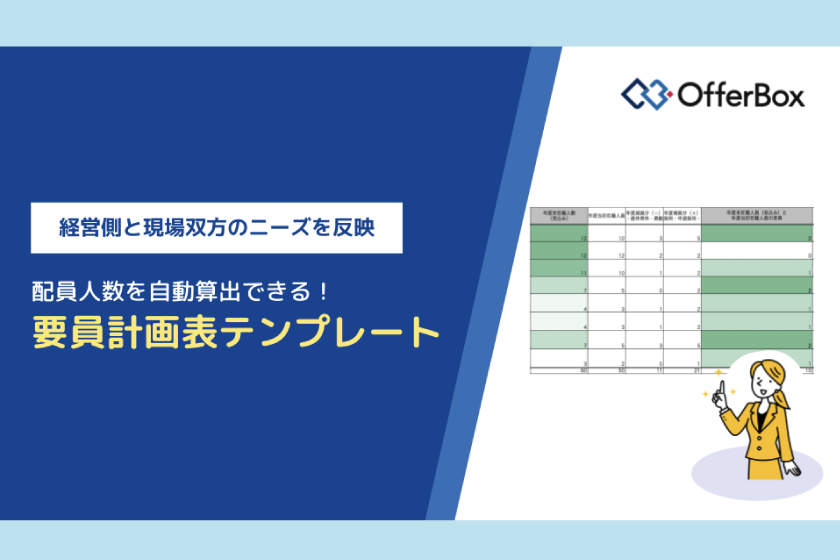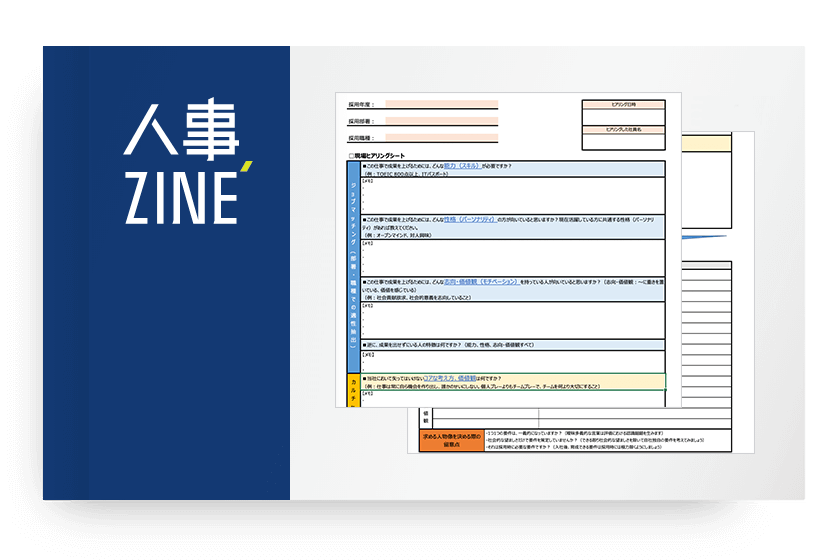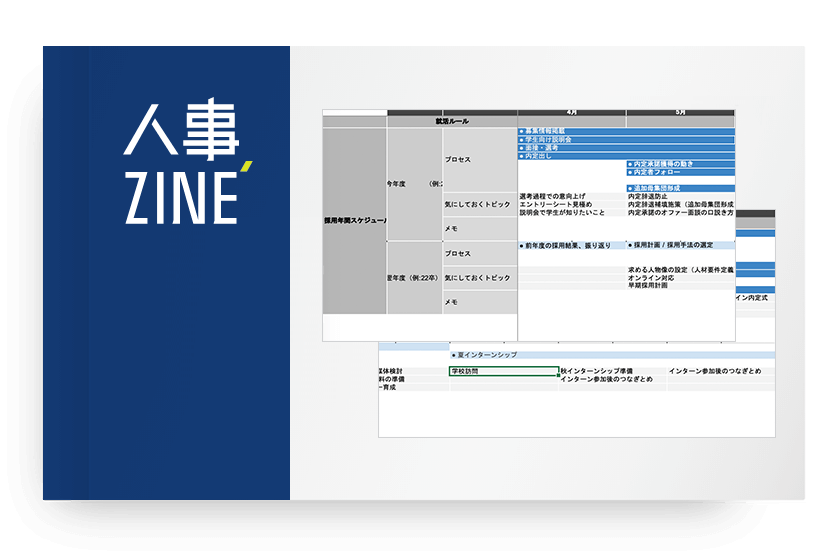チームビルディングとは?目的や実施のポイント、具体的な企画事例やゲームを紹介

チームで仕事を進めるためには、メンバーがお互いを深く理解し、相互にサポートする環境作りが必要不可欠です。「自社の組織力やチームワークに課題を感じている」と考えている方も多いでしょう。
組織力を高めるために役立つのがチームビルディングです。今回の記事では、チームビルディングの特徴や、具体的な手順を解説します。
こちらの資料では、チームビルディングを行う上でのポイントを、チーム編成前・後・オンラインの場合に分けてさらに詳しく解説しています。本記事と併せてご活用ください。

目次
チームビルディングとは?
チームビルディングとは、目的を達成できる強いチームを作るための手法です。英語で表記すると「Team Building」となり、「チームの構築」を意味します。
チームビルディングは、ただ単に人材を集めることではありません。スキルや能力、経験などを見ずにチームを作れば、それはただの「寄せ集め」となってしまいます。そうなれば、効率的に目的を達成するのは難しいでしょう。
適切なチームビルディングをするためには、それぞれのメンバーが主体的に行動し、チームの目標に向かって進んでいく姿勢が重要です。また目的の明確化やフレームワークの活用も有効でしょう。
チームビルディングの目的

チームビルディングの主な目的は、「人材配置の最適化」「社員エンゲージメントの向上」「理念・ビジョンの共有」の3つです。ここでは、それぞれの目的について詳しく解説します。
人材配置の最適化
まずチームビルディングの目的としてよく知られているのが、人材配置の最適化です。チームがしっかりと機能し、目標達成に向かうためには、さまざまな個性を持ったメンバーを適切に配置する必要があります。いわゆる「適材適所」の考え方です。
また人材配置を最適化すれば、それぞれのメンバーの役割が明確になります。配置後の効果検証を繰り返し、最適な配置ができるようになれば、チームとしての強度が大きく高まっていくでしょう。
社員エンゲージメントの向上
社員エンゲージメントの向上も、チームビルディングの大きな目的です。「社員エンゲージメント」は、企業の方向性に共感し、主体的に行動したいと考える意欲を指します。同じような意味で、「従業員エンゲージメント」と呼ばれることもあります。
チームビルディングをすれば、社員は「自分のスキルや能力を見て配置をしてくれている」と考え、マネジメント側に好印象を持ちます。それぞれの社員の士気が高まってくれば、チームに好影響を及ぼすでしょう。チームビルディングは、このような社員エンゲージメントの向上を目指します。
理念・ビジョンの共有
理念やビジョンを共有するのも、チームビルディングの重要な目的です。チームのビジョンが明確になっていなければ、チームは進むべき方向性を見失ってしまい、上手く機能しなくなります。
チームが上手くいっていない場合は、チームビルディングによって、理念・ビジョンの共有を目指します。例えば、5W1Hなどのフレームワークを使えば、チームの方向性を明確化できるでしょう。これもチームビルディングの重要なミッションといえます。

チームビルディングで役立つ「タックマンモデル」
ここでは、チームビルディングで役立つ「タックマンモデル」というフレームワークについて解説します。
タックマンモデルの仕組み
タックマンモデルは、チームビルディングで必要なものを示したモデルです。タックマンモデルを上手く活用できれば、チームがどのような現状にあるのかを把握できます。
詳しくは後述しますが、タックマンモデルの基本的な仕組みは、5段階のプロセスを使って組織の成長段階を示すものです。
どのように理想的な組織へ成長するのかが分かるので、チームの状態を理解するだけでなく、目的を達成するための施策を考える際にも役立ちます。
タックマンモデルの5段階プロセス
ここでは、先ほどの項目で触れた「5段階プロセス」について解説します。

1.形成期
形成期は、その名前の通りチームが結成された時期を指します。チームメンバーが決定したばかりであり、まだメンバーがお互いのことを知らない状態です。この時期では、まだチームの共通目標・ビジョンが定まっていません。
2.混乱期
混乱期は、メンバー間で対立が生まれている段階です。チームが誕生してから時間が経つと、チームの目的に対する意見の違いなどが原因で、メンバー同士に対立関係が発生しています。まさにチームが混乱している状態であり、メンバー同士の相互理解が必要です。
3.統一期
統一期は、メンバーの相互理解が進み、チームとしてまとまりはじめた段階です。チームの目標や各メンバーの役割などが共有され始めます。ここに来て、初めてチームとしての団結力が機能し、次に機能期に入ります。
4.機能期
機能期は、チームがまとまりを見せるだけでなく、結束力や連動によって効率的に機能し始める段階です。相互サポートできる状態であり、チームの団結力としてはここがピークで、最も高いパフォーマンスを発揮できます。
5.散会期
散会期は、文字通りチームが散会する段階です。プロジェクトの終了やメンバーの異動など、きっかけはさまざまですが、チームには必ず終わりが来ます。最後まで雰囲気がよければ、チームビルディングが有効に機能したといえるでしょう。
チームビルディングのメリット・効果
ここでは、チームビルディングのメリットや、具体的な効果について解説します。
コミュニケーションの量・質の向上
まず代表的なメリットとして挙げられるのは、コミュニケーションの量や質の向上です。組織に関わる全ての人員がチームビルディングの対象となるため、世代や役職の垣根を越えて、コミュニケーションができます。
チームビルディングの具体的な手法はさまざまです。例えばオンラインランチ会を開催するだけでも、コミュニケーションが活発化し、チームとしての結束力が高まる効果が期待できます。
チームの柔軟性の強化
チームの柔軟性が強化されるのも大きなメリットです。チームビルディングを通して、「それぞれのメンバーを理解しサポートしよう」という意識が生まれていきます。
周囲と協力する風土が自然に整ってくるため、既存の固定観念や方法にとらわれずに最適な協業方法を模索するアイデアが生まれ、積極的に試行錯誤を行うなど、柔軟な組織に成長していきます。
チームとしての生産性アップ
チームとしての生産性がアップするのも、チームビルディングのメリットです。コミュニケーションの量と質が高まるので、チーム全体としてだけではなく、社員個人としての能力も深まります。
例えば人との関わりが活発になれば、「この人の期待に応えよう」と考え、自分の成長をよく考えるようになります。こうした個人が集まることで、チームとしての生産性が上がっていきます。
チームビルディングに取り組む際のポイント

チームビルディングに取り組む場合は、いくつかのポイントを意識するのが重要です。ここでは、その具体的なポイントについて、「メンバー編成」「メンバー同士の相互理解」「オープンな議論」の3つのトピックに分けて解説します。
メンバー編成
まずは意識したいポイントは、メンバー編成です。それぞれの能力や経験を考慮し、適切なメンバー編成を行いましょう。
ここで重要なのが、それぞれのメンバーの役割が明確になっているかどうかです。メンバーに具体的な役割を与えられていなければ、チームとしての方向性を見失い、チームビルディングを進めるのが難しくなるでしょう。
メンバー同士の相互理解
メンバー同士の相互理解も重要です。コミュニケーションの量と質を増やし、メンバーのスキルや経験、価値観をチーム全員に共有しましょう。
チームビルディングにおいて大事なのは、「マネジメント側が全てを理解しておけばよい」という視点ではありません。マネジメント側はもちろん、メンバー間での理解を深めることが何よりも重要です。
オープンな議論
チームビルディングをする際は、なるべくオープンな議論を心がけましょう。重要なのは、互いにリスペクトをしながらも、意見の対立を恐れないことです。
チームとして動いている以上、考え方や意見が衝突するのは珍しくありません。「自分が妥協すればよい」と考えるのではなく、建設的な議論を交わすことを意識する必要があります。
チームビルディングを進める手順
チームビルディングを適切に進めるためには、そのやり方をあらかじめ理解しておく必要があります。ここでは、チームビルディングを進める手順について、4つのトピックに分けて解説します。
1.チーム目標の設定
まずはチーム目標の設定をします。適切なチームビルディングをするためには、メンバーそれぞれが価値観・ビジョンを共有するのが重要です。そこで指針となるのが、「チームの目標」です。
チーム目標を設定する際は、「目標達成の定義」「失敗の定義」「目標を達成するために何を行うか」を明確化します。チームのモチベーションを高めるためにも、目標の明確化は必ず最初に行いましょう。
2.役割の明確化
チーム目標が設定できたら、次にそれぞれのメンバーの役割を明確にします。今回の記事でも何度か触れているように、役割の明確化は、チームビルディングの成功を大きく左右する重要な作業です。
役割を明確化する際は、「目標達成のために何をすべきなのか」「それぞれのメンバーが目標達成のために何をできるのか」を考えましょう。
3.解決策の模索
チームビルディングを進めている際に、どこかのタイミングで、チーム内で何らかの問題が発生することがあります。その際は、問題や課題の特定作業を行い、どのように解決するかを模索しましょう。
もしも問題を乗り越えられれば、チームとしての結束力が強固になり、それぞれのメンバーの経験値も上がります。ピンチをチャンスに変える発想が、チームビルディングをより適切に進めるためのカギになるでしょう。
4.コミュニケーションや情報共有
チームとしての活動が進んできたら、コミュニケーション・情報共有の量と質を高めていきます。相互にサポートする経験値が深まれば、チームとしてのまとまりがより強くなるでしょう。
この対人関係を軽視してしまうと、チームに亀裂が入る原因にもなりかねません。コミュニケーション・情報共有のシステムは、なるべく早期の段階で整えておきましょう。
チームビルディングの具体例

チームビルディングの具体例が気になる方も多いでしょう。ここでは、「ゲーム」と「ワークショップ」の2つのカテゴリーに分けて、チームビルディングの具体例を紹介します。
ゲームの事例
ここではゲームの事例について紹介します。
謎解き脱出ゲーム
謎解き脱出ゲームは、いわゆる「リアル脱出ゲーム」に分類されるものであり、謎解きをしながら部屋(または施設)からの脱出を目指すゲームです。ホラー調やSFなど、ゲームによってさまざまなコンセプトがあります。
謎解き脱出ゲームで重要なのは、部屋から脱出するために、全員で考えて行動しなければならない点です。問題を解決するため、必然的にコミュニケーションが生まれてくるので、チームとしてのまとまりを強められます。
無事脱出できれば、ゲームの成功体験から、「チーム全体で物事をこなす楽しさ」が存分に味わえるでしょう。
ジェスチャーゲーム
ジェスチャーゲームは、チームメンバーのジェスチャーを見て、問題を解決するアイスブレイクです。例えばチームの1人が、何らかのお題を渡されます。そしてチームメンバーにはそれを見せずに、ジェスチャーでモノを表現し、ほかのメンバーにそれを当ててもらうといったゲームです。
1つのチームでやってもよいですし、複数のチームに分けて競争形式にするなど、拡張性が高いのも大きな魅力です。比較的気軽に始められるゲームなので、チームメンバーと簡単なコミュニケーションを取る際に役立ちます。アイスブレイクとして適切なゲームの1つといえるでしょう。
タワー建築ゲーム
タワー建築ゲームは、ランダムに材料を配り、それを使って最も高いタワーを作るゲームです。材料の指定は特になく、マシュマロなどのあまりベタつかないお菓子などでも構いません。またオフィスであれば、ホチキスやペンなどの事務用品も、材料として適しています。
タワー建築ゲームの魅力は、「一番高いタワーを立てる」という目標をチームで共有し、それに向かって主体的に行動できる点です。チームとしてのコミュニケーション力だけでなく、問題解決能力も高まるため、チームプレーに必要な幅広いスキルを養えます。
ワークショップの事例
ここではチームビルディングに役立つワークショップの例を紹介します。
ショーアンドテル
ショーアンドテルは、事前にテーマに沿ったもの(自分の好きなもの・自慢できるものなど)をメンバーに用意してもらい、それについて発表してもらうワークショップです。簡単な質問タイムを設けることで、メンバーが持っているものについての理解が深まります。
ショーアンドテルの魅力は、「メンバーの意外な一面」を知り、チームの相互理解のきっかけになることです。質問タイムが設けられるので、ただ相手の発表を聴くだけでなく、質問を通して質の高いコミュニケーションを実現できます。オンライン上でできるのも大きなメリットです。
チェックイン
チェックインはとてもシンプルで、「今現在感じていること」「思っていること」を率直に話し、チームで共有するワークショップです。進行役のファシリテーターを事前に用意し、その人がメンバーに「今どう感じていますか?」と聞きます。返答は「楽しみです」「緊張しています」など、ポジティブでもネガティブでも構いません。
チェックインは、タックマンモデルにおける形成期を中心に、幅広いタイミングで有用です。例えば会議が始まる前に、チェックインを用いるだけでも、参加者のモチベーションを刺激できます。メンバーに、「会議に参加している」という自覚を与えるのが、チェックインの役割です。
使命と氏名
使命と氏名は、まず自分の氏名を書いてほかのメンバーに見せてから、「今後どのような使命を持って業務を進めるのか」を発表するワークショップです。「自分の氏名に込められた意味を読み解き、自分の使命を解釈する」といった方法が一般的ですが、さまざまなアレンジがあります。
これはメンバーが集まったばかりであり、お互いに名前を知らない状態で有効なワークショップです。「出会ったばかりの人の名前を覚えられる」だけでなく、「その人がどのように物事を考えるのか」も同時に理解できます。モチベーションにつながりやすいワークショップです。
まとめ

チームビルディングは、チームの理念やビジョンを共有し、目的を達成するために必要不可欠です。自分のチームが今どのような状態にあるのかを考えるためには、本記事で紹介した「タックマンモデル」の5段階プロセスを参考にしてください。
チームビルディングを採用すれば、コミュニケーションの活性化やチームとしての柔軟性・生産性の向上など、さまざまなメリットを得られます。チームビルディングを効率的に進めるためにも、まずは大まかな手順を理解しておきましょう。
具体的なゲームやワークショップを通して、チームとしてのあり方をもう一度考えてみてはいかがでしょうか。
チームビルディングを自社に取り入れるために、さらに詳しい解説をお求めの方は、こちらの資料もご活用ください。