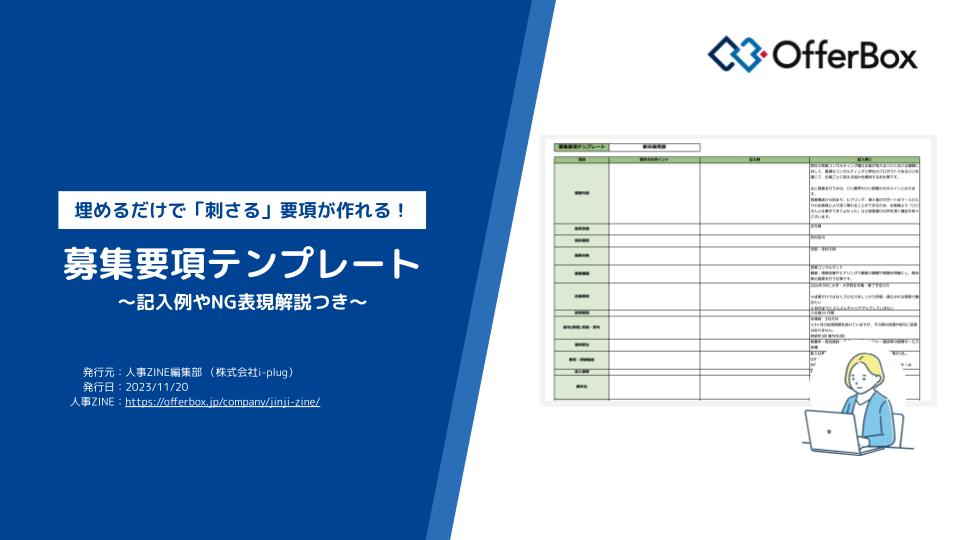【企業向け】説明会・面接後に企業から学生へ送る「お礼メール」の内容とは?

採用活動をしている企業は、学生との接点づくりや関係構築にさまざまな対策を講じています。会社説明会、面接などで接点のあった学生に、企業側から「お礼メール」を送るのもその一つです。ビジネスシーンでは商談や面談後にお礼メールを送るのは常識となっていますが、説明会に参加してくれた学生にお礼メールは必要でしょうか。
また、面接の後日には合否の連絡をすることになりますがその前に、お礼メールはしたほうが良いのでしょうか。
お礼メールが必要だとしても内容はビジネスメールと同じでいいのか、そもそもどういう内容にすればいいのかわからない、という場合もあるかと思います。そこで本記事では、学生にお礼メールを送る理由、タイミング、内容などを解説します。
また、こちらの資料では、最新の新卒採用市場の動向を踏まえ、採用戦略を立てる際のポイントを解説しています。ダウンロードしてご活用いただければ幸いです。

目次
説明会後のお礼メールで、丁寧さや誠実さをアピール

なぜ学生に対してお礼メールを送った方がいいのかについての理由を、マイナビの「就職モニター調査」の結果から見出すことができます。この調査の中の「印象のよかった個別企業セミナーの理由」という設問に対して、『就活生への対応が丁寧だった』が43.9%と、対応の丁寧さが好印象の理由で3位に挙げられています。
- 社員が魅力的だった 48.4%
- セミナーの雰囲気が和やかだった 44.6%
- 就活生への対応が丁寧だった 43.9%
つまり、社員の魅力やセミナーの雰囲気だけでなく、イベント自体のオペレーションや受付対応など、企業としての丁寧な取り組みが学生に好印象を与えていることになります。
会社説明会における学生への対応とは、イベント当日の受付や質疑応答の対応だけに限りません。これには、イベントの告知と参加受付、イベント前後のメールによる連絡といった細かい作業も含まれています。特に会社説明会が終わった後に適切なタイミングで会社側からお礼メールがあると、学生側に「学生に丁寧な対応をする企業」という好印象を持ってもらいやすくなるのです。
また、企業が会社説明会後にお礼メールを送ることには、丁寧さを印象づける以外にも、自社の今後の採用スケジュールを良いタイミングで伝えるという役割もあります。
就職活動の選考スケジュールは過密になりやすいため、早い段階で今後のスケジュールを伝えておけば、学生の予定を押さえやすくなりますし、学生の側も日程の調整がしやすくなります。
この時、お礼メールに説明会後や面接後の流れやステップなどが簡潔に書かれていると、忙しい学生もスケジュールがイメージしやすく、さらに好印象を与えることができます。
特に就職活動を始めて間もない学生においては、企業から自分に向けての配慮が大きければ大きいほど、その企業への好感度が上がる傾向があると言われていますので、適切なタイミングで内容に十分配慮したお礼メールを送ることはとても有効です。つまりお礼メールは、もっとも実施しやすく、それでいて企業に対して好印象を与える効果の高い取り組みだと言えるのです。
説明会後のお礼メールを作成・送信する時のポイント
作成時のポイント
お礼メールでは、凝った内容や美辞麗句を並び立てるよりは、端的に「参加していただき、ありがとうございました」という感謝の気持ちを前面に出すことが大切です。
以下に作成時のポイントを挙げます。
参加者とだけ共有できる情報を盛り込む
お礼メールを送る企業側は何人もの学生に対して送信するのと同様に、受け取る学生側も複数の企業から同様のメールを受信していると考えられます。つまり、全員に対して同じような文面で送ると埋もれてしまうだけでなく、いかにもテンプレートを使いました、という義務的な文面では気持ちも届かないということになります。
例えば、説明会があった日の天候を踏まえて、「昨日は悪天候の中、説明会にご参加下さいまして、誠にありがとうございました」や、送り先となる就活生の一人ひとりに呼びかけるように、「〇〇さんに弊社の雰囲気や魅力が伝わり、ひとつの参考にしていただけていれば幸いです」、質疑応答の話題「質問にありました海外ボランティアについては、……」など、参加者と自社とだけで共有できる内容について触れた話題を挿入すると、より丁寧さと親密さを感じさせるメールになります。
質問しやすい雰囲気を作る
お礼と連絡だけでなく、以下のように質問を促すような言葉を添えておくと、さらに優しい印象を与えることが可能です。
「説明会の内容でまだ聞き足りないことや、時間が経って聞きたいと思ったことがありましたら、遠慮なくメールでもお電話でもご連絡いただければと思います」
学生は、自分からはなかなか質問を言い出せないことが多く、きっかけを与えてあげることが大切です。
また、ここで出た質問や相談は、他の学生も同様に考えている可能性も高いため、今後の説明会の改善にも繋がります。質問しやすい状況を用意することはとても有効なポイントです。
情報を分かりやすく整理する
お礼メールには、セミナーや説明会参加後の流れの他、自社の採用ホームページの更新情報や、企業としての最新のトピックスなどさまざまな情報を盛り込むことができますが、情報は分かりやすく整理して伝えることが大切です。情報が散漫になってしまったり、全体のボリュームが過度になってしまうと、肝心の内容が伝わりにくくなってしまうからです。
逆に、項目と要点だけといったいかにも事務連絡用といった素っ気ないメールにもならないように、語りかけるような、親しみの持てる文章にすることを心がけましょう。
ターゲット層により内容を変える
説明会、面接などイベントにより学生へのお礼メールの送信数、内容が変わるのは当然です。さらに言えば、オンライン化により、参加者の視聴行動ログ解析が可能となり、その志望度・本気度を見極めたメール内容の差別化が可能です。次のステップにつなげたい学生に対して、企業側の本気度を訴えることも大切です。
ターゲット層を明確に分類し、内容を十分検討してから送るようにすれば採用の精度が向上します。
送信のポイント
送信するにあたってのポイントとしては以下のようなものがあります。
遅くとも翌日までに送信する
複数の説明会に参加している就活生は、参加後に時間が経ってしまうと印象が薄れていきます。お礼メールが届くまでに何社かの説明会に参加していればなおさらです。お礼メールは、当日、あるいは翌日には送信することが大切です。
メールアドレスや宛名を十分にチェックする
メールアドレスや宛名を間違えてしまうとせっかくの苦労も台無しです。逆に「気遣いのできない会社」「信頼できない会社」という印象を与えてしまいますので、細かい配慮が求められる業務でもあります。
間違い防止対策としては、学生に送信する前にメールをテスト送信してチェックしたり、元データとなる宛名リストに間違いがないかを確認し、宛名・送信先のダブルチェックを別の担当と入念に行うなど、細心の注意が必要です。
この他、人的なチェックだけでなく信頼できるソフトやツールを活用することも間違い防止に有効です。例えばエクセルのマクロなどを利用し、名前の部分をリストから読み込んで自動変換できるようにしておくと、宛名の間違いを防げるとともに、効率アップも期待できます。
最近はメール配信システムでも同様の処理が可能なものがありますので、使用しているメールシステムが変換可能なものか、機能を確かめることも大切です。
返信の繰り返しを防ぐ
なかには、企業からのお礼メールに、お礼の返信をしてくる学生もいます。お礼のお礼のさらにお礼と、際限がなくなりますので、学生からのメールに質問が含まれてない限り、学生からの返信に再度返信する必要はありません。お礼メールに、「ご質問がなければ返信不要です」の一文を添えて送るのもひとつの気遣いと言えます。
説明会後のお礼メールの文章作成例
では、実際にどのようなメールを送ればいいのか、上記のポイントを踏まえて、会社説明会後に会社側から送るお礼及び選考日程連絡メールについて、基本となる例文をご紹介します。
<タイトル>
【株式会社○○○】会社説明会ご参加の御礼と今後の選考日程のご連絡
<本文>
●●●●様
はじめまして、XXXX株式会社△△担当の○○と申します。
昨日は、悪天候にも関わらず弊社の会社説明会にご参加いただき、誠にありがとうございました。
多くの方にお集まりいただけただけでなく、説明後の質疑応答タイムには熱心なたくさんの質問をいただくことができ、おかげさまで盛況のうちに会社説明会を終了することができました。併せてお礼申し上げます。
会社説明会の内容については、十分ご理解いただけましたでしょうか?
●●様に弊社の雰囲気や魅力がしっかりと伝わり、参考にしていただけたようであれば幸いです。
もし会社説明会の内容でまだ聞き足りないことや、時間が経って聞きたいと思ったことがありましたら、遠慮なくメールでもお電話でもご連絡いただければと思います。
また、本日付で弊社採用ホームページに、女性活躍推進に関する取り組みを紹介するページを新しく公開しましたので、ぜひご一読ください。座談会は必見です。
http://www.・・・・・・・・・
なお、今後の選考日程は以下のようになっておりますので、ご確認ください。
【○月○日(○)】エントリーシートのご提出期限
【○月○日(○)〜○月○日(○)】WEB適性検査
【○月○日(○)〜○月○日(○)】一次面接
今後の選考への参加をご希望される場合は、上記の期日【○月○日(○)】までにエントリーシートのご提出をお願いいたします。
ご提出いただきました方に、WEB適性検査の詳しいご案内を差し上げます。
それでは、●●様からのエントリーシートを心待ちにしております。

面接後のお礼メールを作成する時のポイント
基本的な書き方は説明会のお礼メールと同じです。ただし、説明会の時とは異なり、すでに何度かやりとりがあった後になりますので、文章の書き出しは「はじめまして」ではなく、「お世話になっております」か、少し親しみがある表現としては「お疲れ様です」が適しているでしょう。
お礼を書いた下には、面接後のスケジュールを箇条書きで分かりやすく記載します。いつ頃までに面接の結果が出るのか、1次面接を通過した場合には、2次面接がいつ行われるのかということを記してください。学生は複数の企業を併願している可能性があるので、自社の合否を待てずに他社に決めてしまうことがないように、スケジュールはしっかり伝えておきたいところです。
説明会・面接後に企業から学生へ送る「お礼メール」の内容まとめ
企業側は説明会・面接後のお礼メールは必ず送らなくてはならないものではありませんが、学生にお礼を丁寧に伝えて好印象を残し、忙しい学生にタイミングよく次の選考スケジュールを知らせることができる優れたコミュニケーション手段であり、学生の志望度を上げるためにも重要な意味を持ちます。
本稿では、学生に届く膨大な情報の中でも、「埋もれない・心に届く」お礼メールを作成するために、
- お礼メールを送る理由
- タイミング
- 送る際のポイント
- 文書作成例
の4項目に分けて解説しました。
「お礼メールを送ってみようとは思うけど、どんな風に書けばいいか分からない」という人事担当者の方も、本稿のポイントと例文を参考にしながら、自社の社風やターゲット像に合わせたお礼メールの送信を検討してみてはいかがでしょうか。
また、こちらの資料では、最新の市場動向を分析し、これからの採用を成功させるために重要なポイントを解説しています。最新の学生の傾向を押さえて、学生の心を掴む選考過程の設計にお役立てください。