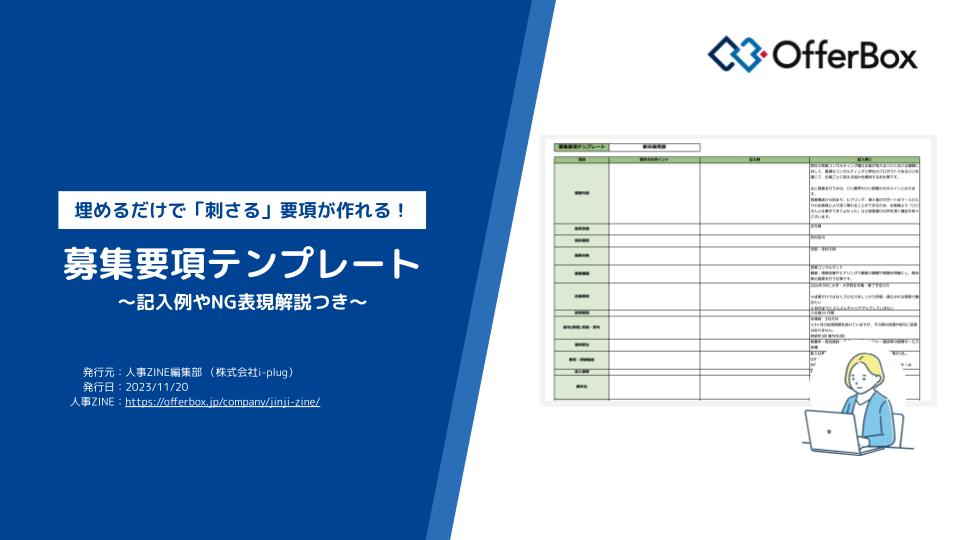座談会とは?メリットや種類・テーマ例と進め方のポイントを解説

採用活動において、学生の企業理解を深め、自社に親しみを感じてもらう有効な方法の1つに「座談会」が挙げられます。しかし、座談会の開催にあたって「学生にとって魅力的なテーマや企画が思い浮かばない」「どのような流れで開催すればよいのか分からない」「ただの雑談で終わってしまい、学生に自社の魅力を伝えられていない」といった悩みを抱えている担当者も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新卒採用における座談会の役割やメリットを再確認したうえで、座談会の基本的な進め方、学生にとって魅力的なテーマ例、企画する際のポイントなどを解説していきます。
また、座談会の形式やコンテンツの準備にお悩みの採用担当者の方のために、「学生にとって魅力的な座談会をつくるポイント」をご用意しました。学生の心を惹きつける座談会を企画するポイントをフェーズ別、開催形式(オンライン/対面)別にくわしくご紹介しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次
新卒採用における座談会とは?

新卒採用における座談会とはどのような位置付けで、どのように開催されるものなのでしょうか。まずは、その特徴や近年の開催形式をご紹介します。
座談会の特徴
座談会とは、ひとことでいえば「社員と学生が話をする場」です。学生にとっては説明会で聞き逃したことや素朴な疑問・不安などを質問する場で、企業はより会社のことを深く伝えたり学生の意見・関心を知ったりする場と位置付ける傾向があります。
座談会の一般的な傾向は以下の通りです。
- 開催のタイミング:説明会の後や選考の初期の段階
- 企業側の参加者:さまざまな部署の若手社員を中心に複数人
- 選考への影響:選考の参考にすることも可
- 服装:「スーツやそれに準じる服装」の指定が多い
説明会は企業から学生へ伝える形式が多いものですが、座談会は「学生から会社へ」自由に質問することも可能で、リラックスした雰囲気で行われるのが特徴です。数人の社員で多数の学生を相手にすることが多く、双方向のやり取りだからこそ企業側も学生側も相互理解を深めることができます。
近年の座談会の開催形式
座談会は会社説明会の後などに対面で行われることが多くありますが、コロナ禍をきっかけに近年はオンラインでの開催も増えています。
オンライン座談会は学生が自宅から参加できるため、学生にとって服装を気にせずリラックスして参加できるメリットがあります。遠方に住む学生も気軽に参加できるため、企業側は多くの学生に自社を知ってもらえるというメリットもあるでしょう。
企業側が座談会を実施する目的・メリット

新卒採用において多くの企業が座談会を実施していますが、どのような目的があるのでしょうか。座談会の目的やメリットを紹介します。
企業と学生の相互理解を深める
採用売り手市場が続くうえでは、採用活動において企業が学生を一方的に選定するのではなく、学生に「選んでもらう」ことの重要性も高まりました。このような背景から、企業から学生への一方向ではない、双方向性のある採用活動(学生と企業がマッチングする採用活動)が主流になりつつあります。座談会は、学生と企業がお互いのことを知るための、双方向のコミュニケーションができる有効な手段として注目されているのです。
企業にとっては、「学生の本音の部分を見ることで選考の参考にする(採用後のミスマッチを防ぐ)」ことも目的の1つとなります。ミスマッチが防止できれば、自社の求める人材を採用できる可能性が高まるだけでなく、早期離職防止や仕事のやりがい向上につながるといったメリットがあるのです。
入社後の不安を払拭する
座談会には、学生に向けて「企業の風土や現場の雰囲気などを見て、入社後のイメージをつかんでもらう」、「応募者同士が顔を合わせることで、入社後についての不安を払拭してもらう」という目的もあります。
座談会では、実際に企業で働いている社員の人柄や雰囲気、リアルな話を直接知ることで社風を体感できます。また、社員と学生、応募者である学生同士での相互理解を進めることで、入社後をイメージしやすくなるでしょう。
社内の一体感が生まれる
座談会は、採用に向けた社内の一体感を醸成することにも役立つイベントです。
座談会は採用・人事担当者だけでは開催できません。学生にとって「現場の空気感が肌で感じられるような場」とするためには、現場社員の参加やその他の協力が不可欠です。
最も学生との接点が多いのは採用・人事担当者ですが、たとえ現場経験があるとしても採用活動を行うにあたって現場から離れていれば最新の状況をキャッチアップするのが難しいことも生じます。
そこで座談会で企業の風土や現場の雰囲気を学生によりよく伝えるには、現場の第一線で活躍中の社員にも座談会に参加してもらうことが重要となります。
このように、座談会は採用・人事部門だけでなく部門横断的な取り組みが必要となり、さらに座談会の企画運営にあたっては携わるさまざまなメンバー間の意思疎通も求められるため、社内の共通認識の醸成につながるでしょう。
学生が座談会に参加するメリット

座談会をより意義のあるものにするためには、学生にとってのメリットを理解しておくことも大切です。
まず大きなメリットとなるのが、社員と直接コミュニケーションすることを通じて、会社や社員の雰囲気が把握できることです。学生は企業の事業内容だけでなく、社風や周囲の社員相性がよいかどうかも重視しています。
このため、複数の社員から生の声を聞ける座談会を、会社の雰囲気を掴める貴重な場と捉えている学生も多いのです。
また、他の学生の質問を聞いて情報収集できること、採用担当者に覚えてもらえる可能性があることもメリットに挙げられます。学生の座談会に対する満足度を高めるには、座談会を積極的に質問できる場にすることが効果的です。
座談会の種類
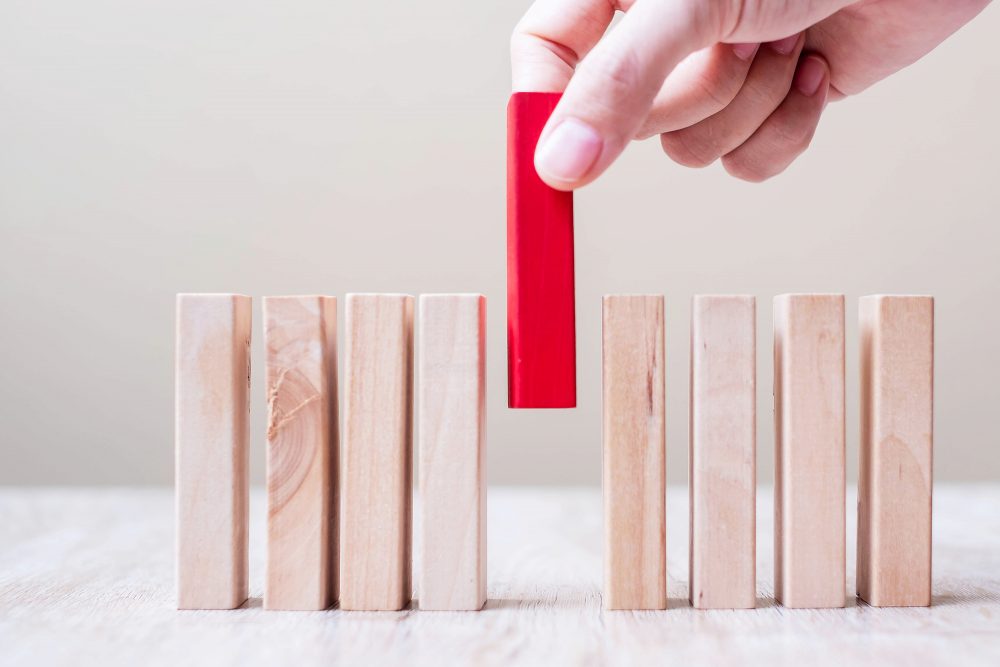
座談会は、大きく以下の2種類に分けられます。それぞれ特徴やメリットが異なるため、自社が座談会を開催する目的に合った形式を選択することが大切です。
テーブル形式
テーブル形式とは、学生数名と社員1~2人が一緒にテーブルを囲み、会話する方式です。場合によっては、一定時間ごとにメンバーを入れ替え、学生と社員が相互に交流を深めます。カフェのような雰囲気でフランクに交流を楽しむことから「ワールドカフェ形式」とも呼ばれています。
テーブル形式は、時間を区切ってメンバーを入れ替えるため、たくさんの学生と接点を持てる点がメリットです。学生もさまざまな社員から企業の情報を収集でき、職場の雰囲気を把握できます。
一方で、時間が限られており1人の学生とじっくり交流できないというデメリットもあります。興味を持ってくれた学生には、別途面談の機会を設けるなどしてフォローするとよいでしょう。
パーティー形式
パーティー形式は、テーブルに食べ物や飲み物を用意し、立食パーティーのような雰囲気で開催する座談会です。参加学生は自由に動き回って、話を聞きたい社員と自由に交流を深めます。
テーブル形式とは異なり、学生が志望する職種の社員からじっくり話を聞ける点が特徴です。ただし、自分から話しかけるのが苦手な学生は、誰とも話せなかったり孤立したりする可能性があります。企業側は馴染めずにいる学生がいないか気を配り、社員側から話しかけるなどフォローしましょう。
座談会のテーマ例

座談会は学生と社員が自由に交流を楽しむ場ではあるものの、「何を話せばよいのか分からない」という事態に陥ることも少なくありません。せっかくの場を有意義にするためにも、テーマを決めておくとよいでしょう。
ここでは、代表的なテーマの例を3つ紹介します。
テーマ例1:職種についての仕事内容・働き方
特定の職種や部署の社員と交流すると、仕事内容や働き方に関する理解を深められます。「入社後はどのような仕事をするのか」「どのような役割を期待されているのか」を具体的にイメージでき、志望するうえでの判断や、入社の備えがしやすくなるでしょう。
より職種へのイメージが膨らむよう、若手社員やベテラン社員、エース社員などさまざまな立ち位置の社員を参加させると効果的です。「入社直後の仕事内容」「仕事をこなすなかでの成長」「成果を出すために必要なこと」などを伝えられ、学生の理解度向上につながります。
テーマ例2:若手社員のリアルな声
前年の新入社員や、入社2~3年目の若手社員との交流を促すと、入社直後のイメージが膨らみます。「入社後数年間はどのような仕事をするのか」「どのようなことを困難に感じるか」「その困難をどのように乗り越えたか」など、リアルなエピソードを伝えられ、入社後のミスマッチ防止につながるでしょう。
学生からの質問により具体的に答えるため、よくある質問に対してはあらかじめ回答を用意しておくとスムーズです。「入社1年目はどのようなことに苦労するか」「入社に備えてどのような準備をすればよいか」など、学生からよく受ける質問に対して具体的なエピソードを添えた回答を用意しておくと、座談会の満足度が高まります。
テーマ例3:職場風土・福利厚生といった社内環境
現場社員だけでなく、人事担当者や役職者に質問できる場を用意すると、自社の風土や社内制度に関する理解が深まります。「普段どのような環境で仕事をしているのか」「福利厚生としてどのような制度を用意しているのか」など、包み隠さず社内の現状を伝えましょう。
自社の福利厚生や制度の充実度について知ってもらいたい場合は、実際に制度を利用して働いている社員にも参加してもらう方法が有効です。子育てや介護、趣味などと仕事を両立している社員に実際のエピソードを語ってもらうと、社員の私生活を重視している企業姿勢をアピールできます。
座談会を企画するうえでのポイント

座談会を企画する際にはどのような点を意識すればよいのでしょうか。企画を決める際のポイントを紹介します。
テーマを明確にする
まずは、「座談会を通じて学生に何を伝えたいのか」「どのような魅力を知ってほしいのか」を明確にするため、テーマを設定します。座談会は学生と社員がフランクに交流できることがメリットですが、単なる雑談に終わってしまうと、自社の魅力が学生に届かないかもしれません。学生に有意義な時間を過ごしてもらうためにも、魅力的なテーマを設定することが大切です。
前段でも触れた通り、職種理解を深めてもらいたい場合には、若手社員や中堅以上のエース社員など立ち位置の違う社員と交流してもらうと仕事のイメージが膨らみます。自社の社内環境をアピールしたい場合は人事担当者に質問する場を作るなど、目的に合ったプログラムにするとよいでしょう。
また、テーマが明確になったら話す順番もあらかじめ決めておきましょう。全体の流れを決めておいた方が話が脱線しにくく、座談会全体に一貫性が出て、より学生の理解が深まります。
参加する社員を厳選する
テーマが決定したら、そのテーマにふさわしい社員を選定し、参加を依頼します。座談会で交流する社員は、学生にとって企業の顔となる存在です。どのようなテーマであっても、学生にとってロールモデルとなり、「こんな人がいる会社なら入りたい」と思える社員を選定しましょう。最近では、候補となる社員の了解のもとに適性検査を行い、応募者の属性や価値観に合う社員を厳選して座談会に参加させるという企業もあります。
また、参加する社員には座談会のテーマや目的、伝えたい魅力などを事前に説明し、共通の認識を持って座談会に臨んでもらうことが大切です。座談会の成功は参加する社員の資質と言動に左右されるといえるほど重要な役割であるため、経営陣や参加社員の上長とも連携を取り、関係者一丸となって座談会に取り組む姿勢を構築しましょう。
参加社員はテーマによってさまざまな組み合わせにする
若手社員だけ、特定部署の中堅社員だけ、若手社員と中堅社員、特定大学のOB・OG社員、女性社員だけ、上司と部下など、参加者の組み合わせはさまざまにありますので、テーマに応じてどういう組み合わせにするかが工夫のしどころです。
例えば、「配属後の仕事イメージを伝える」という内容の場合、どうしても若手社員からの情報だけでは乏しく、仕事に精通した中堅以上の社員からでないと深い話は聞き出せないものです。ただ、近い未来の仕事をイメージしてもらうには、若手社員のほうがリアル感がありますので、中堅以上の社員と若手社員の組み合わせで考えるとよいでしょう。
一方、「給与への満足度」や「休日・休暇のとりやすさ」などを本音で語ることをテーマにする場合は、やはり若手社員とフランクに話せたほうが場は活性化します。
他のイベントと同時に開催する
座談会は、他の就活関連イベントと同時に開催すると、学生の参加率が高まる可能性があります。座談会のみを単独で開催すると、企業側にとっても準備に手間がかかるだけでなく、学生も座談会のためにわざわざ企業を訪問しなければならず、参加のハードルが上がってしまいます。
インターンシップや会社説明会、選考初期の集団面接、内定者フォロー面談など、他のイベントと同時に開催すると、会場の確保といった企業側の手間が軽減され、学生も一連の流れで参加しやすいというメリットがあります。
ただし、座談会をオンラインで開催する場合は、そもそも参加のハードルが低く、他のイベントとの兼ね合いに配慮する必要はそれほどありません。対面型の座談会とは別に、オンライン座談会も積極的に取り入れると、より多くの学生との接点創出につながるでしょう。
質問させることで学生の本音を引き出す
座談会ではフラットに会話ができるため、説明会など他のイベントよりも学生が質問をしやすい傾向があります。説明会や選考面接時に聞きそびれたことを質問してもらえれば、より企業理解が深まるだけでなく、学生が抱いている不安や疑問の払拭につながります。つまり、「本当は気になっているけど、なかなか聞けない」という本音の質問を座談会で引き出せれば、自社に対する信頼性が高まり、志望度の向上が期待できるのです。
座談会で学生の本音を引き出すためには、リラックスできる雰囲気づくりが重要です。社員から積極的に話しかけたり、丁寧な回答を心がけたりすると、「聞きたいことを正直に聞いても大丈夫そう」と学生に安心感を持ってもらえ、本音の質問を引き出せるでしょう。
事前に学生の質問例を確認しておく
座談会に参加する社員には、あらかじめ学生がしやすい質問例を周知しておくと安心です。当日までに質問例をメールなどで知らせ、目を通しておいてもらいましょう。
普段は採用に関わらない現場社員にとって、座談会への参加は緊張を伴うイベントです。質問に対して心構えができれば緊張感が緩和され、学生からの質問にもスムーズに回答できるようになります。
座談会の流れが滞らず、よい雰囲気で進めることができれば、学生もリラックスして積極的に参加できます。結果として、企業への好印象につながることも期待できます。
座談会を実施する際のポイントは、こちらの資料でも解説しています。座談会を開催するタイミングや対面・オンラインの使い分け方など、学生にとって魅力的な座談会を開催するコツをまとめた資料ですので、あわせてご活用ください。

座談会の基本的な進め方・流れ

座談会当日の基本的な流れは、以下の通りです。
参加者に座談会のテーマを提示する
最初に、参加する学生へ座談会のテーマを提示すると、会話がスムーズになります。「テーマに対してどのような質問をするか」「社員に何を話してもらうか」を考えながら座談会に参加でき、「ただの雑談で終わってしまった」という事態が起こりにくくなるでしょう。
また、座談会で複数のテーマを扱う場合は、テーマとあわせて話す順番も提示することが大切です。「興味のあるテーマが扱われるか」「どのタイミングで質問をするか」などを学生が考えやすくなり、座談会の満足度向上が期待できます。
社員から話し始める
座談会のスタートと同時に、学生から質問するのは難しいものです。まずは社員側から話し始めてもらいましょう。最初に話す内容は座談会の雰囲気を左右するので事前に決めておくのがおすすめです。
例えば最初は社員が自己紹介や会社紹介をしたうえで全員でアイスブレイクなどを行い、その時のテーマに沿った会話を始めていく、という流れが考えられます。
時間は最低でも10分は確保する
開催形式によりますが、グループ分けして複数の人と話すのであれば少なくても10分、グループを固定するのであれば30分は確保しましょう。
一方で座談会は、話が盛り上がると時間を忘れがちな点にも注意しましょう。特にグループで開催する場合は、ある一定の人とのやり取りに時間を取られてしまうと参加者全体では不満を感じることになります。
「参加者の平均的な満足度をあげる」「多くの参加者と接点をもち選考に進んでもらう」という目的を達成するためには時間配分を決めて進行することが重要です。
「参加者に前もって座談会の終了時刻を伝えておく」「司会者に進行を任せて従ってもらう」などの対策が有効です。
座談会における学生の質問例

仕事や社風、求める人物像などに関する学生からのよくある質問例を、テーマ別に紹介します。自社で座談会を開催する際の参考にしてください。
仕事に関する質問
採用サイトや企業情報では分からないリアルな情報を聞かれる傾向があります。また、良いことも悪いことも含めて理解したい、と考える学生が多いです。
- 日々の仕事のやりがいは何ですか?
- 業務を進めるうえで、大変なこと、つらいことは何ですか?
- 入社してから分かった御社の強みと弱みを教えてください。
これらの質問に対しては、社員だからこそ話せる具体的なエピソードを添えて回答すると効果的です。やりがいを感じたプロジェクトやそのなかでの苦労話など、座談会だからこそ話せるエピソードを複数用意しておくと、学生の仕事理解が深まります。
社風に関する質問
社内の人間関係や雰囲気は、特に質問が多いテーマの1つです。学生は、自分に合っているかどうか、働きやすいかどうかを知りたいと思っています。
- 社内の雰囲気をどのように感じていますか?
- 社員間の交流は活発ですか?
- 上司や先輩社員はどのような人ですか?
社内環境に関する質問は、説明会や選考の場で聞きにくいと感じる学生も多く、疑問や不安に対して明確な答えを提示することが大切です。隠したり曖昧にしたりせず、率直に回答すると学生の安心感につながります。
人物・パーソナリティに関する質問
選考対策として聞かれることが多い質問です。学生は、得られた回答をエントリーシートや面接でのアピールに活かしたいと考えています。
- 一緒に働くならどのような人材が欲しいですか?
- 入社後に必要となる資格やスキルはありますか?
- 活躍している社員の特徴を教えてください。
学生とのマッチ度向上が期待できるため、企業側も求める人物像については積極的に情報提供するとよいでしょう。「どのようなスキルがあると仕事がスムーズになるか」「活躍している社員は学生時代にどのような経験を積んできたか」など、求人票からは分からない具体的な人物像を提示すると効果的です。
座談会を企画するうえでの注意点

座談会は会社の魅力を伝える格好の場ですが、あまりに力を入れすぎて情報過剰となってしまったり、フランクな雰囲気から不用意な発言をしてしまうなど落とし穴もあるので注意が必要です。以下の点には特に注意しましょう。
学生の意向度を下げないようにする
座談会は、学生が企業とのマッチ度を判断する指標の1つであり、結果として「自分に合わない」と判断する学生もいるでしょう。とはいえ、企業側の軽率な発言や態度によって学生の意向度を下げてしまう事態には注意が必要です。
例えば、「学生のプライベートを詮索する」「友達のように馴れ馴れしく接する」など、参加する社員の発言や態度によって学生の意欲が低下するケースは珍しくありません。カジュアルな場だからといって社員が好き勝手にふるまうのではなく、座談会を開催する目的や社員の役割を事前に共有し、学生が気持ちよく過ごせる環境づくりを心がけましょう。
話しやすい環境づくりをする
テーマと参加する社員を厳選して開催しても、それだけでは活発で話しやすい雰囲気の座談会になるという保証はありません。特に学生の側は現場社員と話すのは緊張するものです。場が活性化するように、会が始まる前からさまざまな工夫と準備を整えておくことが必要です。
例えば、参加する学生に会社側参加者のプロファイルシートを事前に配布しておいて、それぞれの参加者に対する質問を考えておいてもらえば、その場の思いつきで質疑応答するよりはるかに効果的です。
さらに質問票をあらかじめ回収する形にすれば、質問に対する回答を準備しておくこともできます。
また、社員の側にも配慮が必要です。例えば先輩社員の話題が尽きないように、「入社を決めた理由」などよくある話題だけでなく、「仕事でつまずいた時にどう乗り越えたか」など、できるだけ具体的に職場の雰囲気が伝えられるようなトピックをまとめてもらい、その中から話題を提供するようにすることも話しやすい環境づくりに有効です。
まとめ

採用活動において双方向性を活かせる座談会の重要性に注目が集まっています。人事のみで完結した採用活動で生じがちなミスマッチを防止する効果が期待できるからです。
座談会を成功させるためには、現場社員や経営陣とも連携を密にして全社的に取り組む、十分な準備と明確なテーマ設定を行う、などのポイントを押さえることが大切です。
また、最近普及しているオンライン座談会なら、いつでもどこからでも参加できるため、他のイベントとの関連にこだわることなく開催することが可能です。
座談会は直接的に選考には関わらない一方で、応募者に会社の魅力を知ってもらうための重要な接点でもあります。
特に「応募者が現場の空気感を知り、入社後のイメージを掴みやすくなる」というメリットは座談会ならではのものです。ミスマッチを防ぐための一策として、まずは座談会で「会社の空気を伝える」ことを始めてみてはいかがでしょうか。
座談会のテーマ企画や開催方法にお悩みの場合は、こちらの資料がおすすめです。学生にとって魅力的な座談会を企画するポイントや、オンライン座談会を開催する際の注意点などをまとめた資料ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。