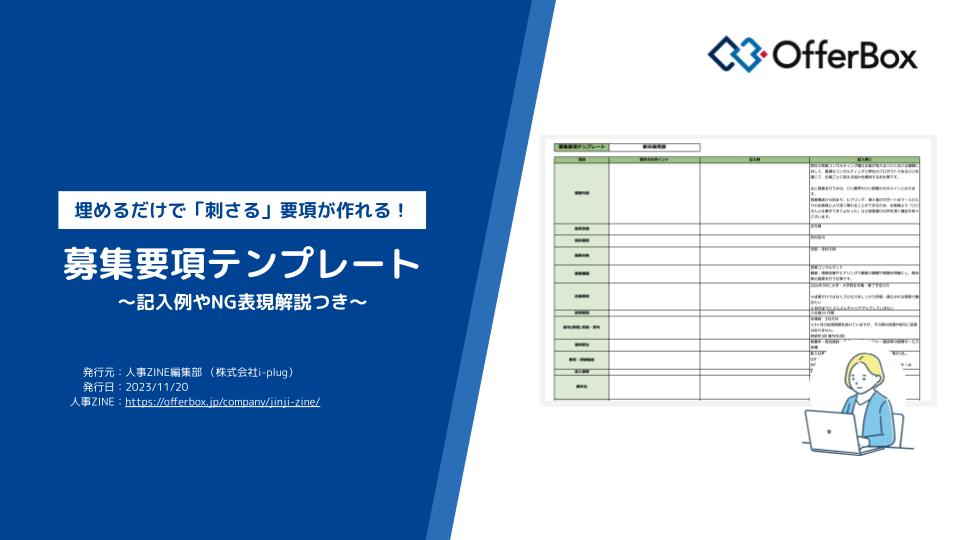ダイレクトリクルーティングの4つのメリット|採用成功のポイントとは?

ダイレクトリクルーティングは、従来型の「待ち」の採用手法とは異なり、「攻め」の採用手法といわれています。取り入れることで、採用活動にどのような変化があるのでしょうか。また、どのような採用課題を抱えた企業がダイレクトリクルーティングを導入すべきなのでしょうか。
この記事では、ダイレクトリクルーティングの代表的な4つのメリットや取り入れる際の注意点、おすすめのサービスなどを紹介します。
ダイレクトリクルーティングをご利用された事のない採用担当者の方のために「はじめてのダイレクトリクルーティング〜新卒採用編〜」をご用意しました。
ぜひ、ダウンロードして自社の新卒採用活動にお役立てください。

目次
ダイレクトリクルーティングとは?
はじめに、ダイレクトリクルーティングの特徴や必要性など、基礎知識を解説します。
ダイレクトリクルーティングの特徴
ダイレクトリクルーティングとは、データベースのなかから自社とマッチ度の高い候補者を選定し、スカウトメールを送るなどして企業側から直接アプローチを図る採用手法です。採用媒体に求人を掲載して求職者からの応募を待つ従来型の採用手法と違い、企業が先行して働きかける「攻めの採用」といわれています。
ダイレクトリクルーティングが注目されている背景
売り手市場が続く昨今、新卒・中途問わず、多くの企業がダイレクトリクルーティングを導入しています。その背景として、労働力人口の減少により、自社とマッチする人材の採用が困難になったことがあげられます。
従来の採用市場では、ナビサイトに求人を掲載して求職者からの応募を待つ採用手法が主流でした。しかし、厳しい売り手市場のなかでは、自己応募を待つだけでは自社の採用要件を満たす人材との接触機会を得ることが難しくなっているのです。
さらに、終身雇用が崩壊して労働力の流動性が高まったことも相まって、求人広告や人材紹介にかかる採用コストが高騰しています。採用コストを抑えつつ、求める人材にピンポイントで接触する必要性が高まったため、ダイレクトリクルーティングに注目が集まっているのです。
ダイレクトリクルーティングの4つのメリット

企業が応募者に直接アプローチを図るダイレクトリクルーティングでは、次のようなメリットを得ることができます。
1.自社の求めるターゲット層と接触できる
ダイレクトリクルーティングの最大のメリットは、自社の採用要件を満たすターゲット層を事前に選定し、ピンポイントでアプローチを図れる点にあります。
ナビサイトや採用イベントなどを活用する従来の採用手法では、母集団の質を企業側がコントロールできませんでした。しかし、ダイレクトリクルーティングではデータベースに登録されている候補者のプロフィールを事前に確認し、マッチする人材にのみスカウトを送れるため、ターゲット層と効率的に接触できるのです。
2.潜在層にも幅広くアプローチできる
自社に対する志望度や転職する意欲がまだ高くない「潜在層」にアプローチできることも大きな特徴です。
従来の手法では、自己応募してきた人材としか接点を持てなかったため、自社を知らない層や業界への興味が薄い層の興味喚起が難しい点がデメリットでした。一方、企業が自ら接触を図れるダイレクトリクルーティングでは、このような潜在層にもアプローチが可能なのです。
また、中途採用においては「今すぐでなくても、条件が合うオファーがあれば転職したい」と考えている層もダイレクトリクルーティングのデータベースに登録しています。そのような層に自社をアピールし、「カジュアル面談」という形で接点を持てるのです。
3.採用コストを削減できる
ダイレクトリクルーティングの料金体系は、データベースの利用料を支払う「先行投資型」と、採用が決定した段階で費用が発生する「成功報酬型」の2種類に分けられます。新卒採用における成功報酬の相場は、30万~50万円程度といわれています。
ダイレクトリクルーティングが必ずしもナビサイトよりも安価というわけではありませんが、運用が安定して採用活動を効率化できれば、採用コストを抑えることが可能です。
4.採用ノウハウを社内に蓄積できる
マッチ度の高い人材と出会うため、人材紹介サービスや求人広告代理店を利用している企業も多いでしょう。効率よく母集団を形成できる手段ではありますが、自社内に採用ノウハウがたまらないというデメリットには留意すべきです。自社のアピールや動機付けといった集客の部分を外部に頼りきりになり、自社の採用力低下を招く可能性も考えられます。
ダイレクトリクルーティングでは、ターゲットへのアプローチから選考における動機付け、内定承諾まで一貫して自社で取り組みます。結果として、自社の採用力の強化につながるのです。

ダイレクトリクルーティングのデメリット
多くのメリットの一方、ダイレクトリクルーティングにはデメリットが存在することも事実です。デメリットを把握し、無理のない導入を目指しましょう。
フローが確立するまで手間がかかる
ダイレクトリクルーティングは、ナビサイトへの掲載やSNS・イベントでの声掛けといった「たくさん集める」ための工数・コストを削減できる代わりに、「事前に絞って見極める」という個々の候補者に対する工数は増える側面があります。さらに、見極めた候補者それぞれにカスタマイズしたスカウトメールを作成し、動機付けになるようフォローしなければいけません。
従来の「50人集めて1人採用する」ような採用に対し、ダイレクトリクルーティングは「5人に会って1人採用する」手法といえます。社内フローが確立するまでは、採用担当者に負担がかかるかもしれません。
長期的な取り組みが必要
個々の候補者に丁寧なフォローを行って少しずつ志望度を高めるダイレクトリクルーティングは、一朝一夕で成果が出るタイプの採用手法とはいえません。
候補者の目に留まるよう個別に作成したスカウトメールで自社の魅力をアピールしたり、意欲の低い候補者に対してカジュアル面談を実施したりなど、地道な取り組みが必要です。その結果として潜在層にも自社の魅力を届けることが可能になりますが、反応が返ってくるようになるまで試行錯誤を繰り返す根気が必要でしょう。
ノウハウがないと実施が難しい
ダイレクトリクルーティングでは、候補者との対話のなかから魅力となる訴求を見極め、個別対応によって関係性を構築する力が求められます。
しかし、そのような提案力や傾聴力、合意形成力などの採用ノウハウには個人差があります。採用担当者個人の戦闘力の差が顕著に表れやすく、担当者が変わった途端にうまくいき始めるというケースも珍しくありません。
ダイレクトリクルーティングを実施する手順
ダイレクトリクルーティングを導入する際は、まず自社の求める人材要件を明確化します。要件は、スキルや経験といった技術面と、人柄や価値観といった人柄面に分け、さらに「必須条件」「歓迎条件」に階層化するとスムーズです。
実施にあたっては、人材の選定基準やスカウトメールの作り方、採用までのフローなど一連のプロセスをマニュアル化しておきます。ダイレクトリクルーティングは個人対個人のやりとりになることが多いため、マニュアルに沿って作業を進めるとミスを防止できます。
一連の採用活動が終了したら、振り返りを実施するのも重要です。スカウトメールの開封率や選考通過率、内定承諾率などをデータ化し、採用プロセスのブラッシュアップに活用しましょう。
ダイレクトリクルーティングを成功させるポイント

ダイレクトリクルーティングを導入し、成果を出すためのポイントを紹介します。
求める人物像を明確に言語化する
ダイレクトリクルーティングのデータベースは、候補者が登録しているプロフィールや適性検査の結果から検索できる仕組みになっています。ターゲット層にアプローチしたくても、「自社が求める人材」が曖昧な状態では、ターゲティングも定まりにくいでしょう。求める人物像を明確に言語化するところまで準備しておくと、検索軸に落とし込みやすくなります。
求める人物像の設計は、ダイレクトリクルーティングにおいて最重要事項であるといえるでしょう。
採用担当だけでなく全社で取り組む
ダイレクトリクルーティングの特性や意義を経営陣に理解してもらうことも重要です。担当者が候補者との地道な交渉に力を入れても、経営陣から応募者数や面接の設定数を求められてしまい、担当者が板挟みになることも少なくありません。
採用担当者1人で採用を進めるのではなく、まずは経営陣を含むチームや会社全体で方向性を共有しましょう。ターゲットとなるのはどのような人材か、どのくらい予算をかけられるか、目標達成のためにどのくらい工数がかかるか、対応できるリソースはあるかなどを明確にしたうえで取り組むと、経営陣の理解も得られやすいでしょう。
PDCAを実施する
ダイレクトリクルーティングは、あくまでも自社の採用課題を解決する選択肢のひとつです。「自社ならではの採用ノウハウ」を確立するためには、結果をふり返り試行錯誤を繰り返す姿勢が必要です。「重点的に攻めるターゲット層を設定し直そう」「自社PRの優先順位を変えてみよう」といった粘り強さが求められます。
比較的導入がうまくいっている企業でも「なぜうまくいったか?」「改善できそうなところはないか?」と常に自社の採用ノウハウをブラッシュアップを図ることで、さらなる成果につながります。
個々の応募者に向き合う覚悟が必要
ダイレクトリクルーティングによって集客にかける手間は削減できますが、その分候補者1人ひとりに向き合う誠実さや熱量が必要になることは覚悟するべきです。自社のことを理解してもらうだけでなく、候補者のことも深く理解しなくてはなりません。
候補者と深く向き合うと「このようなことを不安に感じていたんだな」「自社にこういうイメージを持ってくれていたんだ」という気づきも出てくるでしょう。企業と学生の深い相互理解によって、自社にマッチする人材を獲得する可能性が高まるのです。
ダイレクトリクルーティングが向いている企業
自社の求める人材にピンポイントでアプローチできるダイレクトリクルーティングは、採用要件が明確に定まっている企業に向いています。
仕事に対する価値観や考え方など志向面に高い基準を設けていたり、専門職の採用で特定のスキルや経験のある人材を募集していたりする企業は、求める人材の絶対数が少なく、母集団形成を困難に感じているでしょう。そのような企業こそ、ダイレクトリクルーティングによって潜在層も含めたターゲット層と効率的に接触することがおすすめです。
また、前述の通りダイレクトリクルーティングは個々の候補者と時間をかけて向き合う熱意と根気が求められます。手間をかけても自社の採用要件に適う人材を獲得し、自社の採用力を強化する熱量がある企業でないと導入は難しいといえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングのサービス比較
実際に利用できるダイレクトリクルーティングサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なサービスの一部を比較して紹介します。
新卒向けダイレクトリクルーティングサービス
新卒向けのダイレクトリクルーティングサービスのうち主なものは以下の通りです。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
・文理問わず幅広い属性の学生が多く登録している |
|
・登録者の約半数が国公立・GMARCH以上 |
|
・予算に合わせて複数の料金制度を選べる |
中途向けダイレクトリクルーティングサービス
中途向けのダイレクトリクルーティングサービスのうち主なものは以下の通りです。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
・経営幹部、管理職、専門職などハイクラス層に特化した媒体 |
|
・特にIT/Web業界の人材が豊富 |
|
・大手企業出身者やリーダー候補など若手ハイキャリア層に特化した媒体 |
まとめ
ダイレクトリクルーティングを活用すると、次の4つのメリットを得ることができます。
- 自社の求めるターゲット層と接触できる
- 潜在層にも幅広くアプローチできる
- 採用コストを削減できる
- 採用ノウハウを社内に蓄積できる
一方で、個々の候補者を丁寧にフォローする必要があり、熱量と根気のいる手法であることも事実です。導入の際は、採用要件を明確にし、自社にとってダイレクトリクルーティングが最適な手法なのかよく検討したうえで、サービスを選定しましょう。
最後に、本記事では紹介しきれなかったダイレクトリクルーティングの概要を基礎から徹底的に解説した資料をご用意しています。こちらもあわせてご覧いただき、検討材料としてご活用いただければ幸いです。