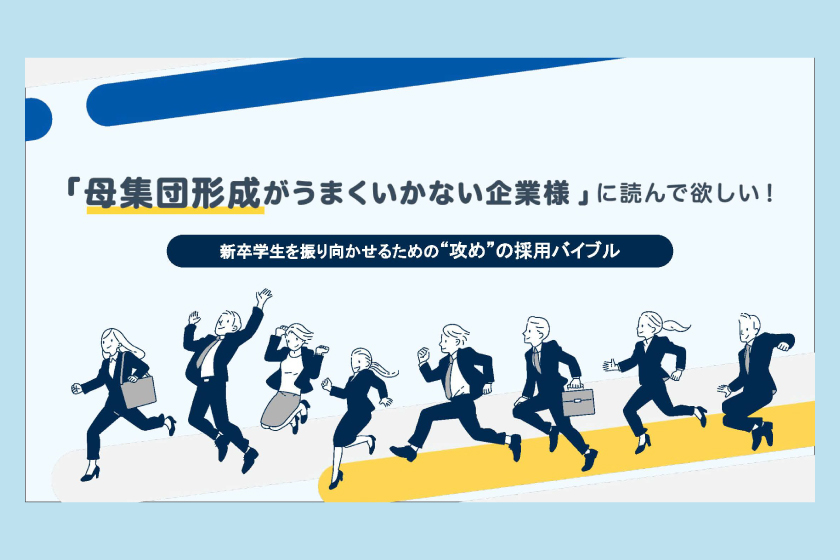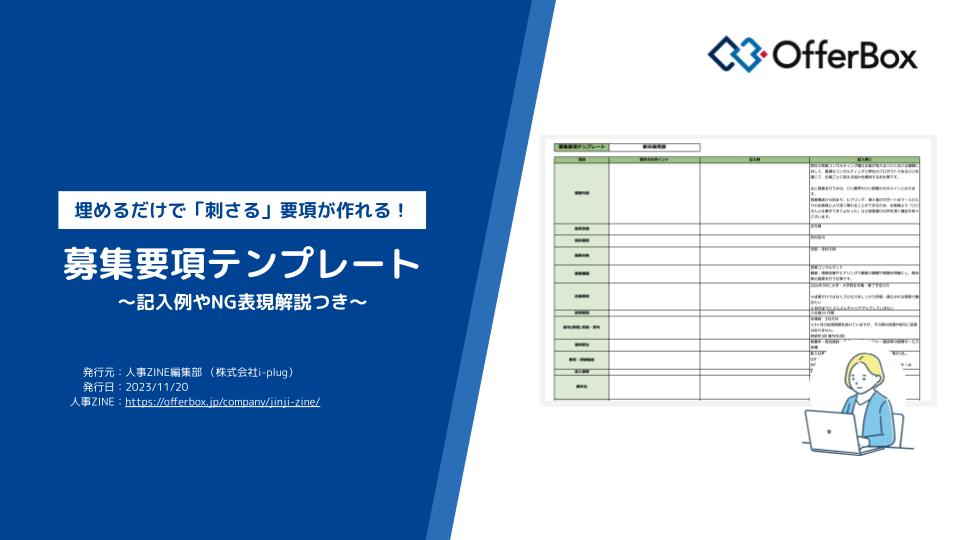リクルーター制度とは?5ステップで導入!メリットや適任者の特徴を解説

就職活動の早期化や通年化が起こるなか、自社に合った人材にアプローチをする方法として注目されているのが「リクルーター制度」です。しかし、「そもそもリクルーターとは何?」という疑問を抱えている方も多いでしょう。
そこで今回の記事では、リクルーター制度の概要やメリット・デメリット、導入時に重要なポイントなど幅広く解説します。実際の導入方法についても触れていますので、リクルーター制度を導入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
また、どのように出会いたい学生と関係を構築するべきかについてお悩みの採用担当者の方は、本記事とあわせてこちらの資料もご活用いただければ幸いです。
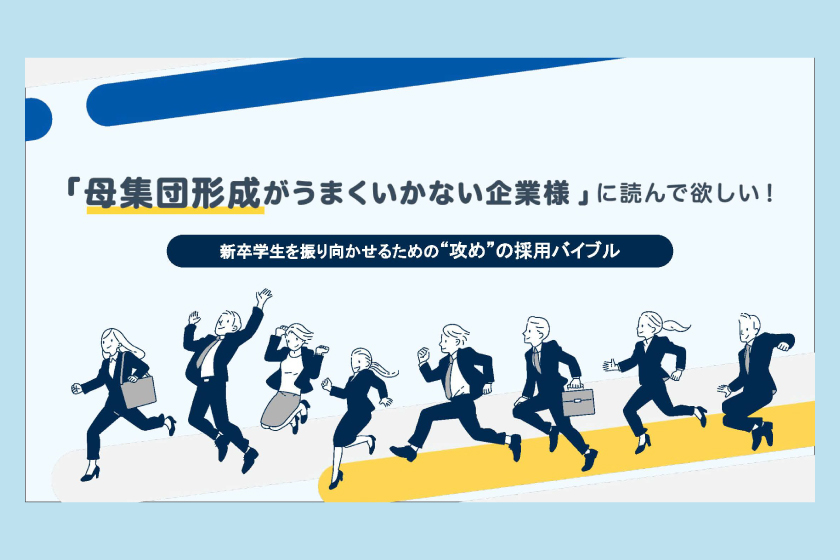
目次
リクルーターとは

「そもそもリクルーターとは?」と疑問に思っている方も多いでしょう。ここでは、リクルーターの定義や役割、そしてリクルーター制度の概要について詳しく解説します。
リクルーターの定義
リクルーターの定義は、「採用担当として、就活生のサポートなどの役割を担う人」です。ただし一律に定義が設定されているわけではなく、リクルーターの活用方法は企業によって若干異なります。例えば採用専門として担当することもあれば、他の業務と兼ねて取り組むケースもあります。
リクルーターとして選ばれることが多いのは、就活生に年齢が近い若手社員です。ただし昨今では、より業務や経営に関する深い話ができるとして、中堅社員やベテラン社員がリクルーターとして活躍することもあります。
リクルーターの役割
リクルーターの主要な役割は、質の高い母集団を形成することです。母集団を形成するためには、「量」と「質」の両方を追求しなければなりません。リクルーターは、母集団形成の業務のなかでも、特にその「質」を高めるためにさまざまな取り組みを実施します。
また自社のプロモーションや悩み相談など、「リアルなやりとり」を通して、就活生に対する理解を深めたり、就活生に理解を深めてもらったりするという役割もあります。さらに就活生が内定を獲得した後も、入社前のフォローを徹底し、内定辞退などのリスクを最小限に抑えるというのも重要な役割です。
リクルーター制度の概要
リクルーター制度とは、既存社員がリクルーターとなり、学生や求職者などとの関係を構築し応募・選考にあたってのサポートを担当する制度です。
リクルーターは、人事部門の社員が担当することもあれば、現場経験のある社員を起用することもあります。特に、採用ターゲットの要件が「理系工学分野」などと具体的に決まっており、社内に同じ出身の社員がいる場合は、学生を理解しやすく人脈を活用できる可能性があるのでリクルーターを担当することもあるようです。
リクルーター面談とは?3つの種類を紹介

リクルーターの代表的な業務がリクルーター面談です。大きく分けると、「スカウト」「説明会」「カジュアル面接」の3つがあります。ここでは、リクルーター面談の代表的な形式について、3つのトピックに分けて解説します。
スカウト
スカウトは、就活生に直接アプローチして、企業に合った人材を選ぶ方法です。リクルーターとして選ばれた社員が、出身大学のOB/OGとして、就活生にコンタクトを取ります。
また人脈以外にも、求人サイトなど、各種サービスのデータベースを利用する方法もあります。いずれにせよ、「特定の就活生に対して直接アプローチをする」という点で共通しており、採用要件に合致した母集団形成に大きく役立ちます。
説明会
説明会を通して、リクルーター面談を行う方法もあります。それほど規模の大きくない説明会であれば、参加する就活生の数は、数人程度が基本です。説明会兼面談のような形で、就活生の不安を聞いたり、解決策を提案したりします。
就活生は、企業に関する「リアルな情報」を知りたがっています。説明会では、質疑応答の時間を設けて、就活生の疑問や不安を解消するよう取り組むのがよいでしょう。リクルーターや企業に対して、親近感を持ってもらいやすくなります。
カジュアル面談
カジュアル面談・カジュアル面接は、選考段階の面接のようなかしこまった場ではなく、カフェなどの落ち着いた場所で面談をする方法です。本来の面接と比べれば、就活生が幾分かリラックスして臨めるため、本音を聞き出しやすくなります。
カジュアル面談をどのように活用するかは、企業によって異なります。選考が始まる前にカジュアル面談を導入し、その感触によって一次面接や二次面接を免除するケースや、本選考のインターバルとして挟まれることも珍しくありません。
リクルーターに適している人の特徴

リクルーターは、就活生と接触する都合上、全ての社員に任せられる仕事ではありません。ここでは、リクルーターに適している人の特徴を、「親しみやすさ」「傾聴力」「組織や業務への理解の深さ」の3つに分けて解説します。
親しみやすい
まずは「親しみやすい人」です。これには色々な意味が含まれているものの、最も分かりやすいのは、就活生と年齢が近い若手社員でしょう。親しみやすいリクルーターであれば、就活生に心を許してもらいやすくなり、本音を引き出しやすくなります。
もちろん親しみやすさとは、ただ年齢が近いだけではなく、気さくな人柄などの要素も該当します。特に自社の興味を喚起するなど、「認知から興味のプロセス」を重視したい場合は、親しみやすさのあるリクルーターを選出しましょう。
傾聴力がある
リクルーターを選ぶ場合は、「傾聴力」も重要なキーワードになってきます。確かにリクルーターは、自社の魅力を伝えなければならないため、「話す力」を中心としたコミュニケーション能力が求められます。
しかしリクルーターの役割は、就活生に理解を深めてもらうだけでなく、同時に就活生への理解を深めることでもあります。そのためには、「就活生がどのような悩みを抱えているのか」をヒアリングし、情報として整理しなければなりません。
組織や業務への理解が深い
組織や業務への理解が深い人も、リクルーターに向いています。例えば入社15年以上の中堅〜ベテラン社員は、業務内容だけでなく、経営戦略やマネジメントなどの高度なトピックにも対応可能です。
若手社員よりも高いレベルで自社について話せるのが、中堅〜ベテラン社員の大きな魅力でしょう。就活生の「認知」や「興味」のために若手社員をリクルーターに選出し、入社の意思固めのために中堅〜ベテラン社員を起用するなど、状況によって担当を変えている企業もあります。
自身がリクルーターに向いているか、適性を知りたい方は、「採用・人事タイプ別診断」をぜひお試しください。所要時間3分で、あなたが得意とする仕事のスタイルを分析します。

リクルーター制度を導入する企業側のメリット
リクルーター制度を導入すると、企業にとってさまざまなメリットがあります。ここでは、「自社に合った人材に直接アプローチできる」など、リクルーター制度のメリットを詳しく解説します。
自社に合った人材に直接アプローチできる
まずは、自社に合った人材に直接アプローチできることです。先述のように、リクルーター制度では、OB/OG訪問や大学での個別説明会などさまざまなパイプを通して就活生に接触します。
また就活生と個別に接するため、その人の能力だけでなく、人柄や価値観なども深く理解できるようになります。そのうえで自社が求める人材であると分かった場合にはよりきめ細かくアプローチする、といった施策も可能です。
就活生の本音を引き出せる
就活生の本音を引き出せるのも、リクルーター制度を導入する大きなメリットです。通常の説明会や面接に臨む場合、就活生は「就職活動向けの自分」を演じる傾向にあり、リアルなやりとりがしにくい状態にあります。
就活生と年齢の近い社員をリクルーターにし、カジュアル面接などの場を用意すれば、就活生の本音を引き出せる可能性が高まります。就活生への理解が深まれば、採用するかどうかの判断だけでなく、採用後の配属にも大きく役立てられるでしょう。
就活生の志望意欲を高められる
就活生の志望意欲を高められるというメリットも見逃せません。
リクルーター制度を取り入れていれば、就活生の属性、志向、価値観などを深く知ったうえで、個別のアプローチが可能になります。個々の就活生が就職先選びにあたって重視するポイントを理解したうえで、それぞれの相手に響く訴求がしやすくなるので、他の採用手法よりも志望意欲を高めやすいのです。
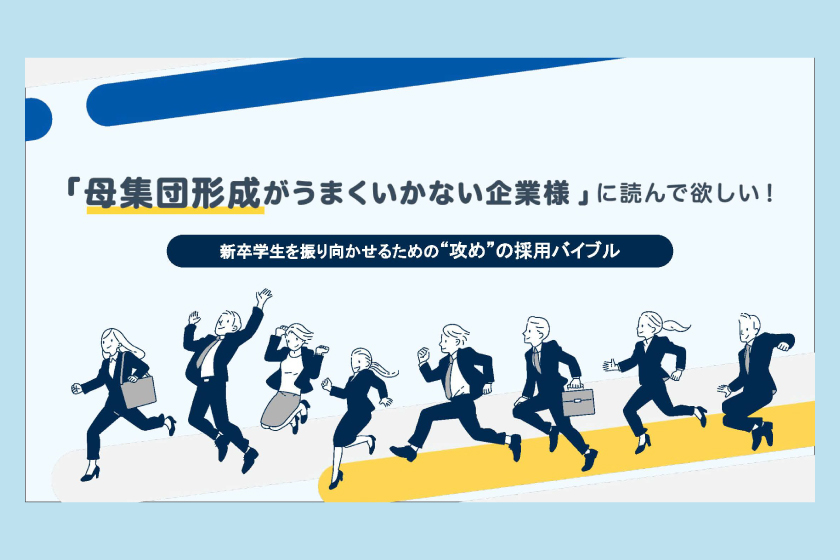
リクルーター制度を導入する企業側のデメリット
リクルーター制度には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。メリット・デメリットをよく整理したうえで、制度の運用を考えましょう。ここでは、リクルーター制度を導入する企業側のデメリットを、3つ解説します。
リクルーターの質に依存する
まずはリクルーターの質に依存することです。リクルーターとして適性がない人をアサインし、もし就活生に失礼な態度をとってしまえば、リクルーターだけでなく企業全体の印象が悪くなります。
リクルーター制度を成功させるためには、適した人を選ぶだけでなく、その人を育成するのも重要です。「リクルーターの質がリクルーター制度の成功を左右する」といっても過言ではないでしょう。
アプローチする人材に偏りが生じる
アプローチする人材に偏りが生じるのも、リクルーター制度のデメリットです。OB/OG訪問など、特定のパイプを利用する都合上、「同じ大学の人だけ」などアプローチする人材が限定されてしまう可能性があります。
人材の多様性を考える場合は、多少のデメリットも覚悟すべきでしょう。毎年採用が遅れているのであれば、リクルーター制度による状況の改善が期待できます。ただし、採用する人材の質にそこまで大きな問題がない場合は、導入するかどうかをよく検討しましょう。
通常業務に支障が出る可能性がある
通常業務に支障が出る可能性があるのも、リクルーター制度の見逃せないデメリットです。リクルーターは、外部に委託しない限りは、自社の社員から選出するのが基本になります。その人が他の業務を担当している場合は、ポジションから外れてもらうか、リクルーターと兼務してもらわなければなりません。
リクルーター活動に多くの人を割いてしまうと、通常業務に支障が出てしまう可能性があります。リクルーター制度を導入する場合は、事前のシミュレーションを徹底しましょう。
リクルーター制度導入のステップ

リクルーター制度の導入は「制度の整備」「アプローチ先の指定」「リクルーター候補の選出」「育成・アサイン」「制度の開始」の5ステップです。ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説します。
1.リクルーター制度の整備
まずはリクルーター制度の準備です。制度の概要を社内で共有し、社員に認知してもらいます。リクルーター制度における、運用のルールも策定しておきましょう。具体的には、カジュアル面接をする際の飲食費や出張費など、費用に関する事柄です。
またここでは、おおまかな採用活動の方向性を決めておく必要があります。「既存の採用ではどのような課題があるのか」「どのような人材を獲得すべきか」など、社員にとって分かりやすい形でまとめましょう。
2.アプローチ先の指定
リクルーター制度の準備ができたら、次にアプローチ先の指定を行います。具体的には「どの学校にリクルーター制度を適用するか」を決めます。適用する学校のリストアップや、リスト外でもリクルーターを派遣する範囲の決定をしておきましょう。
さらにOB/OG訪問や、大学での個別説明会など、リクルーター面談の方法を確定させておくのも重要です。リクルーター候補の選出や育成に役立てるためにも、具体的な方法は前もって想定しておきましょう。
3.リクルーター候補の選出
アプローチ先の指定が終わったら、次にリクルーター候補を選出します。ここが、リクルーター制度の成功・失敗を分ける重要なポイントです。先ほど紹介した、「リクルーターに適している人の特徴」を参考にして選ぶとよいでしょう。
既存社員からリクルーター候補を選ぶのが基本であり、ひとまず就活生と歳が近い若手社員を選ぶのが無難です。業務や組織に関する深い話をしたい場合は、中堅社員やベテラン社員を検討しましょう。
4.リクルーターの育成・アサイン
次に、リクルーターの育成・アサインを行います。リクルーターとして選ばれる人のなかには、採用活動に携わった経験がない人もいるでしょう。リクルーターは、いきなり始めてこなせるようなものではないため、社内での育成が必要です。
具体的には「自社が欲している人材」「訴求したい自社の魅力」「採用計画の詳細」などの情報を、リクルーター候補に伝えます。こちらも、リクルーター制度を成功させる重要なポイントなので、必ず実施しましょう。
5.リクルーター制度の開始
全ての準備が整ったら、リクルーター制度を開始します。先ほど紹介した「スカウト」「説明会」「カジュアル面接」の3つのリクルーター面談を軸に、制度を運用していきましょう。
リクルーター制度導入のポイント

リクルーター制度を導入する際は、いくつかのポイントを意識しておきましょう。ここでは、事前準備の徹底やリクルーターの選出など、制度導入時のポイントを詳しく解説します。
事前準備を徹底する
事前準備とは、リクルーターの選出や育成する仕組み、アプローチ対象の選定基準の決定などを指します。事前準備ができていないと、適切なリクルーター候補を選出できなかったり、導入時にさまざまな問題が発生したりします。前もって、組織のなかで方向性を共有しておきましょう。
また、自社が求める人材に効率的かつ効果的にアプローチするうえでは、外部ツールの導入も有効です。ダイレクトリクルーティング系のサービスなどの利用も、就活生にアプローチする際に効果を発揮する可能性があります。自社のリソースに応じて検討するとよいでしょう。
リクルーターの選出に気を付ける
事前準備のなかでも、リクルーターの選出には細心の注意を払いましょう。リクルーターの選出は、結果を左右する重要なポイントです。
リクルーターは、就活生のロールモデルともなる存在です。人柄のよさや、コミュニケーション能力が高さだけでなく、「この人のように働きたい」と思ってもらえるような人材を選出できればベストです。
選出を適当に済ませずに、「社員の適性を見極める」「社内教育を含めてパフォーマンスを出せるリクルーターを用意する」などの工夫を徹底しましょう。
導入後のレビューを行う
採用管理システムなど、外部のツールを活用して、レビューをしやすい環境を整えておくのも重要なポイントです。リクルーターや責任者を含めて振り返りを行い、課題を洗い出しつつ、PDCAサイクルを回していきます。翌年以降に向けて、コツコツとノウハウを積み上げていくイメージです。
また導入後のレビューも大切ですが、採用担当者で認識を共有しておき、トラブルが起こった際もスムーズに対応できる仕組みを整えておく作業も必要です。特に採用活動は、企業ブランドを傷つけるリスクもあるため、より慎重になる必要があります。
まとめ

採用活動が早期化している現代において、リクルーター制度の重要度が増してきています。メリット・デメリットの双方を整理し、導入するべきかどうかをよく検討しましょう。
制度を導入する際に、特に気をつけておきたいのが「リクルーターの選出」です。リクルーターは、採用活動の成功だけでなく、企業ブランドにも大きく関わります。選定後の育成も徹底し、効果的に運用できるように準備をしておくのが重要です。
母集団形成に課題を感じている場合は、スカウト型の採用がおすすめです。「新卒学生を振り向かせるための”攻め”の採用バイブル」は、スカウト型採用に関する課題解決に大きく役立てられます。検討されている方は、まずはこちらの資料をご覧ください。