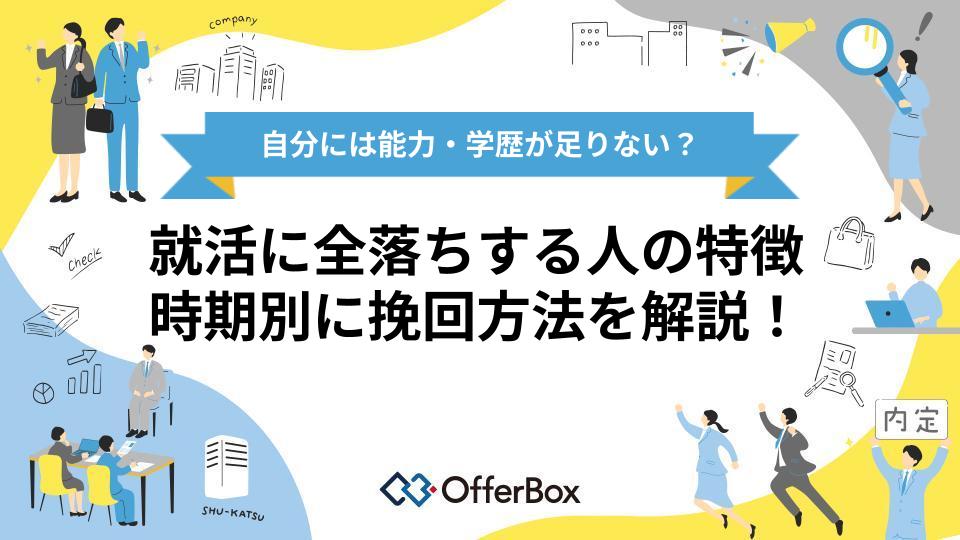
>>【無料】「OfferBox」に登録してオファーを受け取る
就活で選考中の企業に全て落ちてしまうと、不安や焦りから「自分は能力が無いのかも」「学歴が高く無いからだ」などと自暴自棄になる人もいるかもしれません。
しかし、全落ちしたとしても、軌道修正できれば挽回は十分可能です。なぜならそれは各選考過程での準備ややり方を知らなかっただけで、必要な対策を丁寧におこなえば内定をもらえる可能性はまだまだあります。
本記事では、就活で全落ちする人の特徴や必要な対処法を選考フェーズごとに解説、立ち直り方などを詳しく紹介します。最後まで読んで、全落ちしてしまったときの挽回方法を理解し、不安な気持ちを払拭し、今日から内定獲得に向けて動き出せるようにしましょう。
OfferBoxは、就活生の約24万人(※1)に利用されている新卒逆求人サービスです。
プロフィールや自己PRを登録しておくと、あなたに興味を持った企業からオファーが届く仕組みで、「就活の一歩を踏み出せない」「就活に疲れてしまった」という方にも使っていただきやすいでしょう。
累計登録企業数も約20,423社(※2)と豊富なため、ぜひ活用してみてください。
(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより
(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)

目次
就活に全落ちする人の特徴を選考フェーズごとに解説
就活で全落ちしてしまう原因は、エントリーシート、グループディスカッション、面接などそれぞれの選考フェーズで異なります。
まずは自分がどの段階で落ちることが多いのかを振り返り、自分に当てはまることはないか、それぞれの対策方法を確認していきましょう。
エントリーシート(ES)で落ちてしまう人
ESは、企業との最初の接点です。ここで魅力を伝えきれなければ、次のステップのグループディスカッションや面接に進むことすらできません。
ESで落ちてしまう人には、「エントリーシートを使い回し」「就職難易度の高い大手・有名企業ばかりを受ける」「業界や企業数を絞りすぎ」という3つの特徴があるのでそれぞれ解説してきます。
一度完成させたエントリーシートを使い回し
多くの学生がやってしまうのが、一度作成したESをその後ずっと同じ内容のまま使い続けてしまうことです。
就活を進める中で新しい経験をしたり、自己分析が深まったり、選考を受ける中で面接官からの質問や反応を通じて、自分のどの部分が評価されやすいかが見えて、より効果的な表現方法を見つけたりすることがあります。
例えば、最初は「アルバイトでリーダーを務めた」という表現が、「チームの売上を前年比120%向上させるために、メンバーのモチベーション向上施策を3つ実行した」というように、より具体的な表現にブラッシュアップできたりします。
ESの内容については、選考を進めていく中で定期的により良い中身にアップデートしていくことは常に心がけましょう。
ただ、毎回ESを作成し続けることに手間がかかるのは事実です。そんな時は、オファー型就活サービスを活用して効率化することも手の一つです。オファー型なら、プロフィールを見てあなたに興味を持った企業からオファーが届く仕組みなので、毎回ESを書いて提出する手間を減らすことができます。
オファー型就活の「OfferBox」なら、毎回ESを作成し提出する手間がなく効率的!
就職難易度の高い大手・有名企業ばかりを受けている
テレビCMで見るような知名度の高い企業や業界最大手ばかりを受けるのも危険です。
なぜなら、そうした企業は応募者も多く、競争倍率が非常に高くなり、優秀な学生でも落ちることは珍しくありません。
大手や有名な企業を目指すのは悪いことではないですが、中堅・中小企業やベンチャー企業の中にも、大手企業に劣らない事業内容や成長性、働く環境など魅力のある企業は数多くあります。
大手や有名な企業と同時並行でも良いので、初めから選択肢を狭めず、視野を広げて様々な企業にエントリーしていきましょう。
業界や企業数を絞りすぎて選択肢が少ない
1つの業界だけ、特定の企業のみを受けることも全落ちを招くリスクがあります。
この業界・企業に行きたいという志は大切ですが、就活の初期段階の自己分析がまだ浅い段階で「自分にはここしかない」と思い込んでしまうと、全落ちだけでなく、入社後のミスマッチの危険もあります。
最初は興味の範囲を広く持って、少しでも面白そう、自分に合っていそうと感じた業界や企業の説明会や選考に参加してみることがおすすめです。
また、オファー型の就活サービスなら、自分のプロフィールを見て自社にマッチしていると思った企業があなたにオファーをもらえる可能性があります。
自分の経験がこんな分野でも活かせるんだ、と自分の知らなかった業界や企業へと就活の視野を広げることができるので、オファー型の利用も検討しましょう。
オファー型就活の「OfferBox」なら、様々な業界・企業への視野を広げられる!
グループディスカッションで落ちてしまう人
グループディスカッションは多くの学生が苦手と感じる選考です。
普段大学の授業や日常生活で経験しないため、そもそもどのように進めれば良いのか、メンバーの役割分担、評価ポイントなど基本を知らないがゆえに苦手意識を持つ人が多くいます。
逆にポイントさえ抑えれば、次回のグループディスカッションから自信を持って参加できるようになるので、ここでよく確認しましょう。
グループディスカッションで企業がみているポイントを把握していない
多くの学生が、何かすごい意見を言わなければ・誰よりも目立たなければと勘違いしがちです。
しかし、グループディスカッションの目的は正しい答えを出すことではなく、企業が見ているのは、与えられた時間の中で、チームとしてより良い結論を導き出すためのプロセスの部分です。
具体的には、以下のようなポイントが評価されています。
- コミュニケーション力:相手をいら立たせず自分の意見を伝えられる
- 協調性:自分の意見だけでなく、他の人の話も真剣に聞いているか
- 態度や印象:話す時の明るさ、言葉遣い、貧乏ゆすり・髪をいじるなどの挙動がないか
- 論理的思考力:数字や過去の事例を使い、客観的に自分の意見を説明できるか
準備不足で、議論のスタートラインにすら立てていない
グループディスカッションには、議論をスムーズに進めるために型が存在します。まず、議論の進め方や役割は確実に抑えておきましょう。
進め方や役割を知らないまま臨むと、全く自分をアピールできないまま終わってしまいます。
【基本的なグループディスカッションの進め方】
- 自己紹介・役割分担を決める:簡単な自己紹介と、議論を円滑に進めるために役割を決める。
- 時間配分・前提確認:お題に対して、どのステップにどれくらいの時間をかけるかを確定させる。
- アイデア出し:メンバー全員で自由にアイデアを出す。
- 議論・アイデアの整理:出てきたアイデアを整理し結論の方向性を定める。
- 結論・発表:スライド作成など指定の発表準備をして、議論の結果を簡潔に発表。
グループディスカッションでは次のような役割があり、チームメンバーの適性を考えながら、自分が貢献しやすいポジションを探しましょう。
| 役割 | おすすめな学生 | |
| ファシリテーター | 議論を効率的に進めメンバーの意見を整理する | 議論を整理してまとめるのが得意。リーダーシップをアピールしたい。 |
| 書記 | 話し合った内容をメモし、整理する | 議論の要点を捉えて適切に整理できる。 |
| タイムキーパー | どんな議論にどれくらい時間を割くかを管理する | 議論に熱中しすぎず全体を俯瞰して見ることができる。 |
| 発表者 | グループでまとめた内容を全体で発表する | 大人数の前で話すことが得意。 |
気付かないうちにNG行動・発言をしている
グループディスカッションの際に、以下のような行動は減点対象になりやすいため注意が必要です。
- 発言がほぼゼロで存在感がない:議論に参加する意欲がないと見なされ減点対象になる。
- 話の腰を折り議論を脱線させる:協調性がなく、自分のことしか考えていないと判断されてしまうため、議論の流れを読み、適切なタイミングで建設的な発言をする。
- 論破ばかりで対話が成立しない:相手を打ち負かすことが目的になり、チームワークを阻害すると判断される。異なる意見が出た場合に論破ではなく、意見に折れたり、折衷案を探る姿勢が必要。
グループディスカッションの基本や選考通過率、お題例など詳細が知りたい人は以下の記事も参考にしましょう。
>>【無料】「OfferBox」に登録して就活の視野を広げる
面接で落ちてしまう人
書類選考やグループディスカッションを通過しても面接で毎回落ちてしまう人には、「用意した原稿をそのまま読む」「準備不足」「企業とのマッチ度がアピールできていない」などの共通した課題があります。
ここでは、面接で落ちてしまうことの原因とその対策を確認します。
用意した原稿をそのまま読み上げる
ESの内容や事前に準備した原稿の内容を丸暗記で話すのは注意が必要です。なぜなら、面接官は学生の人柄や考え方を知りたがっているため、自分の言葉で伝えることが非常に重要です。
対策としては次のポイントを実践しましょう。
- キーワードのみのメモを用意し、録音しながら自分の言葉で語る練習をする
- 大学のキャリアセンターや友人に模擬面接をしてもらいフィードバックをもらう
準備不足で質問に答えられない
面接でよくつまずくポイントの1つが、「なぜなのか」の深掘りです。
表面的な回答しか用意していないと、
「なぜそう考えたのか」「その経験で何を学んだのか」「もう一度やるならどう改善するか」の質問に答えられず説得力が一気に減ってしまいます。
エピソードを話す際は、背景、課題、自分は何をしたのか、その結果どんな成果が出たか、そこからの学びは何か、までを整理しましょう。
具体的な対策としては、自分自身で「なぜ」を10回問いかけることで、面接官の追加質問にも対応できるようになりますので実践してみましょう。
企業の指針や文化と異なるアピールをしている
企業研究が浅い状態で、「私の強みは挑戦力です」「その強みを御社で活かします」といった汎用的なアピールをしても、面接官には響きません。
企業の事業内容や指針・文化、求める人物像を理解していないと、「うちの会社でなくても良いのでは?」と思われてしまいます。
以下のように企業が求める人物像と、自分の強みを適切にリンクさせることが必要です。
【新しいアイデアや柔軟な思考を求めるベンチャー・スタートアップ企業】
- 強み:「新しいアイデアを生み出す発想力」
- エピソード:「アルバイト先でシフト作成の効率化に向けたアプリ導入を提案し、シフト作成の作業時間を週3時間短縮した」
【顧客ファーストを掲げる老舗企業】
- 強み:「相手の立場に立って考える共感力」
- エピソード:「部活で意見対立が起きた際、全員の話を個別に聞き、双方が納得できる解決策を見つけてチームを1つにまとめた」
【海外拠点を持ちグローバルに展開する企業】
- 強み:「多様性を受け入れる柔軟性」
- エピソード:「留学生との共同プロジェクトで文化の違いを理解し、それぞれの強みを活かしてプロジェクトの成功に導いた」
就活の面接について対策やコツ、マナーなどの詳細をもっと知りたい人は以下の記事も参考にしましょう。
全落ちした時期別の挽回策
前章までは、選考フェーズごとで全落ちする原因とその対策について説明してきました。
実際の就活では、全落ちしてしまった場合の対策は、時期によって動きが異なります。そのため、この章では、全落ちした時期に応じた対策について解説していきます。
大学3年生は準備不足の可能性が高い!準備や自己分析を徹底しよう!
大学3年の段階で全落ちしている場合の多くは、準備不足が一番の原因である可能性が高いです。この時期はまだ時間に余裕があるため、基礎からしっかりと準備し直すことで挽回は可能です。
まず、実践することは「自分の強みや経験を整理し直す」ことです。
ここでは、STARフレームワークを使って、過去の経験を棚卸しする方法が有効です。以下の表の記入例の部分を自分に当てはめてみましょう。
| 確認内容 | 記入例 | |
| S (Situation) | 自分の強みが発揮した時の状況 | ・バイト先で、新人スタッフの定着率が低かった・ゼミの共同論文でメンバーの意見がまとまらない |
| T (Task) | どのような課題や目標があったか | ・新人教育のマニュアルが古く、業務を覚えきれない・期日内に質の高い論文を完成させることが目標 |
| A (Action) | 具体的にどう行動しましたか | ・動画を取り入れた新しいマニュアルの作成を主導・各メンバーの意見の共通点と相違点を可視化して話し合い |
| R (Result) | その結果何が得られたか | ・半年後の定着率が50%から80%に向上・感情的な対立がなくなり無事論文を完成、教授から最高評価を獲得 |
面接とグループディスカッションのスキルを磨く
自己分析で自分の強みをアピールすべきことが明確になれば、次はそれを伝える練習が必要です。
就活サイトや企業が実施するセミナーやキャリアセンターの講座を活用して、フィードバックを受けながら改善を進めることが大切。以下で、面接とグループディスカッションのスキルを磨くことができるので実践しましょう。
- 大学のキャリアセンターの模擬面接
- 企業が実施する面接・グループディスカッション対策セミナー
- OB・OG訪問でのフィードバックをもらう
- 模擬面接の様子を録画しAIにフィードバックさせる
- 友人や先輩にアドバイスをもらう
場数を増やし視野を広げる
就活序盤には経験として、選考の場数を踏むことも重要です。
場数を踏むと、面接官に刺さる強みやエピソード、面接官の反応を踏まえ話す内容を見直せたり、思わぬ業界や企業と出会うこともあります。
様々な企業に直接エントリーすることも良いですが、オファー型就活サービスの利用も検討してみましょう。オファー型だと、興味を持っていなかった業界・企業からもオファーを受けることができるので、想定していなかった選択肢を増やすことができます。
また、様々な企業を見ることで、業界や職種に対する理解も深まり、自分に本当に合った企業を見つけることができるので、就活序盤のうちに視野を広げることもできます。
>>【無料】「OfferBox」に登録して就活の視野を広げる
大学4年生4月〜6月はさらに視野を広げつつ、選考企業数を増やす
大学4年生の4月から6月にかけては、多くの企業で本格的な採用活動が行われる時期です。
この時期に全落ちしている場合は、もう一段階、企業の幅を広げて選考を受ける企業の数を増やすことを意識しましょう。
具体的な手法としては、業界や企業規模で視野を広げていくことです。
例えば、食品業界を中心に見ているなら、食品を扱う商社や食品パッケージを開発する化学メーカー、食品の生産管理システムを運営するIT企業など、少し視野をずらしてみましょう。また、大手企業のみを受けていた場合には、同じ業界内の中堅・中小企業にも目を向けてみましょう。
他にもこの時期には、3年時に経験したアルバイトやサークル活動、学業での取り組みなども、ESや面接回答に組み込んでいきましょう。
強みやエピソードの中身も重要ですが、ESや面接ではそのエピソードが「いつの話か」という点も見られています。当然、大学1年生の頃のエピソードよりも、大学3年生の直前の話の方がより今の自分に近い姿なので、説得力も増してきます。
就活を進めながらも、インターンや学業、アルバイトでの成果をアップデートされていくので、ESや面接回答の鮮度を保つことは意識していきましょう。
>>【無料】「OfferBox」に登録して就活の選択肢を広げる
大学4年生7月以降は就活の軸や目的を見直す
4年の夏休みの時期になっても内定がないと、周りは内定を獲得しているのにと、精神的にかなり追い詰められるかもしれません。この時期で全落ちの場合は、一度立ち止まって軸や目的を根本的に見直すことが必要です。
例えば、軸を業界から価値提供や働き方に広げることも1つの手です。
世の中にどんな価値を提供したいか、どんな人とどのような環境で働きたいかなど、特定の業界へのこだわりを捨てることで、選択肢をぐっと増やすことができます。
また、新卒一括採用だけがルートではないため、長期インターンやアルバイトでスキルを磨きながら、就職活動を再スタートすることや、アルバイトからの正社員登用を狙うことも検討しましょう。
もしもまだ、大学4年の7月で就活を何もしていない場合の進め方やポイントは以下の記事で詳しい内容を解説しています。
>>【無料】「OfferBox」に登録して効率的に就活を進める
場数や企業の軸を増やすならオファー型就活サービスがおすすめ
全落ちした時の対策として、「場数を踏む」「選考企業の視野を広げる」とお伝えしてきましたが、その際におすすめなのが「オファー型就活サービス」です。
プロフィールを登録すればES提出が不要で効率化
オファー型就活サービスでは、自己PRやガクチカなどを1度入力するだけで複数の企業からオファーをもらうことができます。
従来の就活だと、応募する企業ごとにESを作成・提出する必要がありました。そのため、多くの企業に応募しようと思うと多くの時間を要します。
ですが、オファー型就活サービスでは、プロフィールを見た企業からオファーが届く仕組みになっているため、企業ごとにESを作成する手間が大幅に減り、より多くの企業との接点を効率的に持つことができます。
時間を節約できることで、その分を面接対策や企業研究に充てることができ、選考対策により多くの時間を割くことにもつながります。
プロフィールを改善して企業に刺さる強みを発見
オファー型就活サービスでは、プロフィールの内容によってオファーの数が変わります。
最初はオファーが少なくても、プロフィールの入力割合や内容を改善していくことで徐々にオファーの数を増やすことが可能です。
プロフィールを改善していくことは、自分の魅力や強みを客観視する良い機会にもなります。
どのような表現をすると企業からの反応が良いのか、どのようなエピソードが評価されるのかを試行錯誤することで、自分のアピールポイントや改善すべきポイントを知り、その後の選考にも活かせます。
見ていなかった業界からもオファーを受け取り視野が広がる
自分から企業を探すと、どうしても興味のある分野に偏りがちです。
しかしオファー型だと、本来なら自分では選ばなかった業界や職種の企業との接点ができ、自分が全く知らなかった隠れた適性や新たな興味を知るきっかけになります。
実際にOfferBoxを利用した吉田ももこさんは、製薬会社志望だったにも関わらず、全く視野に入れていなかった商社からオファーを受け取り、最終的にその企業に就職を決めました。
吉田さんは「専攻とは関係ない業界からオファーが来て『私でもこういう職種につけるんだ』と気づかされることが何度もありました」と振り返っています。
MR志望のはずが2月にオファーされた商社に内定! 吉田 ももこさん
特別選考の案内が届きES が免除になる場合も
オファー型就活サービスの場合、企業はあなたに興味があって、オファーを送るため、通常の選考フローとは異なる特別選考の案内をもらえることがあります。
例えば、ES提出が免除されていきなり面接から始まったり、選考ステップが短縮されたりするケースが多々あります。
通常の応募では書類選考で落とされてしまう可能性がある企業でも、オファー経由であれば面接まで進める可能性が高くなることもあります。
>>【無料】「OfferBox」に登録して効率的に就活を進める
オファー型就活サービス「OfferBox」は企業があなたをしっかり見てくれる
ここでは、オファー型就活サービスの1つである「OfferBox」の特徴について解説します。
特に次の内容がOfferBoxの強みです。
- プロフィール入力率8割以上で平均41件のオファー
- 企業が学生にオファーを一斉送信できない
- 学歴によるオファーの偏りがない
- 2万社を超える企業が登録
OfferBoxは、プロフィールの入力率を80%以上にするだけで、平均41件のオファーを受け取れる(※1)というデータがあります。
なおかつ、企業から学生へオファーを一斉送信することができないため、「あなたの経験は我が社で活かせそう」「この価値観なら自社の文化に合いそう」とプロフィールをきちんと読んだ41社からオファーをもらえるチャンスがあります。
通常の就活において、数多くの企業を受けることは非常に時間がかかって非効率ですが、プロフィールをきちんと埋めるだけで多くの企業と接点を持てるのは、OfferBoxに登録してみる大きなメリットです。
実際にOfferBoxを利用した学生は次のようについてコメントしています。

Y.Mさん

W.Kさん

M.Tさん
加えて、「オファー型は学歴上位が有利では?」といった声もありますが、実態はそうなっていません。
「旧帝大・早慶」「MARCH・関関同立」「その他国立」「日東駒専・産近甲龍」「その他」に分類した場合でも、学歴によるオファー受信の偏りはありません。(※2)
【OfferBoxの学歴によるオファー受信数の割合(OfferBox2023年卒データより)】

他にも、OfferBoxは、登録企業数の多さも強みの1つです。登録企業数は20,580社(※3)で、メーカーやITをはじめ、商社や広告・出版など多くの業界での利用が進んでいます。また、東証プライム上場企業のうち68%が利用しており(※4)、規模の大きい企業からオファーを受け取れる可能性もあります。
※1 OfferBox2023年卒利用実績データより
※2 OfferBox2023年卒利用実績データより
※3 企業登録数とは、これまで当社アカウントを開設した企業数であって、直近で利用していない企業を含みます(2025年5月時点)
※4 OfferBox2023年11月時点実績データより、累計社数より算出。累計社数にはこれまで当社アカウントを開設した企業数であって、直近で利用していない企業を含みます。
>>【無料】「OfferBox」に登録して効率的に就活を進める
就活で全落ちして立ち直れないときの対処法
ここまで読んでも「全落ちしたショックから立ち直れない」「どうしてもモヤモヤが晴れない」人もいるでしょう。メンタルを回復し、気持ちを新たに再び就活に取り組むための対処法を提案します。
気持ちを紙に書き出す
結果が出なかった悔しさや就職先が決まらない不安など、心の内を紙に書き出しましょう。モヤモヤしている気持ちを言語化するだけでも、多少なりともストレス解消になり、すっきりする人もいます。また、言葉にして書き出す作業は1人で簡単におこなえますし、感情が整理され、冷静かつ客観的に自分を把握することが可能です。
期限を決めて休む・気分転換する
いったん就活を思い切ってやめてみる方法もあります。就活は長期戦になりやすいため、疲れ切ったままでは就活の振返りや自己分析も十分にできないでしょう。
就活とは関係のないことをしてリフレッシュすれば、気持ちや思考を切り替えられるかもしれません。ダラダラと休むのではなく、1週間などと期間を決めて休むと再開しやすいでしょう。
就活での上手なストレス解消法は、以下の記事で紹介しています。
人に相談する
自分1人ですべて解決しようとせず、必要に応じて人を頼ることも大切です。精神的にきついなと感じている人は、無理せず誰かに相談してみてください。
相談相手は、家族や友達など親しい人でも構いませんし、しっかりと全落ちした原因を分析したいなら就職エージェントや大学のキャリアセンター、就職指導課などでアドバイスを求めることも有用です。
>>【無料】「OfferBox」に登録してオファーを受け取る
就活の全落ちに関するよくある疑問
就活の全落ちに関するよくある疑問は以下のとおりです。
- 就活で全落ちしてしまう確率は?
- 理系学生や大学院生の就活でも全落ちすることはある?
それぞれの疑問に対する回答を見ていきましょう。
就活で全落ちしてしまう確率は?
2023年卒業生の3月時点での進路確定状況を見ると、就活を経験した人のなかで大学生の96.3%が進路が確定しています。つまり、3.7%の人は卒業の時点で進路が確定していないということです。
また、2023年卒業生の書類選考を受けた平均数は11.4社で、最終面接を受けた企業の平均数は4.1社、内定した企業の平均数は2.2社でした。つまり、平均して9.2社不採用になっています。
具体的に就活に全落ちした確率はわかりませんが、この結果を見ると全落ちの確率は0%ではないということがわかります。
そのため、自己分析や企業・業界研究、選考ごとの対策をしっかり行って就活した方がよいでしょう。
理系学生や大学院生の就活でも全落ちすることはある?
理系学生や大学院生は専門知識を学んでいるため、就活に有利だと言われています。しかし、実際のデータを見ると2023年度卒業生の3月時点での文系大学生の進路確定者は96.6%、理系大学の進路確定者は95.7%で、大学院生の進路確定者は96.7%でした。
この結果を見ると、理系大学よりも文系大学の方が若干進路確定者の割合が高くなっています。また、大学院生は大学生よりも若干進路確定数の割合は多いものの、さほど変わりません。
理系大学生や大学院生であっても就活で全落ちする可能性はあるため、しっかりと対策を行いましょう。
気持ちを切り替えて就活を再スタートさせよう
就活で全落ちしてしまうと、どうすればいいのか不安になることでしょう。しかし、不採用になった原因を分析して対策すれば、就活の後半であっても十分挽回できます。
就活の成功はたくさん内定をもらうことでも、早期に内定をもらうことでもありません。自分の強みや特性を活かしてやりがいを持って働いたり、自分が望む働き方ができたりする企業に入社することが就活の成功です。
「OfferBox」ならあなたのプロフィールを見て、興味を持った企業からオファーがもらえるので、強みや特性が活かせ、価値観の合う企業と出会える可能性があります。
自己分析ツール「AnalyzeU+」で自分の気づいていない強みや特性、職種適性もわかるので、ぜひ登録して活用してみてください。



