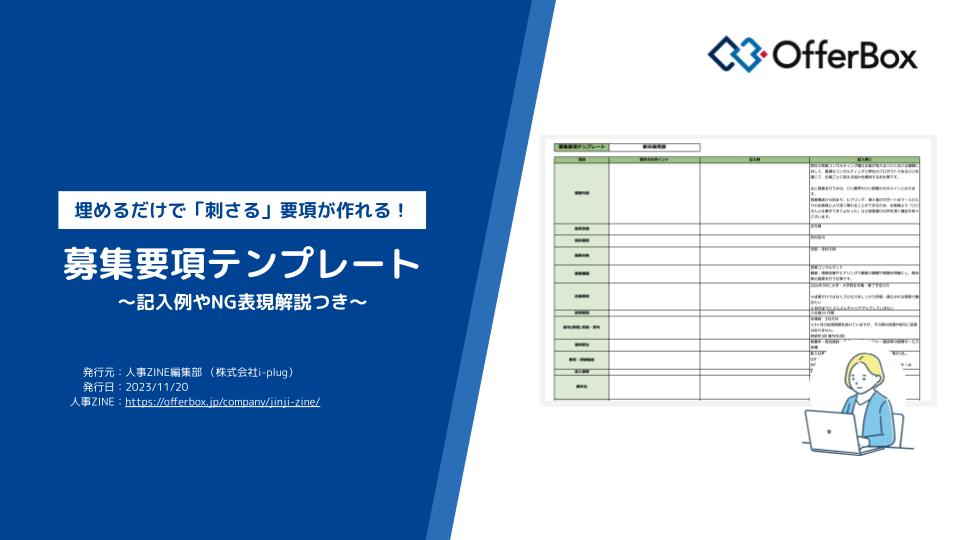採用ターゲットを設計する方法・フレームワークや効果的なアピール方法

「求人広告を出しても、求める人材からの応募が少ない」「無駄な応募が多く、採用の効率が悪い」といった課題を抱えている企業は、採用ターゲット設計の見直しが必要かもしれません。採用ターゲットの設計は採用活動の基本であり、明確なターゲティングによって求める人材に的確な訴求ができるだけでなく、採用フローの最適化などのメリットが期待できます。
今回は、採用ターゲットを設計するメリットや設計に使えるフレークワーク、効果的なアピール方法などを紹介します。
また、人事ZINEでは効果的な採用ターゲットの策定の仕方にお悩みの採用担当者の方のために、資料「ペルソナ設計フレームワーク」をご用意しています。すぐ使える社内ヒアリングシート(Excel)つきで、自社の採用ターゲット設計にお役立ていただけます。

目次
採用における「ターゲティング」とは?

そもそも「ターゲティング」とはマーケティング用語で、どの顧客層に自社製品を売り出すか選定することを指します。
市場規模や自社の強み(弱み)、参入障壁、競合の戦略など、さまざまな要素を考慮して「自社製品・サービスが訴求しやすい顧客層」=「ターゲット」を選定することで販売戦略が成立するのです。
これを採用に当てはめてみましょう。すると、「ターゲット(顧客層)=採用したい人材の特性」「自社製品=自社そのもの・採用ポジション」と捉えることができます。
肝心なのは、「だれに何をどう伝えるか」を明確にしていくことです。
採用におけるターゲティングとは、「長期的に活躍してもらえる人材」の特徴を明確にし、彼らに対してどのような訴求ポイントを以ってアプローチしていくかを見極めることと言えるでしょう。
弊社YouTubeチャンネルでは、「求める人物像の定め方」について解説した動画を公開しています。お時間のある時にご覧いただけると幸いです。
新卒採用でターゲットを明確に設定する5つのメリット

新卒採用でターゲットを明確に設定すると、ペルソナ像を具体的に言語化でき、採用活動がスムーズになるなどの変化が期待できます。ここでは、ターゲット設定によって得られる5つのメリットを紹介します。
自社が求める人材を獲得しやすくなる
採用ターゲットが明確になると、採用活動においてペルソナに合わせた訴求ができ、自社の採用条件にマッチする人材を獲得しやすくなります。
求める人材の獲得で重要なのは、企業がアピールしたい情報ではなく、学生が知りたい情報を的確に提供することです。ターゲット設定が不明瞭だと、ありきたりな情報しか発信できず、ターゲットの興味や関心を引き出せません。また、競合他社の求人に埋もれてしまったり、条件に合わない人材からの応募が増えたりする可能性も考えられます。
ターゲットの属性だけでなく、生活環境やパーソナリティといった詳細なペルソナまで設定すると、求められる情報を具体的に想像できるでしょう。
効果的な採用手法を選定できる
ターゲット像と訴求すべき内容が明確になると、それに合った採用手法の選択も容易になります。
例えば、元々の母数が少ない専門技術を持った人材をターゲットにするのであれば、ダイレクトリクルーティングを利用してターゲット層にアプローチし、「自社で専門性をどのように活かせるか」「どのようなキャリアが用意されているか」といった点を直接訴求するのが効果的です。他にも、ビジョン・価値観の一致を重視するなら、インターンシップを実施して相互理解を深めたうえで採用につなげるという考え方もあります。
採用手法の選択は採用活動においてとても重要な観点ですので、ターゲットに適した媒体を検討しましょう。
母集団の形成・応募数増加に役立つ
応募数を増加させ、十分な母集団を形成する意味でもターゲット設定は重要です。
応募数獲得に苦戦している企業の中には、できるだけたくさんの応募を得ようと、誰にでも当てはまるような応募条件を設定しているケースがあります。しかし、求める人物像や訴求ポイントがあいまいな求人は、学生が「自分にぴったり当てはまっている」と感じられないため、かえって印象に残らず応募につながらない場合が多いのです。
「自社で活躍できるのはどのような人材なのか」「どのような貢献を期待しているのか」がはっきり伝わる求人の方が、入社後に求められている活躍を予想でき、学生にとっても応募がしやすくなります。その結果、全体的な応募数の増加につながり、母集団形成に役立ちます。
採用フローの最適化につながる
ターゲットを絞ると、集客の段階で確度の高い応募に絞り込むことができ、結果として採用フロー全体の最適化につながります。特に、ダイレクトリクルーティングや人材紹介などを活用する場合は、自社の条件にマッチする人材に絞り込んだアプローチが可能です。ターゲット像に合致する学生に絞ってリソースをかけられるため、人的コストの削減が期待できます。
また、経営戦略と紐づけたターゲットを設定すれば、企業の成長を見越した採用活動が可能です。「組織成長を見越して管理経験のある人材を採用したい」など、中長期的な視点で採用計画が策定できます。
社内で採用基準を周知徹底しやすくなる
企業が求めている人材をターゲット像や採用条件として言葉に落とし込むことで、社員間の認識を統一できる点も大きなメリットです。
ターゲット像が明確になっていないと、採用条件や採用基準がはっきり定まらず、採用フロー全体に一貫性がなくなってしまいます。「会社がどのような人材を求めているのか」という共通認識が社員間に浸透していない状態のまま採用を進めてしまうと、選考や合否判定にバラつきが生じて、ミスマッチの原因になりかねません。
採用ターゲットと採用条件が言語化されていれば、採用に関わる全ての社員が共通の人物像を想定して活動できるだけでなく、入社後のミスマッチを防止でき、定着率やエンゲージメントの向上も期待できます。
採用ターゲット・ペルソナを設計する際のフレームワーク・決め方

採用ターゲットやペルソナを設計する際は、フレークワークを活用するのがおすすめです。ターゲットやペルソナ設計に活用できるフレームワークや効率的な設計方法を紹介します。
基本項目をもとに要件を洗い出す
まずは、以下の基本項目をもとに求める人物像の要件を洗い出します。
- 潜在能力(学力・思考力)
- 具体的スキル(専門性、技術知識、保有資格)
- 経験(顧客折衝、企画、研究)
- 属性(性別、年齢、地域)
- 勤務条件(給与、勤務時間、勤務地)
このように、まずは属性面に関するターゲットの情報を明確化します。最初は質を気にせず、ブレインストーミング形式で多くの項目を書き出し、後ほど精査する方法がおすすめです。
パーソナリティ・価値観を整理する
続いて、ターゲットの人柄や価値観に関する項目を整理します。それぞれ以下のフレームを参考に、求める要素を書き出してみましょう。
<パーソナリティのフレーム>
- 開放性:知的好奇心の程度
- 勤勉性:自己統制力やまじめさの程度
- 外向性:社交性や活動性の程度
- 調和性:利他性や協調性の程度
- 神経症傾向:ストレス耐性度
各項目について、「高い・やや高い・普通・やや低い・低い」の5段階で定義するとよいでしょう。
<価値観のフレーム>
- 理念重視/ビジネス重視
- 自己評価/他己評価
- 過程重視/結果重視
- 専門追求型/組織貢献型
- 仕事重視/プライベート重視
- 給与重視/仕事内容重視
- 私仕混同/私仕分離
こちらは二者択一になっており、自社で活躍している社員の傾向などを参考にしながら、どちらがターゲットに近いかを基準に選択します。
コンピテンシー要件を確定させる
コンピテンシーとは、特定の職務において優れた成果を出すために必要な個人の能力や行動特性です。自社で高いパフォーマンスを発揮している社員の行動特性を分析し、要件として言語化した「コンピテンシーモデル」を確立して採用活動や人事評価に役立てる方法を「コンピテンシーフレームワーク」と呼びます。
コンピテンシーモデルを確立すると、自社で活躍しているのは具体的にどのような要素を持った人材なのかを、具体的に言語化できます。実際に成果を挙げている社員をモデルにするため、よりリアリティのある要件を策定できるのがメリットです。
事業方針・戦略をもとに人物像を決める
採用ターゲットは、会社の事業方針や経営戦略と密着したものであるべきです。この理由には、これからの事業展開の方向性によって、「どのような人材が、どのくらいの人数、いつまでに必要なのか」が異なることが挙げられます。
また、採用した人材がすぐに活躍できるとは限らず、人材を教育・育成し、安定した成果を出せるようになるまでにはある程度時間がかかることもあるため、中長期的な事業計画をもとに育成計画を立てることも重要です。
将来的な見通しが立っていると、求職者にとってもどのような活躍が期待されているのか把握しやすく、ミスマッチが起こりにくいというメリットもあります。
既存社員の特徴を抽出する
コンピテンシーと似た方法ですが、社歴の長い社員やチームの中心として活躍している社員の特徴を抽出すると、意外なヒントが見つかることがあります。
社内には、業績に直接関わらなくても、チームの調和を高めるのが得意な社員や、相談役として頼られている社員など、さまざまな特性を持った社員がいるはずです。スキルや経験だけでなく、人柄や性格などにも着目し、社員の特徴をリサーチすると、今まで気がつかなかった重要な要素が発見できるかもしれません。
要件を優先度順に分ける
ここまで洗い出した要件は「MUST(必須)、WANT(歓迎)、NEGATIVE(不要)」の3つに分類して整理します。
MUST(必須)は、文字通り絶対に外せない要件です。あまり必須要件を増やしすぎると適合する人材がいなくなってしまうため、極力3~4個程度に収めましょう。WANT(歓迎)は、必須ではなくても、できれば持っていてほしい要素です。NEGATIVE(不要)は、反対に自社にとって適していない人物の要件です。例えば、専門職採用において「要件としている専攻を修了していない」などがここに含まれます。
要件を優先度順に分類すると、採用ターゲット像がより明確かつ現実に即したものになります。

採用ターゲットに訴求すべきポイントと効果的なアピール方法

採用ターゲットが明確になったら、ターゲットに合った訴求ポイントやアピール方法を検討・選択することが重要です。ここでは、代表的な訴求ポイントやアピール方法を紹介します。
会社の安定性・優位性
特に中途採用や専門職採用においては、業界内での自社の安定性や優位性を訴求すると効果的です。企業が中長期的に業績を伸ばしている点や、業界内で確かな立ち位置を築いている点などをアピールすると、求職者の安心感につながります。
具体的には、自社の事業に関する業界内での評価、売上の推移、業界内でのシェアなど、優位性や成長性を示す客観的なデータをもとに説明すると説得力があります。組織拡大の変遷や財務力の推移などが視覚的に理解できるよう、図や画像を用いて解説するとより理解を深めてもらいやすいでしょう。
企業ビジョン・社風
企業ビジョンや自社の価値観、社風などに関する訴求も重要です。ビジョンへの共感や仕事へのやりがいは、会社・業務へのエンゲージメントや定着率にも影響を与えます。特に、パーソナリティ面が重視される新卒採用やスタートアップ企業の採用などでは、重点的に訴求すべきポイントです。
また、新卒採用において、学生は「一緒に働く仲間にどのような人がいるか」「職場はどのような雰囲気なのか」を重視する傾向があります。そのため、社員の働く姿を紹介するコンテンツや経営陣を身近に感じられるインタビューコンテンツなどを発信すると効果的です。
習得スキル・経験
「入社後にどのようなスキルや経験を積むことができるか」「どのようなキャリアビジョンを描けるか」も、求職者にとって重要な関心事です。専門職採用では特に重視する求職者が多いので、より詳しく記載するとよいでしょう。
その際、習得できるスキルや携わる業務を列挙するだけでなく、実際のキャリアモデルや社員の事例などを交えて紹介すると効果的です。「どのようなスキルを持って入社し、どのような職種・役職を経験したのか」「それによってどのようなキャリアを得られたか、今後はどのようなキャリアに向けて経験を積んでいるのか」などを例示すると、求職者はその会社における将来像を明確にイメージしやすくなります。
評価制度・職場環境
評価制度や職場の就労環境、待遇などについては、包み隠さず情報をオープンにする姿勢が大切です。あまり情報を公開したがらない企業も少なくないからこそ、社内制度に関して詳しい説明があると、求職者から信頼感を得られる可能性があります。
評価制度については、評価基準や等級制度、その制度を設計した理由などについても説明があるとベターです。待遇面については、リモートワークやフレックスタイム制の導入有無、年間休日数や有給消化率などについて記載があると、自社の働きやすさを訴求できます。
社内の快適さや設備の充実度など就業環境について訴求したい場合は、写真や動画を活用してオフィス内の様子を発信すると、視覚的に理解が深まり効果的です。
ダイレクトリクルーティングを用いて「応募が来ない」採用を脱却しよう!

近年新卒採用市場でもシェアを広げている「ダイレクトリクルーティング」という採用手法はご存知ですか?
従来のように、応募や紹介を待つ採用方式ではなく、必要と判断される人材に「企業側から」コンタクトをとる方法です。求人媒体のスカウト機能や、オファー型、逆求人型と呼ばれるとような専門媒体、またSNSを使ったソーシャルリクルーティングや社員からの紹介を用いたリファラル採用もダイレクトリクルーティングのひとつと言われています。
ダイレクトリクルーティングを使えば、狙ったターゲットに自らアプローチをかけることができるので、応募を待つだけの採用と比較し、「ターゲティング」をより強化することが可能となります。
つまり、「ターゲティング」を駆使しダイレクトリクルーティングを効率的に運用することができれば、これまで「待つ」ことしかできなかった候補者に自ら会いにいくことができ、さらに、自社の求める人材とのマッチング効率のアップが実現できるのです。
下記の記事でダイレクトリクルーティングの特徴や向いている・向いていない企業についてご紹介しています。ぜひご覧ください。
まとめ

本記事では採用ターゲットを設定する重要性や具体的な設定方法についてご紹介しました。
採用ターゲットを明確に言語化すると、自社が求める人材を獲得しやすくなり、採用手法・フローの最適化にもつながるといったメリットがあり、また「入社後にどのような活躍を期待されているか」が求職者にはっきり伝わるため、求職者にとっても応募しやすい求人を作成できるようになります。
ターゲット像やペルソナを設定する際は、本記事で紹介したフレームワークや考え方をはじめ、既存の方法をもとに自社ならではの方法を模索するのも一手です。
こちらの資料では、採用したい人材のペルソナ設計に役立つフレームワークや、社内共有に使える資料作りの方法を紹介しています。採用ターゲットの設計方法をご検討中の方は、ぜひご活用ください。