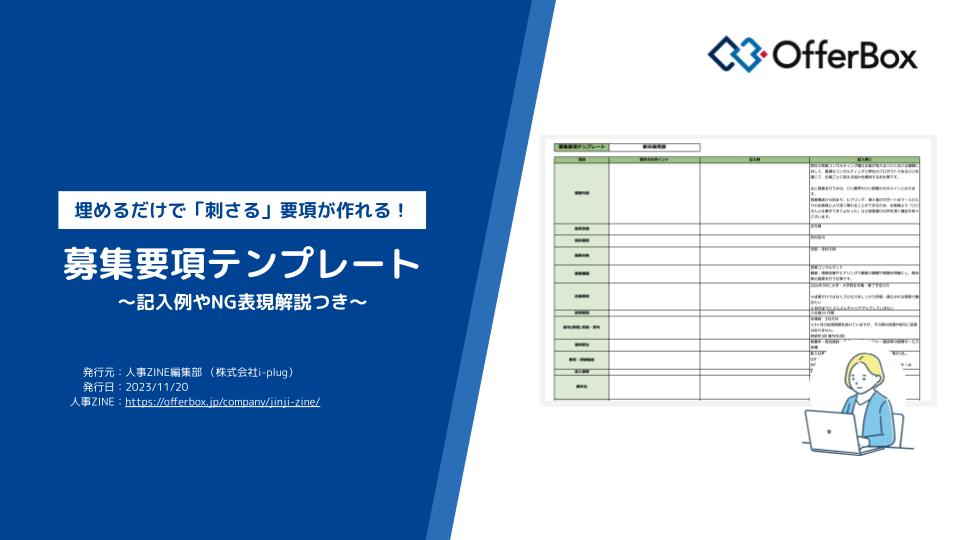リファラル採用とは?メリット・デメリットや運用方法を解説!

人材採用における悩みとしてあげられる採用活動にかかるコスト。ナビサイトのような求人媒体を利用する従来の手法では、一定のランニングコストがかかるうえ、求めている人材に出会えないという問題もあります。
このような課題を解決する手法の1つとしてリファラル採用が注目を浴びています。リファラル採用を導入する際にはメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。
本記事では、導入事例を参考にしながら「どのような企業に向いているのか」「どのような方法で導入するべきか」について解説していきます。ツールやコストの目安も紹介していきますので、参考になれば幸いです。
自社に合う人材を採用するには、ダイレクトリクルーティングという手法もおすすめです。人事ZINEでは、ダイレクトリクルーティングを検討している採用担当者の方向けに「はじめてのダイレクトリクルーティング」という資料を作成しています。わかりやすく基礎から解説していますので、ぜひダウンロードしてください。

目次
リファラル採用とは?採用担当者が知っておきたい基礎知識

リファラル採用とは、自社に勤務する社員から友人・知人を紹介してもらう採用方法で、「リファラルリクルーティング」とも呼ばれます。リファラル(Referral)は「紹介」や「推薦」、リクルーティング(Recruiting)は「求人」や「採用」という意味です。
主にアメリカなど海外で採用されている手法でしたが、近年はベンチャー企業を中心に、日本でもリファラル採用を取り入れる企業が増えています。
縁故採用との違い
縁故採用とリファラル採用は紹介を通じて行われる点で共通しています。
しかし、縁故採用は主に社内の幹部人材や重要な取引先からの後押しにより、採用することを前提に進められるもので、面接や筆記による審査が行われない、または形式的に済ませられることが一般的です。
一方、リファラル採用における紹介者は社内の全員が対象であり、紹介があったからといって採用することが前提ではなく、自社の採用基準をもって審査が行われます。
通常の採用と比較した採用率の違い
一般的に、リファラル採用の採用率は通常の選考と比較して高くなります。
理由は、ミスマッチの可能性が低くなることです。業務内容や社風をよく知っている社員が「自社に合う」と見極めて誘う人材であるため、採用基準に合う可能性が高いのです。応募者側も社員から詳しく話を聞き、働くイメージを持った状態で選考に臨むため、ミスマッチが起こりにくくなります。
また、書類選考や面接など一部の選考ステップが省かれることが多いのも、通常の選考より採用率が高い理由として挙げられるでしょう。
リファラル採用の動向

就職みらい研究所「就職白書2023」によると、全体の18.0%の企業がリファラル採用を実施しており、前年より3.0ポイント伸びています。
従業員規模別に見ると、以下の通りです。
| 5,000人以上 | 17.2% |
|---|---|
| 1,000~4,999人 | 24.8% |
| 300~999人 | 18.7% |
| 300人未満 | 12.3% |
地域別に見ると、以下の通りです。
| 北海道・東北 | 15.0% |
|---|---|
| 関東 | 21.9% |
| 中部・東海 | 12.9% |
| 関西 | 17.4% |
| 中国・四国 | 16.9% |
| 九州 | 17.1% |
このデータによると、基本的にリファラル採用は従業員規模が大きな企業での導入が多く、全国的に利用されているといえるでしょう。
リファラル採用が注目されている背景・理由

今後、労働力人口が減少し、売り手市場が進行する見通しのなか、他社も選択する可能性の高い求人サイトへの掲載や人材紹介サービスの利用、会社説明会などのイベントでは人材の確保が難しくなると考えられています。
これらの採用手法は、基本的に求職中の人材にアプローチするものであり、求職者が少なくなれば他社との競争は激化し、効果が薄れるため結果的に採用コストが増加します。
一方、リファラル採用は自社の社員に知人を紹介してもらうため、現在求職・転職を考えていない層にもアプローチできる可能性があり、さらに同じ手法で他社と競い合う必要がなくなるため採用コストを削減できる可能性が高まります。
このように、アプローチできる人材の層の拡大と、他社との採用競争を避けることによる採用コストの削減という理由で、現在リファラル採用が注目されています。
リファラル採用を取り入れるメリット

既にリファラル採用を積極的に活用している企業も多く、リファラル採用には大きなメリットがあることが発信されています。その一方で、導入の難易度が高い採用手法ともいわれています。
リファラル採用の導入を検討する前に、他の採用手法と比較した場合にどのようなメリットを受けることができるか、どのようなデメリット、リスクが考えられるかを理解しておきましょう。
リファラル採用では、「社員からの紹介」という点を有効に活用すれば多くのメリットを得ることができます。
- 採用コストを大幅に削減できる
- マッチング精度を向上させやすい
- 早期離職のリスクを低減できる
- 採用市場に出てきていない人材と接点を持つチャンスがある
- 社員のエンゲージメントの向上が期待できる
- 自社の改善点を把握できる
1.採用コストを大幅に削減できる
リファラル採用は社員が自ら自社を紹介してくれます。そのため、求人サイトへの掲載料や人材紹介エージェントの紹介料といった採用活動の広報にあたる部分の費用が発生しません。
自社のエンゲージメントが高ければ高いほど、紹介する社員に自社のことをより魅力的に、より詳細に語ってもらうことができ、適切に実施すれば採用コストを大幅にカットできます。
企業によっては、紹介してくれた社員に対するインセンティブ(報酬)を用意しているところもありますが、それを考慮しても1人あたりの採用コストを抑えることができるでしょう。
紹介報酬の特典を大きくしすぎると紹介者による候補者の質が下がってしまう可能性があるため、インセンティブ制を設ける際には適切な運用を心がけましょう。
2.マッチング精度を向上させやすい
入社後のミスマッチを防ぎたいと考えているのは、企業側にとっても求職者側にとっても同じことです。
つまり、企業が自社にマッチする人材の獲得を課題としているのと同様に、求職者側もまた転職先(入社先)に自身のニーズに合った企業かどうかを見極めたいと思っています。
採用ホームページや求人サイトの掲載情報は企業からの一方的な情報発信となるため、求職者側からするとどうしても表面的で局所的な情報に感じてしまう部分もあります。
しかし、知り合いからの紹介であるリファラル採用は、実際に働いている社員かつ知り合いからの情報なので信頼性が高く、企業内部の実情までしっかりと知ったうえで選考に進むことができます。
3.早期離職のリスクを低減できる
マッチング精度の向上に伴って、求職者がエンゲージメントが高まった状態で入社してくれる可能性が高まり、早期離職のリスクも低減します。
リファラルで採用に至った場合、紹介者は自社の魅力を自らの口で語ることで自身のモチベーションアップに繋がり、候補者は「入社するからには知人(紹介者)の面目を潰すようなマネはできない」という責任感が生まれます。
このように紹介者と候補者双方の帰属意識が高まることも離職率の低下に繋がっているといえるでしょう。
4.採用市場に出てきていない人材と接点を持つチャンスがある
多くの場合、求人情報は転職(または就職)の意思を示している求職者向けに公開されていますが、リファラル採用では採用市場に出てきていない潜在層(転職サイトや転職エージェントに登録していない人材、就業中でまだ転職を考えていない人材)も含めてアプローチをかけることができます。
現時点で行動を起こすつもりがなくても、すでにその企業で活躍している知人からのアプローチが興味を示すきっかけとなるかもしれません。
こうした採用市場に出てこない人材との接点を生み出すことができるのは、他の採用手法ではなかなか実現が難しいリファラル採用の強みだといえます。
5.社員のエンゲージメントの向上が期待できる
リファラル採用は紹介者が採用担当者の役割を担うため、自社の魅力や自身のキャリアを見直すきっかけになりやすく、仕事へのモチベーションアップが期待できます。
候補者にとっても、企業の魅力を聞いてから入社することで、理想と現実のかい離を防ぎやすいでしょう。早期に会社への愛着を抱いてもらえる可能性もあります。
以上により、紹介者と候補者双方のエンゲージメント向上が期待できます。
6.自社の改善点を把握できる
自社の改善点を客観的に把握することは難しいものですが、リファラル採用は紹介者と候補者の関係性が近いため、入社した候補者から紹介者に率直な意見が伝わる可能性が高いでしょう。
そのような意見を反映することで自社の課題が浮き彫りになりますし、改善することで社員全体の満足度が高くなるというメリットがあります。
リファラル採用のデメリット

多大な恩恵を与えてくれるリファラル採用ですが、適切に活用できなければ採用率が低下し、企業活動そのものにもマイナスの影響を及ぼすことがあります。
リファラル採用のデメリットや注意点を事前に知っておくことが、導入後のリスクを最小限に抑えることに繋がるので、しっかりと理解しておきましょう。
- 社員と候補者の関係性に配慮が必要
- 社員の認識不足によるミスマッチのリスクがある
- 人材の多様性の妨げになる場合がある
- 採用された社員が辞めにくい
- 公正な評価システムの可視化が必要になる
- 採用から入社まで時間がかかる
1.社員と候補者の関係性に配慮が必要
リファラル採用は、あらゆる採用手法のなかでも特に「人と人との繋がり」を活用する方法であるため、選考中や採用後の人間関係には細心の配慮が必要です。
例えば、可能性として下記のようなことが予想されます。
- 不採用になった場合、社員(紹介者)と候補者(被紹介者)の関係が悪化してしまう
- 入社後の双方の配置関係や評価基準の差異などで一方の職務に対するモチベーションが下がってしまう
- 入社後に一方が転職・離職を選択すると、もう一方も同様の選択をする可能性がある
このように、リファラル採用は「人間関係の影響力」を最大限活用できる採用手法であると同時に、適切に運用できなければ「人間関係の影響力」がマイナス方向に働いてしまうリスクもあることも念頭に置いておきましょう。
2.社員の認識不足によるミスマッチのリスクがある
リファラル採用の強みには、紹介者を通じた「企業の手が届きにくい層へのアプローチ」と「マッチング精度の向上」がありますが、これらはあくまで紹介者の自社や募集ポジションに対する正しい理解と認識が前提となって成立します。
紹介者が日頃から採用活動やチームのマネジメントに携わっている社員でなければ、自社が求める人物像やスキルを正しく理解し、候補者に正しく伝えるのは意外と難しいものです。また同様に、紹介者は候補者の保有スキルや性格、価値観をしっかりと理解し、自社で活躍できる人材かを的確に判断することも求められます。
例えば紹介者が募集ポストとは別のセクションに在籍しており実態を正確に知らないまま誤った情報を伝えてしまうと、面接時や場合によっては入社後に「事前に聞いていた話と違う」としてミスマッチという結果に繋がることがあります。
リファラル採用における募集ポストの情報や候補者の評価基準は社内全体で共有しておくことが重要です。
3.人材の多様性の妨げになる場合がある
「類は友を呼ぶ」と言われるように、多くの人は自分と同じ価値観を持つ人に魅力を感じ、活動や行動を共にする傾向があります。
リファラル採用を日常的に実施しているのであれば、「人材の偏りが生じていないか?」というところに注意が必要です。
価値観の一致は組織力を高める要素にもなりますが、思考がマンネリ化しやすく新しい発想や議論が生まれにくいという側面もあります。
「企業の社風・適性に見合った人材を集めやすい」ことがリファラル採用の特徴ではありますが、一方で組織としてさまざまなタイプの人材を“バランスよく”採用することの重要性も忘れないようにしましょう。
4.採用された社員が辞めにくい
紹介者と候補者の関係性が近いということは、候補者が入社後に「この会社は自分に合わない」と思っても、紹介者に気を遣って言い出しにくい可能性があります。
「会社を辞めたいのに辞めにくい」という状況は候補者のモチベーション低下だけでなく、同部署や社内全体への悪影響も懸念されるでしょう。
さらに紹介で入社した社員のモチベーションが低いことによって紹介者の肩身が狭くなり、紹介者自身が精神的に追い込まれるリスクもあります。
5.公正な評価システムの可視化が必要になる
紹介者と入社した候補者への公正な評価がなければ、リファラル採用は機能しない可能性があります。
そのためにはリファラル採用後に高パフォーマンスを発揮した社員の評価システムだけでなく、紹介者に支払う報酬額や支給方法も可視化する必要があります。部署や社員ごとの課題を把握し、PDCAを回して再現性を持たせることも大切です。
逆にいうと、公正な評価システムの可視化がなければ、社員のモチベーション低下に繋がりかねない点はデメリットです。
6.採用から入社まで時間がかかる
リファラル採用は即入社が難しいかもしれません。紹介者は候補者の選定に時間をかけるのが一般的ですし、候補者が自社にとって魅力的であればあるほど、すでに他の会社で活躍しているケースが多いでしょう。
その場合、候補者が他の会社をすぐに退職できるとは限りません。候補者が業務の引き継ぎを終え、退職手続きを行い、自社に入社してもらうまでに数週間以上かかることも十分に考えられます。
リファラル採用の導入・運用にかかるコスト

リファラル採用には、求人広告掲載料などの大きなコストはかかりません。かかるコストとしては以下の3点が挙げられます。
- 紹介者へのインセンティブ
- 必要経費への補助
- ツール・サービスの利用料金
紹介者へのインセンティブ
1つ目は紹介者へのインセンティブとして支払う報酬です。採用1人あたり1万~30万円ほどが相場ですが、あまり高くしすぎると報酬だけが目当ての紹介が発生しやすくなります。適度な金額に調整しましょう。
企業によっては採用が決定した時点ではなく、応募の段階でインセンティブを設定したり、金銭の代わりにソーシャルギフト、割引券などを支給するケースがあります。
必要経費への補助
2つ目は必要経費の補助です。紹介者と候補者が会食する際の経費を会社が支給することで、紹介者の金銭的な負担を軽減できます。例えば会食代のうち一定額を支給するなどが考えられるでしょう。
注意点として会食だけが目的とならないように、経費申請で一定の証拠を提出させたり、同じ月内の会食回数を制限するなど、事前のルール作りが大切です。
ツール・サービスの利用料金
3つ目はリファラル採用を支援するツール・サービスの利用料です。これについては、後章のツール紹介のセクションで解説します。
リファラル採用が向いている企業とは?

以下の3つの特徴を持つ企業では、リファラル採用がプラスの効果を発揮しやすいといえます。
- 従業員エンゲージメントを高めたい中小企業
- 採用コストを抑えて求めている人材を獲得したい中小企業
- 知名度の低いスタートアップやベンチャー企業
リファラル採用は基本的に中小企業やスタートアップに適しています。
従業員エンゲージメントを高めたい中小企業
リファラル採用の魅力の1つは「従業員エンゲージメント」を高められる点です。紹介する側・される側両者のエンゲージメント向上が期待できるため、これからビジネスを軌道に乗せたいスタートアップ企業や、社員の定着率を高めたい中小企業に適しています。
採用コストを抑えて求めている人材を獲得したい中小企業
リファラル採用は、前述の通り「費用を抑えられる」ことがメリット。中小企業で、大量の採用が不要な場合には、リファラル採用だけでまかなえることもあるでしょう。他の採用方法と併用するとしても、求人サイトや転職エージェントだけに頼るよりも費用を抑えられます。
知名度の低いスタートアップやベンチャー企業
スタートアップやベンチャー企業の成長には、継続した採用が必須です。ただ、企業規模の小さい段階では、採用コストを十分にかけられない場合も少なくありません。
リファラル採用であれば、スタートアップが大手企業と同じ土俵で戦うことなく採用活動ができます。また、リファラル採用はこれまでメインの採用ターゲットとしてこなかったものの自社と親和性が高い可能性があるセグメントや、中途市場であれば転職潜在層(まだ転職市場に出ていない人材)にアプローチできる点もメリットです。
「仲間づくり」の意味合いが強いスタートアップやベンチャー企業の採用では、ぜひ取り入れたい採用手法といえるでしょう。
リファラル採用の進め方・運用方法

冒頭でお話した通り、リファラル採用は「自社の社員に人材を紹介してもらう」採用手法であり、上記で紹介したメリットを最大限に活かし、リスクを最小限に抑えるための施策は企業によってさまざまです。
そのなかで自社がリファラル採用を成功させるためにまず取り組むべきことは、「社内全体を巻き込む体制の構築」です。
社員からの紹介が基軸となる採用手法のため、まずはリファラル採用に協力してもらえる組織作りからスタートしましょう。
具体的にいくつか例を挙げると下記のようなことです。
- 紹介の意欲喚起を行うインセンティブ制度の新設
- リファラル採用の制度概要・プロセスを周知
- 従業員エンゲージメントの向上
紹介の意欲喚起を行うインセンティブ制度の新設
企業によっては「会食代の補助」や「入社半年後に○万円の報酬」といった紹介特典を設けているところがあります。
採用コストがかえって高くなってしまったり、自己利益のために候補者を探す社員が現れたりするようであれば、実施しない方がよいかもしれませんが、紹介の意欲喚起に繋げるという目的であればインセンティブ制度が有効に機能する場合があります。
リファラル採用の制度概要・プロセスを周知
社員に協力してもらうためには、「リファラル採用」がどういうものであるかを社内で認知してもらい、その仕組みや会社全体で取り組むことの重要性を理解してもらわなければなりません。
リファラル採用を実施する目的や現状の採用課題といった採用計画の核となる部分も含めてしっかりと周知すれば、社員は自社が求める人材を正しく理解し、自社にマッチしそうな人材を紹介してくれるようになります。
紹介から選考、採用までのフローだけでなく、「もし自分が紹介した人が落ちてしまったらどうしよう……」などと社員が紹介をためらうことがないように、不採用だった場合の対応(フォロー)も示しておきましょう。
従業員エンゲージメントの向上
普段の業務で人事業務や採用活動をしていない社員に知人を紹介してもらうためには、社員が自発的に紹介したくなるような職場環境を構築する必要があります。
自身の大切な友人に入社してもらうという取り組みのため、そもそも従業員エンゲージメントの低い企業ではリファラル採用を実施するべきではありません。
経営陣を始めとする社員全員が当事者意識を持って、職場環境や福利厚生、人事制度などの改善を自発的に考え、社員が自信を持って「是非友人に紹介したい!」と思えるような組織作りが求められます。
リファラル採用を成功させるためのポイント

ここではリファラル採用の成功に繋がるポイントを紹介します。
獲得したい人材像を明確にする
リファラル採用では獲得したい理想の人材を明確にすることが大切です。
保有スキルや経歴など、自社で働いてほしい人物像がクリアになれば紹介者にスムーズに伝えられますし、その人物像に近い友人・知人がいれば、紹介者も積極的に声をかけるでしょう。
社員にとってのメリットを伝える
リファラル採用に協力することのメリットを社員に周知させましょう。具体的なメリットを伝えて「自分から積極的に動きたい」と思ってもらえれば、自社にマッチした人材を採用できる可能性が高くなります。
インセンティブの存在を伝えるだけでなく、インセンティブの内容は金銭なのか、それとも割引券やソーシャルギフトなのか、支給の決定は採用段階なのか、それとも応募段階なのか、といった条件の明確化がポイントです。
社内全体を巻き込む体制・ルールを構築する
特定の社員にリファラル採用の存在を伝えるだけでは効果は限定的です。社内全体を巻き込むことで、よりリファラル採用は機能します。
そのためにはリファラル採用のルール整備だけでなく、そのルールを全社員が確認できるようにすることがポイントです。
リファラル採用の誘い方を社員に周知する
リファラル採用を実施する際には、制度や誘い方を社員に周知することが必要です。定期的な周知メールや社内報での紹介を継続しながら、時間をかけて浸透を目指しましょう。
ただし、効率的で質の高い採用をするためには、「自社に合った人材を紹介してもらい採用する」「ミスマッチを防ぐ」などリファラル採用の目的やメリットも同時に理解してもらわなくてはなりません。
制度を周知するだけではなく、その目的や採用したい人材、成功例についても丁寧に伝える努力が必要です。
ダイレクトリクルーティングなど他の手法を試す
リファラル採用による人材採用が進まない場合、ダイレクトリクルーティングのような他の手法を導入するという選択肢があります。
ダイレクトリクルーティングは企業が直接スカウトする方法で、転職サイトのスカウトメールや、SNSを利用したソーシャルリクルーティングが一般的です。
リファラル採用は紹介者が積極的に動かなければ「待ちの採用」になりますが、ダイレクトリクルーティングは企業の裁量で採用活動を進められる「攻めの採用」です。
リファラル採用がうまく機能しない場合は、ダイレクトリクルーティングの導入を検討しましょう。

リファラル採用を実施する際の注意点

リファラル採用を実施する際の注意点には以下があります。
- 選考プロセスをすり合わせておく
- 不採用時のフォロー体制を整える
- リファレンスチェックを検討する
- 報酬の支払いが違法にならないように制度設計する
それぞれ詳しく解説していきます。
選考プロセスをすり合わせておく
紹介者と候補者に対して、「リファラル採用も一般選考と同じプロセスを経る」と事前に伝えることで誤解が起きにくくなります。
候補者が「縁故採用のように確実に採用される」と勘違いしている場合、不採用によって反感を買うおそれがあります。紹介者も候補者との関係が悪化するだけでなく、「せっかく紹介したのに不採用にされた」と会社に不信感を抱くかもしれません。
そうならないためにも、リファラル採用は推薦制度であると双方に伝え、納得してもらうことが重要です。
不採用時のフォロー体制を整える
リファラル採用は通常の選考より採用率が高いとはいえ、全ての応募者が採用となるわけではありません。ただ、社員の紹介によって採用活動を行うという特性上、不採用時のフォロー体制を整えておくことは大切です。
選考に落ちることによって紹介した社員と応募者が「気まずい雰囲気」になってしまわないよう、選考過程や不採用時の連絡、該当する社員へのフォローには十分な配慮が必要です。
リファレンスチェックを検討する
リファラル採用だけで候補者の人間性を深く知ることは難しいものです。その場合はリファレンスチェックを検討します。
リファレンスチェックとは、候補者をよく知る第三者から、候補者の人間性やスキルなどを聞き出す調査をいいます。
基本的な流れとして、まずは候補者にリファレンスチェックの概要を説明して同意を得た後、候補者が前職の会社に依頼したうえで、企業が前職の会社に質問を行います。
候補者に無断で前職の会社に問い合わせる行為は、個人情報やモラル的に問題がある可能性があるので注意しましょう。
報酬の支払いが違法にならないように制度設計する
職業安定法の第40条により、労働者の募集を行う社員にインセンティブを支払うことは禁止されています。本来は、人材紹介をするためには許可が必要となるからです。ただし、「募集情報の紹介も業務のうちの1つ」として給与体系に組み込むなど、場合によっては認められる可能性もあります。こういった点も考慮しながら、違法とならないよう制度設計しましょう。
違法とならないためのポイントとなるのは以下の2点です。
- 就業規則や賃金規定で明確にルール化する
- 高額すぎるインセンティブを設定しない
日本企業のインセンティブ相場は1万~30万円程度といわれているため、これより高額になりすぎない金額を設定するとよいでしょう。
リファラル採用で活用できるツール・サービス

リファラル採用で活用できる有料ツール・サービスの具体例としては、以下の3つが挙げられます。
- Refcome(リフカム)
- MyRefer(マイリファー)
- リファ楽
Refcome(リフカム)
株式会社リフカムが提供する「Refcome」はリファラル採用を支援する総合的サービスです。
簡単操作で知人を紹介できるアプリにより紹介を促し、そのスカウト数や応募者数といった数字を見える化するシステムにより率先的に紹介をしてくれた社員や紹介を活発化させるための改善点の把握が可能です。情報発信のツールとしても利用でき、リファラル採用に関するニュースを発信することにより周知と定着化を図れます。
また、導入および定着化について経験豊富なアドバイザーに相談でき、採用全般に関する支援を受けられます。
MyRefer(マイリファー)
株式会社TalentXが提供する「MyRefer」はリファラル採用の制度設計から採用成果の創出までを支援する総合的サービスです。
社員が最短30秒で紹介が可能なアプリと、紹介活動を可視化するシステムに加えて、社内説明会や広報など制度の認知と紹介促進のための各種施策代行によりリファラル採用の導入から定着化を図れます。
また、定例ミーティングで社員の活動状況をした課題と解決策の提案を受けられます。
リファ楽
パーソルワークスデザイン株式会社とオンサイト株式会社が提供する「リファ楽」はLINEを利用したリファラル採用のシステムツールです。
国内での利用率が高いLINEを使用した採用システムで、メールや電話より応募の敷居が低いことを強みにしています。また、LINEだけで求人紹介から応募、入社手続きまでを完結できることに加えて、月額55,000円~という低コストが特徴です。
また、導入後は担当コンサルタントに相談できるなどの支援を受けられます。
リファラル採用を導入している企業事例

多くの企業が実際にリファラル採用を導入しています。3つの具体的な事例から、その効果を確認しましょう。
- freee株式会社
- 株式会社デンソー
- 富士通株式会社
freee株式会社
クラウド型の会計ソフトで知られるfreee株式会社の事例は、スタートアップにとって参考になります。
freee社は事業の立ち上げ初期で知名度が低かった時、「求人への応募が少ない」という悩みを抱えていました。しかし、リファラル採用の導入により、多くの採用を実現しています。
リファラル採用を促進させるための施策として特徴的なのは、紹介者が候補者とする会食代に補助を出すのではなく、オフィスに来てもらい社内で食事をしてもらう制度です。これにより、候補者に会社のことをより深く知ってもらう機会をつくっています。
出典:freeeのリファラル3カ条|社内で協力体制をつくる秘訣とは
株式会社デンソー
世界トップクラスの自動車部品メーカーである株式会社デンソーはリファラル採用を通じた「仲間づくり」の取り組みをスタートしています。
多様な専門性や経験、価値観を重視する同社はエージェントによる採用では潜在層と繋がることができないこと、そして自ら仲間づくりするカルチャーの醸成の必要性、さらに入社後のミスマッチを減らすことを理由にリファラル採用を取り入れています。リファラル採用による採用がキャリア採用の1割を超えることが目標です。
また、リファラル採用を導入するにあたり、採用活動の負担を軽減するためにリファラル採用のツールを導入しています。
出典:大変革期を勝ち抜くデンソーの採用変革──約4.5万人の社員とリファラル採用に取り組む意義と人財戦略
富士通株式会社
富士通株式会社は、先端技術を扱えるエンジニアを確保するためにリファラル採用を導入。累計90名の採用に成功し、1.2億円の採用コストを削減しています。
ICT人材の獲得競争が激化しているなか、エージェントや求人媒体以外の採用チャネルの開拓が課題であり、特に専門性の高い技術を有する人材は転職市場に顕在化していないことから注目したのがリファラル採用です。
リファラル採用の認知度を高めるために、説明の機会を増やすことや入社者のインタビュー記事の掲載などを行っています。
出典:富士通が3万3千人の全社員に展開してリファラル採用に取り組む理由
リファラル採用以外にも検討したい最新の採用手法

リファラル採用はメリットが多い方法ですが、あくまで職場環境への満足感や人間関係があってこそ成り立つものであり、思い通りの人材確保に直結するとは限りません。そこで、リファラル採用以外にも検討する価値のある採用方法を紹介します。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、自社が求める要件に合う人材を探し、企業側から直接アプローチする手法です。先述の通り、ナビサイトや求人広告は人材からの応募を「待つ」というのが基本的な考え方であるのに対して、ダイレクトリクルーティングは「攻めの採用」とも呼ばれています。
メリットとして、「自社が獲得したい人材を絞り込んでアプローチすることでマッチングの精度が上がる」「自社の採用要件に合致しない応募者への対応を減らし採用コストを抑えられる」「現時点では自社を認知・志望していない潜在層の人材に対してもアプローチできる」などの点が挙げられます。
ソーシャルリクルーティング
ソーシャルリクルーティングはSNSを活用した採用手法です。必ずしも直接的な採用活動を主とするのではなく、SNSを通じて自社から情報発信を行い、その延長に採用窓口を設置するなどして採用に繋げることもあります。
メリットとして、「求人媒体やエージェントサービスなどに支払うコストが発生しない」「求人情報を求めていない潜在層にアプローチできる」「発信する情報に自社の社員や職場環境を盛り込むことで、働くイメージを具体的に伝えられる」といったことが挙げられます。
アルムナイ採用
アルムナイ採用とは、自社を退職した人材を再び採用する手法です。完全に関係性が絶たれた人材にアプローチするのではなく、退職者とのゆるやかな関係を維持できる仕組み(アルムナイ制度)を作り、これを前提に採用活動を行います。
メリットとして、「求人媒体やエージェントサービスなどに支払うコストが発生しない」「すでに業務経験があることから採用要件を満たす人材が多い母集団が形成されている」「退職後に得た経験や知識に経験に期待できる」といった点が挙げられます。
まとめ

社員の協力を無くしては実現できないリファラル採用。知人・友人に自分の会社を紹介しようと思えるのは、会社への愛着や職務のやりがいがあってこそです。
リファラル採用によって、社員に自社が求める人材を紹介してもらうには、社員満足度を高め自発的に紹介したいと思えるような職場環境でなければなりません。
そういった意味では、リファラル採用とは「人が人を呼ぶ仕組み」をつくる採用活動と解釈してもよいのではないでしょうか。
採用コスト削減といった短期的な成果だけを見るのではなく、「友人を紹介したくなる企業」「人材が自然と集まる働きがいのある企業」を目指し、長期的なスパンで「人が人を呼ぶ仕組み」を定着させていきましょう。
なお、ダイレクトリクルーティングを検討していきたい方向けにダイレクトリクルーティングの基礎を徹底解説した資料をご用意しています。ぜひダウンロードしていただき、本記事とあわせて検討の材料としてご活用ください。