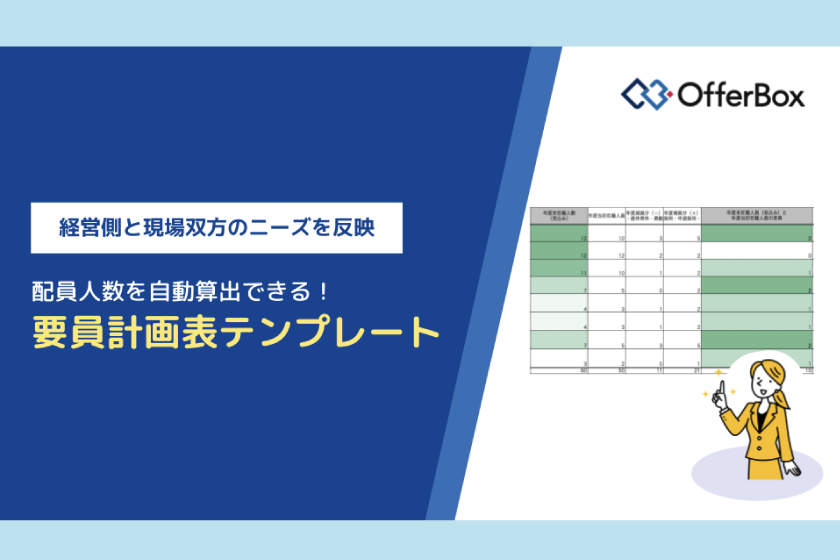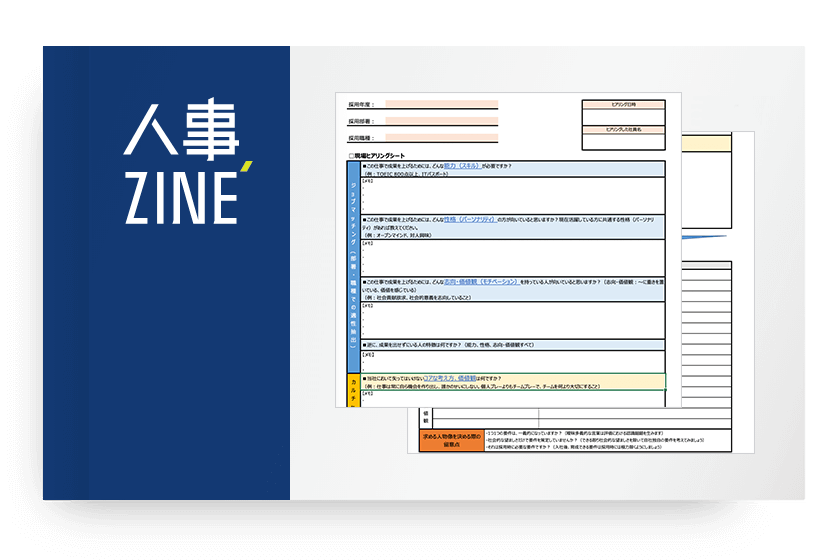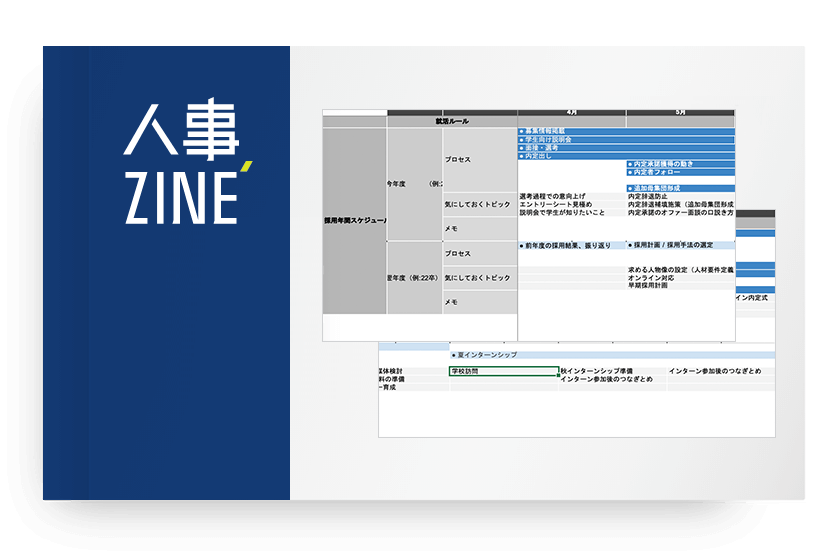採用ミスマッチの原因と対策とは?早期離職を防ぐコツを徹底解説!

新入社員の早期離職は企業にとって重要な問題であり、離職に直結する採用ミスマッチの防止を課題とする企業は多いことでしょう。
採用ミスマッチによる離職が増えると、その人材にかけた費用が無駄になるばかりか、改めて採用するにもさらなる時間と費用がかかってしまいます。さらには、人手不足により既存社員の負担も増えるため、組織全体のパフォーマンス低下につながりかねません。
そこで今回は、採用ミスマッチの現状や発生する原因、採用ミスマッチを防止するための対策などを解説します。
また、人事ZINEでは最新の新卒採用市場を分析した資料をご用意しています。Z世代の特徴を踏まえ、採用戦略の策定にご活用いただける内容となっていますので、是非ダウンロードして自社の新卒採用にお役立てください。

採用ミスマッチとは

採用ミスマッチとは、企業側と求職者側の認識やニーズにズレが生じている状態です。企業側にとっては採用したい人物像と実際に採用した人物がマッチしていないことを、求職者側にとっては理想とする仕事内容や職場環境、社風と実際の仕事がマッチしていないことを指します。
採用ミスマッチには、募集段階での会社説明が不十分であったり、面接官の判断にミスがあったりなど、複数の原因が考えられます。早期離職や組織全体の生産性低下といったデメリットにつながるため、採用ミスマッチの防止は企業にとって避けられない課題といえるでしょう。
採用ミスマッチによる悪影響

採用ミスマッチが発生すると、企業に以下のような悪影響を及ぼす可能性があります。
早期離職の増加
最も代表的なデメリットとしては、早期離職の増加が挙げられます。思い描いていた仕事内容や職場環境、労働条件などと実際の仕事にギャップがあると、社員は仕事に対して意義を見出せず、モチベーションが低下してしまうためです。
また、早期離職が増えるとせっかくかけた採用コストの損失にもつながります。これまで採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、代わりの人材を探すための採用コストも発生するため、企業にとって大きな損失になりえます。
社内のパフォーマンス低下
企業側が求める役割と社員の希望や特性にギャップがあると、社員が本来持っているポテンシャルを活かしきれません。社員は思ったように活躍ができず、モチベーションだけでなく生産性の低下につながります。
また、チーム内にモチベーションが低い社員がいたり、離職が続いたりすると、組織全体のパフォーマンス低下が懸念されます。採用活動や新人教育に関わっている社員は「これまでかけた苦労が水の泡になってしまった」と精神的なダメージを受けるだけでなく、次の人材を採用するまで既存社員の負担が増えるため、企業に対して不満を募らせる可能性もあるのです。
企業イメージの悪化
離職率が高いと、企業に対するイメージダウンにもつながります。昨今はSNSや口コミサイトなどを通して企業の評判が広まりやすく、早期離職の増加によって既存社員が不満やストレスを抱えていると、ネガティブな情報が浸透してしまうかもしれません。
離職率の高さから、求職者に「ブラックなのではないか」というイメージを持たれてしまうと、採用活動にも悪影響があるでしょう。さらには顧客や取引先から「社員に無理を強いているのではないか」といった不信感を抱かれてしまうこともあり、企業活動全体に影響を与える可能性もあるのです。
採用のミスマッチと早期離職の状況

入社後の状況について調べた「入社後状況に関する調査」(2022年2月、キャリアチケット調査)では、新入社員の約4割が入社した企業に対して「入社前の期待を下回る」と回答しています。最も期待を下回った理由としては「希望の配属先、仕事内容ではなかった(14.8%)」「ワークライフバランスを実現できなかった(13.9%)」「スキルを磨きにくい環境だった(11.5%)」が上位でした。
また、厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」(2023年10月付)によると、新規学卒就職者で3年以内の離職率は「高校卒」で37.0%、「短大等卒」で42.6%、「大学卒」で32.3%となっており、いずれも前年と比べて増加しています。
「Biz Hits」による新卒3年以内に転職経験がある人に向けたアンケート調査(2021年6〜7月調査)では、新卒で入社した企業を離職した主な理由として、以下が挙げられていました。
- 仕事内容が合わない
- 人間関係が悪い
- 勤務時間・休日への不満
これらの結果から、昨今の若手人材は自分の希望する職種でスキルを磨いてキャリア形成することを重視している傾向がうかがえます。
終身雇用が変化しつつあり、若い世代が転職に抵抗を感じなくなったのも離職の一因である可能性がありますが、採用段階の工夫によってある程度ミスマッチは防止できるでしょう。
採用のミスマッチが起こる原因

採用ミスマッチが起こる主な原因は、以下の4つです。
- 会社側・求職者側で認識の齟齬がある
- 採用したい人物像の定義があいまい
- 面接官の判断ミスがある
- 内定者のアフターフォローが充実していない
それぞれ、詳しく解説します。
原因1.会社側・求職者側で認識の齟齬がある
前掲の入社後状況の調査や早期離職に関する調査で「ワークライフバランスを実現できなかった」「スキルを磨きにくい環境だった」「仕事内容が合わない」「勤務時間・休日への不満」などが挙げられていた通り、会社側と求職者側で認識の相違があるとミスマッチの原因になります。
会社説明会や面接、採用サイトでの企業紹介で、好印象を与えようと良い点ばかりをアピールしていると、誤解を生んでしまうかもしれません。採用段階で条件や仕事内容について事実と異なる説明をしたり、誤解を与える言い方をしたりしないよう注意が必要です。
実際の採用活動では、現実的な情報開示を指す「RJP」の理論を実践するとよいでしょう。詳しくは後述します。
原因2.採用したい人物像の定義があいまい
企業側が採用ターゲットを定義できておらず、求めている人物像を求職者へ明確に伝えられていないことも一因です。募集ポジションではどのような活躍が求められるのか、将来的にどのような役割を担ってほしいのかについて企業側のイメージが明確化されていなければ、求職者とイメージをすり合わせることも難しいでしょう。
採用活動を開始する前に、人物の要件を具体的に定めることが重要です。人物像の決定においては「コンピテンシー」を基準にする方法が有効です。詳しくは、後述の「コンピテンシー面接を実施する」で解説します。
原因3.面接官の判断ミスがある
面接官が求職者の本質を見極められず、表面的な情報のみで判断してしまっているケースもあります。
例えば、学歴や職歴、保有資格といった履歴書にある情報ばかりに着目してしまい、隠れたポテンシャルや人柄を見逃してしまうのはよくあるパターンです。一般的に評価される経歴を持った人材だからといって、必ずしも自社の戦力になるとは限りませんし、一方で面接で深掘りしてみると書類では把握できなかった魅力を発見できるケースもありえます。
別のケースとして、面接時の印象を重視しすぎているケースもあるでしょう。明るく話し上手で、ハキハキと受け答えできる人物は好印象ですが、募集ポジションによってはコミュニケーション能力よりも特定タスクの実務能力が重視されることもあります。面接官個人の主観によって判断するのではなく、採用基準に沿って面接を進める体制の構築が必要です。
原因4.内定者のアフターフォローが充実していない
内定者に対してアフターフォローの体制が人事でできていないと、内定辞退や早期離職を引き起こします。
新卒であれば「社会になじめるのか」、転職者であれば「新しい職場でやっていけるのか」など不安を抱えるものです。放っておくと不安が大きくなり、会社に対する不満につながります。
採用のミスマッチを防ぐ7つの対策

次に、採用のミスマッチを防ぐ具体的な対策を紹介しましょう。
ターゲット絞り込み型の採用手法を導入する
ミスマッチを防ぐために、最近は採用手法にも新たな試みが増えています。その一つがダイレクトリクルーティングです。
ダイレクトリクルーティングでは、従来の応募者を待つという受け身の手法とは違い、ダイレクトリクルーティング用の求人サイトやSNSなどを活用し、企業が能動的に直接求職者へアプローチしていきます。
マス向けの求人広告などでの募集では、必ずしも企業側が求める人材が応募してくれるとは限りませんでした。その点、ダイレクトリクルーティングであれば、求職者のことを詳しく知ったうえで、本当に欲しいと思える人材をスカウトできます。
アプローチされた側も、自分のプロフィールをよく知ってから連絡をもらっているので「欲しい」と思ってもらえているという安心感があります。また、人材は最初から企業に好ましい印象だけを持っているわけではないものですが、冷静に話を聞いて判断してもらえる点もミスマッチを防ぎやすくなる要因です。
RJP(Realistic Job Preview)を実践する
RJPは「現実的な仕事情報の事前開示」と訳され、採用活動における企業側の正確な情報開示を指します。アメリカの産業心理学者ジョン・ワナウス氏が提唱した採用理論で、情報開示により以下4つの効果が得られるとされています。
- セルフスクリーニング効果:
正確な情報を与えることで、求職者が自ら企業の適合性を判断できる。 - ワクチン効果:
デメリットも隠さず伝え、現実と理想のギャップを最小限に抑える。 - コミットメント効果:
労働条件や福利厚生についてありのままの情報を開示し、企業への信頼感を深める。 - 役割明確化効果:
入社後に求められる役割を明確化し、業務への意欲を高める。
例えば「残業が多いが、完全週休2日制で、有給休暇は入社して15日後から利用できる」など、マイナスに感じられる情報も事前に開示しておけば、入社後のギャップを低減できるだけでなく「ありのままの情報を開示してくれる会社」というプラスのイメージにつながります。
採用ブランディングを行う
採用ブランディングを強化して、自社に関するさまざまな情報を発信することも有効です。
オウンドメディアやSNSを活用して、自社で働く社員やリアルな職場環境、経営ビジョンなどの情報を発信すると、求職者は「どのような環境で、どのような社員と一緒に働くのか」が具体的にイメージできます。また、写真や動画を用いた情報発信も可能で、求職者に企業のリアルな環境を知ってもらえる点もメリットです。
企業理解が深まるだけでなく、自社の認知度向上にもつながるため、自社とマッチする人材からの応募が集まりやすくなります。
インターンシップ・体験型入社を導入する
いくら情報開示をしたところで、実際の社内の雰囲気や社員の働き方を本当に知ることはできません。そこで、インターンシップや体験型入社を導入するとよいでしょう。
学生側は、実際の業務に従事してもらったり、社員と接してもらうことで、会社で働くイメージを持つことができます。
また、会社側としては、どの社員と相性が良いのか、どのような業務と相性が良さそうか、逆に相性の悪い社員や業務、どの程度社内の雰囲気が合ってしているかを確認することができます。
適性検査を実施する
採用のミスマッチを起こさないために、会社側が求める人物像を事前に明らかにしておくことは必須です。しかし、いくら求める人物像を明確にしていたとしても、エントリーシートや面接だけで見極めることは難しいことです。
そこで、客観的なデータとして活躍するのが適性検査です。
適性検査では、その人の性格や行動力がどれくらいか、コミュニケーション能力やストレス耐性、強みや弱みなどをさまざまな観点で分析することができます。適性検査を用いることで、統計的に求める人物像と一致度が高いタイプであるかを見極めたうえで、さらに面接を行うとより効果的でしょう。
求める人物像を明確にし、客観的なデータも参考にしながら選考を進めることで、より適切な人材を採用できるようになるでしょう。
コンピテンシー面接を実施する
客観的な採用基準を定める手法としては「コンピテンシー面接」を活用してみるのも一手です。コンピテンシー面接とは、社内で活躍する社員の行動・思考パターンを指標として面接時の基準値を設け、より求める人物像にマッチした人材を見極める面接手法を指します。
コンピテンシー面接では、社内で活躍する社員(コンピテンシーモデル)の共通点を探すことが最も重要です。その社員がとった行動事例などを詳しくヒアリングし、応募者の行動特性と比較して客観的に判断できるよう指標を設定します。例えば、応募者の過去の経験について、「どのように行動したか」「なぜそうしたのか」などを深掘りし、「モデル社員の思考・行動パターンやと合致する傾向を持っているかどうか」を確認するのです。
このように、コンピテンシーをもとに面接の判断基準を明確にすると、面接官の主観のみによる判断を防ぎ、面接・評価の精度を高められるでしょう。
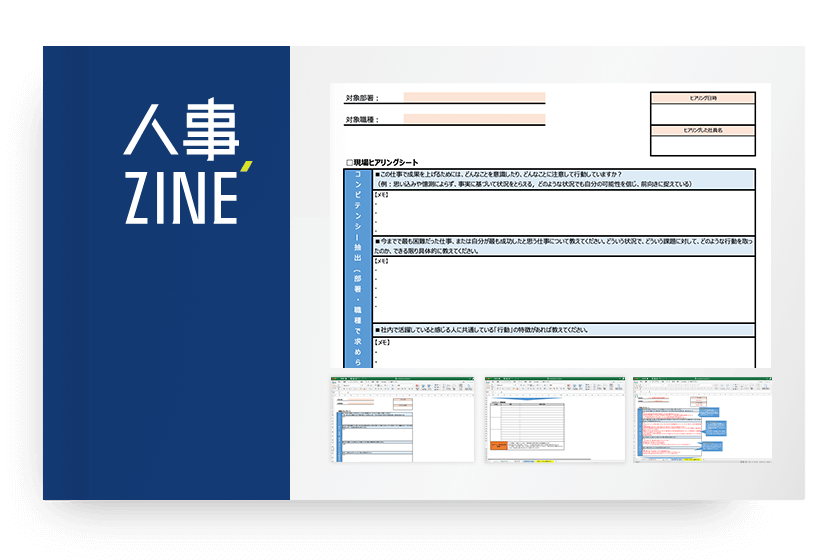
内定者への定期的なアフターフォローをする
内定を得た安心から、就活時には気にならなかった不安が気になることがあります。入社後も継続して不安を持っていると、「退職」「転職」といった言葉が頭に浮かび始めてしまいます。そのため、積極的かつ定期的なアフターフォローが大切です。
内定者は「会社の普段の雰囲気を確認したい」「同期にどのような人がいるか知りたい」「この会社で本当によかったか再確認したい」などと思っています。
そこで、スケジュールなどの連絡以外でも、こまめに連絡を入れることが大切です。また、同期に会える内定者懇談会や、人事が内定者の悩みを聞く面談、先輩社員との座談会、会社に親しめる社内イベントなどを催すことをおすすめします。
ただし、注意点がいくつかあります。
- 学業の妨げにならないようにする
- 学生も予定があるので早めに開催の連絡を入れる
- 面談や懇談会に参加するのは、学生と触れ合うのが得意な社員を選ぶ
- 重要度が高くなければ、自由参加とする
- 参加できなかった人には後から電話やメールでフォロー
以上の点を参考に、アフターフォローの計画を練ってみてください。
まとめ

この記事では採用ミスマッチの原因と対策方法について紹介しました。採用ミスマッチを防ぐためには、以下のポイントが重要です。
- 会社を客観的に見て情報を正しく伝える
- 内定者とのコミュニケーションを密にする
- 求める人物像や時代に合わせて採用方法を変化させる
また、Z世代の新卒採用の重要なポイントや効果的な採用手法を解説した資料もご用意しています。市場動向を踏まえて効果的な手法をより詳しく検討したい方はこちらの資料もご覧ください。