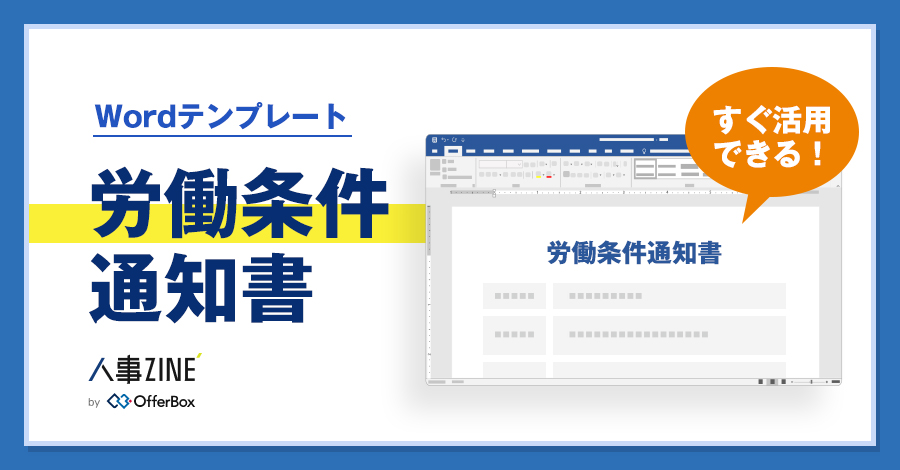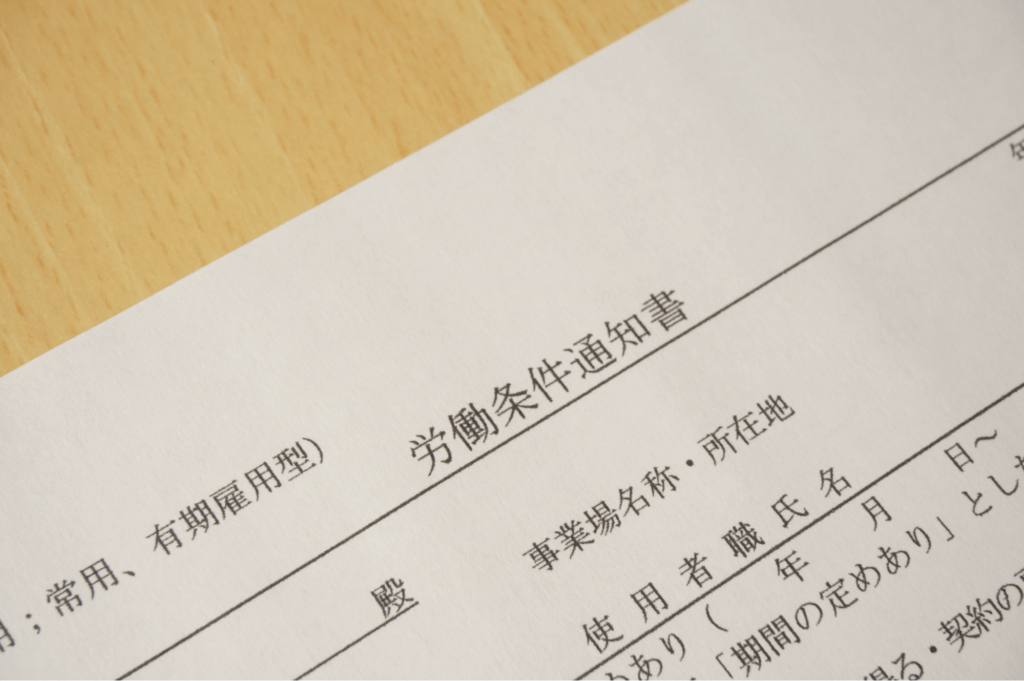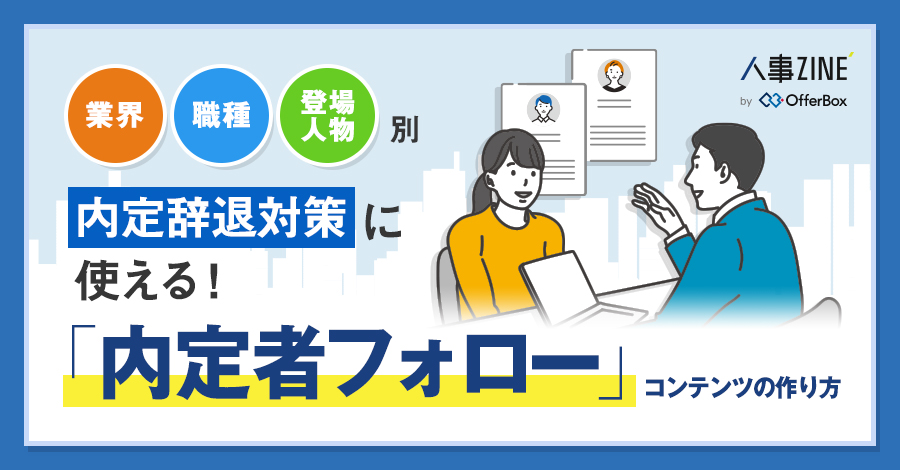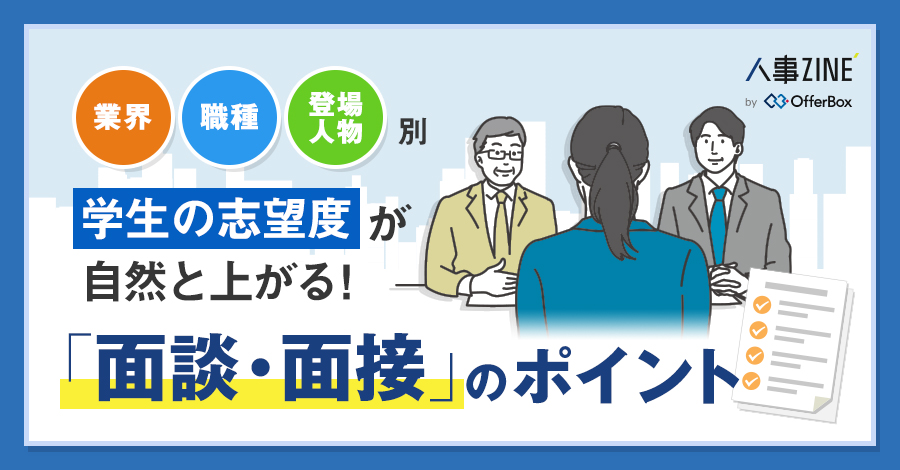特別有給休暇とは?年次有給休暇との違いや主な休暇例と導入時の注意点

特別有給休暇は、従業員の働きやすい環境を整えるうえで重要な制度の1つです。季節ごとの休暇やリフレッシュ休暇などさまざまな種類があり、法的なルール・ガイドラインも多いため、設計する際は丁寧に進める必要があります。
本記事では、特別有給休暇と年次有給休暇との違いや主な種類、そして導入時の注意点について詳しく解説します。さらに、同一労働同一賃金の視点から、特別有給休暇の運用方法も取り上げます。
人事ZINEは「【サンプル】労働条件通知書」をご提供しております。Word形式でダウンロードでき、特別有給休暇といった労働条件を書面に取りまとめる際に便利です。労働条件通知書を作成する際はぜひご活用ください。
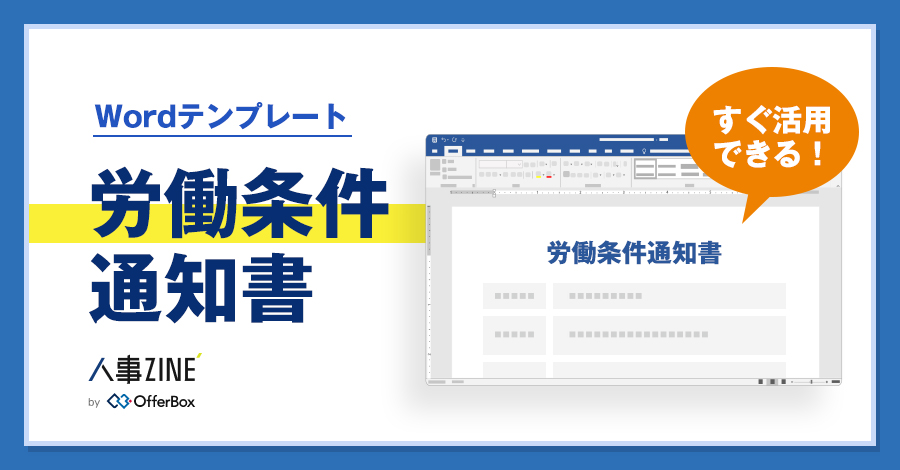
目次
特別有給休暇とは

特別有給休暇とは、労働基準法で定められている年次有給休暇とは別に、企業が独自に定める夏季休暇や慶弔休暇といった休暇制度です。ここでは、年次有給休暇との違いや主な種類といった主なポイントを解説します。
特別有給休暇と年次有給休暇の違い
特別有給休暇は、法定外の制度であることから、付与要件や日数、支給額について企業が独自に設計できます。
一方、年次有給休暇は、労働基準法で定められている法定休暇であり、一定の要件を満たした場合に付与する有給休暇です。
フルタイムの労働者なら「入社日から継続して6ヶ月間勤務し、労働日のうち8割以上出勤する」という要件を満たせば10日間付与します。それ以降は勤続1年ごとに付与日数が1〜2日ずつ加算されていく仕組みです。
年次有給休暇は従業員の権利であり、請求があった場合は正当な理由がない限り企業側は取得を認めなければなりません。
特別有給休暇の主な種類
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 夏季・冬季休暇 | ・お盆や年末年始の期間を一斉に休暇とするケースが多く、土日を含めて5~7日程度
|
| 結婚休暇 | ・婚姻した際に与える休暇
|
| 忌引休暇 | ・親族が亡くなった際に与える休暇
|
| 出産休暇 | ・配偶者の出産時に与える休暇であり、5~7日程度が多い |
| リフレッシュ休暇 | ・一定の勤続年数に達した時に、3~5日程度というケースが多い
|
| バースデー休暇 | ・誕生日に与える休暇であり、1日程度としている企業が多い |
| 病気休暇 | ・従業員が業務外の原因による疾病、生活保障を図ることを治療に専念させるため、傷病休職制度とは別に有給で取得できる制度
|
| 裁判員休暇 | ・裁判員に選出された従業員が裁判員としての責務を果たすために使う休暇
|
特別休暇の主な種類は、「夏季休暇」「冬季休暇」のほか、慶事・弔事の際に取得できる「慶弔休暇」、配偶者が出産した時の「出産休暇」などがあります。
そのほか、「裁判員休暇」「リフレッシュ休暇」「病気休暇」などを導入している企業もあります。
厚生労働省「企業用アンケート調査結果(特別有給休暇)」によると、主な特別有給休暇の導入率は以下の通りで、それ以外は15%未満に留まっています。
- 裁判員休暇:62.4%
- リフレッシュ休暇:48.2%
- 病気休暇:44.5%
給与の取り扱い
夏季・冬季休暇、慶弔休暇、出産休暇などは有給としているケースが多い傾向にあります。さらに前掲の調査によると、その他に以下のような休暇も有給としている割合が高めでした。
- リフレッシュ休暇:94.0%
- 裁判員休暇:81.5%
- 記念日休暇:80.3%
なお、裁判員休暇について、支給額のなかから裁判員として支給される日当相当を差し引くことは、法務省公式サイトにて「問題ないと考えられる」と示されてます。
参考:法務省「従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&A」
雇用形態ごとの取り扱い
企業によっては、特別有給休暇の有無や支給額を雇用形態ごとに分けるケースがあります。
例えば夏季・冬季休暇などは一律に付与する一方、長期雇用を前提としたアニバーサリー休暇などは、無期契約雇用である正社員などに限定しているというケースが挙げられるでしょう。
こういった、雇用形態によって休暇の有無や支給額に差をつけることが必ず問題となるわけではありませんが、後述するように同一労働同一賃金の考え方に照らして非合理な待遇の差が生じないような仕組み作りを行う必要があります。
同一労働同一賃金に沿った各種休暇の取り扱い方針

働き方改革関連法の成立を受け、2020年4月に「同一労働同一賃金」の施行が開始されました。これにより職務内容やその他の事情が同じ従業員に対しては、正規・非正規といった雇用形態を問わず「不合理な待遇差」を設けることは禁止されています。
特別有給休暇をはじめ、各種休暇を付与する際も、同一労働同一賃金のガイドラインに沿った取り扱いをする必要があります。
ここでは特別有給休暇に加え、主な休暇の種類ごとに、不合理な待遇差を生じさせないための注意点を紹介します。
参考:厚生労働省 働き方改革特設サイト「同一労働同一賃金」
特別有給休暇
特別有給休暇の種類や趣旨によっては、正規・非正規社員に差を設けることが禁止される場合があります。
差があっても問題にならない可能性が高いのは、正社員と非正規社員で業務内容や変更範囲が明確に異なっており、正社員に対して業務内容や業務負担に対して報いる目的で特別有給休暇を付与する場合です。例えば正社員のみに転勤の可能性があり、実際に転勤が発生した際にリフレッシュ休暇を付与するのは妥当とみなされる可能性があります。
一方、正社員と非正規社員で業務内容や変更範囲に明確な差がないにもかかわらず、正社員のみに勤続年数に応じて特別有給休暇を付与するようなケースでは、「不合理な待遇差」として同一労働同一賃金に反する恐れがあります。
夏季休暇・年末年始休暇
年間休日に夏季休暇や年末年始休暇が組み込まれている場合は、その夏季・年末年始休暇日はもともと休日として扱うことになっているため、日給者・時給者が一律に無給となることに問題はありません。
ただし、年間休日に組み込まれておらず、「夏季や冬季に◯日、それぞれ有給で休暇を付与する」という制度の場合、正社員のみに与えているようなケースは不合理に当たる可能性があります。
なお、2020年10月の最高裁判決(日本郵便(佐賀)事件)では、正社員とは異なり有期契約社員に付与しないことは不合理と判断しています。
慶弔休暇・健康診断での勤務免除
基本的には、給与上の取り扱いのほか付与日数などの処遇を合わせることが望まれます。ただし、厚生労働省の告示によれば、勤務日数が少ない労働者の場合は、「勤務日の振替での対応を基本とし、振替が困難な場合に慶弔休暇を与える」という対応でも問題にならないとされています。なお、給与上の取扱いが同一となっていない場合は、不合理な待遇差となる可能性が高いと考えられます。
また健康診断に伴う勤務免除・有給保障についても、正社員と非正規社員で同一の利用・付与を行わなければならないとされています。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
病気休暇
厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」では、「病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏まえて同一の付与を行わなければならない。」としています。
ここで特に重要なのは「雇用期間に応じて付与を判断すること」であり、雇用形態によって不合理な待遇差をつけてはならないという点です。
なお正規・非正規社員によって、病気休暇といった労働条件が違うことに対する考え方は、過去に最高裁判所で異なる判決例が出ており、個別の状況によって適切に判断する必要があります。
特殊なケースの有給休暇の取り扱い方法

コロナ禍においては休業を余儀なくされた企業が多くあり、多くの経営者・担当者が従業員の休業手当の扱いで判断に迷うことになりました。今後同じようにやむを得ない事情で休業が発生した場合にどのように有給休暇を扱えばよいのか、過去に多く見られたケースにも触れながら、取り扱い方法の例を紹介します。
年次有給休暇の取り扱い
休業することを企業が命じた場合、基本的には、労働義務がある日に対して労働義務を免除する行為であることから、労働義務がある日に利用されるはずの「年次有給休暇」を従業員が取得することは本来の趣旨に添いません。
一方、会社が休業を命じる前に従業員が休業予定日に年次有給休暇を申請した場合は、年次有給休暇の取得を認める必要があります。
ただし画一的なルールがあるわけではなく、このように年次有給休暇を休業命令より先に申請していない場合であっても、休業日において、年次有給休暇の取得を認めることは企業の任意になります。
特別有給休暇の取り扱い
新入社員で入社歴が浅い場合は年次有給休暇の残日数が少ないことから、企業によっては、救済する目的で特別有給休暇を与える企業もあります。
例えば、
- 勤続1年は5日
- 勤続2年は4日
- 勤続3年は3日
- 勤続4年は2日
- 勤続5年は1日
というように、段階的に特別有給休暇を付与することが考えられます。このような運用を取り決める場合は、労使協議のうえ協定を締結するなどの手続きが必要です。
特別有給休暇を導入するステップ

ここでは特別有給休暇を導入するステップを説明します。
1.制度目的の決定
どのような特別有給休暇を導入すれば企業にとって効果があるか、従業員がどのようなものを求めているかなどを検討します。従業員の定着率向上を目的とするならば、アンケートを実施することも有効です。
2.特別有給休暇の条件や申請手続き方法の決定
特別有給休暇をどのような条件で付与するかなどを決める必要があります。
例えば、「誰を対象とするか」「いつ取得できるか」「何日取得できるか」「給与は有給か無給か」などです。同一労働同一賃金を念頭におき、正規社員と非正規社員との間で不合理な格差が生じないように設計してください。
3.労使協議
制度案を作成後、労使協議を行い可能な限り意見を吸い上げます。
就業規則の改定手続きにおいては、「同意」ではなく「意見」を聴取することで足りますが、労働条件は労使対等な立場で決定することが原則ですので可能な限り聴取した意見は尊重してください。
4.就業規則の改定
取り決めた制度の内容に基づき、就業規則を改定します。就業規則案を作成し、自社で機関決定のうえで、従業員代表の意見書を添付して労働基準監督署へ届出します。
就業規則改定の手続きの詳細については、就業規則とは?制定ルールや不利益変更対応など具体的な実務を解説!を参考にしてください。
5.制度の周知・推進
手続きを一通り終えたら、就業規則の周知とともに制度の内容を周知します。
制度を利用してもらいやすくするため、「特別有給休暇の取得強化月間を推進」「取得者に対するアンケートの実施」「取得状況の結果報告」など周知することも利用促進の手段として有効です。
労働条件通知書とは?
特別有給休暇といった労働条件は、従業員側に書面で明示する義務があり、新たに雇い入れする際や労働条件に変更があった場合は「労働条件通知書」を提示する必要があります。以下の資料「【サンプル】労働条件通知書」を活用いただければ、テンプレートをもとにスムーズに作成できます。労働条件通知書を作成・整理する際はぜひご活用ください。
資料ダウンロード特別有給休暇を導入する際の注意点

特別有給休暇を導入する際には、行政のガイドラインだけでなく、社内の実情や従業員のニーズを考慮した運用が求められます。本セクションでは、特別有給休暇の導入において特に重要なポイントを解説します。
年次有給休暇とは切り分けてカウントする
特別有給休暇は、年次有給休暇とは異なる法定外休暇として付与するものです。このため、特別有給休暇を取得した日数は、年次有給休暇の取得義務(年5日以上)に含めることが原則認められていません。
例外的に、「理由を問わない」「時期を限定しない」といった条件で特別有給休暇を年次有給休暇と同様に設計した場合には、年次有給休暇の日数に加算することが可能な場合があります。しかし、こうした設計がない場合、特別有給休暇の付与と年次有給休暇の取得義務を混同すると、法令違反となるリスクがあります。
特別有給休暇を設ける際は、年次有給休暇と明確に区別し、それぞれの目的や運用ルールを従業員に周知することが重要です。
社内で丁寧に調整する
特別有給休暇を導入する際には、休暇の設計や運用において現場の声を反映しつつ、経営層の理解と協力を得ることが欠かせません。
例えば、業種によっては特別有給休暇の取得が生産数量や店舗運営といった事業運営に影響を与える可能性もあり、休暇付与のタイミングや対象範囲の調整が必要なこともあるでしょう。こういった特別な事情がある場合は、特別有給休暇の取得日を、会社側・従業員側で相談できるルールを盛り込むのも手です。
また、以下のような特別有給休暇の重要な項目は十分に話し合いを重ねたうえで決定しましょう。
- 付与の目的・意図
- 対象の従業員
- 取得条件・付与日数
- 支給金額
まとめ

特別有給休暇は、年次有給休暇とは異なる法定外の休暇制度であり、従業員の働きやすさにもつながる仕組みです。本記事では、特別有給休暇の基本的な仕組みや年次有給休暇との違い、代表的な種類、導入時の注意点について解説しました。また、同一労働同一賃金への対応や導入ステップにも触れました。
特別有給休暇を導入する際は、法令遵守はもちろん、企業の事情や現場のニーズに合わせた制度設計が欠かせません。公平に取得できる環境を整え、従業員満足度の向上につなげましょう。
特別有給休暇といった労働条件をとりまとめた「労働条件通知書」を作成する際は「【サンプル】労働条件通知書」を活用ください。テンプレートをもとにポイントを確認しながらスムーズに作成できます。