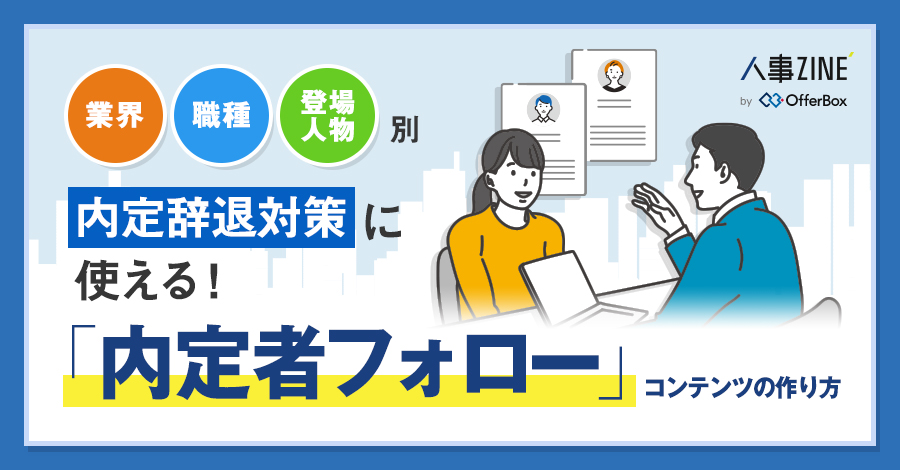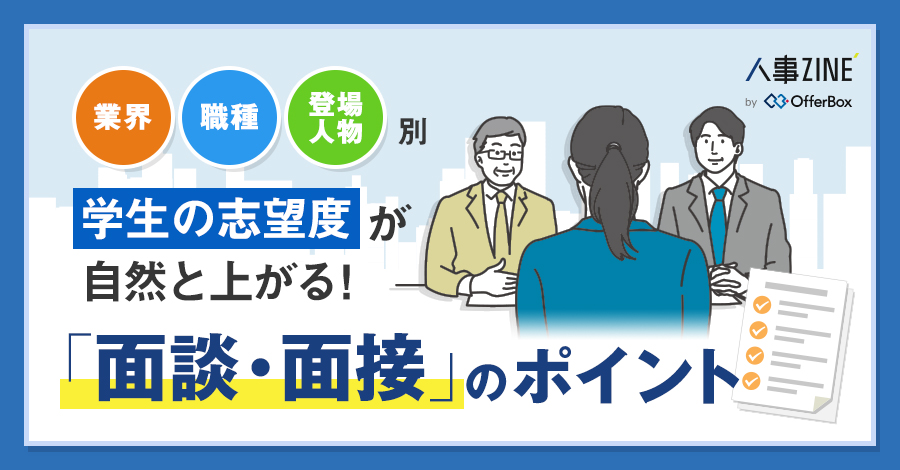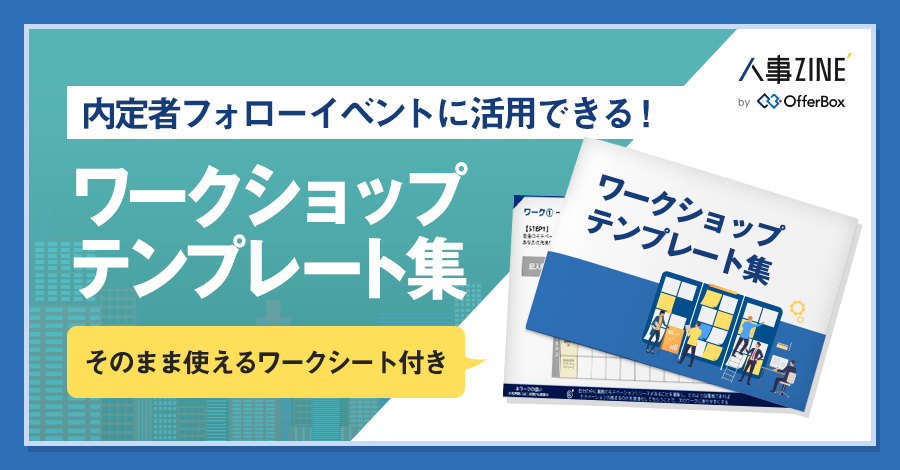即戦力採用の基本と見極め方・チェックポイント・注意点を解説

新規事業の立ち上げや事業拡大において、即戦力となる人材の確保は重要です。終身雇用制度の変化などもあり転職市場は活発化しているという指摘もありますが、自社にとって即戦力となる人材の確保は、容易ではありません。
自社に合った人材を確保するためには、目的に合った採用手法をとることが必要です。また、採用した人材の早期離職を防ぐためには、どのようなフォローをすればよいかも気になるところです。
本記事では、即戦力を採用するメリットとデメリット、見極めるチェックポイント、適した採用方法、人材採用後のフォローなどを詳しく解説していきます。
最新の市場動向に加え、学生が求めているものが分かる独自調査結果、気になる他社の採用状況などをまとめたレポートをご用意しましたので、ぜひご活用ください。

目次
人材採用における即戦力とは?

企業にとっての「即戦力」とは、その企業にとって必要な知識・実務経験などをすでに持ち合わせており、入社後すぐに成果を出すことが期待できる人材です。
従来の採用において、即戦力として対象となるのは社会人経験があり知識や実務経験のある中途採用だと考えられてきました。一方、社会人としての知識や経験の浅い新卒や第二新卒については「ポテンシャル採用」という、今現在の能力ではなく「潜在能力」を評価する手法が用いられてきました。
しかし、即戦力となる人材はその企業が「どのような知識や経験、能力を求めているか」によって違います。そのため、求める内容によっては中途採用である必要がなく、新卒・第二新卒も即戦力候補として注目され始めています。
即戦力採用のメリット

即戦力人材の採用は企業にとって、さまざまなメリットがあります。ここでは、主なメリットについて解説します。
採用後の教育コストを削減できる
即戦力となる人材の多くは、社会人として基本的なルールや礼儀作法が身についています。そのため、新卒研修のような基本的な研修を省くことが可能です。
また、同業他社からの転職であれば、実務に関する研修についても不要な場合があります。同様に、その業務を行うために必須の資格がある場合では、その資格もすでに保有していることが期待できます。
さらに、多くの場合、人材の育成には長い期間が必要とされますが、即戦力採用であればその時間も短縮・節約することが可能です。
これにより、企業は教育や研修にかかる人件費や外部研修費、育成期間などをカットでき、コスト削減につながります。
事業の成長スピードの強化につながる
即戦力となる人材を採用することは、事業の成長スピードの強化につながります。事業の成長とは、新商品の開発や新規事業の開拓、新規店舗のオープンなど事業の拡大を指します。
事業を拡大する際、既存の社員では人数が足りない場合や必要な資格や技術を持っている者がいない場合に事業拡大が停滞または不可能になってしまいます。
この時、研修などの育成期間を短縮することが可能で、必要な知識経験を有した即戦力を投入できれば事業拡大が円滑に進み、結果として事業の成長スピードの強化につながります。
競合他社との成長スピードの差が企業の成功を左右する場合もあり、即戦力の採用は重要な投資といえるでしょう。
社内に新しいノウハウを取り入れられる
社内に新しいノウハウを取り入れられるのも、即戦力となる人材を採用するメリットの1つです。
即戦力の持つノウハウのなかには、他の社員が持っていない知識や技術、経験がある場合があります。それらを社内で共有することで、業務効率の改善や新しいアイデアを期待できます。
例えば、セミナーの講師をしてもらうことでノウハウを共有したり、そのノウハウを既存の業務マニュアルに追加して業務処理を改善することなどが可能です。
社内に無いノウハウを利用する点では専門業者への外注と似ていますが、この場合そのノウハウを社内に蓄積、共有できないという点が大きく異なります。
社内に蓄積できる即戦力のノウハウは、企業全体の利益につながる可能性を持っている点でも貴重です。
即戦力採用のデメリット・注意点

ここでは、即戦力採用のデメリットと、即戦力採用ならではの注意点を解説します。
採用コストが高くなりやすい
即戦力採用は採用コストが高くなりやすい傾向があります。
そもそも即戦力となる人材の人数は少なく、さらに前述の通り即戦力を採用するメリットは多いため、他社にとっても採用したい人材です。その結果、即戦力人材獲得の競争率が高くなり、人材紹介サービスやヘッドハンティングサービスの料金も高額になっています。
「即戦力採用を希望しているがコストの点で難しい」という場合には、外部サービスを利用せずに即戦力となる人材との接点を持てる手法が有効です。社員の紹介による採用手法であるリファラル採用や、退職した元社員と接点を持ち続けるアルムナイ採用などを検討する価値があります。
一括大量採用は難しい
即戦力となる人材の一括大量採用は難しいといえます。
一般的に一括大量採用に向いているナビサイトなどへの求人掲載では、応募者が企業の求める即戦力に合致するとは限りません。
一方、先に挙げた人材紹介サービスやヘッドハンティングを利用する場合では、利用料の高額さに加え、候補者一人当たりの選考に時間がかかるため、一括大量採用には不向きです。
事業所新設などによる人員の増員や大幅な欠員補充などの場合には、即戦力が必要なのか、即戦力でなくても大量の人員が必要なのかを検討する必要があります。即戦力となる人材の採用と、他の採用手法による大量採用を分けることで本当に必要な即戦力の人数確保につながります。
採用した人材が会社になじまない場合がある
即戦力として採用した人材が会社になじまず、早期離職してしまう可能性があります。
会社になじまないという問題は即戦力に限りませんが、即戦力であれば前職で培った仕事のやり方や業界のルールなどが身についていて、さらにそれに自信を持っている可能性があります。それらが自社の独自の文化や業務の進め方と合わない場合、自社になじまない恐れがあります。
また、即戦力になる人材はすでに転職を経験している場合が多く、転職に対する心理的なハードルが低いと考えられるため結果的に早期離職につながるリスクがあります。
新卒採用で即戦力人材を求めるのは有効かという点については、こちらで詳しく解説しています。
即戦力となる人材を見極めるチェックポイント

前述の通り即戦力を採用するメリットは大きいですが、本当に即戦力であるのかも重要です。自社の求める即戦力を明確化したうえで、即戦力となる人材を見極めるためのチェックポイントを3つ紹介します。
経験・保有資格
経験や資格によって自社の求める即戦力であるかを測ることが一般的です。
経験や保有資格は履歴書や職務経歴書により確認することが可能ですが、これだけでは十分とはいえません。
これらの書類は簡略化されているので、「具体的には何をしてきたのか」「実際にはどこまでできるのか」は分かりません。さらに、資格を保有していても実務経験が不十分な場合もあり得ます。面接時に具体的な質問をしたり、技能試験を実施したりすることで、本当に自社の求める即戦力であるかを確認しましょう。
また、応募者本人ではなく、前職の関係者に確認するリファレンスチェックも有効です。応募者の個人情報について訊ねることになるので、実施するにあたっては本人からの了承が必要です。
性格・行動特性
実務をこなす能力があっても、性格や行動特性に問題があれば、求める結果を出してもらうことは困難です。主体性や行動力、コミュニケーション能力は即戦力となるかを見極めるチェックポイントになります。
ただし、これらの要素の評価は、面接官の印象に左右されることが多く、正確な見極めが難しいとされています。そのため、どのような性格や特性であれば自社の求める即戦力になるのか明確な採用基準を設けて客観的な評価をすることが重要です。
性格や行動特性を見極めるための方法として「STAR面接」という手法があります。面接時に「状況→課題→行動→結果」というステップに沿って質問することで、応募者の特性を見極める手法です。
「STAR面接」についてはこちらの記事にて詳しく解説しています。
自社とのマッチ度
知識や経験、能力を有する人材でも自社の社風と合わず、期待していた成果を出せない場合があります。その場合、前述したように早期離職してしまう可能性もあるため、社風とマッチするかという点は重要なチェックポイントです。
面談時は、自社の企業理念やミッションを共有できるかを見極めます。また。社内風土や企業文化などについても説明し、応募者がそれらに肯定的であるか、受け入れがたいものであるかの確認も重要です。応募者の対応によっては、企業側がどこまで譲歩できるのかを検討する必要性もあるでしょう。
自社とのマッチ度というのは、抽象的であり見極めることが難しいものですが、これまでの退職理由の分析や職場環境におけるアンケートによって、どのような点が問題となるかを整理しておくことで精度の高い質問や説明につながります。
新卒採用で即戦力を求める主なケース

即戦力というと、中途採用者を想定することが一般的ですが、新卒採用においても即戦力としての早期活躍を求める場合があります。ここでは、主なケースとして3つ紹介します。
ケース1:専門性の高い職種の採用
IT系やデータサイエンス分野系など、専門性の高い職種では新卒採用に対しても即戦力を求めることがあります。
専門性の高い資格を保有している人材の場合、その資格を取得するまでに専門的な知識や経験を身につけている場合が多く、企業側が即戦力として求める能力に近い能力を持っていることが理由です。例えば、プログラマーやシステムエンジニアなどは学習内容がそのまま実務に反映される職種といえます。
そのため、新卒採用であっても、すでに身についている知識や経験を活かして早期に実務をこなすことが求められています。
ケース2:ベンチャー・スタートアップ企業の採用
企業自体が小規模であり成長過程であるベンチャー・スタートアップ企業においては、新卒採用においても即戦力としての活躍を求めることがあります。
少子高齢化などにより人材不足である企業が多いなか、設立間もないベンチャー・スタートアップ企業は特に人材が不足しがちです。また、既存の社風に染まっていない人材を求めるケースも多く、新卒採用に意欲的です。
また、これらの企業は事業拡大を前提としているので、新入社員に対しても実践を積みながら早期に次の中核メンバーとして育って欲しいという事情があるため、即戦力としての活躍を求められています。
ケース3:外資系企業の採用
外資系企業も、新卒採用において即戦力を求めるケースがあります。
多くの外資系企業では「投資したからには、いかに早く利益を回収できるか」という点を重視しています。そのため、新卒・中途採用に関わらず即戦力が求められます。
つまり、即戦力を求めて新卒採用を行うというよりは、専門知識・取得難易度の高い資格・特殊な経験などを持つことを条件に新卒生であっても採用し、採用したからには成果を求めるという流れです。
入社後は業務に直結した能力の習得のほか、多くの企業ではコミュニケーション能力や語学力、マネージメント能力などが共通して求められます。

即戦力採用の入社後フォローの方法

コストや時間をかけて採用した即戦力である人材に、定着してもらい、その能力を存分に発揮してもらうためには、適切なタイミングでフォローしていく必要があります。ここでは、フォローの方法について説明します。
定期的に面談・コミュニケーションの場を設ける
入社後1〜3ヶ月の間は、不安や悩みを抱えやすい時期とされているため、定期的な面談や日常的なコミュニケーションを積極的に行い、困りごとやトラブルがあった時に相談しやすい環境を作ることが重要です。
特に即戦力採用における人材の多くは中途採用であることが多く、新卒採用のように話しやすい同期生がいるのに比べて孤立化しやすい傾向があるため注意が必要です。
即戦力である人材の抱える仕事への不安や、入社前後のイメージのギャップからくるストレスなどをいち早く把握し、場合によっては積極的に介入してケアすることが早期離職の防止につながります。
研修を実施する
即戦力は新人教育や実務研修などを省けると前述しましたが、自社になじんでもらうための研修は必要です。
特に、入社後の早い段階で「企業理念・社内ルール・社内用語」など自社独自の要素についての研修は重要です。自分だけが分からないルールや用語があると孤立を深めてしまうので注意が必要です。一方、前職との類似点や相違点が分かることは安心につながるでしょう。
研修の題材を問わず、研修という他の社員と交流できる場を設けると、同期生のいない中途採用者にも会話や相談しやすい相手ができることも期待できます。気軽に相談できる相手がいることは仕事に対するストレスを軽減させ、さらにはエンゲージメントの向上にもつながるためフォローの手段としても価値があります。
即戦力採用に適している採用手法

現在、人材採用に活用できる採用手法はさまざまありますが、即戦力人材の採用に適している手法とそうでない手法があります。ここでは、即戦力採用に適している採用手法を紹介します。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、求職者が登録しているデータベースから自社が求める人材に直接スカウトメールを送り、採用につなげる手法です。新卒採用、中途採用ともに対応している手法です。
求人広告を掲載して求職者の応募を待つという手法は、「自社の求める人材に直接アプローチできない」「志望度の高くない応募者の対応に自社のリソースを割かなければならない」などのデメリットから即戦力採用には不向きです。
ダイレクトリクルーティングであれば知名度にかかわらず自社をアピールでき、自社の求める人材へ直接アプローチできるため、即戦力採用に適した採用手法といえます。
また、あらかじめ即戦力候補者に絞って選考できるため、結果的に採用にかかるコストを軽減できるという点からもダイレクトリクルーティングは即戦力採用に有効です。
ダイレクトリクルーティングについてはこちらの記事にて詳しく解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。
人材紹介エージェント
人材紹介エージェントを利用することも即戦力採用には効果的です。これも新卒採用、中途採用ともに対応している手法です。
人材紹介エージェントが自社の採用担当者に代わって、即戦力候補となる人材を発掘し、アプローチしてくれるので自社で人材を探す工程を削減できます。また、人材紹介エージェントという社外の視点から、客観的に人材を見極めてから選考できるという点も即戦力採用に適しています。
しかし、ダイレクトリクルーティングなど他の手法と比較して、一人当たりの採用コストが高額になる可能性があります。また、サービス会社ごとに紹介できる候補者や付随するサービスが異なるため、利用する際には比較検討が必要です。
インターン採用
インターン採用は、学生が希望する企業で職場を体験する「インターンシップ」という制度を利用した採用手法です。新卒採用のみで利用できる手法です。
一定の期間、学生に対応し続けるため、相当の時間や指導者の人件費などがかかりますが、インターンシップを通じて多くの学生と触れ合うことができ、求める人材の発掘につながります。
自社にとって即戦力となる人材を早期に発掘できるという点と、実務を体験してもらいながら人材を見極め入社後のミスマッチを減らせる点が、即戦力採用に適しています。また、直近では形骸化していたとはいえ、従前の就活ルールが見直され、インターンシップを早期の採用活動に利用することが政府より公認されています。
オウンドメディアリクルーティング
オウンドメディアリクルーティングは、直接的な採用手法ではなく、自社のサイトやSNSを通じて情報を発信していくなかで採用につなげる手法です。新卒採用、中途採用ともに対応している手法です。
特徴は求職中ではない潜在層、通常の採用活動では接点を持てない層へのアプローチや採用コストの削減が可能なことです。発信するコンテンツにより即戦力となる人材に自社をアピールできれば、自社サイトやSNS経由での応募にも誘導できる可能性があります。
ポリコレに関する配慮や炎上リスクの回避など手間がかかるというデメリットもありますが、SNSが主要なコミュニケーションツールとして活用されている現在では幅広い層にアピールできる採用手法として注目されています。
まとめ

本記事では、即戦力採用について解説してきました。
即戦力となる人材は企業にさまざまなメリットをもたらします。ただし、その活かし方も企業の工夫次第です。一方で、早期離職などのリスクがあることに注意し、適切なフォローを行うことが重要です。
自社にとっての即戦力となる人材とはどのような人材かを明確にし、適した採用手法で採用できれば、自社の成長スピードの加速や利益の増加につながるでしょう。
最新の市場動向に加え、学生が求めているものが分かる独自調査結果、気になる他社の採用状況などをまとめたレポートをご用意しましたので、ぜひご活用ください。