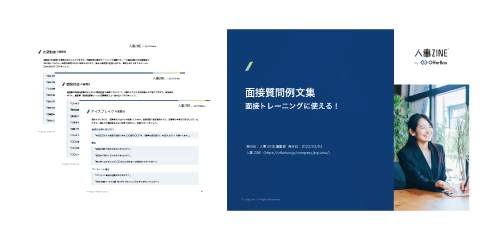【新卒採用】面接官の心得・役割とは?注意したいNG質問・セリフも

現場社員から管理職、役員まで、さまざまな層の方が面接を行う新卒採用面接では、全ての方が面接経験豊富とは限りません。面接官経験がない方の中には、どのように面接に臨むべきか、不安に感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
売り手市場と呼ばれる昨今、「面接」の場は「会社が学生を評価する場所」ではなく、「学生と学生がお互いに理解を深める場所」となりつつあります。そのため、面接官に求められる役割やスキルも従来とは変わってきています。
本記事では、
- 初めて面接官になるので、何を意識すべきか見当がつかない……
- どのような基準で「評価」すべきかわからない……
- 面接でなかなか学生の「素」を引き出せない……
といったお悩みをお持ちの方向けに、面接官として知っておきたい心得を解説します。注意点やタブー質問もご紹介しています。ベテラン面接官の方にもあらためてチェックしていただきたい内容です。
この記事を読んで面接官の心得を理解し、良い面接の場を作っていきましょう。
また、面接で効果的に候補者の人柄を引き出す質問例をまとめた資料もご用意しました。是非ダウンロードして、面接の場面でご活用ください。

目次
新卒採用の面接官となる人が知っておくべきこと

新卒採用は、中途採用と違って社会人経験の少ない学生のポテンシャル(潜在能力)でもって採用することが一般的です。このような選考において、面接官が知っておくべきことを1つずつご紹介していきます。
一般的な新卒採用面接の流れ
面接には個人面接と集団面接がありますが、集団面接は個人面接より多くの人数を効率的に選考していく方法になるので、ここでは基本として個人面接についてご紹介します。
個人面接は1人あたり20〜30分程度であることが多いと思われますが、一般的な流れとしては次のようになっています。集団面接ではこの学生1人当たりの持ち時間を短くして1回(30分程度)の面接内で数人と会話をする形になります。
<面接の流れ(例)>
| 時間 | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 0.5分 | 入室 |
学生がドアをノックし「失礼します」と言ってきた場合は、面接官が「どうぞ」と答えましょう。 |
| 0.5分 | 面接官の自己紹介 |
面接官自身の部署・役職と名前を伝えます。 |
| 0.5分 | 学生の自己紹介 |
自己紹介と言われて自己PRや志望動機まで喋る学生もいるため、必要に応じて「○分程度でお願いします」や「大学名とお名前だけおっしゃってください」などと明確に指示するのが◎。 |
| 2分 | 自己PRや志望動機を聞く |
自己PRと志望動機はまとめて聞いても個別に聞いてもOKですが、あえてこうした定型的な質問をせずに会話の中で聞き出しながら進めることもできます。 |
| 10〜20分 | 深掘り質問をする |
気になった部分を深掘りしていきます。 |
| 5分 | 学生からの質問を受ける |
学生が不安に思っていることを解消し、入社への意欲を高めてもらう重要な場です。 |
| 1分 | 今後の予定などを伝える |
合否はいつまでにどうやって(電話orメール等)連絡するか、合格した場合の次の選考の予定はいつか、学生にもメモをとってもらいながら伝えます。 |
| 0.5分 | 退室 |
学生を見送ります。基本的に面接官はその場で立ち上がる程度で、会議室を出たあとは別の社員が誘導することが多いでしょう。 |
| 3分 | 面接評価シートを記入 |
面接の内容を忘れないうちに、評価や議事録メモなどをシートに記入します。 |
資料【面接質問例文マニュアル】をダウンロードする
人事ZINEでは、面接質問例文マニュアルを解説した資料を準備しております。本記事と併せて、こちらの資料も合わせて実務でご活用ください。
自社が新卒採用をする目的を理解しておく
最初に「自社がなぜ新卒採用を行っているのか?」を理解しておく必要があります。新卒採用はあくまで手段であり、その目的が分からないと、正しい判断ができない可能性があるからです。
人事担当者や役員に直接聞くのも良いと思いますが、もしかすると「毎年やってるから……」というような消極的な回答が返ってきてしまうこともあるかもしれません。
万が一そのような場合には、自分なりにでも「この新卒採用を良いものにするにはどうしたらいいか?」と考え、目標をもって取り組むのが良いでしょう。
新卒採用をする目的については、下記の記事でもわかりやすくお伝えしています。
自社の求める人材像を深く、「具体的に」理解しておく
「求める人材像」の要件定義が重要です。面接官として学生を評価し、採用するか否かに関わる判断をすることになるので、「どういう人材を合格とするべきか」を理解しておかなければなりません。
ただし、求める人材像について、深く「具体的に」理解しておくということが重要かつ難しい部分でもあります。「主体的でコミュニケーション能力の高い…」といった昔ながらの人材要件を掲げている企業はまだ非常に多くあります。
実際にその要件に適うと思って採用しても、「自社では活躍してくれなかった」というケースのほうが多いのではないでしょうか?
活躍する人材の要件というのは、「社会通念上、あったほうが良さそうな能力」、例えば主体性や、積極性、他人への共感、コミュニケーション力…などといった能力とは、必ずしも一致しません。
適性検査などで、「自社で活躍する人材」に共通する資質を可視化する取り組みは少しずつ進んでいますが、実は「他者を攻撃する」のような資質が強い人材が活躍する企業もあれば、同規模・同業種の企業で正反対の資質が必要とされるケースもあります。
可能であるなら、そのような適性検査を受けてもらうなどして、どんな人材が活躍しそうかを「具体的に」把握しておくことをお勧めしますが、会社としてそれが難しい場合でも、自分なりに「どんな人材が入社すれば組織が活性化されそうか?」や、「既存社員の○○さんが活躍しているのは、どんな資質があるからか?」といった深い考察をしておくと良いでしょう。
「面接」をすることの目的を知っておく
書類だけでは測れない資質を見ることができるが、十分な設計は難しい
面接は、きちんと設計されたものであれば、ワークサンプル(実際に仕事またはそれに似た作業をさせた場合の成果)に次いで、実際の入社後の活躍を予測できる選考方法であるとされています。
適性検査(テスト)やエントリーシート、学歴などからだけでは分からない、会ったときの印象や表情を見ることができるほか、質問の深掘りをしたり、ケース問題などを課してその場で適性を見るようなことも可能だからです。
ただ、日本の面接は文化の面からアメリカ等と比較してもまだ設計が甘く、漠然とコミュニケーション力や印象、学歴等によるハロー効果などで合否を出してしまっている部分も大きいとされています。
事実、日本企業における「面接時の評価」と「入社後の活躍」には相関性がないことが指摘されており、「実際に自社で活躍する人材」を見抜ける面接が設計できていないとも言われています。
このことから、面接ではなるべく漠然とした採点基準を排除し、「どの企業の誰が見ても優秀っぽい人材」ではなく、あくまでも「自社で活躍する人材」を見極めるために実施するよう、十分に留意する必要があります。
その部分さえきちんと意識できていれば、書類だけでは知ることのできない部分まで学生を深く知ることができます。
面接は一方的な評価の場ではなく、相互理解と魅力づけの場でもある
また、面接は企業(面接官)が学生を一方的に評価するだけではなく、学生が企業の社員と直接会うことでその社風や価値観などを知る場でもあります。
つまり、面接官となる人は、自分が自社を代表する社員として学生に見られること、その振る舞い次第で学生の志望度を上げも下げもするということなどに注意する必要があります。
ぜひ来てほしいと思った学生にはもちろんのこと、自社を志望して選考を受けてくれる全ての学生に対して、感謝をもって丁寧に向き合いましょう。
どんな質問をして、回答をどう評価するのか?
面接官は以下の2点を整理した上で面接に取り組む必要があります。
- 学生に対してどのような質問を投げかけるか
- その回答をどのように評価するか
質問内容を決めていないと、行き当たりばったりな面接になってしまいます。重要なことを聞きそびれたり、マニュアル通りの質問ばかりになって学生も事前に用意したマニュアル通りの回答しかしてくれない可能性も。
また、回答をどう評価するかという評価軸・評価基準がなければ、質問したはいいものの結局その学生を採用すべきなのかどうかが判断できません。
「『好きな映画は?』と聞いて自分と同じだったので意気投合したものの、その学生が自社に必要な人材なのかどうかはわからなかった。」となってしまっては、面接した意味がないのです。
効果的な質問とその評価ポイントについては「新卒採用の面接で学生に聞くべき、”究極”の5つの質問とよくある質問集を紹介」でも紹介しておりますので、合わせてチェックしてみてください。
面接官の役割は「見極め役」と「会社の顔」

それでは、面接において面接官はどのような役割を担うべきなのでしょうか。大きく分けて、以下の2つの役割が考えられます。
自社に合った人材を見抜く「見極め役」
面接を行う最大の目的は、人柄や性格、仕事に対する価値観といった定性的な情報を直接の対話によって確認することです。
履歴書や職務経歴書といった採用書類は、提出前にプロから添削を受けたり、何度もブラッシュアップを重ねてあるため、実際の人物像とかい離していることも少なくありません。
そのため、面接官は学生と1対1で対話を重ね、「書類の内容に嘘や誇張がないか?話していることが本心なのか?」を確かめる「見極め役」になることが求められます。
応募者の入社意欲を刺激する「会社の顔」
面接官は、学生が最初に深く接する会社の人物です。学生からすると、面接官の印象がそのまま「会社の印象」として刻み込まれます。そのため、面接官は「会社の顔」である自覚を持って学生と接しなければなりません。自分のふるまいが学生の入社意欲に直結することを心に刻み、丁寧な対話や説明を心がけましょう。
結果的に入社に繋がらなかったとしても、学生の印象を向上させることは、学生間やSNS上での口コミに好影響を与えることがあります。
初心者からベテランまで共通、面接官の「心得」マニュアル

ここからは、実際に面接に臨むにあたって必要な「心得」について、いわばソフト面のマニュアルをお伝えしていきます。
面接は画一的・機械的にこなせるものではなく、面接官の個性も「活かす」ことが前提にある選考方法です。
ハード面はあくまでも必須の「前提」ですが、ソフト面に関しては基本をおさえつつも「自分なりの答え」や「自分なりの評価軸」を考えておくことになります。
【心得1】面接の基本は「深掘り質問」と「表情の観察」
まず、面接選考をする目的は、書類選考などでもわかる情報からもう一歩踏み込んだ情報を得るためです。
面接のメリットとしては、1つ目には、過去の体験などのエピソードを聞くだけでなく、「どうしてそのように行動したのですか?」「やり直すとしたらどう改善しますか?」と“深掘り質問”をして、学生への理解を深める、という利点があります。
加えて2つ目に、対面でなければわからない部分、つまり表情や姿勢、立ち振る舞いなども見ることができます。
とくに、話す際の「表情」は非常に重要で、話している内容が嘘でないか、また仕事をする上でも相手と不都合なくコミュニケーションが取れるかなどが測れます。
最近ではAIによる面接アプリなども登場していますが、科学に基づいたこのAI面接も、
- 過去の行動に関する深掘り質問
- 表情の観察
- どの候補者にも均一な質問をする
これらのことを重視した設計になっています。面接で見るべき点は、この3点が重要だということです。
深掘りは基本の「5W1H」で対応できる
深掘り質問が思いつかない…という方は、かの有名な「5W1H」、この中のどれかを聞いてみるだけで、どんどん深掘り質問ができます。
- Who(だれが)
- When(いつ)
- Where(どこで)
- What(なにを)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
※How much(いくらの金額で)を足して「5W2H」とされることもあります。
<例>
- 学生 :サークル活動では会計係として、全員からの会費の徴収を達成しました。
- 面接官 :どのようにして全員から徴収できたのですか?【How(どのように)】
- 学生 :未納のメンバー全員にLINEをして、なぜ払わないのかを聞き、サークルに所属するなら払って欲しいと根気強く伝え続けました。
- 面接官 :なぜ、その方法を選択したのですか?金額を見直すなどの方法もありそうですが。【Why(なぜ)】
- 学生 :金額は運営にどうしても必要なので減らせなかったのと、何よりサークル内で不公平感を産みたくなかったからです。
このように、様々な「5W1H」での質問に対して学生に話してもらうことで、より深い理解ができます。
偽りのエピソードを話す学生が取り繕えない深さまで深掘りする
深掘り質問をすると、学生が「なぜ」「どうやって」その行動をとったかが分かり、
- 今後の仕事においてもどのような状況にどう対応するか
- それが会社のポリシーに沿っているか
- 今いる社員との相乗効果や化学反応を産みそうか
といった詳細なポテンシャルが評価できるようになります。
しかしそれだけでなく、「偽れない深さまで深掘りする」ことで、学生が選考を通過するためだけにマニュアル通りのエピソードを作り上げ、事実でないことを話しているかどうかも分かるようになります。
「なぜそうしたのですか?」「誰がそう言ったのですか?」「例えばどこに行きましたか?」など5W1Hによる深掘りをしていくと、エピソードが偽りのものだった場合、少し回答に窮したり顔色が曇ったりするからです。
面接の様な緊張する場で、涼しい顔で事実を偽れる人というのはそう多くいませんので、「表情」を観察しながら「深掘り質問」をすることで、マニュアル通りでない学生の素顔に近づくことができるのです。
【心得2】本人が楽しく話せる質問をして、「素」を引き出す
学生の素顔を引き出すには深掘りの他にも、「本人が楽しく話せる話題を聞く」というコツもあります。辛かった経験をひたすら聞き出すより、学生が自信を持って笑顔で話せるような話題にするほうが、面接の場も和み、学生はリラックスできます。
どんな人でもいきなり、「死ぬ前に最後に食べたいものはなんですか?」と聞かれて即答で完璧な答えは出てきませんよね。考えたことがない、文章にまとめたことがない回答を、面接の場でうまくスラスラとは話せないのです。
学生は、回答を用意できていない質問をされると、緊張して間を埋めようと焦ったり、思い出しながら話したりしています。面接官の方は、学生が上手に答えられなくても、相槌や会話で話を引き出すよう工夫すると良いでしょう。
昨今叫ばれる「ダイバーシティ」という概念も、人材一人一人の個性を活かし、長所で短所を補い合うことで強い組織になるという考え方に基づいています。
厳しく学生を試すような面接をするより、「この人にはどんな長所があるのだろう?」と良さを引き出すコミュニケーションを取るほうが、学生にも「この会社でなら仕事を頑張れる気がする」と思ってもらいやすく、結果としても活き活きとした組織づくりに繋がるのではないでしょうか?
素」を引き出す理由は、仕事は「日常」になるから
新卒採用において学生の「素」、いわゆる「飾らない本来の姿」を見るべきかどうかについて、人事担当者の間でもいくらか意見が別れることがあります。
「仕事中は少なからず気を張って、多少は飾っていられる人材のほうが優秀だ」「少しも取り繕えない人材では仕事はできない」という考え方の人事もいるからです。
しかし、「採用学」の服部氏によると、やはり「素」の状態で会社にマッチングしていることが重要だとされています。理由は、仕事は「日常」になっていくからです。
新入社員のうちは多少気を張っていたとしても、入社後数年、数十年と経過していけば、毎日朝から夕方まで長い時間を過ごす「仕事」という場では、誰もが「素」になっていくものです。
こういった環境を心理学では「弱い環境」と言い、人間の行動にあまり影響を与えない、つまりその人本来のパーソナリティのままでの行動になりやすいとしています。
逆に、面接という非日常的でプレッシャーのかかる環境は「強い環境」と言われます。強い環境では、本来のパーソナリティよりも環境によって行動が決まりやすくなります。
つまりどういうことかと言うと、面接という強い環境(非日常)では、仕事という弱い環境(日常)においてその人物(パーソナリティ)がどのように振る舞うか、すなわち「入社後に実際に活躍するかどうか」を見極めるのが、非常に難しくなるということです。
面接では、普段とは違う行動になりやすいことを前提として認識した上で、なるべく「素」を引き出すようにしなければ、入社後のミスマッチ(不活躍や不定着)が起こりやすくなるのです。
「素」を引き出すセリフや質問例
それでは、学生の「素」を引き出すために面接で使うと効果的なセリフや質問の具体例を紹介していきましょう。
<面接の導入に効果的なセリフ>
学生に本音を話してもらうには、気負わずに発言ができる空気を作り、リラックスして面接に臨んでもらうことが重要です。「自分の考えを率直に伝えて大丈夫なんだな」と感じてもらうため、以下のようなセリフがおすすめです。
- 今日は、当社のビジョンや入社後の働き方など、お互いのイメージに食い違いがないか確認したいと思います
- ざっくばらんにお話できればと思っていますので、途中で質問を挟んでもらっても大丈夫ですよ
- 答えたくない質問や言いにくいことは、無理せずにおっしゃってくださいね
<アイスブレイクのための質問>
面接官から矢継ぎ早に質問ばかりしてしまうと、「一方的に見定められている」と感じられてしまう可能性もあります。面接前のアイスブレイクだけではなく、途中でも小休止となる質問や問いかけを挟んだほうが、学生もリラックスできるでしょう。
- 面接会場まで迷わず来られましたか?
- 当社まで何分くらいかかりましたか?
- 急に寒くなりましたが、◯◯さんのお住まいの地域はいかがですか?
<価値観や性格を見極める質問>
学生の性格や人柄、仕事に対する価値観や本音を見極めたいときは、具体的なエピソードや考えの根拠を尋ねることが効果的です。以下の質問例を工夫して利用してみてください。
- 強み:ご自身の強みは何ですか?その強みを、当社の仕事のどういったところに生かせそうですか?
- 継続性:過去に、目標に向かって努力してきた経験はありますか?そして、その目標を達成するために具体的にどのような努力をしてきましたか?
- ストレスコントロール:ストレスが溜まってきたら、どのように対処しますか?
【心得3】「面接官ごとに評価が違う」ことは問題ない
面接官が何人もいると、評価が分かれます。これを「採用基準がそろっていない…」と悩む方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、逆に「誰が採点しても同じ評価結果になる」のであれば、複数人が面接に入る必要も、1次、2次…と複数回の面接を重ねる必要もないはずです。
面接官ごとに評価が違うことは、それだけで問題になるのではありません。人それぞれ見ているポイントも違い、好みも価値観も、担当してきた業務などの経験も違います。
そうした複数人の社員の目を通して学生を見極めることで、「私は迷ったが、◯◯◯部の▲▲さんがそんなに良いと言うなら、◯◯◯の分野で活躍できる人材なのかもしれない」など多角的な判断ができるようになるでしょう。
面接において良くないのは、候補者(学生)によって聞く質問がブレてしまい、例えば「ある学生には決まった質問を全て聞くことができたのに、別のある学生とは出身大学に関する雑談で盛り上がってしまい、なんとなく雰囲気は分かったが深掘りはできなかった」というような、面接の“質問ムラ”が発生することです。
このようなことがないように、質問に関しては「新卒採用の面接で学生に聞くべき、”究極”の5つの質問とよくある質問集を紹介」でも紹介したような厳選した数問を共通・必須にしておき、ムラを防止しましょう。
なお、科学に基づき公平な評価をするよう設計されたAI面接アプリにおいても、「どの候補者にも均一な質問をする」ことは非常に重要なポイントとされています。
なぜ「その人」が面接官なのか、目的と見るべきポイントを明確に
人事が面接官を選任する際には、なぜその人を選んだか、その人にどのようなポイントを見てほしいか、という点を明らかにすることが重要です。例えば、
- 長く人事に携わっている人事部の田中さんに、カルチャーフィットを見てほしい
- 会社の中長期戦略を立てている経営企画部の堀部さんに、将来の幹部としての資質を見てほしい
- 入社3年目ながら活躍している若手社員の源さんに、「部下に欲しいか」を見てほしい
- 現場の山本さんに、現場でもコミュニケーションやリーダーシップが取れるか見てほしい
など、面接官の人選には目的を明確に持つ必要があります。
面接官の方も、「人を見る目なんて自信がない」「なぜ自分が面接官なんだろう」と不安なまま曖昧な評価をつけるのではなく、人事担当者に選任の目的や見るべきポイントを聞いたり、自分なりに考えたビジョンをもって面接に臨むようにしましょう。
面接官用の面接評価(採点)シートを作れば認識を揃えやすい
それでも、たくさんの面接をこなしていくうちに、ムラというのは出てしまう可能性があります。
おすすめは、面接官用の面接評価シートを作ることです。すでに以前から使ってきたシートがあるかもしれませんが、毎年の自社の状況や市場の動向、学生世代の価値観なども鑑みて、採用の都度、見直しをかけることをお勧めします。
シートの構成は、
- どの候補者にも共通の質問を必ず毎回聞くようにする
- 回答をメモする
- 回答に対して面接官自身が思ったこと(評価)を記入する
- 共通で持つべき採点基準を明記する
- 総合的な評価結果を記入する
という要素がカバーされていれば良いでしょう。
学生の情報は氏名だけにしておき、面接官には履歴書なども渡さず、学歴や出身地等による先入観(ハロー効果)を持たせないようにするという企業もあります。
面接評価シート様式の例をご紹介
これから面接評価シートを作る人事担当者の方や、自分なりにメモとして持っておきたい面接官の方のご参考に、一例をご紹介します。
<採点シート様式と記入の例>
|
2月17日(月)10:30 面接官氏名【田中 のり子】 |
学生氏名:【山田 あき子】 | 所感メモ |
|---|---|---|
| 自己PR | ・強み:リーダーシップ、まず自分がやって見せる ・カフェのアルバイトリーダー経験 ・売り上げ目標達成、後輩の育成に引き継ぎノートと業務一覧を作成 |
はつらつ声が通る自信ありげ |
| 志望動機 | ・人の人生の転機に関わり、より良い意思決定を助けたい ・強みのリーダーシップを活かしてチームを動かしたい |
ちょっとふわっとしている業界は絞ってない |
|
質問(全員に必ず聞くこと) ①自己PR経験での失敗や苦労 ②自社入社が人生に与える影響 ③短所とカバー策 ④どんなキャラと言われるか ⑤意見が通らなかった経験 |
①経費削減でバイト人数減らされた、やり方変える必要がありそれを提案、社員の説得に他のバイトメンバーの意見を集約して伝えた ②大きなフィールドで経験が積める、蓄積されたノウハウで早く成長できる ③忘れっぽい。スマホのリマインダーアプリをフル活用している ④みんなの姉のようと言われる ⑤バイトで新しい販促キャンペーンが通らなかった。一度諦めたが、また次のチャンスを狙って提案してみたら通った。タイミングも大事と学んだ。 |
バイトの話しか出てこない周り巻き込んでいる説得力あるやり方 |
| 質問(その場で聞いたこと) | ・勤務地のこだわりは? ない ・他に気になっている業界は? ホテル、旅行系 |
将来のビジョン曖昧 |
|
採点基準※3段階(ある〜ない) ①創造力(0から1を作る) ②変革力(既存のものを変えた) ③リーダーシップ ④理念共感 ⑤カルチャーフィット |
①ある ②ある ③ある ④不明 ⑤ない |
優秀そうではある我が強く、既存社員との衝突が心配 |
| 評価A:ぜひ採用したい B:採用レベルに達している C:不足している ★:自社にいないタイプ |
B ★ | ※ここに所感メモが入ります |
【心得4】有意義な面接のコツは徹底的な事前準備
面接は、学生にとっても実りのある時間を提供すべき場所です。そのためには、学生が入念な準備をして面接に臨むのと同様に、会社側もしっかりと事前準備を行う必要があります。面接を有意義な時間にするための、事前準備のコツを紹介します。
正確に会社説明をできるようにしておく
面接は、学生に質問をするだけでなく、学生に自社の魅力をアピールできる場所でもあります。限られた時間のなかで学生に自社の魅力や特性を理解してもらうためには、会社概要や事業内容を正確に説明できるようにしておかなければなりません。特に、学生の動機付けとなる「ビジョン」「ミッション」「バリュー」といった情報をしっかりアピールできるようにしておきましょう。
要点をまとめるだけでなく、口頭で説明する練習もしておくことがおすすめです。
想定質問を洗い出す
面接の途中や最後には、学生から質問の時間も設けることが一般的です。想定される質問をあらかじめ洗い出して、答えを考えておくとスムーズに進められます。質問の洗い出しは、他の面接官や新入社員などにヒアリングするとよいでしょう。
学生が会社に対して投げかける質問は、働く上での疑問や懸念、不安が反映されているものです。面接官が明確な回答を提示できれば、学生を安心させ、会社の印象をアップさせることにもつながります。
トレーニングをする
面接全体の流れを把握し、質問例や回答例などを準備したら、本番を想定してトレーニングを行うとよいでしょう。トレーニングを重ねることで、本番での緊張を和らげるだけでなく、採用基準を使いこなして客観的な判断を下せるようになります。
トレーニング方法としては、ロールプレイングが最もおすすめです。他の面接官とともに、学生役と面接官役を交互にこなしてフィードバックし合うと、チーム全体の面接スキル向上にもなります。
面接の注意点とは?面接でのタブー質問や守るべきモラル

最後に、面接における注意点を解説します。意図せずパワハラやセクハラと受け取られるような質問をしてしまわないよう、注意事項を頭に入れてから面接に臨むようにしてください。
聞いてはいけない「タブー質問」や「セリフ」
面接官になる方に人事担当者が必ず伝えておかなければならないこと、それがこの「聞いてはいけない質問」の存在です。これは、「公正な採用選考」を行うために厚労省が示しているものです。
「公正な採用選考」とは、家族状況や生活環境といった、応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しないことを指します。
こうした事柄は、面接官や企業としては採用基準と関係がないつもりでも、一度聞いてしまうとその印象に引っ張られてしまったり、どうしても合否に影響を与える可能性があります。
そうなると就職差別に繋がるので、「聞くこと」「知ってしまうこと」それ自体をなるべく避けてくださいね、ということです。
厚労省のサイトでは、次のような事柄について質問したり記入させることは「就職差別につながるおそれがあります」として、注意を促しています。
<a.本人に責任のない事項の把握>
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
<具体例>
- 現住所の前は、どこに住んでいましたか?
- お父さんの職業はなんですか?
- 採用書類に自宅付近の略図を添付してください
- お住まいはマンションですか?
<b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観、生活信条に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<具体例>
- 宗教を信仰している家族はいますか?
- 政治活動に興味はありますか?
- 人生においてモットーとしていることはなんですか?
- 尊敬している人物は誰ですか?
- 学生運動についてどう思いますか?
- 学校以外で加入している団体があれば教えてください。
- どこの新聞をとっていますか?
引用元:(厚生労働省「公正な採用選考の基本」(3)採用選考時に配慮すべき事項 より)
また、差別やハラスメントに繋がる恐れがある話題としては、以下にも注意が必要です。
- 恋愛や結婚に関すること
- 交際相手や配偶者に関すること
- 出産や育児に関すること
- 本人の容姿や年齢に関すること
例えば、アイスブレイクのつもりであったとしても「年齢より若く見えますね」「将来は子どもを生む気はありますか?」などの話題はNGです。
質問する側が他愛のない内容だと思っていても、どのような回答が返ってくるか、聞くまでは分かりません。一度聞いてしまえば、それは取り消すこともできません。
もし学生が自分から話そうとしてきた場合であっても、なるべく「そのことは話さなくてよいですよ」と制止しておいた方が安全でしょう。
誠実な態度を心がけよう
前述の通り、学生にとって「会社の顔」である面接官の態度は、学生の印象に大きな影響を与えます。実際に、「面接官の対応が丁寧で入社志望度が上がった」「面接官の態度が悪くて入る気を失くした」という学生の声は少なくありません。以下のような態度は学生の印象を悪くしてしまう可能性があるため、注意するようにしてください。
- 面接に遅刻してきたにもかかわらず、謝罪が無かった
- 相槌も打たず、こちらの話を真剣に聞いているように見えなかった
- 労働条件について質問したら、はっきり答えてくれなかった
身だしなみにも意識を
面接官の身だしなみも、学生の印象を左右します。清潔感がありTPOに合った服装であることはもちろん、社風が伝わる服装を意識することも大切です。
<服装の清潔感>
汚れやシワ、ほころびがないか確認し、体型にフィットした服を選びましょう。
<髪や髭>
くしで全体を整えたり、長髪の人はゴムでまとめたりしましょう。男性は、朝のうちに髭を剃るか、伸ばしている人も適度に整えるようにします。
<社風の伝わる服装>
スーツ着用、オフィスカジュアル、私服OKなど、会社の規定が伝わる服装で参加したほうが、学生も入社後のイメージを膨らませやすくなります。
終わりに 〜面接官は学生が入社前に会う「社員代表」〜

新卒採用の面接官が心得ておくべき基本マニュアルを、ハード面とソフト面に分けてお伝えしました。
初めて面接官になる方は特に、失敗しないだろうか、間違わないだろうかと不安もあるかと思います。
ベテランの面接官の方でも、学生の動向や価値観が年々変化することに戸惑ったり、自社の採用活動や面接のあり方はこのままで良いのかと迷うことがあるのではないでしょうか。そんな方々に、この記事が少しでも参考になりましたら幸いです。
最後に、面接官は学生が入社前に出会う数少ない社員、つまりは会社の「社員代表」です。学生が志望度を高めたり入社を決める動機に、「面接官がとても良い人だったから」とか「面接官が仕事のことを活き活きと語っていたから」といったものも多くあります。
面接官は、評価する側であり、評価される側でもあります。緊張している学生に寄り添いつつ、「あなたと当社がマッチするかどうか一緒に探っていきましょう」という相互理解の姿勢で、面接に望んでいただければ、きっと良い採用活動になるのではないでしょうか。