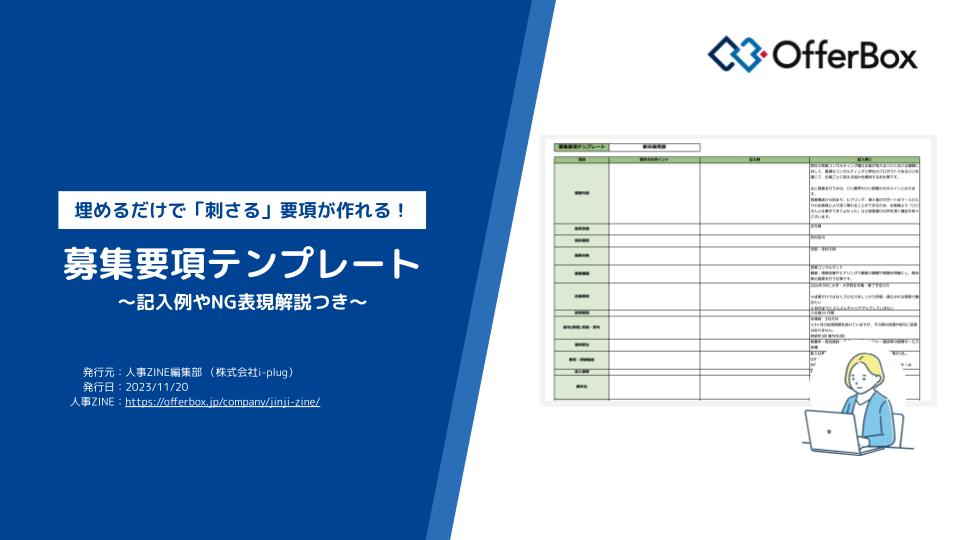新卒向け求人票のテンプレート・書き方と注意したいNG表現を解説

新卒採用の求人票の書き方を調べたけれど、何をどう書けばいいか分からないと困っていませんか?
求人票には必ず記載しなければならない項目があるため、事前に記載ルールを理解しておく必要があります。
大学の就職課に求人票を貼りだしてもらう場合は、自社で決めた自由フォーマットで作成できるケースもあります。本記事をもとに、新卒の求人票の作成ルールや注意点、おすすめフォーマットなどを確認してみてください。
また、「求人票の文面(募集要項)を手軽に作成できるテンプレートをいますぐ欲しい!」という採用担当者の方のために、人事ZINEではテンプレート「募集要項サンプル」をご用意しました。新卒・中途別に記入例やNG表現も記載していますので、お急ぎの方はこちらをぜひご活用ください。
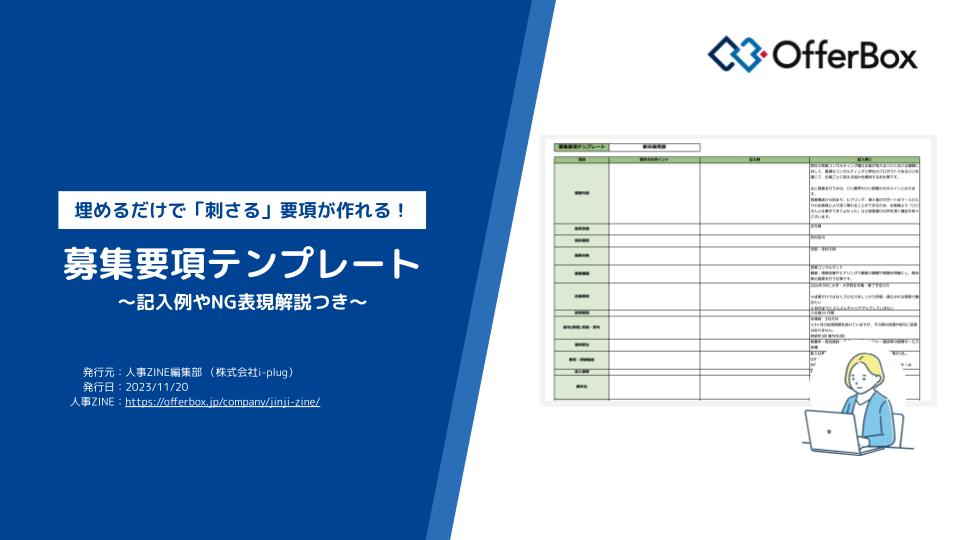
目次
新卒採用の求人票とは

新卒採用の求人票とは、求人募集をする際にハローワークに提出する、求人に関する募集要項をまとめた書類のことです。また、就活エージェントや求人広告、高校や大学のキャリアセンターや就活ポータルサイトに求人情報を掲載するために、募集要項をまとめたものを求人票と呼ぶ場合もあります。
求人票に書く内容は100%自由ではありません。募集時に「必ず記載しないといけない項目」が法律で決められているため、書き方のルールを正しく理解する必要があります。
求人票は、就活生が会社に応募するときの判断材料となる、大切な情報を掲載するものです。採用担当者は正しく情報を網羅し、自社の魅力が伝わる求人票を作成しましょう。
求人票を作成するメリット
新卒採用で求人票を各機関に掲載しても、すぐに採用につながるわけではありません。しかし、求人票を作成して提出することで、次に挙げるようなメリットが得られます。
- 低コストで利用ができる(ハローワークであれば掲載は無料)
- 学校の就職課に求人票を持参しコミュニケーションを取ることで、学校との関係構築を促進できる
- 求人票の露出度を増やすことで就職先の候補として認知してもらえる
新卒採用では求人広告の活用が代表的です。しかし、求人広告だけでは自社を知ってもらうことが難しいかもしれません。さまざまな場所に求人票を掲載して、就活生に自社の存在を認知してもらうことは新卒採用を成功させる上で重要です。
求人票に必ず記載する項目

新卒採用に限らず、求人票の作成にあたっては必ず記載しなければならない項目が職業安定法(第5条の3)で決められています。どの項目を最低限記載するのか、以下で確認しましょう。
- 業務内容
誰でもイメージできるよう、具体的な仕事内容を記載してください。 - 契約期間
無期雇用か有期雇用かを明確に記載します。解雇事由を含む、退職についての取り決めもこちらに記載しておきましょう。 - 試用期間
試用期間の有無を書きましょう。試用期間があれば、その期間についても明示します。 - 就業場所
実際の勤務地や転勤の有無について書きします。複数の勤務地があるときはすべて載せましょう。 - 就業時間・休憩時間
勤務の始業・終業時刻、休憩時間を書いてください。 - 休日・時間外労働就業
残業の有無と休日出勤の有無を書きます。 - 賃金
基本や手当など、1か月に支払われる給与を記載しましょう。固定残業代を支払うときは、その額を明記します。 - 加入保険
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無についてです。 - 募集者の氏名又は名称
会社名や募集者の氏名を明記しましょう。
記載するべき内容の詳細は、後の章で解説します。
求人票の効果的な書き方と活用できるテンプレート

新卒採用における求人票の効果的な書き方を考えている場合は、厚生労働省の「労働条件通知書」にあるモデル様式が便利です。スムーズかつ正確に作成できるという点で、求人票・求人広告作成に大いに役立てられるでしょう。
求人票を書くときに注意したいのは、以下の項目について記入する際です。
- 仕事内容
- 勤務場所・勤務方法
- 賃金・手当
- 勤務時間
- 応募資格
- 選考方法
ここでは、厚生労働省「労働条件通知書」のモデル様式の書き方を参考に、各項目の書き方を紹介します。
仕事内容
まずは仕事内容です。新卒採用であれば、実務未経験者を採用する場合が多いでしょう。未経験の人であってもイメージできるよう、具体的に書くことで応募しやすくなります。他にも、以下のような条件を記載しましょう。
- 就業形態・雇用形態(正社員など)
- 雇用期間(契約の更新の有無も含む)
- 試用期間
「仕事内容」は、応募者が自身が応募している役職について深く理解するための重要な情報源です。業務についての透明性の担保を重視し、応募者が「自分はこの仕事に合っているかどうか」を判断できる具体的な内容を意識します。
勤務場所・勤務方法
「勤務場所・勤務方法」を記載する際は、応募者が具体的に「どこでどのように働くのか」を理解できるようにすることが重要です。まずは、明確な場所の指定として、勤務地の正確な住所を書きます。応募者が理解しやすいよう、アクセス情報(近くの公共交通機関の情報)も明記しておくと親切です。
勤務方法については、「週何日、どこへの出勤が必要なのか」「フレックスタイムやリモートワークが可能かどうか」など、勤務形態について詳しく記載します。「当社ではフレックスタイム制度を導入しており、週に2日間のリモートワークが可能」といった表現は、求人票でよく用いられています。
賃金・手当
賃金・手当で記載したいのは、以下の項目です。
- 基本賃金(月給、日給、出来高給など)
- 諸手当の額または計算方法(○○手当○万円、計算方法:○○○○○○)
- 所定時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金率
- 賃金締切日(毎月○月○日)
- 賃金支払日(毎月○月○日)
- 賃金の支払方法
- 労使協定に基づく賃金支払時の控除の有無
- 昇給・賞与・退職金
基本賃金はもちろん、さまざまな手当を考慮する人もいるため、余すことなく記入します。
勤務時間
勤務時間で記載したいのは、以下の項目です。
- 始業・終業の時刻(始業:○時○分、終業:○時○分)
- 変形労働時間制(導入されている場合)
- フレックスタイム制(導入されている場合)
- 事業場外みなし労働時間制(導入されている場合)
- 裁量労働制(導入されている場合)
- 休憩時間(○分)
- 所定時間外労働の有無
- 休日(完全週休二日制など)
所定時間外労働については、月平均で何時間ほど発生するかを書いておくと、応募者にとってイメージしやすくなります。
応募資格
応募資格で記載したいのは、以下の項目です。
- 必須要件
- 望ましい要件
- 求める人物像
必須要件では、資格・経験・スキルなどの条件を明示します。例えば特定の学位(学士号や修士号)や専攻、資格などです。
望ましい条件では、必須ではないが、あれば有利となる経験・スキルをリストアップします。例えば特定のソフトウェアに対する習熟度や、関連分野でのインターンシップの経験などです。
求める人物像は、「チームで協力しながら業務を遂行できる方」「主体的に業務に取り組める方」など、該当のポジションに求められる個人の特性・態度を記載します。
選考方法
選考方法で記載したいのは、以下の項目です。
- 選考フロー
- 各ステップの詳細
- 日程
まずは選考フローの明記です。例えば「書類選考」「一次面接」「二次面接」「最終面接」「内定」のように、段階を列挙します。「二次面接では部門長との面接」など、各ステップの詳細も書いておくとよいでしょう。
昨今ではオンライン面接も浸透しつつあり、面接がオンラインで行われるのか、オフィスで直接行われるのかを明記しておくのも重要です。
求人票作成時のポイント

求人票を書くときには絶対に記載しなければならない情報があると前述しました。それとは別に、自社で独自のフォーマットを作り、他社とは違う自社ならではの魅力を記載することも大切です。
最低限書くべきことを書いておけばいいと判断するのではなく、就活生の関心を引く求人票を作成する工夫をしましょう。求人票を作成するポイントとして、注意点やコツを以下にまとめたので参考にしてください。
一定期間ごとに内容を更新する
求人票は1回出したら終わりではなく、新しい情報に更新することが大事です。1回公開して反応が少なければ、記載している内容の表現方法を変更するなど見直しを重ねていきましょう。
更新日時などが表記されるので、日付が古いままの求人票だと「もう募集が終わているかもしれない」と判断されてしまう可能性もないとは言えません。特に要注意なのが古いものを出しっぱなしにしているケースです。古い情報を見て応募してきた人とトラブルになってしまうおそれがあります。求人票はある程度のスパンで更新をし、古いままの情報を掲載しないように注意しましょう。
求人票の記載項目・運用ルールを守る
求人票の記載項目・運用ルールを守ることも重要です。本記事の前半でも紹介しているように、「職業安定法 第5条の三」「職業安定法施行規則 第4条2の3」によって、募集時に明示しておくべき項目があります。
- 業務内容
- 契約期間
- 試用期間
- 就業場所
- 就業時間・休憩時間
- 休日・時間外労働就業
- 賃金
- 加入保険
- 募集者の氏名又は名称
上記の項目を事前に把握し、今回紹介した書き方やテンプレートを参考にしつつ、漏れなく記載しましょう。
また職業安定法の改正(2022年10月施行)によって、「的確表示」「苦情処理」「個人情報の保護や秘密保持」などの義務もあります。それぞれの意味は、以下の通りです。
| 的確表示 | 明らかな虚偽や、誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容にすること |
|---|---|
| 苦情処理 | 利用者からの苦情を迅速・適切に処理しつつ、それに必要な体制を整備すること |
| 個人情報の保護や秘密保持 | 特定募集情報等提供事業者に対して、個人情報取扱規定を適用し、個人情報利用目的を明示させること |
労働関連法の規定を守る
労働関連法の規定を守ることも重要です。職業安定法の他にも、求人票・求人広告の出稿において守るべきルールについて触れている法律があります。
- 男女雇用機会均等法
- 雇用対策法
- 労働基準法
- 最低賃金法
男女雇用機会均等法は、性別に基づく差別を禁止しています。そのため求人票では、「男性専用」「女性専用」といった性別による区別を避けるべきです。性別に基づくステレオタイプ、例えば「男性はリーダーシップを」「女性は周囲の助けを求めて仕事を進めて」といった表現も避けたほうがよいでしょう。
雇用対策法では、年齢制限の禁止が義務化されています。そのため「30歳以上は応募禁止」など、年齢を理由に応募を断ったり、年齢を理由に採用・不採用を決定してはなりません。
労働基準法は、労働者の基本的な権利を保護するための基準を定めています。労働時間や休日などについて、法定基準を破るような表現をしてはなりません。最低賃金法についても同様です。
求人票で特に注意したい法律と禁止表現

求人票・求人広告で禁止表現やその他のルールは多くありますが、特に理解しておきたいのが「男女雇用機会均等法」「雇用対策法」の2つです。ここでは、それぞれの法律について、具体的なNG表現例をそれぞれ紹介します。
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法では、以下のような表現を違法としています。
| 違法になる表現 | NG表現の具体例 |
|---|---|
| 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除する | 「男性のみ求む」「女性限定の採用」 |
| 男女で募集・採用条件を分ける | 「男性は営業経験が必要、女性は不問」 |
| 採用選考において、男女で異なる取扱いをする | 「男性は筆記試験、女性は面接のみで選考」 |
| 男女のいずれかを優先する | 「女性優遇の採用」 |
| 求人内容の情報について、男女で異なる取扱いをする | 「男性は月給28万円」(女性の給与を明記しない) |
雇用対策法
雇用対策法は、先述のように、年齢制限の禁止が義務化されています。求人票の記載時は、原則として「年齢不問」にしなければなりません。以下、想定される問題とNG表現をまとめています。
| 想定される問題 | NG表現の具体例 |
|---|---|
| 若者向けの店舗なので若い人材を採りたい | 「30歳以下のみの募集です」 |
| 仕事内容が肉体的にきついので、選考から高齢者をなるべく除きたい | 「50歳以上の人は募集しておりません」 |
| PCやソフトウェアに関する仕事で、なるべく経験豊富な人を採用したい | 「40歳以上のみ応募可能です」 |
「20代活躍中!」「40代や50代の人が活躍している職場です」など、職場の状態を表現しているのであれば、雇用対策法に反することはないとされています。
まとめ
新卒採用の求人票とは、求人募集をする際に、ハローワークや就職課、ナビサイトや就職マッチングサービスなどの媒体に掲載する募集要項をまとめた書類です。必ず記載しなければならない労働条件を理解しつつ、必要に応じてテンプレートを活用しながら記入欄を埋めましょう。空白を少なくすれば、求人票の完成度はより高くなります。
求人票を作成するメリットを理解し、求人申込書の書き方をマスターすることで応募者と接触する機会を増やせる可能性が高まります。求人票を作成したら一定期間ごとに内容を刷新し、自社のフォーマットを用意するなど工夫を加えてみてください。
最後に、「手軽に求人票を作成したい」という人事・採用担当者の方は、こちらのテンプレートもご活用ください。本記事では記載しきれなかった、それぞれの項目の具体的かつ魅力的な記入例をご紹介しております。