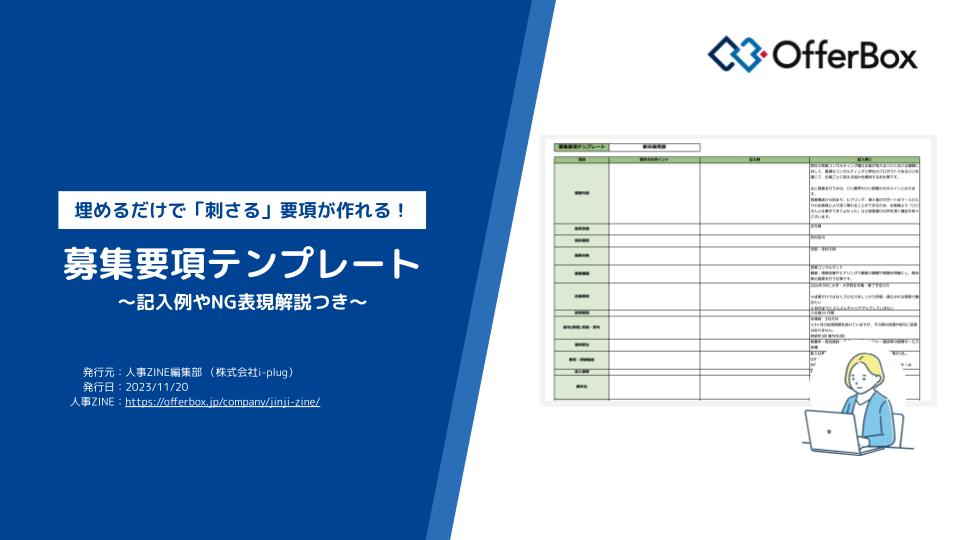1dayインターンシップの特徴・プログラム例と企業が実施するメリット

1dayインターンシップは、長期インターンシップと比べて企業側・学生側双方にとって負担が少ないながら採用ブランディングや相互理解に活用できる手段です。ただし、1dayインターンシップの効果を最大限引き出すには、その特性を理解し、運用体制を整える必要があります。
本記事では、1dayインターンシップの基本的なポイントから、その企画・実施の手順、さらには最大限の効果を得るための方法までを詳細に解説します。
また、本記事では紹介しきれなかったインターンシップのポイントを解説した資料「学生を惹きつけるインターンシップの作り方」をご用意しました。インターンシップ終了後のフォローについても紹介しています。ダウンロードしてご活用ください。

目次
1dayインターンシップとは?

ここでは、採用担当者が押さえておきたい1dayインターンシップの基本ポイントについて解説します。1dayインターンシップの特徴や取り組み状況、企業側が行う主な目的、学生側が参加する理由などをご紹介します。
1dayインターンシップの概要
1dayインターンシップは、座談会や職場見学、ワークショップなどを通じて企業の雰囲気や業務内容を体験できるプログラムです。1日だけのプログラムで、実際の業務にあたってもらうというよりも、座談会や職場見学、ワークショップといった形式が多い傾向にあります。
企業側は、企業や募集職種に興味を持ってもらえる一方で、参加者は一日の体験を通じて会社の雰囲気を体感し、入社すると自分がどのような仕事をすることになるのかをイメージしてもらうことができます。
企業が1dayインターンシップを行う目的
通常、インターンシップとは企業理解の促進と選考を目的として行われることが多いですが、1dayインターンシップは選考と切り分けて行われることがほとんどです。
それではどのような目的で行うのかというと、以下の2つが挙げられます。
- より多くの学生と接点を持つこと
- 体験を通して学生に興味を持ってもらうこと
多くの学生と接点を持つことで、それだけ自社に合った学生と出会う機会が広がります。また、学生にとっても選考とは違った形での企業理解につながり、入社後のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。
その他にも、新人材の発掘に加えて、採用ブランディングや採用・選考プロセスの効率化、学生の動向把握などがあります。就職活動が本格化する前に、1dayインターンシップによってこのように先手を打てば採用活動をスムーズに行える可能性があるでしょう。
1dayインターンシップの動向
現在、多くの企業が1dayインターンシップを取り入れており、学生の多くも参加している傾向にあります。
1dayインターンシップ情報を掲載しているサイトの1つ「リクナビ2025」では、求人を掲載している1万6,594社のうち、「1day仕事体験エントリー予約受付中」なのは、全体の約3割にあたる5,502社でした(2023年5月時点)。学生側についても、2023年卒を対象にした「インターンシップ・1day仕事体験 参加学生の意識調査」によると、1日以下のプログラムに参加したと回答した大学生は、81.2%でした。
「1dayインターンシップ」の呼称をめぐる動き
1dayインターンシップをめぐる動向としては、2017年に経団連が1日のインターンを容認したことから、実施する企業が増えてきたという経緯があります。ただ、「1日では就業体験にならない」「インターンは学生が選考の一環と認識している」という理由で、容認から一転、2021年3月に経団連は廃止する方針で大学側と合意しました。
このような動向から、大手ナビサイトでも現在は「1dayインターンシップ」から「ワンデー仕事体験」などの呼称に切り替えていることは押さえておく必要があるでしょう。
企業が1dayインターンシップを行うメリット

企業が1dayインターンシップを行うことで、採用ブランディングの強化や選考プロセスの効率化、運営コストの削減、学生の動向把握、若手社員のモチベーション向上など、さまざまなメリットがあります。ここでは各ポイントについて順番に解説します。
採用ブランディングの強化
1dayインターンシップは、企業が採用ブランディングの強化を図るために有効な手段です。インターンシップを通じて、企業の考え方・ビジョンや仕事のやりがい、働く環境を学生にアピールし、企業のイメージ向上を図ることができます。また、長期インターンシップよりも手軽に参加してもらえるので、多くの学生に訴求して広くブランディングできるのも利点です。
選考プロセスの効率化
1dayインターンシップを行うと、短期間で多くの学生と接触でき、自社が求める人材との接点を創出しやすくなります。また、学生に実際の業務あるいは業務を模したワークショップに参加してもらうことで、スキル・適性を評価する手がかりを得ることも可能です。さらに、学生とのコミュニケーションを深め、関係を構築することで、学生の意欲・希望進路を具体的に把握できます。こういった理由により、1dayインターンシップは選考プロセスの効率化に役立つ可能性があるのです。
運営コストの削減
1dayインターンシップは、企業側の運営コストを抑えることができます。長期インターンでは、企業側もプログラムの企画・選考や実際の受け入れ・フォロー実施にあたって多くの工数的・金銭的コストがかかりますが1dayインターンシップではそういったコストを削減できます。また長期インターンシップでは、その内容によって学生に対する報酬や手当が必要になるケースが多いですが、1dayインターンシップの多くは報酬が発生しないという点も、コストを抑えられる理由の1つです。
学生の動向把握
1dayインターンシップは短期間で多くの学生と接触でき、また一方的な説明になりがちな会社説明会とは異なって学生とのコミュニケーションの機会が生じるため、企業側は学生の最新の動向や志向を把握しやすくなります。
具体的には、「どのような業界・企業が学生に人気であるか」「どのような条件や福利厚生が求められているか」など、一般的な就職市場の動向も把握でき、採用ブランディングにおける訴求方針の見直しにも役立てられるでしょう。
若手社員のモチベーション向上
1dayインターンシップでは若手社員が学生と直接交流することで、学生の新鮮な視点や意欲に触れて刺激を受け、モチベーションの向上につながる可能性があります。
また、若手社員がインターン生への指導を担当することで、リーダーシップを発揮する機会も増えます。この指導の経験は自己のスキルを再確認するとともに自身の成長を実感する機会となり、モチベーションの向上を促す効果が見込めます。さらに、若手社員が学生に対して自社の魅力を伝える過程で、自社・現在の仕事の魅力を再確認しモチベーション向上につながる可能性もあります。
企業が1dayインターンシップを行うデメリット・注意点

1dayインターンシップの運用には多くの利点がありますが、その一方でデメリットや注意点も存在します。これらを理解し、対策を立てることが企画の成功につながります。
深く実践的なプログラムを提供しにくい
1dayインターンシップでは時間的な制約があるため、深い実践的なプログラムを提供するのが難しい場合があります。時間的余裕がある長期インターンシップと比較して、1日で企業の文化や仕事内容を十分に伝え、学生に有意義な経験をしてもらうことは容易ではありません。
対策として、事前にオンラインでの企業紹介やQ&Aセッションを開催するなど、インターンシップ当日に時間を割かずとも学生に情報を提供する工夫が考えられます。また、インターンシップ当日は、業務のワークショップ形式や現場見学、社員とのディスカッションを組み合わせてプログラムを構成することで、深い理解を促すことが可能です。
学生とのコミュニケーションが薄くなりがち
また、1dayインターンシップでは学生とのコミュニケーションが薄くなりがちというデメリットもあります。1日限定のイベントでは、個々の学生と深く関わる時間が不足しがちで、相互理解を深めるのは簡単ではありません。
そこで「小規模グループでの活動を増やす」「社員一人当たりの学生数を減らす」などして、よりパーソナライズされたコミュニケーションの機会を作ることが考えられます。また、インターンシップ後にも「フォローアップのメールを送る」「SNSでの交流を続ける」など、長期的な関係構築にも努めることが重要です。
費用対効果の測定・検証が難しい
1dayインターンシップは、どうしても取り組む内容が限定的になりやすいため、費用対効果の測定・検証が難しいというデメリットがあります。短い期間では学生のスキルや適性の評価、企業にとっての採用効果を正確に把握することが困難であり、これは長期インターンシップと比較してみても明確なポイントでしょう。
対策としては、定量的な評価指標の設定が挙げられます。例えば、参加学生数、その中での実際の採用者数、参加学生からのフィードバックなどをもとに、効果測定を行うことができます。さらに、インターンシップ後の学生の行動(例えば、企業の公式SNSをフォローする、企業イベントに参加するなど)を追跡し、インターンシップが学生の行動にどのように影響を及ぼしたかを分析することも有効です。
学生が1dayインターンシップに参加するメリット

次に、学生側が1dayインターンシップに参加するメリットも押さえておきましょう。
スケジュールを確保しやすい
学生がインターンシップに参加するには、学業との両立も必要となります。中長期のインターンシップと比較すると、1dayインターンシップの場合、スケジュールを確保するハードルは低く、気軽に参加することが可能です。
多くの企業のインターンに参加できる
1dayインターンシップは期間が短い分、多くの企業のインターンに参加できます。複数の企業のインターンに参加することで視野を広げたり人脈を広げたりできるのは、学生にとって大きなメリットといえるでしょう。
学生が1dayインターンシップに参加するデメリット

実践的な体験はできない
1dayインターンシップでもプログラム次第では実務を体験できますが、現実的に実践的な能力を身につけることは難しいものです。また、1日という短い期間での体験となるため、実際にその業務が自分に向いているか、やりがいを感じられるかなどを判断することは難しいでしょう。
内定に結びつかない
中長期のインターンシップでは内定に結びつくケースも少なくありませんが、1dayインターンシップでは企業側も受け入れる学生が多く、選考とは切り分けて考えることがほとんどです。業界・企業理解をメインに考えるならよいですが「選考に有利に働くものではない」ことは、学生のとってのデメリットになる可能性があります。
1dayインターンシップでは何をする?実施内容の例

1dayインターンシップは、自社にマッチした人材を採用するためのプログラムとして、今や多くの企業で活用されています。ここでは、1dayインターンシップのプログラム例として、企業説明・業界研究、社員との座談会、ビジネスケーススタディ、ワークショップ・グループディスカッション、オフィスツアーなどを取り上げます。
企業説明・業界研究
1dayインターンシップの定番のプログラムの1つが、企業説明・業界研究セッションです。具体的なプログラムとしては、例えば、「企業の市場におけるポジションや将来のビジョンを語るセミナー」や「その業界の最新動向についてのワークショップ」などがあります。
企業は自社のビジョンや事業内容、業界動向を伝え、ブランドイメージを高めることができます。学生は企業や業界について深く理解し、自分のキャリア選びの参考にすることができます。
企業側は具体的な業界のトピックや独自のビジネスケースを紹介することで、学生がより深く理解する手助けをすると満足度向上につながる可能性があります。
社員との座談会
社員との座談会は、学生が企業の雰囲気を直接感じてもらう機会となります。具体的なプログラムとしては、例えば、「若手社員とのカジュアルなランチ会」や、「各部署のリーダーとのパネルディスカッション」などがあります。
企業側は、社員の日常的な経験や企業文化を直接伝え、採用ブランドの強化につながります。学生は社員から直接リアルな情報を得ることで、企業への理解を深められます。
企業側は社員の選定や座談会の内容に工夫を凝らすことで、学生に対する魅力的なメッセージを伝えるのがポイントです。
ビジネスケーススタディ
ビジネスケーススタディは、学生が企業の仕事を直接体験し、企業側が学生の能力を評価するのに適したプログラムです。プログラムの具体例としては、「実際の業界から抽出した課題を用いたグループワーク」や、「過去のビジネス案件をもとにした解決策のプレゼンテーション」などがあります。
ビジネスケーススタディを通して、企業側は学生の思考力やプレゼンテーションスキルを確認でき、優秀な人材を見つける一助となります。一方、学生側は現場のビジネス課題に触れ、企業の仕事内容や求められるスキルを具体的に理解することができます。
企業側は、実際のビジネスケースや、それに近いケースを用いて課題を設定するなどして学生にリアリティと興味を感じてもらうのが重要です。
ワークショップ・グループディスカッション
ワークショップやグループディスカッションは、学生がチームでの問題解決を体験し、企業側が学生の協調性やコミュニケーション力を評価する機会となります。
プログラムの例としては、「新製品のマーケティング戦略を設計するグループワーク」や「世間で話題となっているテーマと業界の関係についてのパネルディスカッション」などがあります。
企業側は学生のチームワークやコミュニケーション力を観察することで、適性を見極める一助となります。一方、学生側は自身の意見を発信し、他者と協働する経験を得ることで、自己成長につながります。
企業側は適切なテーマと難易度を設定することで、学生の参加意欲を引き出すことが可能です。
オフィスツアー
オフィスツアーは、企業が自社の働きやすさや文化をアピールし、学生が働く環境を具体的にイメージしてもらうプログラムです。
例えば、「各部署を巡るツアー」や「もの作りの現場において実際の器具を触ってもらう」といったものが考えられます。
企業側は、実際のオフィス環境や働く雰囲気をアピールすることで、学生の興味を獲得し、さらに魅力的な職場というイメージを持ってもらうことが可能です。一方、学生側は、自身が働く可能性のある環境を直接見ることで、自分が働くイメージを想像してみる手がかりになります。
実施にあたっては「オフィスの特徴のうち特にアピールしたい部分を事前にピックアップして伝える」「社員の働く様子をリアルタイムで見てもらう」などの工夫を通じて、学生に理解を深めてもらうことが重要です。
企業が1dayインターンシップを実施する手順

1dayインターンシップを実施するなら、その目的に合わせて最適なコンテンツを決める必要があります。以下に、実施する際の6つのステップをご紹介します。
1.目的を決める
まずはインターンシップの目的を決めます。自社が採用を行う理由から逆算し、以下の点を明確にしましょう。
- インターンシップの役割は何か
- 何を1dayインターンシップのゴールとするか
2.求める人物像を言語化する
次のステップでは、求める人物像を言語化します。自社に合った、自社で活躍できる人物像はどのような人かを言語化してみましょう。
言語化は、「インターンを通してどのような学生と接点を持ちたいか」というターゲットを明確にすることにつながります。また、インターンに関わる社員全員で意識合わせができるメリットもあります。
3.開催形式を検討する
ここまでの流れを踏まえて、接点を持ちたい学生に出会うにはどの開催形式が適切かを検討します。「セミナー形式が最適か」「ワークショップにするのか」「どのような形式であれば自社のインターンシップの目的が達成されるのか」を考えましょう。
4.伝えるべき自社の魅力を決める
形式が決まれば、詳細のプログラムを検討します。1dayインターンシップは短い期間で学生に興味を持ってもらうことが必要となるため、伝えるべき自社の魅力は何か、学生の目線で考えましょう。
- 自社の持つビジョン
- 自社の安定性や成長力
- 商品力や事業内容
- 給与や福利厚生など待遇面
- キャリア形成や成長機会の有無
- 組織の風土
- 仕事内容
上記は一例ですが、自社の魅力を整理し、何を伝えるべきか分析してみてください。
5.要素を整理する
ここまで紹介したステップに沿って、1dayインターンシップの全体像を決めていきます。5W1Hの考え方を用いると整理がしやすいでしょう。
- 誰に(WHO)→どのような学生に?
- 何のために(WHY)→インターンの目的は?
- いつ(WHEN)→開催時期は?
- どこで(WHERE)→開催場所は?Webなのか対面なのか
- 何を(WHAT)→伝える内容は?
- どのように(HOW)→開催形式やコンテンツ内容は?
6.フォローする
1dayインターンシップを開催したら、その後のフォローまで行うことが重要です。具体的には、メールでの採用サイトの案内やエントリー受付、会社・工場見学会などの案内が挙げられます。
学生は多くのインターンに参加するため、自社に興味を持ってもらうには終了後もコンタクトを取り続けることが大切です。インターンのみで終わらせず、計画的にフォローを実施しましょう。
企業が1dayインターンシップを最大限活用する方法

1dayインターンシップを最大限活用するためには、採用ターゲットに魅力的なプログラムを用意し、積極的なコミュニケーションを推進し、PRとフォローアップにも力を入れることが必要です。
採用ターゲットに訴求できるプログラムを用意する
1dayインターンシップは、通常のインターンシップと比較するとわずかな期間とはいえ、企業の魅力を伝える良い機会となります。学生が自社に関心を持ってもらうためには、採用ターゲットに訴求できるプログラムを用意することが重要です。
例えば、業界研究やビジネスケーススタディ、職種体験、ワークショップなどは、参加者に対して企業の仕事内容や企業文化を深く理解してもらうための有効な手段となります。このようなプログラムを通じて、求職者が自社の魅力を具体的に感じられるようにすることが、1dayインターンシップを最大限に活用するための鍵となります。
積極的なコミュニケーションを促進する
1dayインターンシップは、企業と学生が直接交流する絶好の機会です。そのため、積極的なコミュニケーションを促進することが求められます。
社員との座談会やグループディスカッション、質疑応答の時間を設けることで、参加者は企業の実情を直接把握できます。同時に、企業側も参加者の思考パターンや仕事に対する考え方を知り、より適切な評価やフィードバックが可能となります。
PRとフォローアップにも力を入れる
1dayインターンシップの成功には、事前のPRと事後のフォローアップが不可欠です。
PR活動としては、企業のWebサイトやSNSを活用してインターンシップの情報を広め、ターゲットとなる学生に情報を届けることが重要です。また、インターンシップ後のフォローアップとしては、参加者のフィードバックを収集し、また次回のインターンシップや採用活動への参加を促すなど、学生の関心を維持する活動が必要です。
長期インターンシップと比較して、1dayインターンシップは限られた時間内で成果を出さなければならないため、事前のPRと事後のフォローアップは特に重要です。
1dayインターンシップを実施するポイント

1dayインターンシップの企業事例
ワンデーインターンシップの具体例として、以下にいくつかの企業の実例をご紹介します。
新菱冷熱工業社「XR技術を用いた現場体験」
新菱冷熱工業は空調設備の設計・施工を行っている企業。ワンデーインターンシップでは、事業内容や仕事内容が体感できるようなプログラムを複数用意しています。以下はその一例です。
- 会社説明&最新技術XRの体験
- 研究所の施設見学&先輩社員との座談会
- 建築設備業界の説明&施工管理の現場見学、体験
いずれのプログラムも、座談会やグループワークが組み合わされており、「建物に命を吹き込む」仕事内容を肌で感じられる内容が特徴です。
ボルテージ社「ゲーム設計の体験」
ボルテージは映像・音声・音楽ソフトやインターネットコンテンツなどの企画・制作・販売を行う企業です。ワンデーインターンシップでは、シナリオディレクション体験やゲーム設計体験など、実際のボルテージでの業務がコンパクトに体験できるプログラムを行っています。
業務体験だけでなく、現場社員からのフィードバックも実施しており、働き心地や社風を体験できるのも特徴といえるでしょう。
アソビュー社「業界分析と新規事業提案」
アソビューは、「遊び産業」という新しいフィールドの創造を目指す企業です。ワンデーインターンシップでは、アソビューの事業に関わる体験ができるプログラムが用意されています。
まずは観光業界や地域課題・課題解決のためのソリューション営業について学んだうえで、グループワークを実施。最後は社員に向けてプレゼンを行い、そのフィードバックまでがもらえるため、学生側にとっては社会人としての業務の流れを体験することができます。
パーク24社「オンライン開催の謎解き業界研究」
パーク24は、タイムズの駐車場やカーシェアを提供している企業です。ワンデーインターンシップは、オンライン参加できる「謎解き」を通して業界研究ができる形式で行っています。
グループワークでの謎解きを通してパーク24グループに関するオリジナルの課題に取り組むことで、学生は楽しみながら業界研究ができ、課題解決能力やコミュニケーション能力を磨くことのできるコンテンツが特徴です。
まとめ

ワンデーインターンシップは2023年現在、多くの学生の支持を集めており、今後も多くの企業が開催していくものと見られます。
ワンデーインターンシップにはメリットが数多くあります。導入するなら「どのように学生に興味を持ってもらうか」「1日で体験してもらうにはどの程度のコンテンツが適切か」など、学生目線に立って検討しましょう。
学生の心を掴むインターンシップを設計したい採用担当者の皆さまは、こちらの資料もご覧ください。自社のインターンシップの設計・実施にご活用いただける内容になっています。