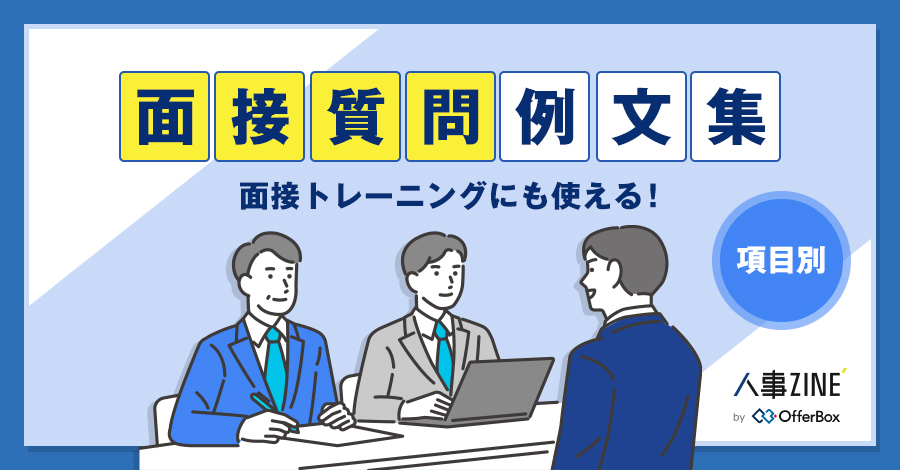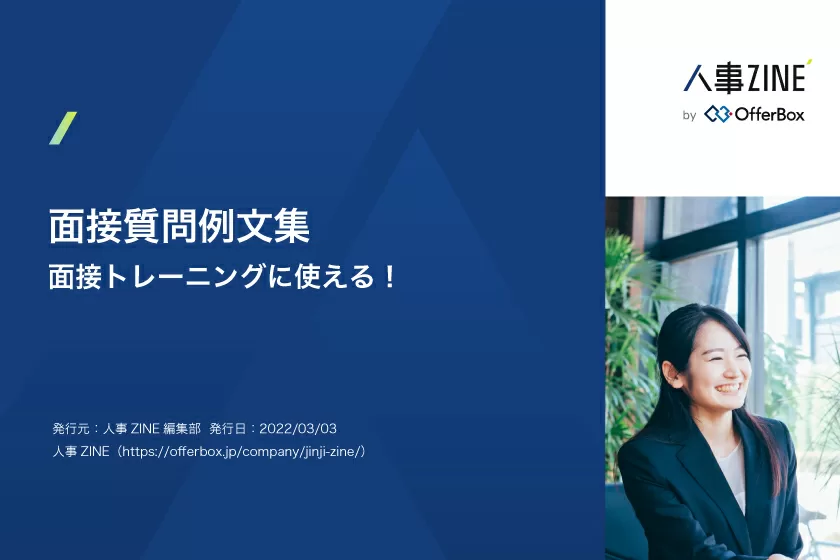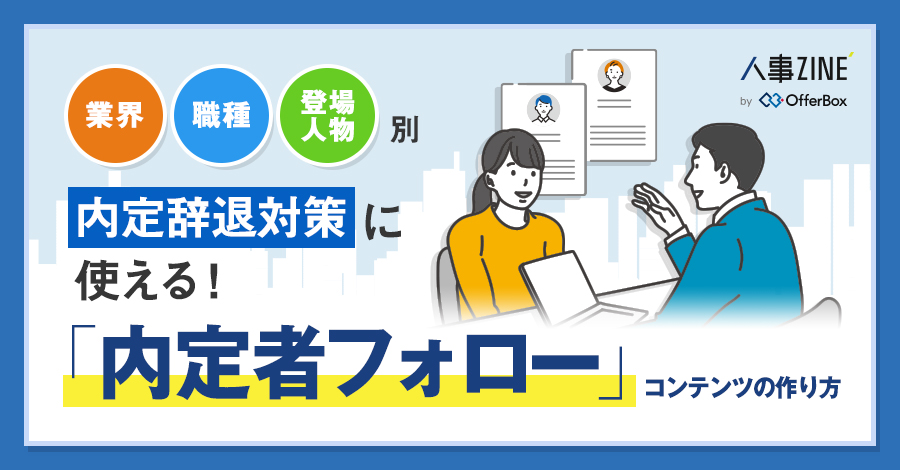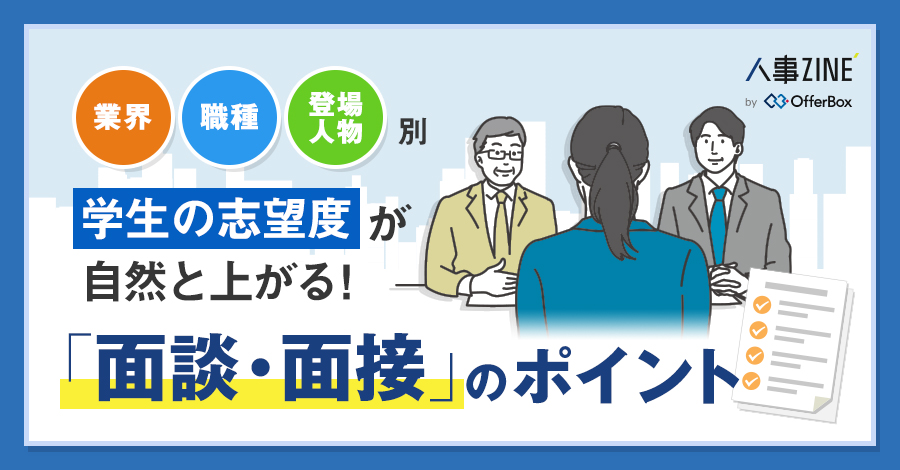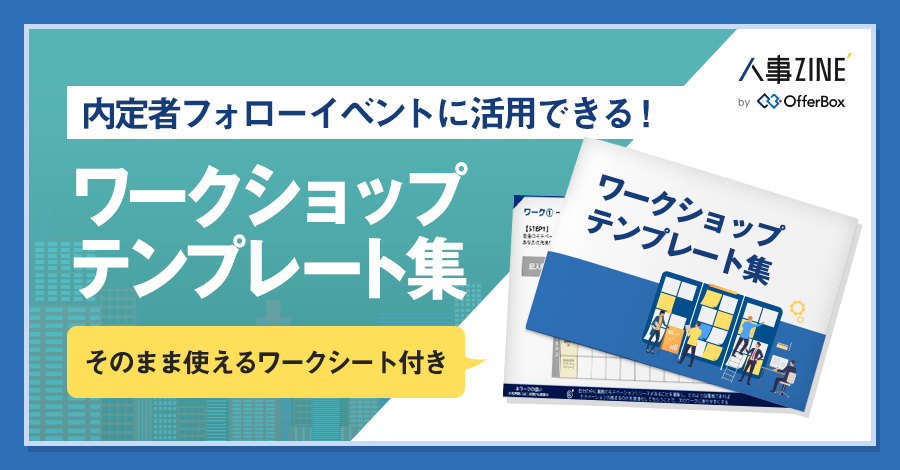【面接官向け】面接アイスブレイクの会話ネタ・質問例10選とNG例

応募者の緊張をほぐし、リラックスした状態で面接に臨んでもらうために活用したいのがアイスブレイクです。適度に取り入れることで、応募者との距離を縮め、本音を聞き出すことにも役立つでしょう。
この記事では、アイスブレイクに使いたい鉄板の会話ネタを、質問例を交えてご紹介します。注意点やNG例もあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、面接のアイスブレイク以外の質問例も知りたいという面接官の方は、人事ZINEが提供している資料「面接質問例文マニュアル」もご覧ください。面接においてパーソナリティーやキャリア志向、志望動機といったポイントを見極めるために効果的な質問例をまとめております。ダウンロード可能で、すぐにご活用いただけます。
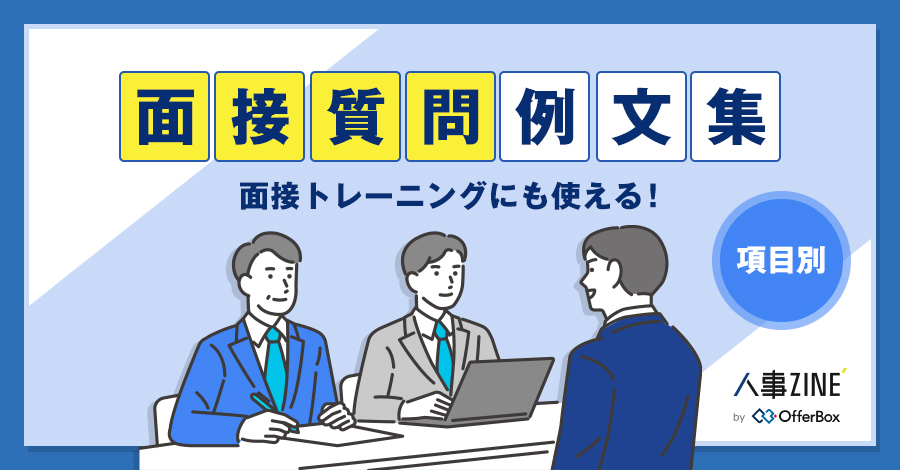
目次
面接でアイスブレイクを活用する目的

アイスブレイクは「氷を溶かす」という意味で、初対面同士の緊張をほぐすコミュニケーションのことを指します。アイスブレイクを面接に取り入れると、以下のような効果が期待できます。
- 応募者の緊張を和らげる
- 応募者の本音を引き出す
- 会社のイメージアップ
以下に1つずつ、詳しく説明しましょう。
応募者の緊張を和らげる
アイスブレイクの第一の目的は、応募者の緊張を和らげることです。
応募者が緊張した状態で面接に臨むと、思うように自己PRができず、消化不良の面接となってしまう可能性があります。これは応募者にとってデメリットですが、面接する側にとっても、その人本来の力が把握できなくなってしまう点で大きなデメリットといえます。
アイスブレイクによってリラックスした状態で面接が進むと、自然なコミュニケーションができ、相互の理解につながるのです。
応募者の本音を引き出す
リラックスした状態で面接に臨んでもらうことで、応募者の本音を聞けるのもアイスブレイクのメリットです。
応募者が落ち着いた状態でスムーズにやりとりができると、何気ない会話からその人本来の考えや、率直な意見、入社後の希望などを引き出せるでしょう。応募者の本音や「素の人物像」が見られると、応募者のポテンシャルや自社との相性を正確に判断しやすくなります。
また、率直な希望を聞くことができれば、入社後のミスマッチ回避にもつながります。採用のミスマッチを減らすことは、面接で達成するべき重要な課題です。詳しくは下記ページもご参照ください。
会社のイメージアップ
アイスブレイクは、自社のイメージアップにもつながります。
一般的に、応募者は「自分を出せた」面接官や企業に対して好感を持ちます。逆に、面接官に対して委縮してしまったり、自然な自分を出せなかったりした企業には、悪いイメージを持ってしまうことも少なくありません。
好ましいイメージを持ってもらうことは、応募者の志望度を上げることにもつながります。また、結果的に採用に結びつかなかった場合でも、好印象を残すことは自社にとってプラスとなるでしょう。
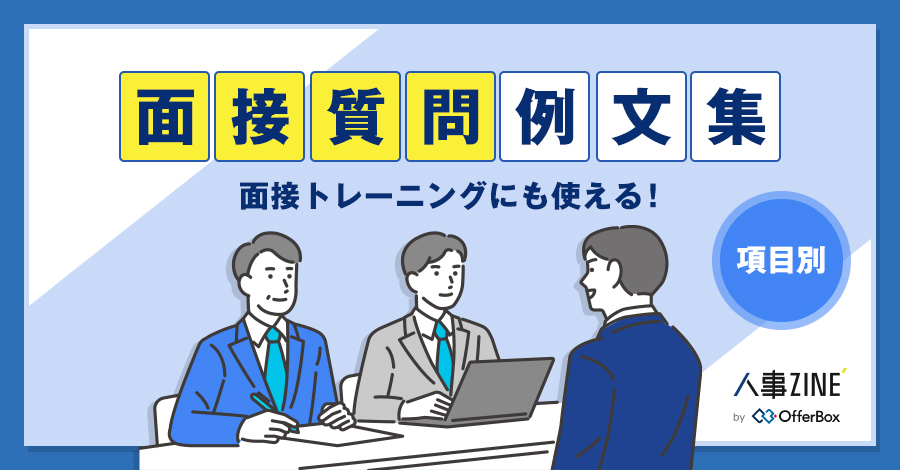
【質問例付き】個別面接でのアイスブレイクの会話ネタ7選

ここでは、個別面接のアイスブレイクで活用できる会話のネタと質問例を7種類紹介します。
1.趣味や特技
履歴書に趣味や特技が書いてある場合は、アイスブレイクとして触れてみるとよいでしょう。プライベートな話題で盛り上がると、面接前に距離を縮めることができます。また「履歴書を見てくれている」と感じると、応募者に好感を持ってもらえるかもしれません。
【質問例】
「履歴書を拝見したのですが、趣味は登山なんですね。どのようなきっかけで始められたんですか?」
「趣味はフットサルなんですね。実は私も同じで、週末はよくやっているんですよ」
「〇〇さんの特技は書道とのことですが、今も続けてらっしゃるんですか?」
2.休日の過ごし方
趣味や特技と同様、休日の過ごし方に関する質問もアイスブレイクにはおすすめです。応募者に聞くだけではなく自分も話すことで、お互いに自己開示ができます。
通常の土日以外にも、ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始が近い時期であれば、どのような休日を過ごしたかを聞いてみてもよいでしょう。
【質問例】
「〇〇さんは普段、お休みの日はどのように過ごされているんですか?」
「この間のゴールデンウィークはどこかお出かけされましたか?」
「昨日まで夏季休暇だったので旅行に行っていたんですよ。〇〇さんはどう過ごされましたか?」
3.ゆかりがある土地
ゆかりがある土地も、リラックスして話しやすいテーマです。現在住んでいるエリアや留学経験がある国、旅行で訪れたことがある場所などについて話し、共通点があると話が盛り上がりやすくなります。
なお厚生労働省が示しているガイドライン「公正な採用選考の基本」では本籍や出生地を問うことは就職差別につながる恐れがあるとしています。そのため、プライバシーには配慮してあくまでもリラックスできる話題として活用することがおすすめです。
【質問例】
「大学は〇〇市なんですね。有名な観光スポットがありますが、行ったことはありますか?」
「オーストラリアへの留学経験があるんですね。印象に残っている出来事はありますか?」
4.当日の交通手段
応募者に来社してもらって面接する場合には、当日の交通手段について触れてみましょう。当日に経験したことは応募者にとっても話しやすいため、出会ってすぐのアイスブレイクにおすすめです。
さらに、自宅からの通勤経路や交通量に不安がある様子なら、混雑しにくい通勤ルートや分かりやすい道について伝えると喜ばれるでしょう。
【質問例】
「今日は〇〇線でいらっしゃいましたか?混雑していませんでしたか?」
「駅からここまで迷われませんでしたか?」
「朝早くからありがとうございます。ご自宅からここまでどれくらいお時間がかかりましたか?」
5.季節や天候
アイスブレイクの鉄板ネタともいえるのが、季節や天候などの世間話です。初対面でも話しやすい話題のため、会ってすぐ、席についてすぐに話をしてみるとよいでしょう。特に応募者が遠方から来社する場合やオンライン面接では、意外に盛り上がる話題です。
【質問例】
「ここ数日で一気に冷え込みましたね。朝、寒くなかったですか?」
「最近、会社の前の桜が咲きまして。〇〇さんのお住まいのエリアはもう暖かいですか?」
「今日、夕方から雪が降るそうですよ。オンライン面接だと心配しなくていいのが嬉しいですね」
6.時事ネタ
大きなイベントやニュースなどの時事ネタもアイスブレイクの鉄板ネタです。特に、誰もが話題にするようなオリンピックやワールドカップは応募者も見聞きしている可能性が高いため、盛り上がりやすいでしょう。
注意すべき点としては、宗教や政治に関するネタは本人の思想に関わるため避ける必要があります。選挙の時期などはつい話題にしてしまいがちなので、注意しましょう。
【質問例】
「一昨日のワールドカップ、見られましたか?凄かったですよね」
「今回のオリンピックでは金メダルラッシュですよね。どの競技か、見られましたか?」
「万博、ご興味ありますか?始まりましたね」
7.面接当日の状況
面接当日・就職活動の様子や、ツールに関する話題もアイスブレイクとして気軽に出せる会話ネタです。特にオンライン面接の場合、慣れていない応募者はそれだけで不安を抱えてしまうことも少なくないため、面接前に不安を取り除く効果もあります。
オンライン面接の場合は、接続状況を確認した後に聞けば、自然な流れでアイスブレイクにつながるでしょう。
【質問例】
「現在のお住まいは大阪とのことですが、面接などで東京には何度か来られているんですか?」
「オンライン面接は何度かご経験されていますか?」
「オンライン面接は初めてなんですね。最近では便利になりましたよね」
人事ZINEでは「面接質問例文マニュアル」をご用意しています。面接で応募者のパーソナリティやキャリア志向、志望動機などの重要テーマを見極める質問例をまとめています。面接において応募者を的確に見極める質問の方法をご検討中の方はぜひご活用ください。
資料ダウンロード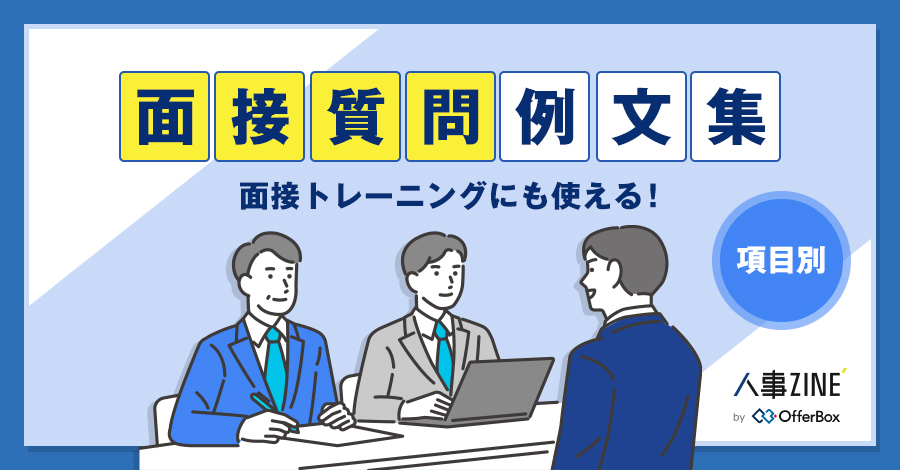
【会話例付き】グループ面接でのアイスブレイクのアイデア4選

ここではグループ面接のアイスブレイクで役立つ4つのアイデアを紹介します。
1.リレー式自己紹介
グループディスカッションなど、グループで取り組む選考のアイスブレイクとしておすすめなのが、リレー式自己紹介です。
各自が自己紹介をする前に「〇〇さんの隣の◇◇です」「〇〇さんの隣の◇◇さんの隣の△△です」など、リレー式で自己紹介をしていきます。シンプルですが、後ろの方になると自然に難しくなり、ゲームのような楽しさがあって盛り上がりやすい方法です。
【会話例】
「〇〇さんの隣の◇◇です。私の趣味はサッカーです」
「〇〇さんの隣の◇◇さんの隣の△△です。私の趣味は〇〇さんと同じでカフェめぐりです」
2.GOOD&NEW
GOOD&NEWというアイスブレイクも、グループ面接やグループディスカッションなどでおすすめです。
これは応募者が1人ずつ、最近よかったこと(GOOD)と、新しく発見したこと(NEW)を発表していく方法です。短い時間で応募者にとっても話しやすく、お互いの「素の姿」が垣間見られて盛り上がりやすいのがメリットです。
【会話例】
「最近良かったことは、昨日、生姜焼きがおいしく作れて、家族に喜んでもらえたことです」
「今朝、テレビで生活のお役立ちグッズとして“レンジでパスタをゆでるグッズ”を知りました。パスタが好きなのでぜひ買って活用したいです」
3.ヒーローインタビュー
ヒーローインタビューは、その名の通り、成功体験についてインタビューする形で人物紹介する方法です。
具体的には、ペアを組んで一方がインタビュアー、他方がインタビュイーとなります。インタビュアーは、相手の成功体験について質問し、詳細を引き出します。あえてポジティブな出来事をテーマにすることで場が和みやすく、またインタビューのやりとりを通して人柄が垣間見れるという点も魅力です。
【会話例】
「最近、上手くいった出来事はありますか?」
「その時の工夫や苦労を教えてください」
4.共通点探し
共通点探しは、参加者同士でグループを作り、制限時間内にできるだけ多くの共通点を見つけるゲームです。例えば、訪れたことがある観光スポット、趣味、好きな食べ物など、さまざまな話題で共通点を探ります。
共通点探しは、短時間でお互いの共通点を発見して親近感を引き出す効果があり、アイスブレイクとして有効です。
【会話例】
「私はスポーツ観戦が趣味なのですが、あなたはどのような趣味がありますか?」
「私は〇〇に訪れたことがあるのですが、あなたが行ったことがある場所について教えてください」
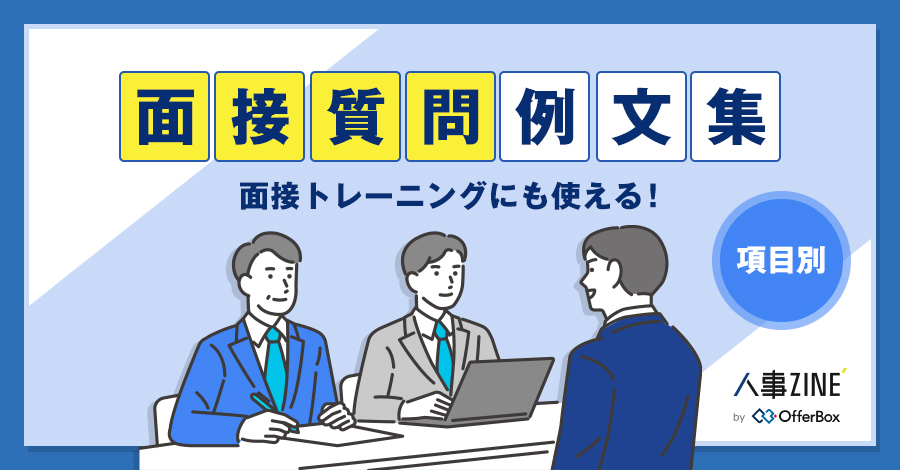
面接でアイスブレイクを効果的に行うためのポイント

ここでは、効果的にアイスブレイクを行うためのポイントをご紹介します。
アイスブレイク以外の要素も含めた面接全般のコツについては、下記ページも参考にしてください。
応募や面接参加への感謝を伝える
効果的にアイスブレイクを行うには、まず来社のお礼と自己紹介から始めましょう。
アイスブレイクは大切ですが、さらに大切なのは基本的なマナーと面接官の第一印象です。まずは丁寧にお礼を伝えることで応募者への謝意・敬意を示しましょう。
オンライン面接であれば、接続状況や音声の聞き取りやすさの確認を行ったうえで、面接を受けてくれたことへのお礼を伝えます。
クローズドクエスチョンで話を展開する
アイスブレイクの最初には、まずクローズドクエスチョンから話を展開するのがおすすめです。一般的に質問のパターンには2種類あり、以下の違いがあります。
- クローズドクエスチョン:YESかNOで答えられる質問
- オープンクエスチョン:自由に回答できる質問
例えば、交通手段を問う質問では、「本日は電車でいらっしゃいましたか?」と聞くのはクローズドクエスチョン、「本日はどのような交通手段でいらっしゃいましたか?」と聞くのがオープンクエスチョンです。
クローズドクエスチョンは回答が限定されるため応募者が答えやすく、オープンクエスチョンは自由に回答できるため話が広がりやすいという特徴があります。そのため、最初は答えやすいクローズドクエスチョンから始めるのがアイスブレイクには向いています。
面接官側も自己紹介・自己開示する
面接官側も自己紹介や自己開示をすることは大切です。
面接では面接官が次々に応募者に質問していくことになりますが、一方的に質問を受けると「いかにも見極められている」という印象を与えかねず、相手が本来持っている魅力を引き出しにくいでしょう。
そこで、面接の最初の段階では面接官側も自己開示して、相手に心を開いてもらうことが大切です。また、面接を進めるなかでも適宜自己開示して余計なプレッシャーを与えないよう配慮することも有効でしょう。
選考に影響しないことを伝える
アイスブレイクをする際は、「選考に影響しない」と明らかにしておくことも効果的です。
アイスブレイクの目的はあくまでも場を和ませ、応募者の緊張を解くことですが、応募者からすると何気ない会話であっても「このやりとりも選考に影響するのではないか」と身構える可能性もあります。
これでは緊張を解くことは難しいため、アイスブレイクはあくまでも顔合わせであり、安心して会話に参加してもらうようアナウンスすることが大切です。
アイスブレイクにかける時間を決めておく
どのくらい時間をアイスブレイクにかけるか、あらかじめ決めておきましょう。目安としては面接時間の10分の1程度。例えば30分の面接なら3分、1時間の面接なら6分までが目安です。
アイスブレイクが盛り上がりすぎて面接時間が少なくなってしまうのは本末転倒ですが、逆に短すぎても、応募者の緊張をほぐしてリラックスしてもらうアイスブレイクの目的を果たせなくなります。目安の時間を意識しながら、応募者の様子を見てタイミングを計るとよいでしょう。
アイスブレイクはいつ・どこで使う?導入タイミングと設計のコツ
アイスブレイクは、面接の冒頭で応募者の緊張をほぐすために活用されることが一般的です。しかし、単に「場を和ませる雑談」として扱うだけでは不十分で、面接全体の構成や質問の流れを踏まえて設計することが重要です。
特に個別面接では、受付から着席・自己紹介のタイミング、グループ面接ではアイスブレイクにかける時間や進行順とのバランスが求められます。本セクションでは、面接の種類や目的に応じた効果的な導入タイミングと設計のコツを解説します。
面接フローのどこで使うと効果的か
アイスブレイクを効果的に使うタイミングは、応募者が最も緊張している「面接開始直後」が基本です。入室後すぐや、面接官からの軽いあいさつ後、いきなり本題に入る前に短い雑談を挟むと、応募者が話しやすい雰囲気を作れます。
ただし、緊張が和らいでくる中盤以降にアイスブレイクを入れると、唐突感が出る場合もあるため注意が必要です。特に個別面接では「自己紹介前後」、グループ面接では「開始5分程度のオープニング」として取り入れるのが効果的です。
雑談から自然に移る導線の作り方
アイスブレイクから本題に自然に移行するには、会話の“接続点”を意識した導線設計が重要です。たとえば「最近読んだ本は?」といった雑談の流れから、「好奇心旺盛な方なんですね。それでは、志望動機をお聞かせください」と自然につなげると違和感がありません。
逆に雑談と本題の間に間が空くと、切り替えが不自然になりやすいため注意しましょう。雑談は応募者の反応や性格を探る機会でもあるため、本選考への“準備運動”と捉え、滑らかな移行を意識しましょう。
アイスブレイクと本選考質問の繋ぎ方
アイスブレイクの後は、応募者の緊張がほぐれた状態を維持しつつ、本選考の質問へ移行することが理想です。そのためには、アイスブレイクで得た情報を橋渡しとして活用すると効果的です。
たとえば、「休日はものづくりが趣味」と聞いた場合、「では、その好奇心が仕事にどう活かせるかを伺いたいのですが」と繋げることで、スムーズに深掘りできます。このように、雑談の中から選考につながる要素を拾い、自然な流れを作ることが面接官の腕の見せどころです。
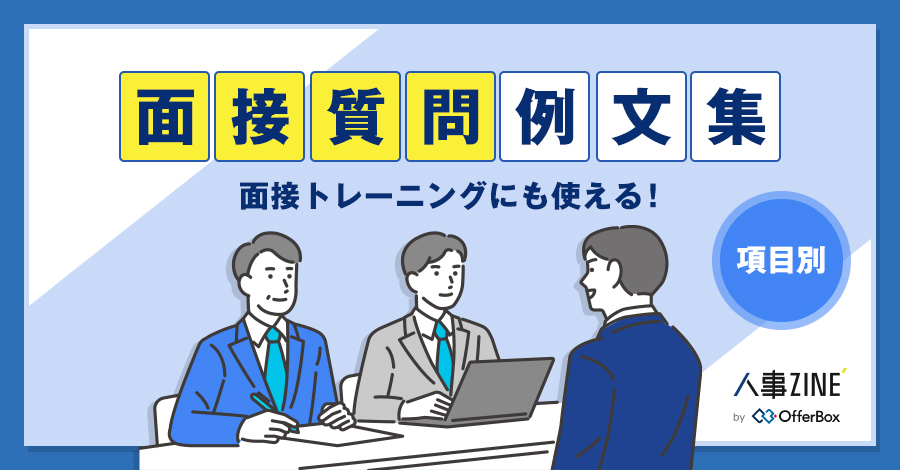
面接官必見!アイスブレイクの失敗例面接官が注意すべきアイスブレイクのNG質問と失敗例

アイスブレイクはかしこまらない話題を選ぶことで場の雰囲気を和ませる効果がありますが、かといってどのような話題でもよいわけではありません。ここでは、面接官がアイスブレイクの際に注意すべきNGな質問を紹介します。
配慮が必要な事項に関する質問
場を和ませるのが目的であったとしても、応募者のプライバシーに関する事項など、配慮が必要な事項を話題にすることは避けましょう。
前掲の厚生労働省のガイドライン「公正な採用選考の基本」では、応募者の適性・能力にもとづいた採用選考基準が示されており、「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項」に関する質問は控えるべきとされています。例えば以下のような話題は避ける必要があります。
- 出身地や本籍
- 家族・生活状況
- 政党・宗教・思想
- 身体状況・健康状況
その他にも、愛読書や尊敬する人物、社会運動など、注意すべき話題はいくつかあります。こういった話題は採用選考において就職差別につながりかねない事柄であり、仮にアイスブレイクであっても控えましょう。
自社への志望度に関する質問
自社への志望度を問うような質問もプレッシャーになる可能性があります。面接が進むなかで質問する分には有効な可能性がありますが、アイスブレイクの段階ではかえって緊張感を生じさせる恐れがあるため、控える方がよいでしょう。
関連して、他社の選考状況についての話題も、必ずしもNGではないものの注意しましょう。就職活動の話題は応募者にとって身近なテーマではありますが、やはり「自社への志望度が高いのか?」を確かめる意図があると受け取られ、かえって緊張感を増やしかねません。
プライベートに踏み込む質問
性別や恋愛対象などに関する質問は、ハラスメントにあたる場合があるので避けましょう。また、性的指向と性自認に基づく理由で特定の人(LGBTなど性的マイノリティの人)を排除しないことが必要です。そのため、そもそもアイスブレイクで持ち出す話題としてはふさわしくありません。
オンライン面接では応募者のプライベートな空間が写り込んでしまう可能性があります。背景に映った部屋を見て、並んでいる本や雑貨などが目に留まったとしても「その本は何ですか?」など聞かないようにする配慮も必要です。
扱いが難しい時事ネタ・ニュースに関する質問
時事ネタやニュースを使ったアイスブレイクも避ける方が無難でしょう。
例えば災害や有名人のスキャンダル、業界の不祥事のようなネガティブなニュースは、それだけで場の雰囲気が重くなる可能性があり、アイスブレイクとして適切ではありません。
また、選挙やプロスポーツのように人によって意見・好みが分かれやすいトピックもアイスブレイクには向いていないでしょう。双方が異なる意見を持っている場合は反応に困りますし、トピックによっては個人的な価値観に触れてしまう可能性もあります。
心理状態についての質問
心理状態について質問することも、アイスブレイクには向いていません。
例えば面接では、応募者の気をほぐすことを意図して「緊張していますか?」「よく眠れましたか?」といった質問をするケースがあります。しかし、これは「はい」とも「いいえ」とも答えにくい質問であり、また面接の評価も気になるため本音で回答しにくく、リラックスにはつながりません。
また、一般論として、初対面の人を相手には自分の心理状態を打ち明けにくいものであり、特にアイスブレイクのような面接の序盤でこういった心理面を尋ねるのは避けた方がよいでしょう。
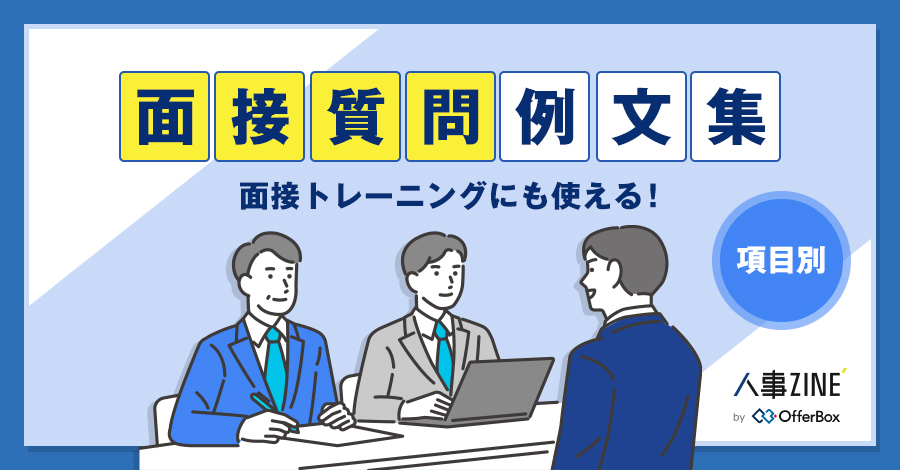
オンライン面接におけるアイスブレイクの注意点

最後に、オンライン面接におけるアイスブレイクの注意点についてもご紹介します。
オンライン面接では、以下の3点に気をつけましょう。
- 最初に接続状況と操作方法を確認する
- 聞き取りやすい話し方を心がける
- 意識して聞いている姿勢を示す
オンライン面接に慣れてない応募者の場合、それだけで緊張してしまうこともあります。そのため、「接続状況に問題があったり聞き取りにくかったりする際は遠慮なく声をかけて欲しい」「もし途中で接続が切れてしまったら、こうしましょう」など、事前にトラブル時の対応を伝えておくと、応募者も落ち着いて面接に臨めるでしょう。
またオンライン面接では、対面の時と比較すると相手の様子が分かりにくくなるものです。なるべくゆっくりと大きな声で話し、応募者が話している時には大きくうなずくなど意識してリアクションすることを心がけましょう。
オンライン面接を成功させるためのコツについて詳しくは、こちらのページで解説しています。
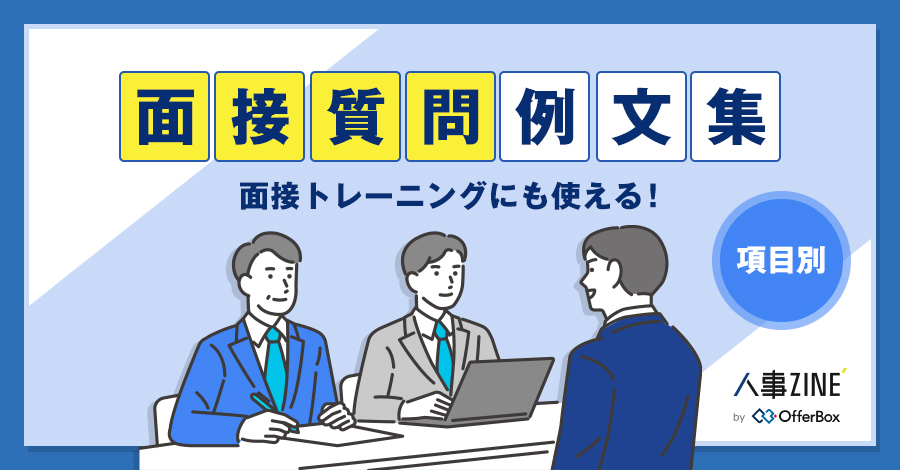
まとめ

面接にアイスブレイクを取り入れることは、「応募者の緊張をほぐしリラックスできる状態にする」「応募者と面接官の距離を縮める」などのプラス効果が期待できます。また、応募者に本音で自社に対する希望を伝えてもらうことで、採用や配属のミスマッチを減らす効果も期待できるでしょう。
ただし、アイスブレイクに合った話題を選び、適切な時間を区切って行うなどの工夫も必要です。今回ご紹介した内容を踏まえ、アレンジするなどしてぜひ活用してみてください。
また、アイスブレイク用の質問以外にも、候補者の人柄を引き出す質問のバリエーションを用意しておくことは大切です。人事ZINEが提供している資料「面接質問例文マニュアル」では、応募者の志望動機やキャリア志向などを見極める例文をまとめております。こちらの例文を活用すれば、面接において的確に応募者を評価することが可能です。面接においてマッチングの精度を高めるヒントをお探しの方は、ぜひご活用ください。